
南北朝時代に発生した中世的庶民喜劇で,能,歌舞伎,文楽(人形浄瑠璃)などとともに日本の代表的な古典芸能の一つ。特に能とは深い関係をもつところから〈能狂言〉とも呼ばれる。能が主に古典的題材をとり上げ幽玄美を第一とする歌舞劇であるのに対し,狂言は日常的なできごとを笑いを通して表現するせりふ劇という対照をみせている。
狂言という芸能の成立事情は明らかでない。しかし人を笑わせる滑稽な演技の淵源は,遠く古代までさかのぼることができるはずである。アメノウズメノミコトの岩戸舞をはじめ,《古事記》《日本書紀》の伝承の中には喜劇的所作を伴うと思われるものがいくつか見いだせる。だがそれがまとまった芸態として記された例となると,平安中期の藤原明衡(あきひら)作と伝える《新猿楽記》まで下らねばならない。そこには京の街で演じられた猿楽として〈妙高尼の襁褓(むつき)乞い〉〈東人の初京上り〉といった滑稽技と,それを演じた役者の名が記されている。ただこれらの芸は多分にまだ即興性を残すものであったようで,これを後代の諸芸能とどこまで結びつけてよいかは問題がある。しかしこうした〈猿楽〉,つまり即興的滑稽演技が一つの劇の中にとり入れられ,洗練され定着する過程で狂言という喜劇芸能が形成されたということはいえそうである。特に狂言の成立した南北朝時代に,社会の変革に伴ってくりひろげられた下剋上的事象の数々は,こうした笑いの芸能に多くの題材を提供したと思われる。伝統的な滑稽技と,この時代特有の世相風刺の笑いと,この二つが接合したところに,中世庶民喜劇狂言の誕生をみたわけである。
このころ観阿弥・世阿弥による能の大成があった。当時〈猿楽能〉と呼ばれていたことからもわかるように,能ももとは即興的滑稽技から出発したものであるが,早々にその滑稽面をふるい落とし,歌舞の要素をとり入れ新しい芸能として大成した。この能と狂言とは,いちはやく提携したようである。もっともこの段階における狂言は,一応の成立をみたとはいうものの,能のように内容が定着していたとは考えられないので,どのような形で能と提携したのか具体的な事情はよくわからない。ただ世阿弥の《習道書》や《申楽談儀》などから,(1)同一舞台における能と狂言の交互上演。(2)能におけるアイ(間狂言)の存在。(3)能役者の演ずる《翁(おきな)》の中で《三番叟(さんばそう)》を狂言役者が担当すること--という現在にも通じる両者の関係は,少なくとも世阿弥の周辺ではすでに成立していたことが知られるのである。
こうして能と深いかかわりをみせながらも,狂言の即興性と流動性は中世末期ごろまではなお続いたようだ。室町時代の狂言の芸態をしのばせる唯一の伝書《天正狂言本》(1578年奥書)の《末広がり》をみると,〈大名出て人を呼び出す。都へ行ていかにも高い末広がり買うて来よと言ふ。さて上る。都に着きて呼ばはる〉といった簡単な記述で,16世紀末になっても,狂言はだいたいのあら筋だけを決め,あとは即興的なせりふと所作で演じられる程度の芸能であったことがわかる。しかしその反面,狂言の内容がともかく書き留められるようになったこと,またそこに記されている100余番の狂言の約8割が,今日演じられるものとほぼ同内容であることからみると,この《天正狂言本》の時代には狂言の流動がようやく終わり,内容定着の兆しをみせてきたことも同時に推察されるのである。
江戸時代に入ると,狂言は能とともに武家の式楽となって幕藩体制に組み込まれる。能のシテ方支配が確立し,狂言方はワキ方・囃子方とともにその服属下に入った。しかしそれは同時に,狂言方が武士に準ずる待遇を受け,演目も定着し,役者は技芸を磨くことに専念できるという体制でもあった。こうして狂言は古典芸能としての道を歩み始めたのである。古典芸能としての狂言は,この時期に整備される。大蔵(おおくら)流(本家・弥右衛門派,分家・八右衛門派),鷺流(本家・仁右衛門派,分家・伝右衛門派)の2流がまず確立し,ついで,京都禁裏御用をつとめまた尾州藩・加賀藩のお抱えでもあった和泉(いずみ)流(宗家,三宅派,野村派等)が勢力を伸ばし,ここに狂言界は三流鼎立時代に入る。このほかに南都禰宜(なんとねぎ)流,脇本,田中等の群小流派も存在したが,これらはしだいに前記三流に統合されたり,新興の歌舞伎の世界に加わったりなどして消滅したようである。
また,せりふがしだいに定着してきたことや,流派意識が強まったことから,台本の書き留めもなされるようになった。大蔵虎明(おおくらとらあきら)が1642年(寛永19)に書写したいわゆる《大蔵虎明本》は,その最初の完備した台本である。ほかに古台本としては正保ころ(1644-48)のものと思われる和泉流の天理本《狂言六義(りくぎ)》,享保初年かとされる《鷺保教本》等がある。これ以降も狂言の詞章は,多少の流動をみせつつしだいに洗練が加えられ,それに伴って整備された台本が各流儀ごとに次々と書き留められるようになった。このほかに一般に普及した台本として,1660年(万治3)から1730年(享保15)にわたって刊行された《狂言記》《狂言記外》《続狂言記》《狂言記拾遺》があり,各50番,計200番の狂言の詞章を収める。早く滅んだ群小流儀の台本によったものらしいが,正統の流儀の台本が公開されなかった当時としては,狂言の内容を知る唯一の読み物として歓迎され幕末まで再三版を重ねた。
明治維新を迎え武家階級が没落するとともに,狂言界も大きな変動を余儀なくされた。それまで士分として俸禄を受けていたのが一時に収入の道を絶たれたわけで,この新しい事態に対応できない者も多く,三流の家元も家業を廃し,次々と絶家するという状態となった。しかし大蔵流では,東京の山本東次郎家,関西の茂山(しげやま)千五郎家,茂山忠三郎家といった有力弟子家によって芸統が維持され,また和泉流も,京都から三宅庄市,金沢から野村与作らが上京して東京における和泉流の発展に力を尽くした。現在では両流の家元も再興され,大蔵流では前記の諸家や茂山忠三郎家から分かれた善竹(ぜんちく)家が主として東京・関西で,和泉流では野村万蔵家,三宅藤九郎家,野村又三郎家,名古屋の狂言共同社の人々が主として東京・名古屋でそれぞれ活躍している。ただ鷺流だけは,明治時代に中央で滅んだ後は再興されず,現在山口市や佐賀県地方,新潟県の佐渡にわずかにその芸が伝えられるにすぎない。
現行の大蔵・和泉2流の芸風の違いは,東京大蔵流が格調を重んじた演技であるのに対し,和泉流はそれに洒脱味が加わり,名古屋和泉流,関西大蔵流と西へ移るにつれてそれがいっそうくだけた芸風となる。このように狂言の芸風は,流儀の違いよりも,その在住する土地柄,また役者の個性によるところが大きい。
現在上演される狂言の曲目は大蔵流が約200番,和泉流が約250番である。その大部分は重複するが,流儀によって台本に多少の相違もあり,流儀独自の曲もある。その作者については南北朝時代の学僧玄恵(げんえ)法印らを挙げる伝承があるが,もとよりこれは信用できない。一部に知識層の関与があったにせよ,大部分は代々の狂言師の手によって制作されたとみてよいであろう。狂言の分類方法はいくつかあるが,ここでは大蔵流の分類により代表曲を表に示す。
狂言は笑いの芸能とされているが,それは単なる滑稽に終始するのではなく,その笑いにもいくつかの種類が含まれている。今それを,〈祝言の笑い〉〈風刺の笑い〉〈単なる滑稽〉の3点に分けて述べておく。
〈笑う門(かど)には福来る〉ということわざもあるように,古来笑いには寿祝と相通じる性格があった。笑いの芸能である狂言においても,その中に含まれる祝言寿祝劇としての面を忘れてはならない。脇狂言という祝言を主題とした一類があることもその現れである。大黒天や恵比寿(えびす)が出現して参詣人に福を授けるとか(《夷大黒》ほか),諸国の百姓の年貢上納を描くとか(《筑紫奥》ほか),果報者が登場するとかのめでたい主題(《末広がり》ほか),めでたい内容の狂言がこれに属する。脇狂言以外の曲でも,なにかといえば〈天下治まりめでたい御代(みよ)でござれば〉とか〈世の中ようて田がよう出来て,このようなめでたいことはござらぬ〉といったせりふを挿入してその場を祝福しようとしている。ほかに劇中で演じられる歌舞・囃子物,語り等にもめでたい内容のものは多い。このように祝言性は,しばしば脇狂言以外,狂言という芸能全体に及んでいるのである。これは狂言が長いあいだ式楽として演じられてきたことと関係があろうが,式楽性が消滅した現在でも,狂言が笑いの芸能である以上,この祝言劇としての側面は無視できないのである。
狂言が成立する背景に,南北朝から室町時代にかけてもり上がった下剋上の風潮があったことを思えば,その中に世相風刺の笑いが含まれるのは当然であろう。《看聞日記》応永31年(1424)3月11日には《公家人疲労(困窮)ノ事》という狂言が演じられた記事があるし,《天正狂言本》の中の《近衛殿申状》という狂言では年貢減免について訴える農民も登場している。ただこれらの狂言が後世に伝承されなかったことからもわかるように,現在の狂言からはそうした世相に密着した風刺はほとんど影をひそめ,代わって人間誰しもがもっている弱点をユーモラスに指摘する形の風刺が主流となっている。つまり狂言に登場する人物は,必ずしも中世の大名・僧侶と考える必要はないのである。そこに現れた大名を通して,いつの時代にもいそうな尊大ぶる人物が風刺されているのであり,僧侶を通しては無学なくせに知識をひけらかしたがる人の心理が笑われているとみるべきであろう。また舞台上の太郎冠者の言動を見ながら,観客は,横着でもあれば反面小心でもあり,狡猾でありながらそれでいて実直でもあるという,太郎冠者ならぬ自分自身の心の矛盾を感じとることもできるはずである。このように狂言の風刺は,かつての中世にだけ通用する風刺から脱皮して,より普遍的な〈人間喜劇〉ともいうべき性格のものに成長しているのである。
単なる滑稽という面からみても,狂言は流動の過程で大きな変化をみせている。狂言が当代劇であった時代の笑いは,風刺の場合と同様,とかく場当りをねらった低俗なものに終始したと思われる。《天正狂言本》の記述をみても,そこには粗野でしばしば卑猥に流れる笑いが充満していたことがうかがえる。それがしだいにふるい落とされて,現在の狂言にみられるような明るいからりとした笑いに統一されていったのである。また,せりふ,所作,語り,歌舞等による笑いが巧みに組み合わされ,祝言,風刺,滑稽性が総合された高度な笑いも生まれてきた。世阿弥はその《習道書》の中で〈笑みの中にたのしみを含む〉ことをもって狂言の理想としているが,現在の狂言において,この境に達した舞台にしばしば接することができる。祝言も風刺も超越した〈和楽の笑い〉,そこに狂言の滑稽の一つの達成をみることができよう。
狂言は能の会において,能と交互に上演されるのが本来の形であるが,最近は能の番数に関係なく,狂言を一番しか挿入しない形式がむしろ通例となりつつある。その代り狂言だけを上演する会が能舞台以外の劇場や学校の講堂のような場所で増えている。もともと登場人物も少なく装置や小道具もほとんど必要としない狂言は,どんな舞台でも手軽に演じられるという強みがある。そのうえ狂言のせりふは,現代語の母胎である中世口語を基調としているし,扮装も様式化はされているが当時の姿をかなり忠実に写しているので,その舞台はいわば〈動く室町庶民風俗絵巻〉の感があり,狂言は古典芸能とはいいながら,現代の誰からも親しまれる条件を備えているといえる。一番の狂言に登場する人物は,ほとんどが2~4人,中には多人数物もあるが,それも主要人物はやはり2,3人で,それ以外の者は立衆(たちしゆう)と呼ばれて一団となって行動する。主役をシテ,それ以外をアドと呼ぶが,和泉流では主アド以外を特に小(こ)アドと呼んでいる。上演時間は大部分は20~40分で,1時間に及ぶものは《武悪》《釣狐》《花子(はなご)》等,数曲にすぎない。
能と違って面の使用はごく限られており,神仏,鬼,動物,醜女(しこめ)等に扮するときに用いられる程度だが,《清水》や《六地蔵》のように,面を鬼や仏像になりすますときの小道具として使う例もある。舞台装置や小道具も少ないが,その代り扇一つで盃や銚子,筆,戸の開閉等を表すし,葛桶(かずらおけ)が腰掛,酒樽,柿の木等になるなど多様な用法をみせる。また酒をつぐときは〈ドブドブドブドブ〉,茶碗を割るときは〈グ(ワ)ラリン,チーン〉,蔵の戸を開くときは〈グヮラ,グヮラ,グヮラグヮラグ(ワ)ラグヮラ〉,家の戸を閉めるときは〈サラサラサラ,パッタリ〉,といった擬音を,演者自身が擬声語で表現するのも,狂言独特の素朴でユーモラスな表現手法である。
狂言はせりふを主体とした演劇であるが,適当に歌舞や囃子物も用いる。それによって酒宴の場の雰囲気をもり上げたり,一番の狂言をめでたくとりなして留めたりする(終わる)のである。ほかに《花子》や《御茶の水》のような恋愛を主題とした曲で,のろけ話や恋のささやきの場を,小歌の吟唱や掛合で表現する例もある。愛情の表現が露骨になるのを避けるためで,そこに喜劇でありながら低俗に堕さぬようにという配慮がうかがえるのである。
狂言の多くは〈これはこのあたりに住まいいたす者でござる〉という自己紹介の名乗りで始まり,〈やるまいぞ,やるまいぞ〉の追込みで終わる。もちろん名乗りの形式はほかにもあるし,留め方にも追込み以外に,囃子留め,笑い留め,叱り留めなど幾つかの型がある。しかしこうした型に分類できるほどに狂言という演劇の構成は類型的である。これは一曲の構成だけでなく,部分的な趣向・表現様式にも及んでいる。また登場人物を大名,太郎冠者,聟,夫婦,鬼,山伏,僧侶,座頭といった15,6種類のものに統制しているところにも,この類型化の傾向がうかがえよう。ただこの類型性がそのまま画一性になってはならない。たとえば大名のせりふをそっくり太郎冠者がくり返す場面があるが,同じせりふをいう中に,大名と太郎冠者の位の差がおのずと出なくてはならぬのである。
これらの類型化は,狂言が近世において整備される過程で多くなされたものであるが,その方向は〈誇張〉と〈省略〉という狂言の演技の二大手法と深くからみ合っている。誇張と省略とは一見相反する表現方法のようであるが,物の特徴的な部分を誇張し,無駄な部分を省略するということは,どちらも表現すべき事象の本質を重点的に浮かび出させる効果的な手段である。狂言の類型化はこの誇張・省略の手法を大きく助長したが,同時にこの二つの手法が狂言の類型化を大胆に推し進めもした。そのことによって狂言は,人間の普遍的でかつ本質的な性格や行動を,力強く鮮明に表現できるようになり,またそれが狂言独自のユーモアの表出にもつながっている。狂言は近世以降の古典芸能化の過程で洗練され整備されたために,一見成立期の活力が減退したかにみえる。しかし子細にみると,やはりこうした表現手法の中に,中世庶民の特徴である現実に立脚したたくましい生命力は,十分受けつがれていることがわかるのである。
狂言は日本で最初に成立したせりふ劇であり,ほかに例の少ない笑いの文学でもあるので,他の分野に与えた影響も大きい。近世初頭の歌舞伎成立期においては,狂言師が歌舞伎の世界に身を投じ,小舞(こまい)の指導をしたり,役者として舞台に立ったりした者も少なくない。歌舞伎芝居を指して〈狂言〉と呼ぶことは現在でも行われているが,その淵源はすでにこの時期に発している。元禄期前後においても,歌舞伎の演目の中には明らかに狂言から出たと思われるものがたくさんあるし,舞踊にも古く初代中村勘三郎所演の《乱曲三番叟》,近世後期まで下ると《寿靱猿(ことぶきうつぼざる)》《朝比奈釣狐》など狂言を材料としたものが数々現れた。歌舞伎以外でも井原西鶴や近松門左衛門の作品,川柳や小咄にも影響を与えているが,ことに十返舎一九の《東海道中膝栗毛》(1802),それに続く《続膝栗毛》には,狂言《丼礑(どぶかつちり)》《附子(ぶす)》《墨塗(すみぬり)》等の趣向がとり入れられ,効果的に笑いをもり上げている。明治以降も,歌舞伎舞踊として《素襖落》《身替座禅(みがわりざぜん)》(《花子》の舞踊化),《棒しばり》《茶壺》といった曲が作られ,松羽目物(まつばめもの)と呼ばれて今日でも人気曲としてよく上演される。また成瀬無極の《文学に現れたる笑之研究》(1917)のように,比較文学研究の材料として狂言がとり上げられるようにもなった。しかし狂言が,能に従属したものでなく独立した演劇として真にその価値を認識されたのは,第2次大戦後のことである。狂言はこの時期に至って,他に類例のない簡潔な構成や手法,おおらかで明るい内容,狂言役者の的確で力強い演技力等が認められ,1950年代には〈狂言ブーム〉という言葉さえ生まれた。これは同時に狂言の演技様式を生かした新演劇運動をも導き,飯沢匡作の新作狂言《濯ぎ川》の上演,岩田豊雄作《東は東》,木下順二作《彦市ばなし》の狂言様式による上演,同じく木下順二作《夕鶴》の能様式による上演に狂言師が参加するなど,新作狂言・新様式狂言の制作となって現れた。その後も狂言の海外公演や外国演劇との交流もさかんになり,狂言界にも新しい気運が起こりつつある。リアリズム方式の行き詰まった新劇の世界でも,狂言に対する関心は今後もなお深まりそうである。
→狂言面 →能 →能装束
第2次大戦後,狂言がはじめて海外で演ぜられたのは,1957年,能とともにパリのサラ・ベルナール座での公演であった。そのころ,能をとりまく有識者の多くは,狂言はせりふ劇であるから,外国人には理解しにくいであろうと考えていた。しかし,この公演で野村万之丞,野村万作,野村又三郎が演じた《棒縛》《梟山伏》はパリの観客,ことに天井桟敷の若者たちから熱狂的な拍手をうけた。また1963年には,野村万蔵・万作らがアメリカ,ワシントン大学の客員として招かれ,狂言の実技を指導し各地で公演を行ったが,アメリカ人の観客は,ときに言葉がわかるのではないかと思うほど,鋭く率直な反応を示した。これらの欧米での狂言の紹介公演の反響は現地の新聞紙上にも報道され,日本人の中にも狂言の笑いはユニバーサルなものであり,演出演技も普遍性をもつという考え方が定着したようである。1965年の西ベルリンの芸術祭で《瓜盗人》を演じた野村万蔵は,ローレンス・オリビエと並ぶこの芸術祭の二大名優であると絶賛をうけた。しかし,狂言一般に対しての批評の中に,動きはおもしろいが,声はサイレンのようで聞きにくいと書かれたものもあり,声がすばらしいという批評の多かったアメリカとは違い,歌の伝統のある国だという印象が強い。その後も欧米をはじめ,インド,南米,中国などで,能とともに公演し,あるいは狂言独自の形で公演が行われてきた。実技指導の面では,狂言の様式的な演技を身につけ,これを基本にして,英語による狂言や,童話劇,ギリシア劇などを演ずるグループがアメリカで生まれているように,狂言の実技を学ぶ俳優や学生も多い。日本で英語狂言のグループを作っているアメリカ人もいる。
専門の演劇人の狂言評価の例としては,レニングラード(現,サンクト・ペテルブルグ)のボリショイ・ドラマ劇場の演出家,G.A.トフストノーゴフが,野村万蔵の《棒縛》を見て,〈スタニスラフスキー・システムの最高の体現である〉と評している。能とは違う面での狂言の写実性が指摘されており,能を見て,〈死ぬほど退屈だ〉と言ったフランスの芸術家(彫刻家O.ザッキン,映画監督J.デュビビエら)の受け取り方と対照的でおもしろい。様式から入って写実に至る,狂言演技の究極が,リアリズム演技の基本的システムと合致するのである。

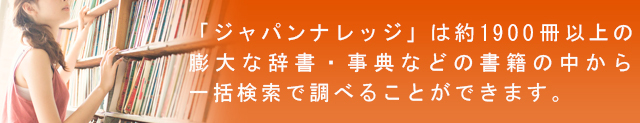
 ンアシライ ...
ンアシライ ...









©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.