
文芸ジャンルの一つであるが,その内容や表現様式は多様である。心の赴くにまかせて,なにくれとなく筆録されたものであり,文章はおおむね断片的かつ短文で,全体の組織構成,順序次第にはとらわれず,自分の見聞や身辺雑事,感懐や体験をつづる。広く世間に読者を期待することもなく,せいぜい親子・友人間などせまい範囲に読まれることは考えられていた。ヨーロッパにおけるエッセーと同じように近代では考えられているが,一部の随筆は似ているものの本質的には異なると考えるべきである。読書の際,興味をひいた条を抜抄した抄録集のようなものも日本では随筆に含めており,この種の文献も決して少なくない。〈随筆〉の2字を書名に明確に使用している文献は,一条兼良(1402-81)の著とされる《東斎随筆》(1巻,成立年不明)が最初といわれる。しかし内容は抜抄した短文の説話を集めたもので,編者は私的な書留という心持であったと推定される。随筆に対する自覚を持ったのは近世に入ってからであるが,成書としては古くから存在した。日本における最初の随筆文学とされる清少納言の《枕草子》は,その3巻本の跋文に〈この草子,目に見え,心に思ふことを,人やは見むとすると思ひて,つれづれなる里居のほどに書き集め〉と記している。文学に限定せずに見渡せば,多くの随筆的な文献が存在している。この系統は絶えることなく近世に至って盛んとなり,近代にも引きつがれたのは,日本人に適した表現様式であるためであろう。
中世の随筆といえば,従来,鴨長明の《方丈記》,吉田兼好の《徒然草》の2点があげられる。しかし《方丈記》は漢文の文章の一体である〈記〉を書名とする。〈記〉は〈紀事〉〈志〉〈述〉ともいい,叙事が主で,筋道を立てて書くことである。さかのぼれば慶滋保胤(よししげのやすたね)の《池亭記》など,平安時代の漢文学にいくつもの作品がある。本来《方丈記》を随筆の範疇に入れるのは当たらないのである。一方,《徒然草》は〈つれづれなるままに,日ぐらし,硯にむかひて,心にうつりゆくよしなしごとを,そこはかとなく書きつ〉けたと序段に見え,文字どおり随筆以外のものではない。《方丈記》《徒然草》の2書を,従来中世の随筆として選択したのは,随筆文学の見地に拠るもので,内容で分類する習慣で今日に至っているため,例えば和歌の随筆は歌書に入れるというように弁別される。したがって今後は,他の部門に含まれている書籍中から拾い出すことによって,日本における随筆を見直すことが可能になるであろう。一貫した統一のもとに構成されてない文献は,随筆としてさしつかえはない。例えば法語の類,《一言芳談》《夢中問答集》なども,宗教書中の随筆として見ることができる。
日本の随筆は,古くは僧,学者,連歌師,歌人,武士などに著者が限られていたが,近世になると学問の普及とともに俳人,雑学者,町人,下層武士,戯作者へとひろがった。板行された随筆もあるが,写本で伝わったものが断然多く,翻刻されているのはごく一部にすぎない。板本随筆の中には絵入りのものもあり,絵入写本も多少は存する。内容はきわめて多種多様で,回想,自伝,風俗世相,巷談風説,随想,儒学,国学,医学,芸道,見聞,逸話,考証,紀行などにわたり,一概に律しきれない。それらは近世社会のあらゆる事象にわたっており,近世研究に欠かせない資料群である。
なお近世はきわめて豊富に文献が残り,室鳩巣の《駿台雑話》,松平定信の《花月草紙》,松浦静山の《甲子夜話(かつしやわ)》など著名なものも多いが,ジャンル別に整理して分類しきれないものが少なくない。それらは随筆雑著とされる傾向があり,なかには辞書的なものも含まれている。
近代は随筆においても新たな展開を迎える。伝統的な随筆概念の一方,西欧のエッセーの影響によって,より知的思想的な深みを備えた文章が書かれた。自我意識の覚醒,新聞・雑誌など出版機構の発達は,感想・意見を書いて発表し,また他人がそれを読む機会を促進させた。明治初期にジャーナリズム活動にたずさわった成島柳北,栗本鋤雲(じようん),福沢諭吉らのもの,明治20年代では徳富蘇峰の感想や評論,志賀重昂の風景論などが注目される。だが,近代文学の成立につれて,文学者たちが随筆においても最有力な書き手となり,坪内逍遥,森鷗外のものをはじめ,斎藤緑雨《あられ酒》,幸田露伴《讕言(らんげん)》《長語》,徳冨蘆花《自然と人生》などがまずあげられる。正岡子規たちの写生文は随筆を主領域とする。子規の《墨汁一滴》《病牀六尺》などは死をひかえての感想・観察記録である。明治後期から大正期にかけては,文学史的にも個人史的にも変わり目にあたっており,随筆は自己凝視と表出に適した形式であった。夏目漱石《思ひ出す事など》《硝子戸(ガラスど)の中》,近松秋江《文壇無駄話》,島崎藤村《新片町より》《後の新片町より》,永井荷風《日和下駄(ひよりげた)》,薄田泣菫(すすきだきゆうきん)《茶話》などのほか,漱石門下のいわゆる教養派,白樺派の人々によって個性的思索的感想・記録が書かれている。
このような趨勢は,1923年の《文芸春秋》や《随筆》という雑誌の創刊,新潮社,改造社の〈叢書〉刊行によっていっそう確かなものとなり,ジャンルの一つとしての地位をもつにいたった。大正末から昭和期にかけて,芥川竜之介,谷崎潤一郎,菊池寛,佐藤春夫らが文学的随筆として洗練度を加えた。内田百 の《百鬼園随筆》ほか,寺田寅彦の科学随筆も一つの魅力的な随筆文学である。昭和期戦前では,ほかに青野季吉,大宅壮一,柳田国男,辰野隆,森田たまらがあり,戦後は言論の自由,出版機構の隆盛につれて,高田保,河盛好蔵,池田潔,小堀杏奴(あんぬ),萩原葉子ら各層の人々の中から優れた書き手が現れている。多様化する社会的動向にそって,特定の形式・約束に縛られぬ自由な表現形式が機能を発揮しているわけである。
の《百鬼園随筆》ほか,寺田寅彦の科学随筆も一つの魅力的な随筆文学である。昭和期戦前では,ほかに青野季吉,大宅壮一,柳田国男,辰野隆,森田たまらがあり,戦後は言論の自由,出版機構の隆盛につれて,高田保,河盛好蔵,池田潔,小堀杏奴(あんぬ),萩原葉子ら各層の人々の中から優れた書き手が現れている。多様化する社会的動向にそって,特定の形式・約束に縛られぬ自由な表現形式が機能を発揮しているわけである。
近代以降,西欧の文学に定着しているエッセーのジャンルは,中国には20世紀になってから紹介されたのであるが,それはまだ中国の文学風土に根付いてはいない。モンテーニュやF.ベーコンが中国には出なかったからだとは言えても,しかしそれでは西欧的規準による裁断でしかない。確かに中国にはエッセーと呼ぶにふさわしい作品はきわめて少ないし,〈随筆〉と名のつく代表的な書《容斎随筆》でさえ,その内容は学問的考証で占められている。古来,雑記,雑説,雑録,雑志,雑識とか,漫録,漫筆,漫志,漫抄とか,筆記,筆談,筆乗,叢談,野語,間話などと銘打った,一般に〈筆記小説〉と総称されるものは,大部分は古今の瑣細な事がらや見聞の記録と読書余録的な記述と考証で占められ,著者自身による人生観照や文明批評が語られることは稀である。しかし中国人にとっては,こういう個々の事実や経験の記録そのものが,いわば随筆として享受されたのであり,現在でもそうである。人間内奥の消息や人間性への省察などは,別に詩や文または書簡で開陳された。いわゆる日記文学の中国における未成熟も同様な事情による。ただ明代末期に流行した〈小品文〉(随想類の短い文章)のなかには,まさにエッセーと呼ぶにふさわしい上質の文章が独自な文体で定着しており,中国文学史に新しいページを拓いている。この伝統と近代西欧の教養とを一つに体現した随筆家はただ周作人(しゆうさくじん)だけであった。
→エッセー

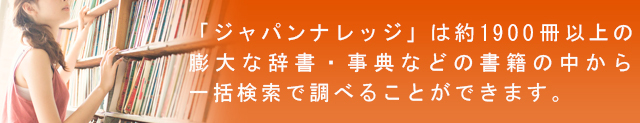
 園随筆
園随筆 園は徂徠の別号。1709年(宝永6)門人の手で編集開始、1713年(正徳3)近 ...
園は徂徠の別号。1709年(宝永6)門人の手で編集開始、1713年(正徳3)近 ... 園随筆】
園随筆】 園随筆】
園随筆】 古典版画東洲斎/画像提供 ...
古典版画東洲斎/画像提供 ... による随筆集。昭和8年(1933)刊行。ユーモアを交えつつ、師である夏目漱石の思い出や、自身の借金にまつわるエピソードなど ...
による随筆集。昭和8年(1933)刊行。ユーモアを交えつつ、師である夏目漱石の思い出や、自身の借金にまつわるエピソードなど ...




©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.