
主として平安時代前期に,数回にわたり宮廷で公式の行事として行われた《日本書紀》の講読・研究の会。《釈日本紀》開題に引く〈康保二年外記勘申〉によれば,養老5年(721),弘仁3-4年(812-813),承和10-11年(843-844),元慶2-5年(878-881),延喜4-6年(904-906),承平6-天慶6年(936-943),および康保2年(965)以後に行われたが,そのうち養老度は完成した《書紀》の披露のためとみられ,弘仁以後が講究を主とするもので,元慶度に至って形式・内容ともにほぼ完成の域に達し,承平度から熱意が薄れて衰退に向かった。盛時の形態は,《書紀》に詳しい学識者を博士,都講,尚復などに任命し,ふつう2,3年にわたって外記曹局,内史局,宜陽殿東廂などで頻繁に集会が持たれ,太政大臣以下多くの公卿・官人が出席して,博士の講義を中心に活発な議論が行われた。全30巻の講究が終了すると,元慶,延喜,承平のときには,侍従所に大臣以下が参集して,盛大な竟宴(きようえん)(講書終了時に催す酒宴)が行われた。宴席では,《書紀》中の聖徳帝王,有名諸臣を題として各自が和歌を作り,その詠歌の声に応じて大歌御琴師が倭琴を弾じ,終わって博士,尚復らが禄を賜って退出した。そのときの和歌は《日本紀竟宴和歌》として,延喜,承平度のものがよく残っている。
講筵はほぼ30年間隔で開かれていて,宮廷の人々がみな一生に一度はこれに触れる機会があるように配慮されていたごとくであり,博士はふつう前回に尚復などを務めた者の中から任命され,前後の講究の一貫性も重視されていたようである。博士が講義に当たって作成した覚書を《日本紀私記》といい,単に《書紀》の本文の語句に訓注を施したものと,講席における問答を逐次筆録したものとがあるが,今日いわゆる甲乙丙丁4種の不完全な《私記》の伝本があって《国史大系》に収められ,ほかに《釈日本紀》《和名抄》その他に数多くの逸文がある。甲本,丁本はそれぞれ弘仁,承平度のもので,その他はみな年次の推定が困難であるが,それらを通じてみると,《書紀》本文の定訓を確立し,それによって《書紀》の漢文的記述のもとになった和文による古伝承の姿を復元することに,一貫した努力が払われていたことがうかがわれる。

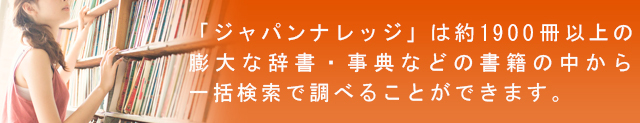










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.