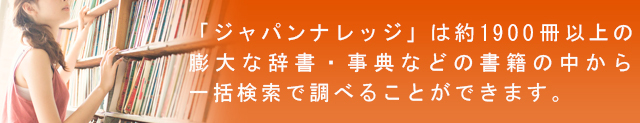1. アヘン戦争
日本大百科全書
ぶざまな敗戦による清朝の権威の失墜とが相まって、やがて太平天国の大動乱を引き起こす要因となった。 アヘン戦争前まで、日本の武士の多くは、中国を文化の源流であり、
2. アヘン戦争画像
世界大百科事典
ておらず,それぞれが事態の打開に動くなかでイギリスはついに武力による解決を図った。総じて,アヘン戦争は,アヘン貿易の歴史的性格がもたらした帰結であったばかりでな
3. アヘンせんそう【アヘン戦争】
国史大辞典
Costin:Great Britain and China,1833―1860(1937).矢野仁一『アヘン戦争と香港』 (佐々木 正哉)
4. 第2次アヘン戦争
世界大百科事典
受けた結果,半植民地への道を強いられていくが,第2次アヘン戦争はまさにその道程を決定づけたものといえよう。→アヘン戦争浜下 武志 アヘン戦争 アロー戦争 アロー
5. あいしんかくらえきちょ【愛新覚羅弈詝】(Àixīnjuéluó Yìzhù)
世界人名大辞典
正式に軍権を与え,湘軍が太平天国に対抗する主力部隊となる.他方,アロー号事件を契機に第2次アヘン戦争が勃発[56],天津条約によって一旦収束する[58]も,大沽
6. あいしんかくらびんねい【愛新覚羅旻寧】(Àixīnjuéluó Mínníng)
世界人名大辞典
を欽差大臣として広州に派遣しアヘン問題の解決を命じる[39]が,イギリスとの対立を惹起し,アヘン戦争が発生[40],敗戦が続くと林則徐を罷免[同].英軍が長江下
7. いしょうこう【韋紹光】(Wéi Shàoguāng)
世界人名大辞典
別名:進可〔†1901[光緒27]〕 中国清代の義兵.広東省南海県三元里(現,広州市)の貧農.アヘン戦争時,イギリス軍の三元里侵攻[1841:道光21]に際し,
8. いりふ【伊里布】(Yīlǐbù)
世界人名大辞典
3.5[道光23.2.5]〕 中国清代の宗室,官僚.鑲黄旗満洲人.進士[1801:嘉慶6].アヘン戦争時,欽差大臣として浙江に赴いたが,イギリス軍と妥協して停戦
9. えききん【奕訴】(Yìxīn)
世界人名大辞典
人.兄の愛新覚羅奕詝(えきちょ)が咸豊(かんぽう)帝に即位すると恭親王に封ぜられた.第2次アヘン戦争で英仏連合軍が北京に迫り[1860:咸豊10],咸豊帝が熱河
10. えきけい【奕経】(Yìjīng)
世界人名大辞典
官僚.満洲鑲紅旗人.吏部尚書,協弁大学士を兼ね[1841:道光21],揚威将軍に任ぜられ,アヘン戦争で奪われた浙江の定海,鎮海の回復を試みたが大敗.寧波奪回と虚
11. えきざん【奕山】(Yìshān)
世界人名大辞典
中国清末の皇族,軍人.鑲藍旗満洲人.道光帝の甥,侍衛出身.伊犁(イリ)参賛大臣,伊犁将軍などを歴任.アヘン戦争時,靖逆将軍として広州に赴任[1841:道光21]
12. おうしゃくほう【王錫朋】(Wáng Xīpéng)
世界人名大辞典
津市)の人.武挙出身.福建汀州鎮総兵[1833:道光13],安徽寿春鎮総兵[38]を歴任.アヘン戦争開戦後,陳化成とともに呉淞(上海市)の防備にあたる[40].
13. おうとくろく【王得禄】(Wáng Délù)
世界人名大辞典
と,義勇兵を招募し平定に協力したため太子少保を,後には太子太保の官銜を授けられた[36].アヘン戦争時,澎湖諸島に駐屯したが病気で陣没.〖文献〗 清史列伝39.
14. かいれい【海齢】(Hǎilíng)
世界人名大辞典
満洲人.西安,江寧の副都統を経て,京口(現,江蘇鎮江)副都統となる[1841:道光21].アヘン戦争でイギリス軍が鎮江に進攻すると,旗兵・青州兵を率いて防戦.奮
15. かつうんひ【葛雲飛】(Gě Yúnfēi)
世界人名大辞典
1[道光21.8.17]〕 中国清代,アヘン戦争時の武官.浙江山陰(現,紹興)の人,武進士[1823:道光3].浙江定海鎮総兵に任じられる[39]も,辞して帰郷
16. かんてんばい【関天培】(Guān Tiānpéi)
世界人名大辞典
字:仲因 号:滋圃〔1781[乾隆46]~1841.2.26[道光21.2.6]〕 中国清代,アヘン戦争時の武官.江蘇山陽(現,淮安)の人,太湖営水師副将,蘇松
17. がんこうちょう【顔浩長】(Yán Hàocháng)
世界人名大辞典
中国清末の広東での反英運動指導者.広東番禺(現,広州市)の貧農.武芸を習い,定拳長のあだ名もある.アヘン戦争中の広州三元里で,平英団を旗印にした武装自衛組織と英
18. がんはくとう【顔伯燾】(Yán Bótāo)
世界人名大辞典
〕 中国清代の官僚.広東連平の人.嘉慶年間[1796-1820]の進士.巡撫,総督を歴任.アヘン戦争中の41年[道光21]に閩浙(びんせつ)総督となると積極的に
19. きえい【耆英】(Qíyīng)
世界人名大辞典
29:道光9],工部尚書[34],戸部尚書を歴任,一時降格されたが盛京将軍となり[38],アヘン戦争が始まるとアヘン取締りと沿岸防備に努めた.欽差大臣[42]と
20. きぜん【琦善】(Qíshàn)
世界人名大辞典
],以後,山東巡撫,両江総督,四川総督等を歴任して直隷総督[31-41:道光11-21].アヘン戦争が始まると,イギリス軍の北上に備えて天津の海防を督励していた
21. きょうしゅうらん【姜秀鑾】(Jiāng Xiùluán)
世界人名大辞典
山区へ進駐,開墾を行い,隘寮(見張り小屋)を設け,原住民の侵入を防いで,巨万の富を築いた.アヘン戦争が起こると,兵を率いて鶏籠で防御に当たり,英国船を撃沈,英軍
22. きょうしんりん【龔振麟】(Gōng Zhènlín)
世界人名大辞典
中国清代の造船,鋳砲技師.江蘇長洲(現,江蘇蘇州)の人.浙江省で県丞に在職時,アヘン戦争に遭い,軍艦建造に携わる.林則徐(りんそくじょ)の下で新式砲車も開発.
23. ぎげん【魏源】(Wèi Yuán)
世界人名大辞典
の間に両江総督陶澍(とうじゅ)の幕友として,大きな成果をあげた淮北の塩政改革にも関与した.アヘン戦争末期に両江総督裕謙の幕友になり,イギリス軍の攻撃に対抗する画
24. ごすうよう【伍崇曜】(Wǔ Chóngyào)
世界人名大辞典
東十三行の中で最も富裕な怡和行を継承[1833:道光13].清朝政府と外国勢力の間に立ち,アヘン戦争・アロー号戦争時期の政治・外交に深く関与した.また蔵書・刻書
25. じょけいよ【徐継畬】(Xú Jìyú)
世界人名大辞典
建で按察使,布政使,巡撫等を歴任.晩年は同文館に勤務した.職務上西洋人との交流が多く,またアヘン戦争に衝撃を受け,世界のことを知るために世界地理書《瀛環志略》を
26. せんこう【銭江】(Qián Jiāng)
世界人名大辞典
東屏〔1800[嘉慶5]~53[咸豊3]〕 中国の釐金(りきん)制度の創案者.浙江長興の人.監生.アヘン戦争後,何大庚とともに《全粤義士義民公檄》を発し[184
27. そうきん【曹謹】(Cáo Jǐn)
世界人名大辞典
1853)はその功績を称え〈曹公圳〉と命名した[38].その後,淡水同知に転任し[41],アヘン戦争では鶏籠(基隆市)と大安(台中市)でイギリス軍を防いだが,病
28. そうこくはん【曽国藩】(Zēng Guófān)
世界人名大辞典
守るための決起と意義づけ,団練への参加を呼びかけている.団練はこうして拡充され湘軍に発展した.第2次アヘン戦争が起こり[56],窮地に立った清朝はこれら漢人の団
29. たつこうあ【達洪阿】(Dáhóng'ā)
世界人名大辞典
〕 中国清の軍人.富察氏の出自.満洲鑲黄の旗人.台湾鎮総兵に着任[1835:道光15]後,アヘン戦争では台湾道姚瑩(ようえい)と共に台湾へ進攻した英軍を防いだ[
30. たんえい【譚瑩】(Tán Yíng)
世界人名大辞典
長く務めた.また地域社会を代表する知識人として,粤秀書院・越華書院などの監院(理事)を歴任し,アヘン戦争後の広州入城問題では政治的にも指導的役割を果たした.広東
31. ちょういへい【張維屏】(Zhāng Wéipíng)
世界人名大辞典
袁州同知,南康知府等を歴任したのち広東に家居した[36].その詩論は性情を主としたもので,アヘン戦争時の《三元里歌》《三将軍歌》等,国難を憂えた詩で有名.黄培芳
32. ちんかせい【陳化成】(Chén Huàchéng)
世界人名大辞典
16[道光22.5.8]〕 中国清代の軍人.福建同安(現,廈門(アモイ))の人.行伍(兵士)出身.アヘン戦争時,福建水師提督としてイギリス艦隊に打撃を与え,江南
33. ていこくこう【鄭国鴻】(Zhèng Guóhóng)
世界人名大辞典
道光21]〕 中国清代の軍人.湖南鳳凰の人.浙江省処州鎮総兵となる[1840:道光20].アヘン戦争時,処州の兵を率い,定海鎮総兵葛雲飛(かつうんひ),寿春鎮総
34. ていしゅそん【丁守存】(Dīng Shǒucún)
世界人名大辞典
頃〕 中国清代の官僚,化学者,機械製造技師.山東日照の人.進士及第[1835:道光15].アヘン戦争時に船砲を製作,以後,天津,広西,山東で新式火器の製造に従事
35. とうていてい【鄧廷楨】(Dèng Tíngzhēn)
世界人名大辞典
が派遣され,林ととともにアヘン厳禁を推進した.その後,閩浙総督に転じ,福建の海防に努めた.アヘン戦争の戦況不利のなか,林とともにイリに流されたが,後に赦されて官
36. はんせいおん【潘世恩】(Pān Shì'ēn)
世界人名大辞典
歴任した.道光年間[1821-50]には体仁閣大学士に至り[33:道光13],軍機大臣を兼任した[34].アヘン戦争が勃発すると,林則徐を支持し,広東に赴いて禁
37. ばいせいきょう【貝青喬】(Bèi Qīngqiáo)
世界人名大辞典
木居士〔1810[嘉慶15]~63[同治2]〕 中国清代後期の詩人.呉県(現,江蘇蘇州)の人.諸生.アヘン戦争期,浙東でイギリス軍と戦う揚威将軍奕経(えきけい)
38. へきしょう【壁昌】(Bìchāng)
世界人名大辞典
国からの侵入勢力の排除にあたった.両江総督となり[43],海軍兵力の増強や砲台の増設など,アヘン戦争後の対外防衛体制の整備に尽力した.〖主著〗 葉爾羌守城紀略,
39. ゆうけん【裕謙】(Yùqiān)
世界人名大辞典
22].湖北各地の知府のあと江蘇で按察使,布政使を歴任し,江蘇巡撫[39:道光19].翌年アヘン戦争が起こり,舟山群島の定海が占領され,その奪回のため両江総督伊
40. ようえい【姚瑩】(Yáo Yíng)
世界人名大辞典
中国清代の文学者.桐城(現,安徽桐城)の人.進士となる[1808:嘉慶13].台湾兵備道に在職中,アヘン戦争が勃発,台湾に侵入した英国船を撃沈する[41:道光2
41. ようしょう【姚燮】(Yáo Xiè)
世界人名大辞典
文,絵画に優れた.挙人となる[1834:道光14]が,会試で挫折し,文章や絵を売って暮らす.アヘン戦争中の疎開等で郷里をたびたび離れ,潘徳輿,魏源,王韜(おうと
42. りくすう【陸嵩】(Lù Sōng)
世界人名大辞典
学金を給付される者)から,鎮江府学訓導に至る[1838:道光18].郷勇(義勇兵)を募り,アヘン戦争時の英軍侵攻[42]や太平天国の攻撃[53:咸豊3]との戦い
43. りせいげん【李星沅】(Lǐ Xīngyuán)
世界人名大辞典
撫,陝甘総督,江蘇巡撫,雲貴総督などを歴任し,官は両江総督に至った[47].アヘンの禁止やアヘン戦争におけるイギリスへの抵抗で知られる.咸豊(かんぽう)帝の即位
44. りょうていなん【梁廷枏】(Liáng Tíngnán)
世界人名大辞典
歴任し,当局から委嘱を受けて,《広東海防彙覧, 1835》《粤海関志, 1837》の編纂の任にもあたった.アヘン戦争を中心に揺れた広州の政治に深く関わり,欽差大
45. りんしょうい【林昌彝】(Lín Chāngyí)
世界人名大辞典
19],各地を巡る.《小石渠閣文集》《衣讔山房詩集》《海天琴思録》《射鷹楼詩話》等の著作でアヘン戦争を痛憤した.〖文献〗 清史列伝73.〖参考〗 林淑貞:詩話別
46. りんそくじょ【林則徐】(Lín Zéxú)
世界人名大辞典
にアヘンの引き渡しを命じ,強硬手段によって大量のアヘンを押収し処分した.反発したイギリスがアヘン戦争をしかけると,恐慌をきたした清廷によって解任され,新疆に左遷
47. ろいつどう【魯一同】(Lǔ Yītóng)
世界人名大辞典
徐や曽国藩に認められるが,会試には及第できなかった.潘徳輿に詩歌を学び,また古文に秀でた.アヘン戦争や太平天国の乱が続く時勢に対して一家言をもち,それらを論じた
48. 璦琿条約
世界大百科事典
両国の共有地とされた。極東進出をめざす東シベリア総督ムラビヨフは,清が太平天国の乱と第2次アヘン戦争に苦しむのに乗じてこの条約を認めさせた。のち清は条約を否認し
49. 上知令
世界大百科事典
除く諸大名,旗本に命じられた。“最寄り”の範囲は,およそ両城の10里四方と考えられる。その目的は,アヘン戦争に伴う対外的危機への対応を直接的契機とした江戸,大坂
50. アジア画像
日本大百科全書
)、アフガニスタン、イラン、トルコなども、相次いで西欧列強の植民地、従属国となった。中国もアヘン戦争(1840~1842)での敗北を契機に半植民地化の道をたどり
 善と広東で交渉を行い、ついに武力を行使して広東省城まで制圧したが、結局条約の締結に失敗したため、イギリス政府はあらためてヘンリー=ポティンジャーを全権に任命した。ポティンジャーは一八四一年七月から厦門・舟山・寧波を占領し、翌四二年に乍浦・上海・鎮江を攻略して南京に迫ったので、清朝はついに屈服して八月二十九日南京条約を締結し、香港の割譲、広州・福州・厦門・寧波・上海の開港、林則徐が没収したアヘン代価六〇〇万ドルの補償、軍事費一二〇〇万ドルの賠償、両国官吏の対等な交渉権などを承認して和を講じた。この後さらに五港通商章程、虎門寨追加条約が追加され、領事裁判権、最恵国待遇条款、関税・国内通過税に関する協定など中国に不利な条項が一層明確に規定され、中国と列国との不平等関係の発端になった。なおイギリスにならってアメリカ・フランス両国も一八四四年に大体南京条約に近い内容の新条約を締結した。
善と広東で交渉を行い、ついに武力を行使して広東省城まで制圧したが、結局条約の締結に失敗したため、イギリス政府はあらためてヘンリー=ポティンジャーを全権に任命した。ポティンジャーは一八四一年七月から厦門・舟山・寧波を占領し、翌四二年に乍浦・上海・鎮江を攻略して南京に迫ったので、清朝はついに屈服して八月二十九日南京条約を締結し、香港の割譲、広州・福州・厦門・寧波・上海の開港、林則徐が没収したアヘン代価六〇〇万ドルの補償、軍事費一二〇〇万ドルの賠償、両国官吏の対等な交渉権などを承認して和を講じた。この後さらに五港通商章程、虎門寨追加条約が追加され、領事裁判権、最恵国待遇条款、関税・国内通過税に関する協定など中国に不利な条項が一層明確に規定され、中国と列国との不平等関係の発端になった。なおイギリスにならってアメリカ・フランス両国も一八四四年に大体南京条約に近い内容の新条約を締結した。