
《同》遺伝因子(genetic factor).遺伝形質を規定する因子.メンデルの法則における基本概念として各遺伝形質(単位形質)に対応して想定され,G.J.Mendelはこれを因子と呼んだが,のちにW.L.Johannsen(1909)が遺伝子(gene)と呼ぶことを提案し,この語が定着した.遺伝子は自己増殖し(⇒複製),細胞世代,個体世代を通じて親から子に継代的に正確に受けつがれ,形質発現に必要な遺伝情報を伝達する.各々の遺伝子は互いに独立の単位であるが,物理的に独立して存在しているのではなく,染色体上にそれぞれ固有の位置を占め,一般には線状に配列して連鎖群を形成している(⇒染色体地図).遺伝子は安定なものであるが突然変異や遺伝的組換えによって変化することがあり,以後の世代には変化した遺伝子が伝達されることになる.古典遺伝学的には,ある形質(野生型)に対する突然変異型の存在によって,はじめてその形質に対する遺伝子が認識され染色体上の位置が決定される.二つの異なった突然変異型遺伝子が同一の遺伝子に由来するものかどうかは,シス-トランス位置効果を利用した相補性検定によって判定される.この方法で検出されるのは機能的単位としての遺伝子であって,シストロンと呼ばれる.遺伝的組換えの有無を判定の規準とすれば,シストロンはさらに小さな単位に細分される(⇒偽対立遺伝子).遺伝子の本体はDNA(一部のウイルスではRNA)であり,そのヌクレオチド配列によって個々の遺伝子が規定される.すなわち遺伝子とは核酸分子上のある長さをもった特定の領域(ドメインdomain)を指すことになる.原核生物の場合,例えば,ある蛋白質に対する遺伝子とはその蛋白質の一次構造(アミノ酸配列)に対応するヌクレオチド配列を指し,翻訳の際の開始点と終止点とにはさまれた部分をいう(⇒蛋白質生合成).その長さは,アミノ酸1個に,連続する3個のヌクレオチドが対応するため(⇒遺伝暗号),蛋白質の分子量に応じて通常数百~数千ヌクレオチド程度のものである.これに対し真核生物の多くの遺伝子では,最終的に蛋白質として翻訳されるヌクレオチド配列が,翻訳されない配列(⇒イントロン)によって分断されており,それらの部分は転写されたRNAの段階で除去される(⇒スプライシング).したがってこれらの遺伝子では,蛋白質の分子量に対応する長さよりも,その分だけ長くなっていることになる.遺伝子にはリボソームRNA(rRNA),トランスファーRNA(tRNA)などのように,転写産物(またはその一部)であるRNA自体が形質となるようなものもある.蛋白質やrRNA,tRNAなどの一次構造を規定している遺伝子を特に構造遺伝子(structural gene)と呼び,一般的に遺伝子というときには構造遺伝子を指す場合が多い.他方DNA(分子)を構成するヌクレオチド配列には,制御領域と呼ばれる特定の配列も存在する.例えばプロモーターやオペレーター,エンハンサーなどのように,転写や翻訳によって機能が発現されるのではなく,特定のヌクレオチド配列そのものが核酸上の特定の部位を指定しているものもあり,ある蛋白質と特異的に結合することなどによって,形質発現や複製などの制御,調節に重要な役割を果たすと考えられている.これらも広義の遺伝子に含めることができる.
遺伝形質を規定する因子。
G.J.メンデル(1865)はエンドウの子葉の色の緑と黄というような対立的な形質を支配する遺伝因子として対立する要素を想定し,両親由来のこのような対立要素,例えばAとa,をもつ雑種が配偶子を形成するとき,Aとaが分かれて別々の配偶子に入り,これが子どもに伝えられてその形質を規定すると考えた。1900年のメンデルの遺伝法則の再発見以降,多くの生物でこのような対立形質の遺伝様式が盛んに研究されるようになり,それぞれの形質に対応してそれを規定する仮想的な遺伝因子が設定されてきた。このような遺伝因子はメンデル因子,または単に因子とよばれていたが,W.L.ヨハンセン(1909)の提案した遺伝子という語がしだいにこれにとって代わるようになった。
サットンW.S.Sutton(1902)らはいち早く成熟分裂における染色体の行動がメンデル因子の行動と一致することを明らかにしたが,さらに,1910年に始まるT.H.モーガンらのキイロショウジョウバエの研究により,遺伝子は染色体に線状に配列して連鎖群を形成しており,一つの遺伝子は特定の染色体の特定の部位を占めていることがわかった。このような研究により,それまで仮想的な存在であった遺伝子が物質的基礎をもつことになり,その構造と機能を物質的に研究する道が開けた。
英語の〈gene〉に対し,日本で〈遺伝子〉という語をあてるようになったのは1936-37年ごろである。1936年に編まれた《遺伝学用語》第1輯ではgeneに対し〈遺伝因子〉が,genotypeやgeneanalysisに対しては〈遺伝子型〉や〈遺伝子分析〉があてられている。そして,37年の田中義麿著の《遺伝学》再版で初めてgeneに対し〈遺伝因子〉〈ゲン〉と並んで〈遺伝子〉が登場し,同年の井上頼数の論文に〈易変遺伝子〉の語が現れる。この時期より古い著書・論文では〈遺伝単位〉〈遺伝因子〉〈因子〉〈ゲン〉〈ジーン〉が用いられており,〈遺伝子〉は見あたらない。
1940年代に入り,ビードルG.W.BeadleとテータムE.L.Tatum(1941)らはアカパンカビの栄養要求性の遺伝を研究し,生体内における物質の生合成経路の各段階がそれぞれ固有の遺伝子に支配されていることを知った。すでに,生化学的研究により生合成経路の個々の過程が酵素に触媒されていることがわかっていたので,ビードルはこれらの知見を総合して一遺伝子一酵素説を立てた。こうして,遺伝子が直接支配するのは特定酵素の生産であり,この酵素を媒介にして遺伝子が生合成産物を支配するものと考えられるようになった。その後,酵素はもちろんのこと,酵素以外のタンパク質の生産も遺伝子の直接的支配下にあること,およびタンパク質の多くは複数の同種あるいは異種ポリペプチドからなることがわかってきたため,一遺伝子一酵素説は一遺伝子一ポリペプチド説に修正・拡張されることになった(ハルトマンP.E.Hartman,1965)。
一方,ベリングJ.Belling(1928)らにより太糸期染色体が染色小粒とそれをつなぐ糸状部分からなる数珠状構造を示すこと,およびC.B.ブリッジズ(1935)らにより唾腺(だせん)染色体が染色性の高い横縞部分と染色性の低い介在部分からなることが明らかにされ,染色小粒や横縞が遺伝子に対応するという考えが生まれた。この考えは偽対立遺伝子の組換えや遺伝子の突然変異機構の研究成果をふまえ,遺伝子は機能(すなわち形質の支配)・組換え・突然変異という三つの現象に共通な基本単位であるとするグリーンM.M.Green(1955)らの《遺伝子の統一概念》へと発展した。
しかし,バクテリアやウイルスが研究材料に登場するに及び,これまで検出不能であったごく低頻度の組換え体の検出が可能となった。そして,ベンザーS.Benzer(1957)らにより,交叉(こうさ)部位や突然変異部位は一つの遺伝子が占める染色体上の領域内に多数存在することが明らかにされ,究極的には単一のヌクレオチド対が交叉や突然変異の単位であることが推定されるに至った。同じことは高等動植物の若干の遺伝子についても証明されてきた。一方,遺伝子の本体がDNAであることが確実になり,バクテリアやウイルスでは一つのゲノムの全遺伝子が単一のDNA分子に組み込まれていること,また,高等動植物においても電子顕微鏡で確認できるかぎりでは,1本の染色体に含まれるDNAは連続した1本の糸であることもわかり,遺伝子の統一概念は自然に消滅した。
1950年代以降の分子遺伝学の発達により,まず,遺伝子の本体とポリペプチドの生産を支配する機構の概要が明らかとなった。ほとんどの生物では二重鎖のDNA(一部のウイルスでは1本鎖のDNAや二重鎖あるいは1本鎖のRNA)が遺伝子の本体をなしており,個々の遺伝子の特異性はそれを構成する4種類のヌクレオチド対の数と配列順序によって決められる。二重鎖DNAの転写によりRNAがつくられるが,この際,2本のDNA鎖のうち1本の鎖における4種類のヌクレオチド,すなわち,デオキシアデニル酸(Aで表す),デオキシグアニル酸(G),デオキシチミジル酸(T),デオキシシチジル酸(C)の配列順序に従ってRNAにおける4種類のヌクレオチド,すなわち,アデニル酸(A),グアニル酸(G),ウリジル酸(U),シチジル酸(C)の配列順序が決まる。転写されるDNA鎖のA,G,T,Cに対応してRNA鎖にU,C,A,Gが配位される。
RNAは機能的に3種に分かれる。タンパク質とともにリボソームを構成するリボソームRNA(rRNAで表す),リボソームへアミノ酸を運ぶ転移RNA(tRNA),およびポリペプチドの一次構造,すなわちアミノ酸配列を規定するメッセンジャーRNA(mRNA)である。mRNAに転写された遺伝情報,すなわちそのヌクレオチド配列がポリペプチドの一次構造に変換される過程を翻訳という。このとき,mRNAを構成するヌクレオチドの三つずつが一組になってポリペプチド鎖の一つ一つの位置に入るアミノ酸の種類を規定してゆく。このヌクレオチドのトリプレットには43,すなわち64の種類がある。個々のトリプレットとポリペプチドに含まれる20種類のアミノ酸との対応関係を遺伝暗号とよぶが,これはニーレンバーグM.W.Nirenberg(1966)らの研究によって完全に解読された。64のトリプレットのうち三つはどのアミノ酸にも対応しない。これらはナンセンスコドンとよばれ,翻訳において終止符の役をする。単一のmRNA分子の翻訳により,単一または複数のポリペプチドがつくられる。生産されるポリペプチドの数はmRNA分子に含まれるナンセンスコドンの数で決まる。mRNAを介して個々のポリペプチドに対応する二重鎖DNAの領域が,一遺伝子一ポリペプチド説にいうところの遺伝子である。このカテゴリーの遺伝子をシストロンまたは構造遺伝子とよぶ。これはポリペプチドの一次構造を決定する遺伝子という意味である。これに対し,転写によって個々のrRNA分子やtRNA分子をつくるDNA領域をrRNA遺伝子やtRNA遺伝子といい,これらがつくるRNAは翻訳されることがない。
遺伝子の本体や作用機構に関する研究と並んで,その作用の調節機構も研究されるようになった。F.ジャコブとJ.モノー(1961)らの研究から構造遺伝子の作用は作働遺伝子や促進遺伝子の働きにより調節されていることがわかってきた。大腸菌のLac遺伝子の場合,その作働遺伝子は他の構造遺伝子が生産するタンパク性抑制物質の結合部位であり,促進遺伝子は転写をつかさどるRNAポリメラーゼの結合部位である。ここに,遺伝子作用の調節に直接関与する種々の物質の結合部位を構成しているDNA領域が新しいカテゴリーの遺伝子として浮かび上がってきた。
その後,転写中のDNA分子や,DNA・DNAあるいはDNA・RNA分子雑種の電子顕微鏡による直接的観察法の確立,およびmRNAの逆転写によるcpDNAの調製,DNAのクローン化,そのヌクレオチド配列の決定などに関する技術的進歩により,真核生物の遺伝子の構造や作用発現について多くの新知見が加わった。遺伝子と遺伝子の間には,スペーサーとかサイレントDNAとよばれる転写されないDNA領域がふつう存在する。その一部はヌクレオチド配列からみて,現在も活動中の遺伝子と起源を同じくする遺伝子の残骸とみなされ,偽遺伝子とよばれる。また,一つの遺伝子の領域内に,転写に先立ってDNA分子内組換えによって除去されてしまうDNA部分や,翻訳に先立ってRNA分子から除去されるRNA部分に対応するDNA部分が存在することもわかった。構造遺伝子の領域内にあって翻訳に関与しないこのようなDNA部分をイントロンintronまたは介在配列とよぶ。これに対し,翻訳にあずかるDNA部分をエクソンexonという。真核生物の構造遺伝子はふつう複数のエクソンとイントロンがモザイク状に配列したものであり,イントロンを包含しない原核生物の遺伝子とは内部構造が異なっている。
このように多様な構造と機能を考慮するとき,遺伝子の包括的定義としては〈DNA(RNAウイルスにあってはRNA)分子中の,遺伝的になんらか固有の意味をもつ,決まった長さのヌクレオチド配列〉とするのが適当と考えられる。ここにいう“遺伝的な意味”は主として機能的なものであり,RNAやポリペプチドの構造を規定したり,遺伝情報の発現・調節に関与する種々の分子の結合や離脱部位を構成したりすることであるが,偽遺伝子の場合のように,その起源を示唆する歴史的な意味も包含する。
遺伝子はその細胞内の所在する場所により,核内遺伝子,染色体遺伝子,染色体外遺伝子,細胞質遺伝子,葉緑体遺伝子,ミトコンドリア遺伝子などに分類される。核内遺伝子と染色体遺伝子,染色体外遺伝子と細胞質遺伝子は同義である。葉緑体遺伝子とミトコンドリア遺伝子はともに細胞質遺伝子に含まれる。これらの遺伝子の間にはその構造や機能に関して本質的な差がない。しかし,染色体と細胞小器官(オルガネラ)DNAの間には次代への伝達様式に差があり,核内遺伝子はメンデルの遺伝法則にのっとって遺伝するが,細胞質遺伝子の伝達はこれに従わない(細胞質遺伝)。遺伝子はまた,その効果の表れ方により主働遺伝子,微働遺伝子,致死遺伝子,ポリジーンなどに分類される。

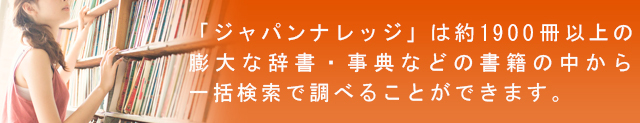
 タ
タ ー
ー [ギ]
[ギ]









©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.