
地質時代に生存していた生物,すなわち古生物(paleobios)の構造,分類上の位置,類縁関係,系統関係,生息環境,生活様式,地理的分布,生存期間など,あらゆる問題を考究し,それによって生物界変遷の様式を明らかにすると同時に地球表層環境と生命の相互作用の歴史を探る科学.古生物学は現生生物学(neontology)と対応する.また,層位学(層序学stratigraphy,⇒生層位学),解剖学,進化学などとは特に密接な関係にある.古生物学はその研究対象から古植物学(paleobotany)と古動物学(paleozoology)に分けられることがある.古動物学はさらに古無脊椎動物学(invertebrate paleozoology)と古脊椎動物学(vertebrate paleozoology)の2分野に大別されるのが一般的である.化石人類の研究に対しては,古人類学(paleoanthropology)の語がある.その他,糞の化石すなわち糞石を研究する化石糞学(coprology)や,足跡の化石(ichnite)を研究する化石足痕学(ichnology)のように,生痕化石を対象とする分科もある.古生物を生物学の立場から研究する学問を純古生物学(paleobiology)と呼び,生態,発生,遺伝,進化などを対象とする.(⇒微古生物学,⇒古生態学)
古生物を研究する科学。生物を扱う点では生物学の一分野であるが,化石を直接対象として地質時代の生物現象を研究する点では地球の歴史科学である。化石に人間が関心を抱き始めた時代を特定することはできないが,少なくともクロマニョン人の遺跡から貝化石で作った首飾が出土していることで,その古さがわかる。化石に関する記述は前7世紀ころのギリシアの学者らが行っており,その生物起源であるという本質をすでに見抜いていた。中国では11世紀の沈括や12世紀の朱熹が化石の成因について記述しているが,西欧世界に思想的影響を及ぼさずに終わった。西欧で化石について知的関心の高まるのはルネサンス時代に入ってからである。しかし当時,化石は発掘物一般を意味し,生物起源・非生物起源の区別はなかった。レオナルド・ダ・ビンチのような学者が何人か化石の一部は古生物の遺物であると述べているにすぎない。16世紀ころはC.vonゲスナー(1516-65)が《発掘物について》という著書で現代的意味での化石を多く扱っているとはいえ,化石についての議論はその石状物質の説明や形状が他のどんなものに類似しているかを論ずることなどに終始していた。17世紀に入り,化石の成因が論議を呼ぶようになり,生物起源と非生物起源の化石の区別が大いに論じられた。とはいえ,当時の学者はキリスト教の教義の枠からはみ出ることはなかったので,神の創造による生物の化石は天地創造とノアの洪水から始まる伝統的歴史年表の中に位置づけられた。18世紀になると,博物学者らによってこのような宇宙開闢(かいびやく)説cosmogonyに磨きがかけられる一方,化石の優れた写生図を伴った体系的分類が進められ,古生物学への下地を作った。18世紀の博物学者らは化石とそれを含む地層の岩質との対応関係をおおまかに知っていたが,W.スミス(1769-1839)によって生層位学(化石層位学)の方法が確立され,広域の地層対比のための化石の価値が明らかにされた。さらに重要な理論的貢献をしたのはG.キュビエ(1769-1832)で,彼は比較解剖学を創始して脊椎動物化石を研究した。彼の《化石骨の研究》(1812)は化石復元のモデル的研究である。彼はまた過去において地球生物の遭遇した〈革命〉を論じ,いわゆる〈天変地異説catastrophism〉を唱えた。これに対して,無脊椎動物化石研究の端緒を作ったJ.B.deラマルク(1744-1829)が反論し,今日の進化論につながる見解を発表した。この論争自体はキュビエの勝利に終わったが,天変地異説の方はC.ライエル(1797-1875)の《地質学原理》(1830)で否定されることになった。ライエルの思想は〈斉一説uniformitarianism〉といわれ,〈現在は過去の鍵である〉ことを強調している。19世紀の第2四半期は産業革命のさなかであって,キュビエ以来の生物学的研究とスミスにより刺激された層位学的研究の結びつきが強化され,化石の層位学上の実用的価値が石炭のような地下資源開発の面で認められていった。化石を研究する科学としての〈古生物学〉という名称は,1834年にド・ブレンビルDucrotay de Blainvilleとフォン・ワルトハイムFischer von Waldheimによりほぼ同時に提唱されている。当時の研究では生物の歴史が大局的には前進的であることが示されていたが,漸進的変化による進化を証拠づける材料が化石の研究からはほとんど出てこなかった。ライエルの斉一説の影響下でC.ダーウィンが《種の起原》を著した当時(1859),化石上の証拠に採用された例はわずかにすぎない。しかし,彼の唱えた自然淘汰説を肯定するにせよ否定するにせよ,その後の古生物学はこの問題に取り組まざるをえなかった。今日ではダーウィンをもって近代古生物学の祖と見なすことが常識となっている。けれども一般的傾向としては,古生物学は生物学より地質学とのきずなを強めていった。現在,いずれの国の大学においても,古生物学の研究教育はほとんど地質学関係学科で行われている。
20世紀の古生物学は関連分野の発展とともに著しく展開した結果,研究対象や方法などによって多くの分科細目に分けられるに至った。古生物の系統発生と分類に関する最も伝統的分野として古動物学と古植物学があり,前者はさらに古無脊椎動物学と古脊椎動物学に分かれる。生痕化石を対象とするのは古生痕学であり,化石病理学や化石糞学もこれに含められる。古生物が死後,化石化するまでの過程は化石生成論の対象であり,これはさらに化石続成論と化石産出論に分けて論じられる。化石化した古生物とその生息環境を扱うのが古生態学で,個体群構造や個体間・種間関係の解析,古環境との関係などが研究される。斉一説の観点に立って古生物の生態や化石化過程の解明のため,現生生物の観察や実験的研究を行うのが現在古生物学(または考現古生物学)である。古生物の地理的分布やその変遷は古生物地理学で扱う。古生物の残した有機物の化石の生化学的研究は古生化学で行われ,地球における生命発生以来の生物進化が分子レベルで追究される。化石の生物学的意義をもっぱら追究する分野はパレオバイオロジーといわれ,純古生物学,生物学的古生物学などと訳されている。これは,いろいろな時代の地層中における層位的分布に主眼をおいた化石の研究をする層位学的古生物学としばしば対置される。対象が微化石で研究手段として顕微鏡の不可欠なのは微古生物学である。その他,化石の安定および放射性同位体を扱う同位体古生物学などがある。
→化石 →進化論

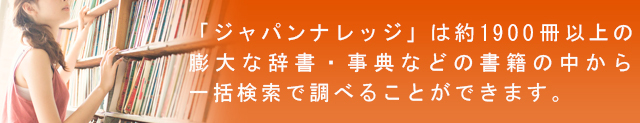










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.