
遺伝現象を研究する生物学の一分科.親の形質がどのような機構で子孫に伝えられるか,個体間の変異はいかにして生じるかという古くからの問いに対して科学的な解答を与えるために生まれたものである.遺伝学の語は英語のgeneticsに対応するが,後者は元来W.Bateson(1906)が遺伝と変異とを研究する学問分野と定義したものである.しかし,その後の発展により,遺伝学の研究は生物学のほとんど全分野とかかわりをもつようになり,現在では遺伝物質の物理的・化学的性質や細胞における遺伝子の発現とその制御機構に関する研究も広い意味での遺伝学に含まれる.遺伝の研究は性の研究と関連して17世紀頃から徐々に行われてきたが,19世紀中頃から,一方では園芸・畜産の発展,他方では進化論の確立にうながされて注目されるようになった.遺伝の基本法則をはじめて明らかにしたのはG.J.Mendel(1865)であるが,遺伝学の目ざましい発展が開始されたのはH.de Vries,C.E.CorrensおよびE.von S.Tschermakの,いわゆるメンデルの法則の再発見(1900)からである.その後T.H.Morgan一派によって遺伝子が染色体上に線状配列することが明らかにされ,遺伝の染色体説が確立された(⇒細胞遺伝学).続いて,遺伝子の本体を明らかにするための努力が重ねられ,H.J.Muller(1927)がX線により人為的に遺伝子突然変異を誘発できることを発見して,突然変異メカニズムの研究が開かれた.遺伝子の形質発現機構の研究は初め生理遺伝学の形をとり,続いて遺伝生化学として生化学的反応の過程と遺伝子の働きとの関連が研究され,G.W.BeadleとE.L.Tatum(1941)の一遺伝子一酵素仮説へと発展した.一方,遺伝学はその誕生以来,進化機構の研究と密接な関係を維持してきたが,C.Darwinの自然淘汰説とメンデルの法則とが生物統計学の方法によって結び合わされて集団遺伝学および量的遺伝学(quantitative genetics)が生まれ,1930年頃に至ってその基礎となる数学的理論が一応確立された.その方法はやがて育種学や進化学に取り入れられ,それらの近代化に大きく貢献した.1940年代には細菌やバクテリオファージが遺伝実験の材料として開発され,これらを用い生化学的手法を大幅に取り入れた研究により,遺伝子の本体がDNAであることが明らかになった.J.D.WatsonとF.H.C.Crick(1953)によってDNAの構造が解明され,遺伝物質の研究に一時期が画された.これを契機として,分子のレベルで遺伝子の構造,複製,転写,蛋白質への翻訳などを研究する分子生物学と呼ばれる一大分野が開け,遺伝学だけでなく広く生命観にも大きな変革がもたらされた.現在,遺伝学の諸分野はその研究材料によって人類遺伝学,微生物遺伝学などに細分されるほかに,研究方法に基づいて,数理遺伝学,統計遺伝学,放射線遺伝学,分子遺伝学,細胞遺伝学などの専門分野の呼び名もあり,さらに取り扱う現象に注目して,行動遺伝学,生態遺伝学,進化遺伝学,発生遺伝学,心理遺伝学,薬理遺伝学,免疫遺伝学などにも分類される.こうした多種多様な分類法からも遺伝学が現代生物学全般に及ぼした影響の大きさをうかがうことができる.(⇒逆遺伝学)
生物界はいろいろの意味で多様である。個体レベルについてみると,別の種に属する個体の間ではもちろんのこと,同一の種に属するものの間にも形態や機能に違いがみられる。また,一つの個体においても卵の受精に始まり,生長・分化して成熟し,やがて老衰して死に至るまでの間,いろいろ形態や機能の変化をみせる。同じことは個体を構成している細胞についてもいえる。同一個体の違った組織や異種属の個体の相同な組織を構成する細胞は形態や機能が互いに多少とも異なるし,単一の細胞についても一つの細胞世代の間にいろいろ形や機能が変わる。また,同種や異種の個体が集合した種々の集団,すなわち同種個体よりなるメンデル集団,属や科のような分類学的集団,さらには群集のような生態学的集団のいずれもが,同レベルの集団間にその広がりや構成に関して差を示すばかりでなく,その一つ一つが年々歳々分布や構成を変化させてゆく。
このように,細胞・個体あるいは集団間にみられる差異,および同一の細胞・個体あるいは集団が経時的にみせる変化の両方を含めて変異variationとよぶ。遺伝学は生物界にみられるこれらすべての変異のよってきたる原因を遺伝物質と関連づけて究明する生物学の一分野である。〈genetics(遺伝学)〉という語をつくったW.ベートソン(1906)は遺伝学を〈遺伝と変異に関する科学〉と定義している。現在の遺伝学は細胞・個体・集団の各レベルについて,遺伝物質の複製・伝達・情報発現の機構を解明し,これらの知見に基づいて変異の生成過程を理解し,さらにはその将来を予測することを目指している。
遺伝の現象そのものについては,おそらく太古の人々も気づいていたに違いないし,アリストテレスも《動物発生論》において遺伝という問題を巡ってかなり深く考察している。たとえば黒人と交わった白人女の娘は黒人ではなかったが,その娘が白人と交わってできた孫が黒人であったという,今でいえば隔世遺伝の事実をあげて獲得形質の遺伝に反証している。
しかし,本当の意味の遺伝学が成立するためには,種の概念,細胞説,有性生殖の認識などが確立される必要があった。モーペルテュイP.L.M.de Maupertuisのヒトの多指症についての研究,ケルロイターJ.G.Koelreuterの雑種の研究などの先駆的業績を経て,ついにG.J.メンデルの登場となる。しかし近代遺伝学の成立はメンデルの遺伝法則の再発見の年すなわち1900年とするのがふつうである。それまで,遺伝をつかさどる物質は液体のようなものであり,子どもでは両親の遺伝物質が,ちょうど白と黒のペンキを混ぜ合わせたときのように混じり合い,再び分かれることがないとする〈融合遺伝〉の考えが支配的であった。このようなときメンデル(1865)はエンドウをつかい,子葉の色の緑と黄のような対立形質について異なる両親を交配し,その後代をいわば家系別に追跡・調査してメンデルの法則に到達した。メンデルのもっとも重要な貢献は,対立形質を支配しているのは対立的な要素(現在の対立遺伝子)であり,子どもは両親からこの要素を一つずつ受けつぐが,これは決して融合せず,子どもが配偶子をつくるとき,分かれて別々の配偶子に入ることを正しく見抜いた点にある。このメンデルの業績は永らく埋もれていたが,1900年にオランダのH.ド・フリースはトウモロコシの研究から,ドイツのコレンスC.CorrensとオーストリアのチェルマックE.Tschermakはエンドウの研究から同じ結論に到達し,メンデルの業績を再発見することになった。この年をもってふつう遺伝学が確立した年とする。後年,W.ベートソン(1906)はメンデルの1866年の論文の結果を整理し,第1(F1の均一性または優劣性),第2(分離)および第3(独立組合せ)の三つの法則にとりまとめた。これがいわゆる“メンデルの遺伝の法則”である。
形質と遺伝子(メンデルのいう因子)の対応関係はそれからも絶えることなく研究されており,形質遺伝学という一つの分野を形成している。この分野では,遺伝子の物質的性質や形質発現の生化学的過程は一応抜きにして,個々の形質を規定している遺伝子ないしは遺伝子群の解析だけを行う。現在では,肉眼的から電子顕微鏡的なものまでを含む形態的形質,物理的・化学的・生物的要因に対する反応性,妊・稔性や生産力を含む生理・生殖的形質,色素・同位酵素・タンパク質分画などの生化学的形質,さらには心理的・行動的形質までが研究対象となっている。
メンデルが遺伝の法則を発見したころからそれが再発見されるまでの19世紀最後の四半世紀は,細胞学がメンデルの法則,したがって遺伝学そのものを生物学へ受け入れるための準備をした期間である。この間,受精において卵と精子の核が合体すること,細胞分裂において染色体が縦裂し,その半分ずつが娘細胞に分かれて入ること,卵と精子から同数の染色体が接合体にもち込まれることなどが知られてきた。そして,メンデルの法則の再発見後間もなくサットンW.S.Sutton(1902)などによって成熟分裂(減数分裂)における染色体数の半減が発見されるに及び,メンデル因子と染色体の行動に完全な並行関係がなり立った。ここに細胞遺伝学とよぶ細胞学と結合した遺伝学の新分野が生まれた。1910年代に入って,T.H.モーガンらはキイロショウジョウバエを用いて,遺伝子と染色体部分の直接的な結びつきを証明し,遺伝に染色体という物質的な基礎を与えた。現在,この分野では種々の遺伝学的現象を細胞学的現象に関連・対応づけるため,核や細胞小器官(オルガネラ)自体およびそれらに含まれる染色体やDNA分子の構造・複製・伝達・化学的組成などを光学・紫外線・蛍光あるいは電子顕微鏡を用いて研究している。
1920年代の半ばに入り,H.J.マラー(1927)はショウジョウバエ,スタッドラーL.J.Stadler(1928)はトウモロコシにX線照射を行い,遺伝子の突然変異が人為的に誘発できることを証明した。ここに,遺伝子の変異性を実験的に研究することが可能となり,突然変異遺伝学とよぶ新しい分野が開けた。現在この分野では電離放射線や紫外線,さらには化学物質による遺伝子突然変異や染色体異常の誘発機構,これら変異原mutagenによるDNAの損傷とその修復の機構,変異原に対する感受性を修飾する遺伝的・環境的要因の解析,さらには変異原の育種的利用などが重要な問題となっている。
C.ダーウィン(1859)は生物の進化が淘汰によることを示す多くの証拠を得たが,淘汰の対象となる変異の出現機構については明らかにできなかった。遺伝子の自然および人為突然変異の研究はこの問題に大きな手がかりを与え,遺伝学が進化機構の解明に深くかかわることとなった。すでに1908年にハーディG.H.HardyとワインベルクW.Weinbergは安定した任意交配集団における遺伝子頻度と遺伝子型頻度の関係について,〈ハーディ=ワインベルクの法則〉とよばれる法則を発見していたが,30年代に入り統計学の進歩と相まって,淘汰・突然変異・繁殖様式・集団構造などを考慮に入れて集団の遺伝的構成の経時的変動を研究する集団遺伝学の基礎がR.A.フィッシャー,J.B.S.ホールデーン,ライトS.Wrightなどによって築かれた。最近は遺伝子やその支配形質の違いを分子レベル,すなわちDNAの塩基配列やタンパク質の一次構造の差異としてとらえ,その集団における挙動が盛んに研究されている。
形質は遺伝子に支配されており,その遺伝子は特定染色体の特定部位を占めていることが形質遺伝学や細胞遺伝学の発達で明らかになったが,遺伝子がいかに形質を決定するかは不明であった。とはいえ,すでに1908年にガロッドA.E.Garrodはヒトの先天的代謝欠陥が酵素の欠如に起因することを示唆していた。30年代に入り,生理遺伝学の名のもとに温度・食餌など環境要因の大きな変化がどのような効果を形質に与えるかを明らかにし,遺伝子の形質発現の機構に迫ろうとする試みがなされたが,この問題の本格的な解明はビードルG.W.BeadleとテータムE.L.Tatum(1941)らによるアカパンカビの研究をまたねばならなかった。ビードルらは特定のビタミンやアミノ酸の合成経路に欠陥をもつ多くの突然変異体を分離し,それぞれについて合成経路のブロックの位置を決定した。さらにこのブロックを支配している遺伝子を分析し,合成経路の個々の段階が固有の遺伝子に支配されていることを明らかにした。当時すでに生化学の分野で酵素が合成・代謝経路を支配していることが知られていたので,ビードルたちの発見から遺伝子が酵素を介して生体内の化学反応を支配し,これを通して形質の発現を規定していることがわかった。生体内の化学的反応過程の遺伝的支配機構を解明するこの分野は生化遺伝学とよばれ,遺伝学の重要な分野となった。
1944年にO.T.エーブリーらはR型の肺炎双球菌にS型の菌から抽出したDNAを与えるとS型に変わり,この変化は子孫に安定して伝わることを証明したが,遺伝子の本体がDNAであるという考えが広く受け入れられるにはそれから10年近い歳月が必要であった。生物の多様性を考慮するとき,遺伝子の本体とみなすには4種のヌクレオチドで構成されるDNAはあまりにも単純に過ぎ,したがって,きわめて多様な存在形態を示すタンパク質のほうが適当と考える強い風潮が当時あったためである。1940年代に入ってからウイルス学が発展し,細胞構造をもつ生物と同様,ウイルスにも遺伝的特性を異にするいろいろの系統があり,これらの間に遺伝子の組換えがおこることもわかってきた。ウイルス粒子はタンパク質とDNA(またはRNA)からなるが,ハーシーA.D.HersheyとチェースM.Chase(1952)はウイルスがバクテリアに侵入する際,タンパク質は宿主細胞の外に置去りにされ,宿主細胞に入るのはDNAだけであることを証明した。これはウイルスの増殖に必要なのはDNAであることを示唆したものである。続いて,J.D.ワトソンとF.H.C.クリック(1953)はDNAの分析的データを完全に満足させる構造として,二重らせんモデルを提案した。このモデルは4種のヌクレオチドからなるDNA分子がいかに容易に多種類の遺伝子をつくりうるかということだけでなく,生物のもっとも重要な特性である自己増殖がどのような機構でおこるかを複雑な説明なしに人々にわからせた点で画期的なものであり,短期間にDNAを遺伝子の本体として認知させることに成功した。ここに,E.L.テータムがDNA時代と名づけた分子遺伝学の時代の幕があいた。分子遺伝学はDNAに基礎をおき,その構造・複製(自己増殖)・遺伝情報の発現と調節などの機構を分子レベルで研究する分野といえる。
この分野の発展により,DNAの複製の様式と機構が大筋において明らかになり,DNAからRNAが転写される機構と,メッセンジャーRNAのヌクレオチド配列がポリペプチドのアミノ酸配列を規定する翻訳機構の解明が進み,翻訳の際に用いられる遺伝暗号も解読された。また,遺伝子作用の分子レベルでの調節機構もかなりわかってきた。1968年には制限酵素が,70年には逆転写酵素(RNA依存性DNAポリメラーゼ)が発見された。これらの酵素を利用して任意のDNA断片をバクテリア中でクローン化することが可能となった。一方,マクザムM.MaxamとギルバートW.Gilbert(1977)らによりDNAのヌクレオチド配列の効率的な決定法が確立され,原核生物のみならず真核生物の多くの遺伝子の構造解析が行われるようになり,真核生物の分子遺伝学が急速に進展する時代を迎えているようにみえる。
遺伝学は生物学の中では比較的新しい分野であり,その歴史は100年に満たないが,すでにきわめて多くの分野に分かれてきている。これらの分野は次の四つの基準を用いてある程度は整理・分類できる。そのうちの主要な分野の発達の経緯と内容はすでに上に述べたとおりである。
(1)対象となる生命現象別の分野 生物は形態・生理・発生・生態・行動・進化というような種々の生命現象を示す。このそれぞれを研究対象とする分野として,形質遺伝学(形態以外の形質も対象とするが),発生遺伝学,生態遺伝学,行動遺伝学,進化遺伝学などがある。生理遺伝学は後述するように手法別の分野とみなすべきもので,生理現象はおもに生化遺伝学で研究の対象とされている。
(2)対象とする生物の構成レベル別の分野 生物界は分子→細胞小器官→細胞→器官→個体→集団→群集という階層構造をなしている。生物学の他領域と同様,遺伝学でもこれら個々の階層に焦点を合わせた研究が行われており,そのうち分子遺伝学,オルガネラ遺伝学,細胞の遺伝学,集団遺伝学などが確立した分野となっている。
(3)研究手法別の分野 これまでに生物学の関連領域で発達した研究手法をいろいろとり入れて遺伝学が進歩してきた。統計遺伝学,細胞遺伝学,放射線遺伝学,生理遺伝学,生化遺伝学はそれぞれ統計学,細胞学,放射線学,生理学,生化学の領域で開発された手法を主要な研究手段として発達した遺伝学の分野である。
(4)対象生物別の分野 これまでに確立された遺伝の原理・法則は多くの生物に適用できる。しかし,“例外のない法則はない”のたとえは遺伝の原理にもあてはまり,メンデルの法則は細胞質遺伝には適用できないし,ミトコンドリアの遺伝暗号は普遍的暗号と若干の点で異なる。したがって,ある生物で発見された遺伝現象やその機構の普遍性をつねに他の生物について検証しなければならない。また,生物の種類によって研究に適した分野とそうでない分野がある。さらに,人類の関心,ひいては遺伝学者の関心が向けられる面が生物の種類によってしばしば異なる。ヒト自身,野生の動植物,栽培・飼養動植物に対する遺伝学の関心は一部の面で本質的に異なる。ここに,生物の種類別の分野がなり立つ基盤がある。これには動物遺伝学・植物遺伝学・微生物遺伝学のように大きな生物群を対象にするものから,人類遺伝学・ショウジョウバエ遺伝学・トウモロコシ遺伝学・アカパンカビ遺伝学のように一つの種属を対象とするものまでいろいろのものがある。

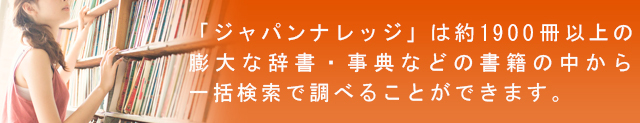










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.