
俳人・歌人。慶応(けいおう)3年旧暦9月17日(陽暦10月14日)伊予国温泉郡藤原新町(松山市新玉町)に生まれる。本名常規(つねのり)、幼名処之助、また升(のぼる)。別号獺祭書屋主人(だっさいしょおくしゅじん)、竹の里人。父隼太(はやた)は松山藩の下級武士。政治家を志し、松山中学校を中退して、1883年(明治16)17歳のとき、叔父の加藤拓川(たくせん)を頼って上京した。やがて一ツ橋大学予備門(旧制一高の前身)に入学し、夏目漱石(そうせき)を知る。この前後に和歌や俳句をつくり始め、また人情本に親しみ落語なども好んだが、当時はやりだしたベースボールにも熱中した。一時、哲学者になろうとしたが、一方、古俳諧(はいかい)の研究を進め、友人と句作に励んだ。1889年に喀血(かっけつ)して子規と号し、翌1890年帝国大学文科大学(現、東京大学文学部)国文科に入学し志望が三転した。当時の新進作家幸田露伴(ろはん)の影響を受け、1891年小説『月の都』を書いたが成功せず、「僕は小説家となるを欲せず、詩人とならんことを欲す」と記して、結局俳人として生きる決意を固めた。
1892年新聞『日本』に『獺祭書屋俳話』を連載。俳句革新運動の先駆けとなる。ついで大学を中退し、日本新聞社に入社。社長陸羯南(くがかつなん)の家の隣(当時下谷区上根岸町)に住み、終生羯南の庇護(ひご)を受ける身となった。1895年、日清(にっしん)戦争に志願して従軍し、帰途喀血、のち脊椎(せきつい)カリエスとなり、死ぬまでほとんど病床に釘(くぎ)づけになったが、その間の7、8年に子規は獅子奮迅(ししふんじん)の働きをした。発表の場は主として新聞『日本』と1897年創刊の雑誌『ホトトギス』で、洋画家中村不折らとの交流により、俳句に自然を描写する写生の重要性を悟り、また蕪村(ぶそん)の絵画的で自在な句境を学び、従来の月並や理屈を排して若い作者の中心となり俳句の革新を進めた。おもな俳論に『俳諧大要』(1895)、『俳人蕪村』(1897)などがある。1898年には和歌の革新に乗り出し、『歌よみに与ふる書』を発表して因襲にとらわれる旧派の歌人を攻撃し、『百中十首』(1898)をもって、当時としては破天荒の斬新な手法による短歌を示した。
子規の俳句は自筆の稿本『寒山落木』全5巻、『俳句稿』全2巻などに2万近く収められ、短歌は『竹乃里歌』に記され、補遺をあわせて2400首ほど。晩年に近づくにつれて俳句も短歌も境涯を生かした至純な境地に進んだのは、『万葉集』からの摂取、また病苦の深まりによるものである。「雞頭(けいとう)の十四五本もありぬべし」「さまざまの虫鳴く夜となりにけり」「いちはつの花咲きいでゝ我目には今年ばかりの春行かんとす」などの作は有名なもの。明治35年9月19日没。
子規は新体詩、小説にも手を染めたが、随筆『墨汁一滴』(1901)、『病牀六尺(びょうしょうろくしゃく)』(1902)、とくに日記『仰臥漫録(ぎょうがまんろく)』(1901~1902)に率直な人間性がみられる。また経験を平明に客観的に書く写生文も提唱して、後世の平易な日本語の成立にも少なからぬ影響を与えた。彼の俳句は、『ホトトギス』に拠(よ)る高浜虚子(きょし)らに、短歌は『アララギ』に拠る伊藤左千夫(さちお)らに継承された。1981年(昭和56)郷里松山市に子規記念博物館が開館した。
2018年10月19日
![正岡子規[百科マルチメディア]](https://japanknowledge.com/image/intro/masaoka-shiki.jpg)
明治の俳人,歌人,随筆家。本名常規(つねのり),幼名処之助(ところのすけ),升(のぼる)。別号獺祭書屋(だつさいしよおく)主人,竹の里人(さとびと)。松山市生れ。松山中学を経て東京の大学予備門に入学。予備門が校名を改称した一高を経て東大中退。1892年には日本新聞社に入社。社長の陸羯南(くがかつなん)とその交友関係から国粋発揮の思想的な影響を受けている。創作としては,少年期から漢詩を試み,のち和歌,俳句に手を染めた。小説にも関心をもち,大学在学中,夏目漱石との交流を通して新文学への理解を深めた。92年《月の都》を幸田露伴に見せ文壇への進出をはかったが,成功せず俳句に専心。明治初年から勢いを得てきた短詩否定の風潮の中で俳句の可能性を見きわめる決意を固め,新しい文学概念で俳諧を見直し発句を独立させて,一句の季節詩の俳句とした。日本の詩という自負をもち自然を対象として,洋画の〈写生〉を応用し,視覚によって現実の事物と密着する表現を定着させた。95年日清戦争を背景とした〈日本〉の自覚のたかまりの中で従軍,帰国の船上で喀血。病臥の生活を送り,《俳諧大要》を著すなど多くの革新事業を病床で推進した。97年から松山で創刊された《ホトトギス》を指導。98年には同誌を東京に移し,俳諧趣味を鼓吹する雑誌とした。また,98年からは短歌革新に着手,《歌よみに与ふる書》を《日本》に連載,《万葉集》の尊重を説き,実作では日常生活を写生した格調の高い作品を示した。別に,写生を文章にも応用して写生文を試み,《ホトトギス》誌上でも風物の写生的短文を募集した。写生文の中心は子規と高浜虚子で,子規の口述を虚子が筆記する中で精細な描写と洗練された口語文体が定着した。晩年には,写生の極致は〈自然〉にあるという幅広い考え方に移行したが,その手法を《墨汁一滴》(1901),《病牀六尺》(1902),《仰臥漫録》(1901-02)など日録の随筆に生かし,病床の出来事を描写するほか,考証,評論などにも自在な筆運びを見せた。そこには病苦を裏面に押しやった平淡で奥行きの深い内容が見える。1902年肺結核で死去。彼の門下には,俳句では虚子,河東碧梧桐ら,短歌では伊藤左千夫,長塚節らが出て,その影響圏は非常に広い。〈鶏頭の十四五本もありぬべし〉。

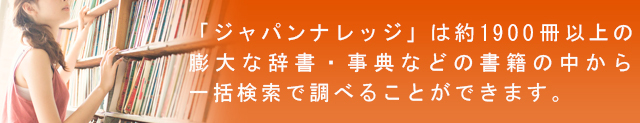
 セーフ。*松蘿玉液〔1896〕〈正岡子規〉七月二三日「走者(通過しつつある者)或る事情のもとに通過の権利を失ふを除外(アウト)といふ
セーフ。*松蘿玉液〔1896〕〈正岡子規〉七月二三日「走者(通過しつつある者)或る事情のもとに通過の権利を失ふを除外(アウト)といふ









©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.