
18世紀初めから1917年のロシア革命までのロシア。帝政ロシアともいう。正式には1721年にピョートル1世(大帝)が皇帝(インペラートルimperator)の称号をとってから,1917年の二月革命でニコライ2世が退位するまでをいう。帝室はロマノフ朝で,その首都はペテルブルグ。東方正教(東方正教会)を国教とし(ロシア正教会),ユリウス暦を用いていた。人口は1724年に約1558万,1812年に約4270万と推定され,帝国時代に行われたただ1回の全国国勢調査(1897)では1億2500万(うちロシア人は5560万)であった。
帝国の歴史は18世紀と19世紀に分けることができ,19世紀はさらにクリミア戦争(1853-56)でその前と後に分かれ,19世紀末~20世紀初めが帝政末期になる。18世紀のロシアは軍事技術から思想,風俗までヨーロッパの文物・制度を貪俗に吸収し,啓蒙専制君主エカチェリナ2世の時代にある意味で模範的な絶対主義国になり,ヨーロッパの一大強国に発展した。しかし女帝の晩年にはフランス革命がおこり,イギリスの産業革命も始まっており,19世紀初めにはナポレオンのモスクワ遠征があった。産業革命と市民革命の時代を迎えて,19世紀にロシアの後進性はかえって明らかになり,世紀前半アレクサンドル1世とニコライ1世が絶対主義体制を保持しながら新しい国際環境のなかで大国ロシアの地位を守ろうとしたが,クリミア戦争に敗れ,この敗戦の衝撃からアレクサンドル2世の時代に〈大改革〉が行われた。この改革で帝国は絶対王政からブルジョア王政への転化の方向をみせたが,続くアレクサンドル3世のもとで政治反動が強まり,国際的には帝国主義時代が始まった。ロシア自身,帝政末期には後進帝国主義国の一つとして資本主義の急速な発展をみ,1906年からはドゥーマ(国会)も発足したが,この時期は1905年の革命をなかに挟み,広い意味ではロシア革命の時代に入る。以下,本項では,まず五つの側面について,ロシア帝国の特質を明らかにし,次いでピョートル1世からロシア革命前夜までの通史を概説する。
ピョートル1世は,17世紀中葉以降,軍事的官僚国家の性格を強くしつつあった西方の絶対主義国をモデルに国家建設に当たった。北方戦争は21年の長きにわたり,彼の国内政策も能率的で確実な徴兵・徴税と軍需品の生産を主目的とした。そのため,スウェーデンなど北欧諸国の新制度を参考に創設したコレギアkollegiya(参議会)の組織でも,外務,陸,海の3コレギアが上位を占め,ほかに工業,鉱業,貿易などのコレギアも設けられた。ピョートルは軍制を改め,軍の装備を改善し,歩兵,騎兵を増強し,ロシアはたちまち大陸軍国となった。ピョートルの晩年にはこの陸軍と新設のバルチック艦隊の軍需品もほぼ自給された。ピョートルは戦争中,外交にも力を入れ,ロシアはヨーロッパの主要国に外交官を常駐させるようになった。モスクワ・ロシア時代以来のロシアの念願であったバルト海への進出を果たしたピョートルも,黒海へのそれには失敗した。その後,エカチェリナ2世が2度のトルコとの戦争(1768-74,1787-91)で黒海北岸とクリミアを併せ,ポチョムキンが新領土の開発・植民,黒海艦隊の建設を進め,女帝(エカチェリナ2世)はトルコ領内の東方正教徒に対する保護権も獲得した。
西方との関係では,ピョートルののちのロシアは通商面ではイギリスと結び,外交面ではオーストリアと結んでフランスに対抗し,ポーランド継承戦争,オーストリア継承戦争,七年戦争に参戦し,とくに七年戦争ではプロイセンを一時窮地に追いこんだ。続いてエカチェリナ2世時代,3次にわたるポーランド分割で領土を大きく西方にも広げ,19世紀初めにはグルジア,フィンランド,ベッサラビアを併せた。東方では18世紀にV.ベーリング以降北太平洋とシベリアの探検・調査をすすめ,アラスカに進出して露米会社を設け,中国とはキャフタ条約を結んだ。日本にはラクスマンを派遣して国交を求め,中央アジアに対してはオレンブルグの基地を設けた。フランス革命で衝撃を受けたロシアは,ナポレオンの台頭で危機感を深め,提督ウシャコフFyodor Fyodrovich Ushakov(1744-1817)のロシア艦隊が東地中海に進出し,スボロフ将軍がイタリアで善戦したが,その後対仏和平とその崩壊,アウステルリッツの戦,ティルジットの和と大陸封鎖への参加などを経てナポレオンのモスクワ遠征を迎えた。これを敗退させたアレクサンドル1世はウィーン会議でポーランド国王を兼ね,神聖同盟を提唱し,その後ウィーン体制の擁護者として振る舞った。ニコライ1世はギリシアの独立戦争,トルコ帝国の内紛に干与して中東への進出をはかる一方,1830-31年のポーランド王国の反乱(十一月蜂起)を粉砕してその憲法を廃止し,49年にはハンガリーに軍を送ってその独立運動を圧殺し,正統主義者の面目を示した。
クリミア戦争はロシア軍の欠陥をあらわにした。18世紀には兵役は事実上終身徒刑と同じで,その後25年になったが,兵士の待遇は極端に悪く,病気や体罰による損耗率も非常に高かった。またナポレオン戦争後アラクチェーエフ体制下の屯田兵制が国民の怨嗟(えんさ)の的になった。兵士あがりの下士官・将校の教養は低く,貴族出身の将校は兵士を農奴扱いした。クリミア戦争敗戦後の軍制改革で1874年までに現役期間は6年(海軍は7年)とされ,兵役に関する身分的特権が廃され,軍隊生活もある程度改善された。クリミア戦争後ロシアは東方では,ムラビヨフ・アムールスキーなどの活躍で清国からアムール川以北と沿海州を獲得し(璦琿(あいぐん)条約,北京条約),アラスカをアメリカに売却し,日本とは千島のウルップ島以北と南サハリンを交換(樺太・千島交換条約)し,中央アジアではホーカンド,ブハラ,ヒバの3ハーン国を併せ,カフカスでもシャミーリらの抵抗を排して征服を完了した。
西方では1863年のポーランド反乱(一月蜂起)後プロイセンに接近し,その支持でパリ条約(1856)の禁止条項を廃して黒海の再軍備を進め,73年三帝同盟を結び,77-78年の露土戦争でバルカンを勢力圏に収めたかにみえたが,ベルリン会議で大幅譲歩を強いられ,国内のパン・スラブ主義的世論の激高で政治危機を招いた。またこのため生じた対独関係の冷却は,穀物輸出と工業製品輸入をめぐる同国との対立でさらに進み,代わって88年以降ロシア外債の引受け手となったフランスとの関係が緊密になり,94年露仏同盟が成立した。東方では91年のシベリア鉄道建設開始,次いで三国干渉,義和団事件などを経て日露戦争に突入した。1905年の革命後フランスから巨額の借款を得,イズボルスキーがイギリスと協商し,日露協約を調印するとともに,軍隊を再建してバルカン政策を再開し,ボスニアの危機は回避したが,バルカン同盟を支援し,第1次大戦に突入した。
ロシア皇帝は専制君主で,1906年のドゥーマ発足後も完全な立憲君主にはならなかった。専制政治はモスクワ・ロシアからの伝統であったが,君主専制を文字どおり実践して統治機構も一新したピョートル1世は,ドイツ官房学(カメラリズム)の影響下に,専制の理念にも神的起源のほか,〈公共の福利〉への奉仕という世俗的存在理由を加えた。しかしこの新しい政治理念が指導層に浸透し,新しい統治機構が正常に機能するまでには数十年を要した。ピョートルののち数代は,みずからは政治の実権を握ることのない女帝と幼帝が続き,君主専制は名目化した。ピョートルは元老院を国政の最高機関としたが,彼のあとにエカチェリナ1世をつけた彼の重臣たちは,最高枢密院を設けて国政を独占し,さらにエカチェリナのあとのピョートル2世Pyotr Ⅱ Alekseevich(在位1727-30)の夭折でアンナ・イワノブナを迎える際,君主権を大幅に制限する〈条件〉を認めさせた。しかしこれは大貴族の寡頭支配を恐れる高官・将官たちの反対で破棄され,君主権制限の試みはこれが最初で最後になった。
アンナは姪の子イワン6世Ivan Ⅵ Antonovich(在位1740-41)を後継者にしたが,近衛部隊による宮廷革命でエリザベータ・ペトロブナ(在位1741-62)がこれに代わった。ピョートル1世の権力の支柱をなした近衛部隊はすでにエカチェリナ1世の即位に重要な役割を果たしており,エリザベータののちもピョートル3世に対する宮廷革命を実行してエカチェリナ2世(在位1762-96)を位につけた。再三の宮廷革命は,ピョートル1世が1722年の帝位継承法で皇帝に後継者指名権を与えたことにも原因があった。母親の永い在位中絶えず将来への不安に悩まされたパーベル1世(在位1796-1801)は,即位直後に直系男子による継承順位を定め,皇位継承に安定性を与えたが,彼自身も宮廷革命で位と命を失った。宮廷革命はこれが最後になったが,モスクワ時代以来の功臣・寵臣に対する皇帝の御料地・国有地賜与とそれに伴う自由農民の農奴化もパーベル時代で終わり,絶対君主の家父長的支配の一つの特徴はロシアでも18世紀末で姿を消した。
元老院はエリザベータによってその地位が回復され,エカチェリナ2世も初めは元老院の整備による集権的官僚政治を志向したが,プガチョフの乱を経験して,1775年の地方改革で県の数をふやすとともに,ある程度の地方分権と貴族中心の地方自治を実施した。この新たな県の制度と85年の都市自治制は1860年代の〈大改革〉期まで続き,女帝が人口数を基準に再編した県は革命まで続いた。元老院の機能強化と地方改革,さらにエリザベータ期からの経済自由化政策のため,ピョートル1世以来のコレギアは外務,陸,海の3者を残して消滅に向かったが,コレギアの特徴をなした幹部会での合議による運営も18世紀末,とくにパーベル期に議長の専決制に移り,これを受けてアレクサンドル1世が大臣を責任者とする省の制度を採用した。
これに続いて法案の最終審議を主任務とする国務評議会gosudarstvennyi sovetが設けられ,元老院は一種の最高法廷となる。この体制が1905年まで続くが,この改革はアレクサンドルがスペランスキーの改革案をいわばつまみ食いしたもので,改革案にあった郷・郡・県・国の段階的代議制は拒否された。みずから招集した国民各層の代表からなる法典編纂委員会に有名な〈訓令(ナカース)〉を与えて法治主義の原則を説いたエカチェリナ2世がすでにそうであったが,彼女のもとで教育された孫のアレクサンドル1世(在位1801-25)も君主専制の原則は譲らず,これは最後のニコライ2世まですべての皇帝が同様であった。国務評議会でも大臣会議でもこれを主宰したのは皇帝またはその代理で,しかも皇帝は会議の多数意見に拘束されず,政府を代表する首相も1905年までは存在しなかったので,大臣たちも個々に皇帝に報告して指示を仰いだ。このほか有力政治家や皇族,廷臣が直接皇帝に働きかけることも可能で,この体制のもとでは政策の整合性と継続性,安定性は保証されにくかった。
ロシア皇帝でピョートル1世に次いで国務に精励したのはニコライ1世(在位1825-55)で,彼はウバーロフの提唱した〈官製国民主義〉を専制のイデオロギーとし,皇帝直属官房を強化して文字どおりの親政を行った。直属官房は第三部がとくに有名であるが,第二部がエリザベータとエカチェリナ2世の法典編纂委員会もなしえなかった1649年の〈会議法典(ウロジェニエ)〉以降の法律の集大成〈ロシア帝国法律大全〉45巻(1830)と現行法を体系化した〈ロシア帝国法典〉15巻(1833)を完成したことは,ニコライ1世期の官僚制の整備とともに,君主専制の制度化・実質化に大きく寄与した。ピョートル1世は1722年の官等表で帝国の官僚制度の基礎を置いたが,彼自身の武官優遇策と教育機関の不備,貴族子弟の武官志向などから,帝国の統治機関は最初から人材不足に悩まされた。このため多くの外国人専門家や沿バルト3県のドイツ系貴族の採用とともに,非貴族出身の下級官吏にも上級官僚への昇進とそれに伴う貴族身分取得の道を開いた。この道は旧貴族の要求で狭められることはあっても,帝国の終焉まで閉じられることなく,ロシア社会の垂直的流動化のチャンネルとしても機能し,帝政の延命にも寄与した。
またこのような人材不足などの理由で,新しい行政機関が十分機能しなかったため,ピョートル1世はその政策遂行のためしばしば軍隊の強制力と組織力に頼った。この軍隊の行政への干与は18世紀半ばまで続き,その後も続いた武官の文官への転身などとあいまって行政の軍事化(軍隊的規律と画一主義の浸透)を招いた。しかし18世紀の近衛連隊と19世紀の憲兵隊は別として,いわゆる軍部が大きな政治力をもつことはロシア帝国ではなかった。
ニコライ1世は即位まで軍隊生活しか知らず,彼の政治姿勢も行政の軍事化を助長した。しかし19世紀初めの大学の増設や官吏任用資格制度導入の提唱などを受けて,ニコライ自身も法律学校などの専門学校を設け,大学,専門学校の卒業生に任用・昇進の優先権を保証した。このため政府機関の中堅官僚の質は急速に改善され,内務省,財務省,司法省の中枢を占めたミリューチンらの改革派官僚が農奴解放を中心とする〈大改革〉の大きな推進力になった。彼らの多くは貴族出身であったが,政府からの給与に大きく依存しており,農奴解放への不満から生じた一部地主の代議制の要望に対しても,専制権力を改革のてことする立場をとった。〈大改革〉後の政治においても官僚はしばしばゼムストボや貴族団dvoryanskoe obshchestvoの自由派,保守派の双方と対立したが,世紀末にはこれは官僚の既得権擁護の保守的性格のものに変わった。
人民の意志派によるアレクサンドル2世(在位1855-81)の暗殺でロリス・メリコフの一種の諮問議会案が撤回されたのち,新帝アレクサンドル3世(在位1881-94)はポベドノスツェフの影響下に専制護持の決意を表明し,続くニコライ2世もゼムストボ代表の国政参加の希望を〈ばかげた幻想〉として退け,この二人の皇帝の下での反動の高まりが,オフラナokhranaと呼ばれる革命防圧機構の強化にかかわらず,帝国を革命の時代に導いていった。各省のなかでは,公安関係から農民行政までの広い権限と知事に対する指揮権をもつ内務省が最も重要で,これに対して19世紀後半には,商工行政をも担当した財務省が有力官庁となったが,それぞれD.A.トルストイとウィッテの活躍に代表される両省の政策面での対立についても,皇帝には調整能力がなかった。
皇帝専制に伴う問題のほかにも,ロシア帝国の官僚支配にはいくつかの弱点があり,その中心をなしたのは地方の問題であった。ロシア語では,普通は〈土地〉を意味する〈ゼムリャzemlya〉という言葉が〈地方〉という意味にも使われた。これは〈中央〉に対する〈地方〉であって,〈官〉に対する〈民〉をも含意した。古くはゼムリャすなわち国土が〈国〉そのものであって,モスクワ時代にはvsia zemlyaという表現で〈全国〉が意味された。そしてこのゼムリャとしての〈国〉は,君主(ゴスダリgosudar’)の統治する制度としての国家(ゴスダルストボgosudarstvo)に先行し,それを支え,時にはそれに対立するものと考えられたが,この観念はロシア人の意識のなかに生き続け,19世紀のスラブ派がロシア史におけるゼムリャとナロードの本源性と国家の人工性を強調できたのもそのためであった。この場合の国家はいうまでもなくピョートル1世以来の西欧化し官僚化した国家のことであったが,ロシア帝国の官僚支配には,ロシア人の伝統思想のなかで十分な正当性をもちえないという弱点があった。
帝国では官尊民卑の風が強く,至るところで官等,制服,勲章がものをいい,貴族社会でも軍歴・官歴の劣るものは家柄はよくても低くみられたという。しかし官僚支配そのものにはロシア人は結局なじめず,常にこれを恐怖と批判と揶揄(やゆ)の対象にした。そのうえこの官僚支配には,行政の網の目が粗く,広大な帝国の隅々,社会の底辺までは及んでいないという弱点があった。すでにエカチェリナ2世の法典編纂委員会で地方の代表たちは,政府の役人の横暴,不正,怠慢を責めるとともに,一見これと矛盾するようであるが,国の地方行政の不備(国の出先機関の不足など)に強い不満を表明していた。そして県の全国的再編とその行政・司法の抜本的改革・整備を主目的とした上記のエカチェリナ2世の地方改革は,ある程度こうした不満に応えるものであり,事実地方行政はこれによってかなり充実した。しかし国家予算と人材不足のため,19世紀においても国の地方行政機関は県どまりで,郡・郷の行政は貴族団の選出する郡警察署長以下の民選の役職にまかされた。
官僚制が整備されたニコライ1世期にも,ロシア帝国の役人の数は,人口比ではフランスなどよりかなり少なく,そのうえ県庁などの地方官庁の知事以下の上級幹部は頻繁に交替し,そのほかの役人は質が悪く,これが政府の政策遂行の大きな妨げにもなった。ニコライ1世は第三部を通して地方行政の実情把握に努め,侍従武官などを派遣して地方官庁の査察を繰りかえした。これがゴーゴリの《検察官》の背景であった。
こうした行政機関の不備を補ったのは,地方住民の自治組織であり,ロシア政府は早くから自治組織に徴税,治安維持などの行政事務を義務として請け負わせ,時には自治組織をみずからの手で育成・強化することさえした。それと同時に政府は自治組織の活動を官僚の統制下に置き,自主的な活動を封ずる政策をとってきた。しかし農民の自治組織(共同体)には常に農民運動の核になる可能性があり,貴族の自治組織(貴族団)も農奴解放時の活動以来皇帝への要請活動などでしばしば政府を手こずらせ,さらにゼムストボの活動が政府の官僚行政の原則を脅かした。これが帝国における中央(国家)と地方(社会)の関係の一般的特徴であるが,具体的には,農村で行政の末端を担ったのは,皇帝の宣言や政府の法令を住民に読み聞かせる責任をもつ村の司祭は別として,農村共同体の選挙制の役職であった。国有地の自由村落では彼らが徴税や徴兵に責任をもち,地主領でも彼らは,領主または管理人の農奴たちに対する徴税,徴兵,警察,裁判官としての権能を大幅に補佐・代行した。
キセリョフの国有地行政改革と1861年の農奴解放は,それぞれに共同体を強化してその自治機能を高めたが,それを通じて農地管理,徴税,秩序維持などについての責任も強化された。この自治組織の強化と責任・負担の増加の並行,自治体による官僚行政の補完・代位は,すでにイワン4世(在位1547-84)の地方自治導入にみられ,その後のピョートル1世の都市自治の実施も,形は西欧の都市制度を模しながら,役人の収奪からの解放を条件に2倍の納税を住民に求めるものであった。ピョートルは農民にも負担能力を超える重税を課し,このため農民の土地放棄や逃亡がふえたので,納税について連帯責任を負う共同体は,各部落・各農家の担税力(家族構成)と保有地(担税地)面積の均衡を維持する必要から頻繁に土地の割替えを行うようになり,これが18世紀のうちに慣行化した。
ピョートル1世は彼の設けた県庁その他の地方機関にも,在地の貴族の参加・協力をはかったが,うまくいかなかった。これを成功させたのはエカチェリナ2世で,女帝はその地方改革で郡警察署長,貴族裁判所の判事など在地貴族の互選による多くの官職を設け,これら官職は1785年の特権認可状zhalovannaya gramotaで設立された郡・県の貴族団の集会で,貴族団長など貴族団そのものの役職とともに選出された。政府はこの貴族団の活動に多くの制限をつけたが,民選の官職・役職にも官等を与え,とくに県貴族団長は知事に次ぐ官等を与えられて県内で有力かつ重要な存在となった。19世紀後半には,彼らは県行政のさまざまな分野に設けられた委員会に常に委員または委員長として参加し,同時に重要なゼムストボの議長を兼ね,帝国の政治システムのなかで〈国家〉と〈社会〉のいわば接点をなした。郡には政府は出先機関をもたなかったので,郡貴族団長の存在はある意味ではもっと大きかった。
農奴解放の準備期に各県貴族団は重要な役割を果たし,その代表たちは中央で政府委員と激しく渡りあい,政府案に対する貴族の不満が一時は深刻な政治危機を招き,官僚政治に対する反発から代議制への要求さえ現れた。これはこの後も散発的ながら貴族団とゼムストボの活動にみられたが,ゼムストボはその成立後,政府の行政の及ばないところを大幅に補完・代行し,ゼムストボに勤める農業技師,統計家,医師,獣医,学校教師などのインテリゲンチャは,ゼムストボ指導部の自由主義地主とともに,官僚政治の有力な批判勢力となっていった。
ロシア帝国は住民の身分的編成を特徴とした。19世紀には特定身分に属さないラズノチンツィ(雑階級人)がふえ,法的にも〈大改革〉期の身分別裁判所の廃止,国民皆兵の実施などで身分差別は一部解消した。しかし農村共同体の維持・強化や,ゼムストボ,ドゥーマの身分別選挙など身分差別は最後まで維持された。帝国の身分制の基礎も,モスクワ時代のそれを再編・強化したピョートル1世によって与えられた。彼はボヤーレboyare(貴族)をドボリャーニェdvoryane(士族)に吸収し単一の貴族身分をつくり,ホロープは彼の人頭税導入に伴い農奴に吸収された。1880年代に廃止されるまで,この人頭税負担の有無でロシア社会は大きく二つに分けられ,僧侶と貴族,それにニコライ1世の創設した名誉市民は人頭税とともに兵役,体刑も免れた。
19世紀末に人口の7割以上がロシア教会に属したが,その僧はシノドの監督下にあり,独身の黒僧(修道士)と家族もちの白僧(俗僧)に分かれ,主教などの教会上層部は前者が占めた。村の司祭などとして民衆に接したのは後者であるが,その教養と生活水準は概して低く,社会的にも重んぜられなかった。
貴族には世襲貴族と一代貴族があり,後者は軍隊や官庁で一定の官等まで昇進した者で,彼らはさらに上位まで昇進すると世襲貴族になった。帝国の世襲貴族の数はそう多くなく,人口比で18世紀に0.5%台,19世紀に約1%であるが,この変化はポーランド分割で貴族の人口比の高いポーランド領を併せたためで,一時は貴族全体の3分の2がポーランド系になり,19世紀末にも彼らが世襲貴族の28.6%を占めた(ロシア系は53%)。貴族は1762年義務的国家勤務から解放されたが,その後も勤務志向が強く,また大部分の貴族は土地だけでは生活できなかった。農奴解放後貴族の土地喪失が続き,1911年の貴族所有地面積は解放時の半分になった。
ロシア帝国は農業国で,人頭税も初めは都市住民が3%だけ,残り97%を農民が負担していた。13年にも農村人口が約85%,農林業従事者が約4分の3を占めた。18世紀初め農民の約2割は国有地,4分の1は教会領に住んでいた。教会領はエカチェリナ2世時代国有化されるが,この国有地の農民は自由農で,これに対し貴族所領の農民が農奴であった。農奴制は18世紀を通じて拡大・強化され,世紀末には,農民の約6割(総人口の約55%)が農奴で,領主によるその扱いも家畜並みに近くなった。しかし19世紀に入ると農奴の人口比は低下し(1858年にヨーロッパ・ロシア総人口の38%),法的にも領主権に制限が加えられ,農奴解放への模索が続き,1861年これが実現した。
19世紀後半には人口増加で農民の土地不足が深刻化し,農業危機がおこり,20世紀に入ってストルイピンの農業改革が行われた。農村の人口過剰はシベリアなどの辺境や国外への大量の移住のほか,農村工業と出稼ぎによってもある程度緩和された。近代ロシアの資本家には,農村工業や穀物取引で成功した農民出身の者が多く,彼らは都市の大商人(クペーツkupets)やさらに名誉市民にもなった。都市小売商などはメシチャニーンと呼ばれて区別されたが,御者,下男,下女など都市の下層の多くは出稼農民であった。
ロシアの工場制工業も農民労働に大きく依存し,18世紀には工場に買われた〈占有農民possessionnye krest'yane〉,工場に編入された〈編入農民pripisnye krest'yane〉,さらに地主工場の農奴労働が特色をなし,ピョートル1世の開発したウラルの冶金業でも前者が大量に使用された。19世紀前半には新たな綿工業を中心に,大半が国有地・私有地の出稼農民からなる〈自由雇用労働者vol'nonayomnye rabochie〉が工場労働力の主力(1804年に47%,60年に87%)をなし,世紀後半にも工業・建設の労働者の大半は出稼農民であった。彼らは農村共同体(ミール)の成員で,工場でもアルテリを組んで働いたが,世紀末にはウィッテの工業化政策で急成長した重工業の熟練労働者を中心に,完全な都市労働者の階層が生まれ,労働運動の性格もこれに伴って変化した。
農民運動と民族運動にも2世紀間に変化があり,前者は18世紀にはブラービンKondratii Afanas'evich Bulavin(1660ころ-1708)の乱,プガチョフの乱にみられたように,モスクワ時代から続いた大量の農民逃亡とコサックの反乱との結びつきを特徴としたが,19世紀前半には農民反乱の件数は多いものの,大規模なものは少なく,農奴解放前後の農民運動の高揚も数年後には鎮静した。これは政府による国内治安の強化やコサック政策の成功によるところが大きく,帝政末期にはコサックは逆に革命鎮圧の先兵となった。農民は19世紀後半のナロードニキらの一斉蜂起への期待にも応えず,農民運動が大きな展開をみせるのは20世紀に入ってからである。
18世紀は,多民族帝国ロシアの民族運動と民族問題においても,バシキールの反乱,マゼパの謀反,プガチョフの乱への異民族の参加など,いわば民族主義以前の民族運動の時期であり,政府にとっても民族問題は宗教や生活形態の違い以上の意味はもたなかった。しかし19世紀にはナポレオン戦争期に始まるロシア人自身の民族的自覚と2度のポーランド反乱(十一月蜂起と一月蜂起)があり,ポーランド系地主の優勢な西部諸県にはゼムストボも導入されなかった。ポーランド反乱はロシア人の反ポーランド感情を高め,70年代には大ロシア主義とパン・スラブ主義の運動が起こった。1881-82年のウクライナでのポグロム以後ユダヤ人に対する居住制限などの政策が時とともに強められ,ポーランド,リトアニア,白ロシア,ウクライナでのロシア化政策も強化され,これがやがてドイツ人の支配する沿バルト3県や中央アジア,カフカスのイスラム教徒にも及び,ロシア皇帝治下のフィンランド大公国の自治権も侵された。これに対して起こった諸民族の民族運動は革命期に大きく発展し,帝国の崩壊を早めた。
18世紀のロシアでは,プロイセン,オーストリアなどと同様,フランスのブルボン朝の宮廷文化が輸入・模倣され,ピョートル1世によるペテルゴーフPetergof(現,ペトロドボレツ)の造営や婦人の同席を義務づけた〈夜会(アサンブレassemblée)〉の導入,エリザベータとエカチェリナ2世の華やかな宮廷生活も,アンシャン・レジームの宮廷文化の模倣であり,両女帝の派手な愛情生活さえがある意味ではそうであった。
18世紀のロシアは初めは神学校と実用的な軍学校しかもたなかったが,1731年貴族の子弟に西欧風の貴族教育を授ける幼年学校が設けられ,やがてモスクワ大学も開かれた。ロシアの上流貴族は留学や遠征の体験からも西方文化を身につけ,世紀末までに完全に西欧化した。学者・思想家ではロモノーソフ,ノビコフ,ラジーシチェフが活躍し,先駆的なインテリゲンチャも世紀末には現れた。19世紀初めカザン大学,ペテルブルグ大学(現,サンクト・ペテルブルグ大学)などが相次いで開校し,ツァールスコエ・セロ(現,プーシキン)のリセーも開かれ,他方カラムジンの活躍,ナポレオン戦争の体験,次いでドイツ・ロマン主義の影響があり,デカブリストの乱ののち,思想界ではチャアダーエフの発言に続いて40年代スラブ派と西欧派の論争が起こった。
文学ではプーシキン,次いでゴーゴリ,音楽では国民楽派の祖M.I.グリンカが現れ,クリミア戦争後のアレクサンドル2世期はロシア・リアリズム文学の黄金時代となり,ツルゲーネフ,L.N.トルストイ,ドストエフスキーらの主要作品が相次いで発表された。思想界,言論界もクリミアの敗戦とともに活況を呈し,《コロコル》が政府上層部でも読まれ,ゲルツェンとチェルヌイシェフスキーに代表される40年代人と60年代人の論争のなかでラズノチンツィ・インテリゲンチャが登場し,《現代人》《祖国雑記》などの雑誌が地方都市でも争って読まれた。
70年代にはバクーニン,ラブロフの影響を受けたナロードニキの〈人民の中へ〉の運動と人民の意志派のテロ活動が当局と社会に衝撃を与えたが,同時にカトコフの国家主義,I.S.アクサーコフらのパン・スラブ主義も現れた。世紀末の80-90年代,文学ではチェーホフが活躍し,社会思想としてはミハイロフスキーらのナロードニキ思想に対してプレハーノフに代表されるマルクス主義が浸透していくが,V.S.ソロビヨフの神秘主義哲学,K.N.レオンチエフの保守主義,さらにL.N.トルストイの人道主義も注目され,後者は遠く日本にも影響を与えた。楽壇では19世紀後半チャイコフスキーらの〈西欧楽派〉とムソルグスキーらの〈ロシア国民楽派〉が活躍し,現在まで続くロシア・バレエとオペラ,演劇の伝統も19世紀末までに生まれた。第1次大戦前の時期はロシア文化のいわゆる〈銀の時代〉で,象徴主義の開花に続いてアクメイズム,未来派といった新しい傾向が文学・芸術の諸分野に現れ,論壇では《道標》によるベルジャーエフ,P.B.ストルーベなどの活動が知識人のあいだに大きな反響を呼んだ。
ロシアの大学はウバーロフらの努力で1840年代にほぼ国際的水準に達し,以後世界的な学究を多数送り出し,クロポトキンの属したロシア地理学協会などの仕事も世界の学界に大きく寄与した。しかし政府による厳しい検閲,大学管理,学園紛争などでメチニコフ,P.G.ビノグラドフら多くのすぐれた学者が外国に移った。大学自治への干渉のほか,帝国政府は中等・初等教育にも統制を及ぼし,1871年にはギムナジウムの教科目に反動的改訂を加えた。さらに政治反動の80年代には下層階級の子女の中等学校入学を禁じ,ユダヤ人子弟の上級学校入学に数的制限をつけ,沿バルト3県のドイツ系学校のロシア化を強制し,初等教育でもゼムストボ経営校に対して教区学校の強化をはかった。しかしこの初等教育の立遅れはロシア社会の最大の欠陥であり,19世紀末になっても学齢該当児童の通学は2割に満たず,ロシア人の5人に4人は読み書き能力がなかった。第1次大戦直前ドゥーマが義務教育の実施を決めたが間にあわなかった。帝政ロシアの社会においてエリートと民衆の格差は教育面・文化面でも非常に大きかったのである。
モスクワ・ロシアはスムータ期にはなはだしく弱体化したが,17世紀の中期以後,君主権と身分制の強化,中央・地方の行政機関,税制,官僚組織の整備,常備軍の増強,教権の俗権への完全な従属(ニコンの失脚)などによって著しく強化され,絶対主義への傾斜を示した。この間,士族階級(ドボリャンストボ)はゼムスキー・ソボルによる国政参与の機会を失いながらも,農奴制の確立とポメスチエ(封地)の世襲化によって地主としての地位を確立するとともに,官僚としても大量に進出しはじめた。絶対主義への傾斜はこの時代の国内市場の成立過程と対応し,この時代には農民の商品生産と家内工業の発達,地主の直営地経営の拡大,都市手工業の分化,商品の種類と取引額の増加がみられ,またアルハンゲリスクその他を通ずる貿易も急増した。政府も工場設立や鉱山開発に外人技師を招く一方,商法を制定して自国商人を保護し,また豪商の協力で重要商品の内外取引を規制・独占するなど,財政・軍事上の必要から重商主義的経済政策をとりはじめた。早くも17世紀半ばにオホーツク海に達し,その後,1689年のネルチンスク条約で一時期を画したシベリアの開拓事業も,多分に重商主義的植民政策の性格をもつものであった。
ピョートル1世(在位1682-1725)の改革は,17世紀後半のこのような社会経済の発展を背景に,これに対応してとられたアレクセイ・ミハイロビチ(在位1645-76),フョードル3世(在位1676-82),さらにピョートルの少年期の摂政ソフィア・アレクセーエブナ(在位1682-89)の3代の政策を継承したものであった。ただ彼はその強い性格から,これまでよりもはるかに根本的な国制改革と積極的な政策を果敢に遂行して,本格的な絶対主義を確立した。しかし彼の改革も実はその多くが戦争遂行のためのものであり,必ずしも計画的なものではなかった。ロシアは1686年トルコとその属国クリミア・ハーン国に対抗してポーランドと同盟し,以後2回のクリミア遠征がおこなわれていたが,ピョートルも初めトルコに対する攻勢を決意して96年ドン川河口のトルコの要塞アゾフを奪取し,さらに対トルコ大同盟の結成を主目的として西ヨーロッパを旅行した。しかしこの同盟結成は失敗に終わり,アゾフも北方戦争の最中トルコに返還された。北方戦争ではロシアは初めナルバの戦に敗れたが,ポルタワの戦を転機に優勢に立ち,ニスタットの和約で念願のバルト海への進出を果たし,ヨーロッパの強国の仲間入りを果たすこととなった。晩年ピョートルはカスピ海西岸を併合し,中央アジアや北アジアにも注意を向けるようにした。
北方戦争初期,南東ロシアにコサックや少数民族の反乱が続発し,これがピョートルの行政改革の一誘因となった。彼の改革によって中央にはボヤーレ(貴族)会議と官署の代りに元老院とコレギア(参議会)が設けられ,地方には県制がしかれ,また総主教の代りに政府機関として宗務院(シノド)が置かれ,君主権が強化された。税制も根本的に改められて人頭税制が創始され,私有地のいっさいの農民,奴僕(ホロープ),浮浪人が同一の農奴身分に固定されるとともに地主に対する人身的隷属を強められた。ボチナ(世襲地)とポメスチエは統一され,士族階級はボヤーレを吸収し,いまや唯一の特権的貴族身分となったこの階級は,同時に,文・武官としての勤務を義務づけられた。他方,免税,高率関税などによって商人の経済活動が奨励され,官営および民営の工場(マニュファクチュア)建設が精力的に進められ,そのため工場に農奴を使用することも許された。軍事,行政,産業の必要から学校などもつくられ,さらに社会生活における旧習打破にも大きな力が注がれた。
ピョートルの改革に対しては何回か保守的な貴族と僧の反対の動きがあり,これは皇帝によって処断されたが,一般の貴族も皇帝の課した厳格な勤務を不満としており,彼の死後しばらく貴族の寡頭政治が続いた。この間,貴族の党派争いからしばしば宮廷革命が起こり,そのさい貴族からなる近衛連隊が重要な役割を果たした。エカチェリナ1世(在位1725-27)とピョートル2世(在位1727-30)のもとではメンシコフAleksandr D.Menshikov(1768-1831)が権力をふるい,アンナ・イワーノブナの代には,初め名門の貴族たちが,君主権の大幅な制限を試みて失敗し,やがてビロンErnest I.Biron(1690-1772)などのバルト地方出身のドイツ人が実権を握った。次いでこれに対する不満がイワン6世(在位1740-41)のもとで爆発し,エリザベータが即位した。彼女の代(1741-62)に,1725年に設立された科学アカデミーに続く美術アカデミーが設立され,またモスクワ大学が創設された。対外的にはロシアはピョートル1世ののち中国とキャフタ条約を結び,ポーランド継承戦争に参加し,トルコと戦って39年ドニエプル河岸に若干の地を得,次いでスウェーデンと戦い,さらにオーストリア継承戦争,七年戦争に参加して強国としての地位を維持した。南ロシアのコサックや少数民族に対する支配も強まり,またベーリングの北太平洋探検がおこなわれて,ロシア人が北アメリカにも進出するようになった。
18世紀前半にロシアの農奴人口は著しく増加した。地主は流通経済の進展につれて,農業経営と,これに付随する賦役労働による農産物加工に対する関心を高め,政府は18世紀半ば貴族銀行の設立,国内関税の廃止,ウォッカ製造独占権の貴族への付与,非貴族企業家の農奴購入禁止,貴族の文・武官としての勤務の義務制の廃止などの施策でこれに応えた。地主貴族の経済活動の活発化に伴って農奴の負担は加重され,その場合,概して南部黒土地帯では賦役が強化され,北部非黒土地帯では貨幣貢租が増徴された。高い貢租を支払うため農民の一部は行商や出稼労働者となり,商人や一部富農のマニュファクチュアのおもな労働力もこの出稼農民であった。18世紀中期には農奴の地主に対する人身的隷属も強化され,農奴の売買も普及しだしたが,これに対して農民反乱もまた増加し,1773年にはプガチョフの乱が起こった。宮廷革命によってピョートル3世(在位1762)に代わった啓蒙君主エカチェリナ2世(在位1762-96)は,即位したのち,その法典編纂委員会に与えた〈訓令〉で法の前における万人の平等をうたって,農奴制についてもかなり批判的であった。しかし,この彼女もプガチョフの乱ののちは身分制の原則を固執し,75年の地方制度の改革と85年の貴族に対する特権認可状で,地方の行政と司法に貴族を参加させ,またその身分的特権を確認し,〈貴族帝国〉の時代を現出せしめた。商工業の自由の原則に基づいて彼女がおこなった独占と産業規制の廃止の政策も,貴族の経済上の特権と利益をそこなうものではなかった。〈貴族帝国〉の時代はロシア農奴制の絶頂期で,農奴制はこの時代に国有地の賜与に伴う自由農民の農奴化などで量的にはなお発展したが,農奴制経済の矛盾もすでに現れ始めていた。
エカチェリナの時代にロシアは2度の露土戦争によって黒海への進出とクリミアの領有という永年の宿望を達し,またポーランドに対する再三の干渉とその成果としての3回のポーランド分割で,数世紀前に失ったウクライナと白ロシア(ベロルシア,現ベラルーシ)の全土を回復するとともに,リトアニアとクールランドを獲得し,ヨーロッパの国際政治におけるその地位を高めた。フランス革命に対してはロシアはこの時代にはなお直接関与するには至らなかったが,国内では自由思想がきびしく取り締まられ,社会事業家でジャーナリストであったN.I.ノビコフや大作《ペテルブルグからモスクワへの旅》を書いたラジーシチェフがその犠牲になった。
帝権を貴族階級からも超越した神聖な絶対権と考えたパーベル1世(在位1796-1801)は,先帝の特権認可状が確認した貴族の諸特権を次々に否認もしくは制限し,他方,農民に請願権を認め,またその賦役日数を制限しようとし,また軍人と官吏に病的なまでに厳格な規律を要求して違反者を厳罰に処した。このため皇帝の統治は貴族階級の恐怖と不満を招いたが,外交政策でも皇帝は,初めフランス革命の国内への影響の防圧と正統主義の立場から対仏大同盟に参加して出兵しながら,のちナポレオンによる革命の終結を期待してこれと和し,逆にイギリスと断交して貿易に打撃を与えたため,宮廷革命が起こって殺害され,その恐怖政治体制と外交政策はアレクサンドル1世(在位1801-25)によって否定された。しかし貴族の黄金時代はパーベルの統治を転機に過ぎ去った。その基礎をなす農奴制経済が,資本主義の発達に伴って,19世紀前半その危機をしだいに深めていったからである。
19世紀前半にロシアの工場数は1804年の2423から25年の5261,58年の1万2259へと増加,労働者数もこの間9万5000から55万にふえ,しかもこのうち賦役労働者に対して雇用労働者の比率が,商人や富農経営の工場の増加と機械導入による自由な労働力に対する需要の増加から,しだいに高まっていった。しかしこの雇用労働者も多くは出稼ぎの貢租農で完全に自由な労働者ではなく,農奴制の存する限り資本主義の発達は制約を受けた。農業においても20年代以後進歩的地主の試みた集約的農業と一部農業機械の導入が,農奴制の存在のため失敗し,一般には耕地の拡大,賦役の強化という方法がとられたが,これも地主経営の窮迫を救うものではなく,かえって収奪が強化されたため農民の暴発が増加した。このような農奴制の行きづまりに対処するため,既存の国家・社会体制を部分的ながら社会のブルジョア的進化に即応させようとしたのがアレクサンドル1世であり,これを同じく部分的な改革によって補強しながら維持しようとしたのがニコライ1世(在位1825-55)であった。
アレクサンドルは即位当初〈若き友人たち〉とともに農奴解放と立憲制を論じたが,農奴解放については,市民と自由農民に土地所有が許され,貴族にその農奴の解放が許され,さらにのちバルト諸県で農奴解放がおこなわれて,ロシア本国の農奴制廃止への第一歩が踏み出されたにとどまり,立憲制も,皇帝がその君主を兼ねることになったフィンランド大公国とポーランド王国では実施されたが,本国ではM.M.スペランスキーなどが何回か草案を作りながら結局実施をみず,かえって参議会に代わって設けられた各省と国務評議会が官僚政治の温床となった。このような改革と官僚支配に対しては最初から地主貴族が強く反対したが,彼らはまた,1805年以来のナポレオンとの戦争を終結させたティルジットの和議ののち,大陸封鎖による農産物輸出の不振に脅かされて外交政策の転換を要求し,結局ナポレオンのロシア遠征を招来したのであった。
ナポレオンの敗退後,アレクサンドルはヨーロッパの解放者としてウィーン会議に臨み,ポーランド王国を創始してその国王となった。彼はこの時までにペルシア,トルコ,スウェーデンとも戦ってそれぞれグルジア,ベッサラビア,フィンランドを手に入れていた。しかし永年の戦争,とくにナポレオンの遠征は国土の荒廃と国庫の枯渇をもたらし,このため軍事費節約の目的で屯田兵制度が実施された。これを推進したのは,アレクサンドルの晩年に軍隊と官僚と警察を支配して反動的な官僚政治をおこなったA.A.アラクチェーエフ将軍で,彼は国民のうらみの的となった。国際政治の面でもこの時代にロシアは,アレクサンドルの提唱で生まれた神聖同盟の保守的側面が現実政治家メッテルニヒの国際的反動政策に利用されることを許した。このため戦後のロシアの政治に対する幻滅から,教養ある貴族出身の青年将校を中心に秘密結社が生まれ,彼らは1825年,ニコライ1世の即位の際,軍事革命(デカブリストの乱)を企てた。
デカブリストの乱で貴族階級に強い不信の念をもったニコライ1世の下でロシアは,皇帝直属官房を中心とする完全な官僚支配の下に置かれた。もっとも,ニコライはアレクサンドルとちがって政治についてなんらの幻想をもたず,それだけに農奴制国家の矛盾についてもかなりの現実的認識をもっていたので,彼の政治には,法典の整備(スペランスキーによる〈ロシア帝国法律大全〉〈ロシア帝国法典〉の編纂),農奴売買の制限,地主の自発的農奴解放の奨励(〈義務農民〉創設に関する法令),国有地農民の地位改善と自治確立(キセリョフの改革),工場付農奴の解放許可,雇用労働者の帰村制限,通貨の安定(カンクリンEgor F.Kankrin(1774-1845)の幣制改革),教育機関の拡充,とくに実業専門学校の設置,などの若干の積極的な面もあった。しかしこれらはいずれも農奴制体制の枠内での部分的改革ないし資本主義育成策であって,専制主義と農奴制の原則は堅持され,これに反対するいっさいの思想と運動は,全国の特高警察の頂点に置かれた皇帝直属官房第三部の直接の弾圧ときびしい教育および言論統制によって抑圧された。この思想統制は1848年のヨーロッパの二月革命および三月革命以後一段と強化され,これ以前から正教・専制・国民性の三原則(いわゆる〈官製国民主義〉)をかかげる文教当局の統制下にあった大学は完全に自主性を奪われ,またM.V.ペトラシェフスキーのグループが社会主義宣伝の疑いで逮捕された(ペトラシェフスキー事件)。しかしこのような弾圧にもかかわらず,ニコライの時代にロシアの思想界は空前の活況を呈し,スラブ派と西欧派の論争が展開されてベリンスキー,ゲルツェンなども活躍し,またプーシキンによるロシア国民文学の確立に続いてその社会性を特色とする多くの作家が活動しはじめた。
国内で憲兵政治をおこなったニコライの政府は国外でも〈ヨーロッパの憲兵〉の役割を果たそうとし,七月革命にはポーランドの十一月蜂起(1830-31)に妨げられて干渉できなかったが,二月革命のさいにはオーストリアの要請で大軍を派してハンガリーの革命を鎮圧した。十一月蜂起の鎮圧後,ニコライはその憲法を廃して自治権を制限し,また旧ポーランド領西部ロシアのロシア化政策を開始した。ヨーロッパ以外ではニコライの政府は,正統主義の原則に拘束されることなく,中央アジアのアラル海岸と極東のアムール川流域への進出を企て,またペルシアと戦って28年若干の領土と貿易上の譲歩を得たほか,同様にロシア資本主義の要求でもあったいわゆる東方問題の有利な解決をその外政の最大の課題とし,はじめアドリアノープルの和議と,これに続くウンキャル・スケレッシ条約で黒海およびボスポラス,ダーダネルス両海峡の事実上の支配権とトルコに対する完全な商権を獲得したが,列強の強い反対にあってロンドン条約(1840)で逆に黒海に封じこまれ,のちこれを強引に打開しようとしてクリミア戦争をひき起こした。
ロシア経済の後進性と官僚政治の欠陥を暴露したクリミアの敗戦後,アレクサンドル2世(在位1855-81)の下でロシアは改革の時代を迎えた(大改革)。しかし改革の中心をなした農奴解放は地主側の強い反対をおしきっておこなわれたものの,61年の解放令で農民は旧保有地の一部を失い,不当に高い土地買戻し金を負担させられ,人格的にも農村共同体に緊縛されることになった。このため解放令の発布後農民運動はむしろ激化し,チェルヌイシェフスキーなど革命的インテリゲンチャの運動も活発になったが,これは政府の弾圧と,ポーランドの一月蜂起(1863-64)の反動で起こった愛国的風潮のため一時おさえられた。反乱後ポーランドと西ロシアではロシア化政策が強化された。しかし政府はこのような弾圧政策の一方で改革事業を継続し,御料地農民への土地売却,財政改革,新大学令の公布などに続いて64年重要な地方自治制度の実施(ゼムストボ創設)と司法改革をおこない,その後も検閲の緩和,国有地農民への永小作権付与,自由貿易の採用,都市自治の強化,中等教育の改革などをおこない,最後に74年に一般義務兵役制を実施した。
61年の農奴解放は不徹底なもので,解放後にも地主経営には農奴制賦役の変形たる雇役がおこなわれたりしたが,農民層の階層分化は多くの法的制約を超えて進行し,これが労働および商品市場を広げて工業と一部農業の資本主義の発達を促し,工業生産は20年間に3倍になり,また鉄道建設が進んで重工業の発達を刺激した。農奴解放後新しい条件に適応できないで多くの地主が没落し,他方資本家階級と専門家階級(医者,弁護士,技師,学者など)が社会的に進出し,後者はゼムストボの一部進歩的地主とともにブルジョア的改革の深化を要求した。これに対してこの時代に教育の普及によって増加した雑階級(ラズノチンツィ)の青年インテリゲンチャは社会主義を志向し,70年代前半に〈人民の中へ〉の運動を起こした。しかしナロードニキのこの大衆運動は農民の反発と官憲の弾圧にあって失敗し,このため彼らの一部はやがてテロ戦術に走り,1881年皇帝アレクサンドル2世の暗殺に成功した。
クリミア戦争後ロシアは一時フランスと和親したが,63年以後プロイセンと接近し,その支持をたのんで黒海艦隊の再建,中央アジアの征服をおこなった。極東ではロシアはアムール川以北と沿海州を手に入れ,アラスカを手離し,ウルップ島以北の千島列島と南樺太(サハリン)を日本と交換した。70年代中期に政府は,しだいに高まってくる国内のパン・スラブ主義的感情を背景に,注意をふたたびバルカンに向け,南スラブの反乱に関与して露土戦争を起こし,トルコには勝ったが,列強の干渉のためビスマルクの主催したベルリン会議で譲歩せしめられた。このためドイツとの関係が一時冷却し,三帝同盟も事実上解体したが,中央アジアでのイギリスとの対立などのため,81年三帝同盟が再締結された。中央アジアでのイギリスとロシアの関係は年ごとに悪化し,85年には一時戦雲がみなぎったが,戦争は回避された。87年ロシアとドイツの間に再保障条約が結ばれたが,このころから両国の貿易上の利害の対立が深刻化し,90年永い友好関係が絶えた。
アレクサンドル2世は晩年皇帝官房第三部の廃止などの改革をおこない,政府部内では自由主義的世論への譲歩の方向が有力になりつつあったが,新帝アレクサンドル3世(在位1881-94)は反動の哲学者,宗務院院長ポベドノスツェフの影響下に専制主義の堅持を宣し,帝の下で最初農民と労働者の地位の部分的改善(旧農奴への分与地売却強制,分与地購入国庫貸付金返済額の引下げ,農民銀行創設,人頭税廃止,工場法設定,婦人・少年労働の制限)に努力した多少とも進歩的な大臣もやがて職を追われ,政治の方向は急速に反動化していった。政府は85年貴族銀行を創設,89年農民共同体(ミール)を貴族出身の地方主事の監督下に置き,翌年ゼムストボの権限を縮小,農民の代表権を制限した。大学自治の制限,教区付属学校の強化,非国教徒とくにユダヤ教徒の迫害(ポグロム),バルト諸県を含む西ロシアの大ロシア化政策の強化など,反動は教育・宗教・民族政策の面にも及んだ。この政策はニコライ2世(在位1894-1917)にも継承され,99年にはフィンランド議会の権限が削減された。
80年代に工業は不況期にあり,農業も穀物輸出の不振などで地主経営・農民経営ともに深刻な危機を体験した。とくに農民経営はその困難がはなはだしく,80年代前半の改革も土地不足と共同体的規制による生産の停滞を解決するものではなく,頻発する凶作と疫病のつど多数の死亡者が出,この状態はシベリア移民のふえた90年代にもほとんど変わらなかった。しかし工業は90年代に急速な発展をとげ,銑鉄,石油,石炭などの生産は10年間に3倍になった。これに伴って生産の集中,銀行資本の産業支配も進み,20世紀初めにロシア資本主義は帝国主義の段階に入った。このような急速な発展は91年の関税引上げ,シベリア鉄道建設開始とこれに続く蔵相ウィッテの財政金融政策(ウォッカ専売,金本位制採用など)によって可能となったが,とくに重要なのは外国資本の役割で,工業におけるその割合は1900年に40%を超えた。外国資本のなかでは,1888年以来ドイツに代わってロシアの外債を引き受け,これに伴って政治的・軍事的にもロシアと接近して露仏同盟で結ばれていたフランスの資本が優越し,パリの金融資本はこの時代ロシア資本主義の近東・極東での市場開拓(ペルシア・ロシア銀行設立,シベリア鉄道建設,三国干渉とこれに続くロシア対清国借款供与,東清鉄道建設,さらに遼東半島租借と南満州鉄道建設)にも協力した。
資本主義の発展には労働者階級の増大と集中が伴い,とくにその集中度は,どの資本主義国にもまさったが,生産技術と労働生産性はなお先進諸国に劣り,また労働者の労働条件も劣悪で,賃金水準は低く,労働者に対する法的保護も薄かった。このため労働運動がしだいに発展して90年代中期にとくに激化し,97年に政府は労働時間制限(11時間半)の法令を出した。労働運動とともに革命運動も盛んになり,インテリゲンチャの間にマルクス主義が普及して1898年ロシア社会民主労働党が結成され,次いで1901年ナロードニキの伝統を継承したエス・エル党が生まれ,03年には自由主義者が解放同盟(カデットの前身)に組織された。1900-03年は恐慌期で全国をストライキの波が襲い,農民暴動が頻発し,また大臣の暗殺なども起こった。これに対し内相プレーベなどの反動政治家は弾圧と言論統制の強化,警察の指導する労働組合の組織,反ユダヤ運動の扇動などで革命の圧力をそらそうとしたが成功せず,対外的勝利による政府の威信の回復をねらって極東で露骨な侵略政策をとり,日露戦争をひき起こした。しかしロシア軍は陸海に連敗したため,国内の革命的気運はますます成長し,05年1月の血の日曜日事件を契機に第1次のロシア革命が起こった。革命の波は〈十月ゼネスト〉で最高潮に達し,このため皇帝はいわゆる〈十月宣言〉で立憲政治を約束し,この後革命の波はようやく後退していった。
革命の後退とともに反動勢力は立ち直り,皇帝は1906年の第1国会開会直前,10月の譲歩を献策した首相ウィッテを退け,国家基本法(憲法)を発布して軍事,外交などの大権と国会閉会中の緊急立法権(いわゆる87条)を留保し,十月宣言からの後退を示した。第1国会は,選挙法を不満とした左翼政党のボイコットにもかかわらず,カデットなどの野党が多数を占めて,とくに農民議員が地主所有地の分配を要求したため,政府はこれを解散した。国会議員は解散の不当を国民に訴え,07年の第2国会には左翼政党も参加して政府を激しく攻撃したが,これも夏には解散され,同時に憲法を無視して選挙法が一方的に改悪され(6月3日のクーデタ),この結果同年末に成立した第3国会では政府に協力的な保守派(オクチャブリスト)と反動派が多数を占めた。このような強引な国会対策を指導したのは,第1国会解散直後に首相となったP.A.ストルイピンで,彼は労働者・農民・少数民族の運動に対しても,革命末期から盛んになった一部の反動的風潮と極右テロ分子の異民族迫害・専制復活の運動を利して,徹底的な弾圧政策をもって臨み,軍法会議で多数の革命家を処刑し,革命で合法化されたばかりの多数の労働組合を閉鎖に追いこみ,また革命で復活したフィンランド議会の自治権をふたたび制限した。世紀初めの恐慌から転じた不況期におこなわれたこのような弾圧は,革命の敗北からおこった民衆の絶望感を深め,労働組合や左翼政党の指導者の動揺,自由主義インテリゲンチャの政治的関心の後退を招いた。
しかしストルイピンはこうした弾圧政策の一方,有名な土地改革をはじめ大規模なシベリア移民,初等教育の普及など若干のブルジョア的改革をもおこない,革命で動揺した政府権力に対する支持層の拡大を図った。ミールの解体と自作農の創設による前世紀以来の農業問題の解決をねらいとした彼の土地改革は,農民層の階級分化と富農経営の発展を促進し,国内の労働および商品市場を拡大して工業の新たな発展の前提をつくり,1910年好景気が産業界を訪れ,第1次大戦までロシア経済は躍進を続けた。しかしそれとともに労働運動もまた活発になり,12年春のレナ事件(ストライキ労働者射殺事件)を契機にストライキの波が急速に高まり,全国的に拡大した。これを反映して12年の第4国会の選挙では極左と極右の勢力が伸び,ストルイピンの死後円滑を欠いていた国会と政府の関係はさらに悪化したが,皇帝はこの間無能な人物を重用してみずからの発言権を高め,また宮廷には予言者ラスプーチンなどが出入りし,大戦直前には国会内外の穏和派も政府と宮廷に対して批判的になりつつあった。
第1国会開会直前,政府はフランスから巨額の借款を供与され,戦争と革命の打撃からの立直りを容易にされたが,この後ロシア外交のフランスに対する従属は強化され,1907年フランスの仲介で英露協商が成立し,極東でもイギリス,フランスの利益にそって日露協商が締結され,ロシアはイギリス,フランスのドイツ包囲計画の一環たらしめられた。英露協商ののちロシアの注意はふたたびバルカンと近東に向けられ,08年オーストリアおよびドイツとの間に危機が生じたが,これはストルイピンの平和政策によって回避された。ストルイピンの死後ロシアのバルカン政策は積極化し,その指導下にバルカンの4国が同盟した。しかしこの同盟は12年秋トルコと戦い,これには勝ったが,内部対立から翌年第2次バルカン戦争を起こし,結局ブルガリアのロシアからの離反とドイツ,オーストリアへの接近,トルコのドイツとの提携強化というロシアにとって不利な事態をもたらした。この間ロシアはイギリス,フランスの財政的援助をも得て陸・海軍の再建・強化に努め,とくに14年になってからはドイツ,オーストリアとの開戦を不可避とみて戦争準備を急いだが,国運をかけるドイツとの戦争の決意は容易につかず,サラエボの凶変後も妥協工作を続け,結局ドイツの宣戦によって大戦に突入した。
ドイツとの戦いは開戦当初全ロシアを愛国的興奮の波にまきこみ,少数のボリシェビキを除いてすべての政党と団体が戦争完遂を誓った。しかしロシア軍が開戦後まもなくタンネンベルクで大敗し,さらに15年夏,東部戦線に攻撃の重点を移したドイツ,オーストリア軍の前に総退却を続けると,挙国一致の体制は急速にくずれていった。イギリス,フランスの利益に左右されてロシア軍が作戦的に無理を重ねたことのほか,軍需品補給に関する官僚政府の無能が,前線での敗退の主要原因であったので,国会と民間団体の指導者はしきりに政府の改造と軍需品補給業務への民間人の参加を要求し,そのさい国会のブルジョア派(オクチャブリストとカデット)は〈進歩派ブロック〉を結成し,軍需工業資本家は戦時工業委員会を組織した。しかし皇帝はこれらの要求を部分的にしか満たさなかったばかりでなく,15年9月新たにみずから総司令官の地位について軍事作戦の指導権をもその手に握り,しかも他方このため前線に出て不在がちな皇帝に代わって皇后の発言権が強まり,この皇后とラスプーチンがやがて,戦争の被害の大きい商業資本家と地主の対ドイツ単独講和の策動の中心になった。このため16年には,前線への補給も増加して戦局がかなり好転したにもかかわらず,国会と政府および宮廷との対立はむしろ深刻化するようになり,皇帝は国政の運営の自信を失い,ひんぱんな大臣の更迭によって行政を混乱させた。
ロシアの経済的後進性という条件のもとで,政府のこのような無能・独善と行政の混乱は,前線における将兵の犠牲を大きくしたばかりでなく,銃後の国民生活をも交戦国中最も早く窮迫せしめ,とくに都市では物価騰貴と食糧不足で生活が苦しくなり,これが戦局の不利,政局の動揺,宮廷と官界の腐敗,戦時成金の横行などと相まって民衆の不満を呼び起こした。早くも15年大都市で労働運動と社会主義者の活動が盛んになり,16年には農村や一部軍隊,さらに辺境の少数民族にも動揺が波及し,大都市のストライキは革命的性格をおびるようになった。このような情勢から国会の〈進歩派ブロック〉を中心とする主戦派のブルジョアジーは宮廷と官僚政府からの戦争指導権の奪取を急ぎ,16年11月にはカデットの指導者であるP.N.ミリューコフが国会で皇后の政治関与を痛烈に弾劾し,翌月事態の重大性をうれえる皇族と有力貴族の手で,ラスプーチンが葬られた。しかし皇帝はこの後もその政策を改めず,このため,17年初めには軍部と政界上層で自由主義的皇弟ミハイルをかつぎだす宮廷革命の計画が進んだが,これが実行に移される前にペトログラードの労働者が立ち上がり,これに軍隊も合流して第2次のロシア革命(二月革命)に発展し,帝政は崩壊した。
→ソビエト連邦 →ロシア →ロシア革命

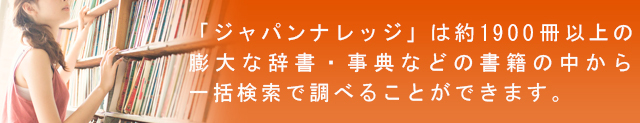










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.