
木綿の浴衣地でつくられた単衣(ひとえ)の長着。家庭での湯上がりのくつろぎ着のほか、夏祭り、縁日、盆踊り、夕涼みなど夏の衣服として着用される。街着にはならないが、夕方の散歩着としては着用する。浴衣は肌襦袢(はだじゅばん)を用いず素肌に着て、素足下駄ばきとし、草履(ぞうり)は履かない。女子は半幅帯を締め、普通の着物よりやや短めに着る。男子は兵児帯(へこおび)を締める。足袋(たび)は履かない。
浴衣地は主として平織白木綿に藍(あい)染めをする。地白に藍、または地藍に白で紋様を出して染める。白木綿は、栃木県真岡(もおか)で織られていた真岡木綿を用いていたが、明治以降、三河地方(愛知県)で織られた岡木綿に押され、近年では岡木綿が浴衣地に用いられている。
浴衣の柄は中形(ちゅうがた)を用い、浸染(しんせん)により藍染めをする。これを中形浴衣といい、普通に浴衣というときはこれをさす。江戸で発達したこの中形は江戸中形とよばれる。6尺(約180センチメートル)1枚の長板(ながいた)に布を張って型置きをし、裏からも表にあわせて型を置き、浸染によって染めるところから長板中形ともいう。手のこんだ染め方によるこの両面物の高級浴衣地の技術は、現在国の重要無形文化財になっている。明治の末ごろからは手拭(てぬぐい)に用いられていた注染(ちゅうせん)の技法を応用して、一反の布を染める手拭中形が浴衣に用いられるようになった。手拭中形は手拭の長さに折り畳み、型糊(かたのり)をつけて、上から染料を注ぎ染めるので、折り返したところから模様が逆に染まる。初めは下級品として扱われていたが近年は模様構成もよくなり、型染め浴衣はほとんどこの方法が用いられている。今日の柄(がら)は、型紙の長さ約1メートルで折り返したところから逆に染まり、その対称の繰り返しとなっている。そして昭和の初頭から機械捺染(なっせん)による片面物の浴衣地が出回るようになった。このほか有松絞り(三浦絞り)、柳絞り、蜘蛛(くも)の巣(す)絞り、博多(はかた)絞りなど、木綿の藍染め絞りの浴衣もある。夏祭り、盆踊り、舞踊の浴衣にはそろいのものが多く用いられ、半身白、半身藍染めによる片身替わり、衿(えり)肩を中心に大きく半円形を描いて染められた首抜き模様、肩山より裾(すそ)に向かってだんだん柄が大きく染められた付下(つけさ)げ風絵羽浴衣など、はでで粋(いき)なものが好まれる。また一方、濡燕(ぬれつばめ)、唐傘(からかさ)、笠(かさ)、柳ひょうたん、朝顔などの小紋風のものもある。
布地は綿平織のほか近年、綿縮(ちぢみ)、綿絽(ろ)、表面に高低のある紅梅織などが用いられ、さらに木綿にかわってポリノジック、ポリエステルなどの化繊、または混紡も用いられている。染め色にも濃淡を出した細川染め(二度染め)や、若い人向きにピンク系、グリーン系など、藍や白以外の地色の浴衣も用いられるようになった。
男子の浴衣の柄は石摺(いしず)り風のものが多く用いられていたが、近年は無地に近い柄から小紋柄風にはでな感じのものまで多様になってきている。子供物には木綿の浴衣地とともにリップルが多く用いられ、子供らしく多色染めになっている。先染め浴衣地には白縞(しま)、白格子などの縞柄のものがあり、これは主として旅館などでの寝巻に用いられ、また歌舞伎(かぶき)役者は、浴衣に屋号、家紋などを染め、ひいき筋への贈呈に用いることもある。また芝居、舞踊のうえでの特殊な場合に、縮緬(ちりめん)浴衣を用いることがある。
浴衣地の布幅は35~36センチメートルである。体格の向上に伴って男物にはキングサイズといって40センチメートルほどのものもつくられているが、女物は柄の関係でまだ少ない。一反の長さは10~11メートルであったが、最近は12メートルぐらいのものも多くなってきた。
浴衣は湯帷子(ゆかたびら)の語から転じたもので、古くは沐浴(もくよく)に麻衣を着用した。湯帷子は普通の帷子に対していう語であり、手拭に対して浴衣を身拭ともいい、年間通して用いられた。のちに浴後に汗取りとして用いるようになった。民間で浴衣を着用するようになったのは、室町時代の終わりから江戸初期にかけて、盆踊りが盛んに行われるようになってからである。江戸後期には浴後に用いるだけでなく、庶民のなかには単衣や帷子のかわりに着用する者もあった。浴後に着用するものは広袖(ひろそで)(袖口の下を縫い合わさない袖)とし、単衣にかえて着用するものは方形の袂袖(たもとそで)にしていた。江戸の婦女の浴衣の袖は、単衣の略用という意味で袂を丸くしていた。木綿のごく細い縞(しま)や絣(かすり)は、広袖にして袖口下に刺縫いをして用いていた。刺縫いの糸はおもに黒を用い、白や茶も用いられた。なお京坂では刺縫いはしない。女性用の雨合羽(かっぱ)がない時代には、武家の女性たちは浴衣をまとい、しごきをして雨よけにも用いた。江戸時代の浴衣は、江戸、京坂の男女とも白地に藍染めの小紋を、また地染(じぞまり)に小紋を染めたものが用いられた。当時型紙の大きさにより大形、中形、小形などの区別があった。中形は一送り鯨尺(くじらじゃく)3寸7分(約14センチメートル)ないし7寸5分(約29センチメートル)の型紙を用いて単純色相で染め上げた模様をいう。中形が盛んに用いられるようになって、中形は着尺地の染模様の代表となった。用いられた模様を、型紙によってあげてみると、紗綾(さや)形、松皮菱(まつかわびし)に松毬(しょうきゅう)、よろけ地に紫陽花(あじさい)、よろけ地に霞(かすみ)と千鳥、変わり格子に流水と桜、瓢箪(ひょうたん)に紋入り蝙蝠(こうもり)、柳に燕(つばめ)など文様は細緻(さいち)なものであった。ほかに大形の紋や白地に藍の縞、鳴海(なるみ)絞り、柳絞りなども用いられた。男子の浴衣の大柄のものには源氏車に立浪(たつなみ)、傘骨と海老(えび)、船の碇(いかり)など、大柄でないものはあらめの匹田(ひった)絞りの大きいものを用い、鳶(とび)の者はその組の記号を表した絞りを着用した。
木綿のゆかた地で単(ひとえ)仕立てにした夏の家庭着。昔,貴人が入浴のときに着た湯帷子(ゆかたびら)から転じた。本来は麻であったが,江戸時代木綿地とふろ屋の普及によって,一般にも湯上りに用いられるようになった。雨合羽のかわりに使った記録もあるが,湯上りだけでなく,庶民の夏の家庭着として,また古いゆかたは寝巻やおしめとして用いられた。人前で着るものとして扱われなかったゆかたが,男女ともに外出にも着るようになったのは明治中期以後,上物ができたからである。現在でも女物の紅梅(こうばい),綿絽(めんろ),綿縮(めんちぢみ)などの中形(ちゆうがた)染や長板本染中形(ながいたほんぞめちゆうがた)の高級ゆかたは,八寸名古屋帯をお太鼓に締めて街着とする。家庭用は裾除(すそよけ)をつけて素肌に着,半幅帯を締めるが,街着とする高級ゆかたには半じゅばんを着る。ゆかたを着る人は年々少なくなってきたが,ゆかた地の甚兵衛(じんべえ)や簡単服などが市販されているのは,吸湿性のよい木綿の肌ざわりと藍と白に代表される日本的な色柄が好まれるからであろう。
ゆかたを中形とも呼ぶのは小紋(小柄)に対しての柄の大きさを意味するが,大,中,小の柄がある。生地は平織が主だがコーマ糸使いが上等で,絽目のある綿絽,強撚糸を使ったさらさらとした肌ざわりの縮,縦横に太い糸を枡目(ますめ)に織り込んだ紅梅などがある。長板本染中形は板張にした生地に型紙を使って両面の柄をあわせるようのりを置き藍染にした高級ゆかたで,その技術は無形文化財として指定されている。昭和初期ごろから盛んに行われた注染(ちゆうせん)中形は,手ぬぐいと同じように生地を折りつけながらのり置きし染料を注いで染めるので,手ぬぐい中形,折付け中形ともいう。簡便な染め方だが,多彩な染分けもできる。ほかに小柄な籠付(かごづけ),絞り,ろうけつなどもあるが,絞りは高価でも家庭用である。男物には白絣,織縞もあり,奇抜で大柄な祭りゆかた,踊り用の絵羽ゆかたなど種類は多い。先染で縞や格子に特徴のある阿波しじら,麻地の中形も街着として用いられる。子ども用には苛性ソーダで凹凸をつけたリップルもある。

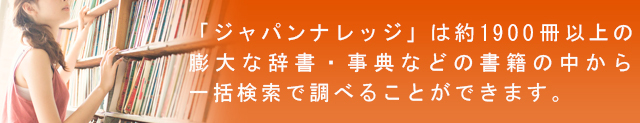
 [オ]
[オ] [ユ
[ユ [ユ]
[ユ]





©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.