
〔名詞〕短歌の上(かみ)の句(五七五)と下(しも)の句(七七)とを、二人が応答してよむ詩歌の一種。平安時代に発生し、はじめは、二人の唱和で一首とする「短連歌(たんれんが)」であったが、中世以降、二人以上(時には一人)で、五七五と七七の句を交互に長く続ける「長連歌」(「鎖連歌(くさりれんが)」とも)が発達し、室町時代に最も盛んに行われた。
例「何阿弥陀仏(なにあみだぶつ)とかや、連歌しける法師の、行願寺の辺(ほとり)にありけるが、聞きて」〈徒然草・89〉
訳何阿弥陀仏とかいう、連歌をやっていた法師で、行願寺のあたりにいた者が、聞いて。
「連歌」の種類と歴史
長連歌には、歌仙(三十六句)・五十韻(いん)・百韻・千句・万句などの形式があり、第一句を発句(ほっく)、第二句を脇(わき)の句、最後の句を挙句(あげく)という。鎌倉時代には、滑稽(こっけい)を主とする無心派(栗(くり)の本(もと))と、風雅を主とする有心(うしん)派(柿(かき)の本)とに分かれたが、後者が優勢となり、やがて二条良基らの『菟玖波集(つくばしゅう)』、飯尾宗祇(いいおそうぎ)らの『新撰菟玖波集』として結晶した。一方、室町末期には、無心派の流れをひくおかしみをねらう俳諧(はいかい)の連歌が起こり、次の時代の俳諧のもととなった。なお、連歌のことを「筑波(つくば)の道」というのは、連歌のもとを、『古事記』にある、筑波をよみこんだ倭建命(やまとたけるのみこと)と火焼(ひたき)の翁(おきな)との問答歌を、連歌の初めと考えることによる。
平安朝時代に主として流行した短(たん)連歌と、鎌倉時代から江戸時代初期にかけて流行した長(ちょう)連歌を、その当時においては、ともに連歌とよんでいたが、一般には後者をさす。それは中世とともにおこり、中世とともに滅んだ、中世特有の詩である。
短連歌は、五七五の前句に別の作者が七七の句を付けるか、あるいは、七七の前句に五七五の句を付けて完結させるもので、『八雲御抄(やくもみしょう)』では、こうした形式のものを一句(いっく)連歌とよんでいる。両人による唱和の詩というべきものであるが、一首の和歌を2人で合作するという意識で詠まれたものもある。それに対して、長連歌は、五七五の句に七七の句を付け、それにさらに五七五の句を付けるというふうにして、長句と短句を交互に付けて一定数に至るもので、院政時代には鎖(くさり)連歌とよばれ、鎌倉時代以後は百韻(100句)が定型とされた。この百韻十巻を千句、千句十巻を万句といった。また、百韻に満たない、五十韻、世吉(よよし)(44句)、歌仙(かせん)(36句)などの形式の連歌もときおり行われていた。
百韻は数人から十数人の人数で制作するのが普通であるが、その参会者を会衆(かいしゅう)とか連衆(れんじゅう)という。まれには1人、2人、3人などで詠む場合もあり、それぞれを独吟、両吟、三吟などとよんだ。百韻を書き留める書式としては、懐紙を横に半折した折紙(おりがみ)四枚を用いて、一(いち)の折(初折(しょおり))の表に8句、裏に14句、二、三の折は表・裏ともに14句ずつ、四の折(名残(なごり)の折)には、表に14句、裏に8句を記すことになっていた。完成期の連歌の規則は、こうした書式のうえに組み立てられていた。
長連歌の最初の句を発句(ほっく)、その次の句を脇句(わきく)、その次の句を第3、最後の句を揚句(あげく)(挙句)、その他の句を平句(ひらく)といい、発句は一座のなかの練達の士、客人、高貴の人などが詠み、その時節の景物を詠み込むものとされていた。発句は句形のうえでも内容のうえでも独立しているが、脇句以下は、その前の句に付けて、前句とあわせて初めて一つの句境を構成するのである。
連歌は数人以上の参会者による合作の詩というべきものであるが、全体としてはなんらまとまった思想も内容も表現しない。連歌の会席で発句が詠み上げられると、参会者はその発句にふさわしい脇句を考え、脇句が提示されると、発句と脇句の構成する世界を思い浮かべて、その世界に没入しその美にひたる。ついで、脇句にふさわしい第三の句を考え、第三の句が提示されると、脇句と第三の句の構成する世界を思い浮かべて、その世界に没入する。そしてさらに、第四の句を考えるというふうにして、鑑賞と制作を繰り返しているうちに、句境は春から秋に、秋から恋へ、恋から述懐へと移り変わっていって極まるところがない。連歌はこうした心的過程のおもしろさを味わうことを目的とした文芸であって、懐紙に書き留められたものは、こうした詩的体験の軌跡を示すものにすぎないのである。
前句と付句の連接の仕方には、素材やことばの縁を手掛りにして付けるものから、イメージとイメージとを交響させる、きわめて高度の付合(つけあい)に至るまで、各種の付け方があり、一巻全体の展開のさせ方にも、芸術的な感興を高める諸種の行様(ゆきよう)があった。それらはすべて、一巻に用いる素材の出度数や間隔や連接の仕方を規定した連歌式目(しきもく)の示すところに則(のっと)ることによって、美的効果を発揮することができたのである。
こうした特殊の詩が中世に流行したのは、連歌の場が、乱世の過酷な現実から人々の心を開放し、風雅に遊ぶことによって、人と人との精神の真の交流を可能にしたからである。しかし、連歌は単なる心の慰みや社交のためだけではなく、諸神への法楽や祈願、祝言、追悼、あるいは夢想の句を得た場合などにも行われた。その種類もさまざまで、普通の連歌のほかに、いろは47文字や神仏の名号などをそれぞれの句の句頭に詠み入れた冠字(かむりじ)連歌、それぞれの句に物の名や熟語や名所その他を詠み込んだ物名(もののな)連歌、和歌の回文(かいぶん)をまねた回文連歌なども行われていた。
『日本書紀』所載の日本武尊(やまとたけるのみこと)と秉燭者(ひともしびと)との唱和、「にひばり筑波(つくば)を過ぎて幾夜か寝つる」「日日並(かかな)べて夜(よ)には九夜(ここのよ)日には十日を」を連歌の起源とする考え方が鎌倉中期以後行われているが、これは片歌(かたうた)による問答であって、和歌の上句と下句による唱和としては、『万葉集』巻八にみえる、尼と大伴家持(おおとものやかもち)との唱和「佐保(さほ)川の水を堰(せ)き上げて植ゑし田を/刈れる初飯(はついひ)はひとりなるべし」がもっとも古い。この短連歌は、平安朝中期から後期に盛行し、『後撰(ごせん)和歌集』『拾遺(しゅうい)和歌集』『金葉(きんよう)和歌集』などの勅撰和歌集にも入集(にっしゅう)している。
院政時代に入ると、この短連歌と並行して長連歌(鎖連歌)が行われるようになる。鎌倉初期になって後鳥羽(ごとば)院を中心とする藤原定家(ていか)、同家隆(いえたか)その他の新古今歌人の間で、この長連歌が愛好されたため、しだいに文芸性の高いものになり、形式も整って、百韻をいちおうの定型とするようになった。それ以後、鎌倉時代の貴族の間では、定家の子孫たちを中心にして、連歌はますます愛好され、鎌倉中期になると、各種の式目が制定され、南北朝期においても規準とされた「建治(けんじ)式」が成立する。また、鎌倉中期には一般庶民の間でも連歌が流行し、3月の桜の花の盛りに、京都の毘沙門堂(びしゃもんどう)、法勝寺(ほっしょうじ)、清水寺(きよみずでら)などの花の下で、道生(どうしょう)、寂忍(じゃくにん)、無生(むしょう)などの地下(じげ)連歌師の指導のもとに、連歌会が開催された。花(はな)の下(もと)連歌がこれで、鎌倉末期にはますます盛大となり、その会には上皇や関白などの貴族も参加している。鎌倉後期の地下連歌師のなかで最大の存在は善阿(ぜんあ)であるが、鎌倉末期から南北朝初期にかけて、善阿門下の信照(しんしょう)、順覚(じゅんかく)、救済(きゅうせい)、良阿(りょうあ)などの地下連歌師を中心にして地下連歌は急速に文芸性を高めていった。そのなかでも救済は二条良基(よしもと)の師となり、良基に協力して、准勅撰の連歌の撰集『菟玖波(つくば)集』(1356)を編集し、さらに「建治式」に改訂増補を加えた『応安(おうあん)新式』(1372)を制定している。良基はその一方において、『連理秘抄(れんりひしょう)』『筑波(つくば)問答』その他の連歌論書を著作して、連歌の句作の理想を示している。このようにして連歌は、和歌にかわって新時代を代表する詩としての地位を確立していくのであるが、南北朝連歌の句風の特色は、地下連歌に特有の奇知的性格を内包した、力強い句風のうちに、幽玄(ゆうげん)の美を指向している点にあった。作家としては救済が卓絶しており、「わかれはこれぞ限りなりける 雨に散る花の夕(ゆふべ)の山おろし」(付句)のような句をつくっている。南北朝後期に入ると、救済の門弟の周阿(しゅうあ)が急速に頭角を現し、一句の仕立てに趣向を凝らした、技巧の目につく句風が流行するようになる。
室町初期の連歌界においても、周阿の亜流の影響は強く、連歌は文芸性を喪失していく。この時代に連歌界の中心的地位にあったのは良基門下の梵灯(ぼんとう)であったが、その作品も時代の風潮から抜け出ることはできなかった。ところが、室町中期に入って、冷泉(れいぜい)派の歌人正徹(しょうてつ)の教えを受けた宗砌(そうぜい)や智蘊(ちうん)が出て、王朝古典の美を連歌に生かした有心(うしん)・幽玄の句風を復興し、さらにその後輩にあたる心敬(しんけい)、専順(せんじゅん)、能阿(のうあ)などの作家によって、その境地がいっそう深められるに及び、連歌は文字どおりの完成期を迎えることになる。この時期に、一条兼良(かねら)は宗砌の協力を得て、『応安新式』に増補改訂を加えた『新式今案(こんあん)』(1452)を制定しているし、心敬は、無常観を根底に据え新古今美を指向した「夢うつつとも分かぬあけぼの 月に散る花はこの世のものならで」(付句)のような優艶(ゆうえん)な作品を残している一方において、中世における真の詩のあり方や表現の仕方、さらには詩人の生き方をも追求した『ささめごと』その他の連歌論書を著作している。
宗砌、心敬、専順に教えを受け、古典にも深く通じていた宗祇(そうぎ)は、先達の作風を集大成して連歌一巻を真の詩にまで鍛え上げ、肖柏(しょうはく)、宗長(そうちょう)などの門弟たちと、『水無瀬三吟(みなせさんぎん)百韻』(1488)のような完璧(かんぺき)の作品を残している。その一方において、宗砌、心敬など7人の先達の句を集めた『竹林抄(ちくりんしょう)』を独力で、准勅撰の連歌の撰集『新撰菟玖波集』(1495)を兼載(けんさい)その他の人々の協力を得て編集しているほか、『吾妻(あづま)問答』『老のすさみ』その他、実地指導に役だつ数多くの連歌論書をも著作している。この宗祇時代の高い達成を背景にして、1501年(文亀1)には、肖柏によって、『連歌新式』の大規模な増補改訂が行われ、これは俳諧(はいかい)の式目の成立にも大きな影響を与えた。宗祇が没し、宗祇に次ぐ存在であった兼載が関東に退隠してのち、連歌界の中心的位置にあったのは、宗祇門下の肖柏、宗長、宗碩(そうせき)などであったが、その没後には宗碩門下の宗牧(そうぼく)や周桂(しゅうけい)が連歌界の中心に位置し、さらにその後を受けて、宗牧門下の昌休(しょうきゅう)や宗牧の子の宗養が、その没後には昌休門下の紹巴(じょうは)が連歌界の指導的位置を占める。
安土(あづち)桃山時代には、多年にわたる乱世の終局と享受層の増大につれて、連歌の句風は平易なものになり、社交の具としての性格をいっそう強めてゆく。ついで江戸時代になると、紹巴と昌休の子昌叱(しょうしつ)との子孫が、ともに里村を名のって幕府の連歌師の職を世襲し、連歌はようやく固定化の時代に入るのである。
詩形式の一つ。5・7・5の句(長句)と7・7の句(短句)を交互に複数の作者が詠み進めて一定の句数(普通は100句)で完結させるもの。一人の作者が詠み通す場合(〈独吟〉という)もある。また100句(〈百韻(ひやくいん)〉という)を10回連作して〈千句〉とすることも多い。
記紀歌謡のヤマトタケルと御火焼之老人(みひたきのおきな)との片歌による問答(5・7・7/5・7・7)を連歌の起源とする立場が古来あり,〈新治(にいばり)筑波を過ぎて……〉というヤマトタケルの歌から,〈筑波の道〉が連歌の別称となった。しかし一般には《万葉集》巻八の尼と大伴家持との短歌の上句と下句による問答が最初とされる。平安時代末ころまではこのような,短歌の上句と下句(下句を先に作るほうが多い)を合作する形式の連歌(〈短連歌〉という)が盛んに行われた。その多くが機知諧謔を中心とする即興問答的なものであったが,和歌的情趣を意図したものもあり,11世紀ころには詩としての完成度を求めるものも出現する。
短連歌が展開して3句以上連作されるようになる時期は明確ではないが,《今鏡》によれば12世紀はじめにすでにあった。13世紀に至り,50句,100句等の長いまとまりで詠むことが多くなり,やがて百韻の形式が基本になる。その動向の中心となったのは後鳥羽院とその周辺にいた藤原定家・同家隆らの歌人であり,連歌は和歌に付随したものとして詠まれるのが当時の一般的なあり方であったこと,さらに和歌的情趣による,いわゆる〈有心(うしん)連歌〉を詠む有心衆(柿本衆)と,滑稽諧謔を中心とする,いわゆる〈無心(むしん)連歌〉を詠む無心衆(栗本衆)との両派に分かれて競作するような場合もあったことが注意される。このころから,複数の作者による共同制作が定式化し,詠作上の種々の約束事が集積され,連歌の座の運営を円滑にする努力がなされるようになり,連歌式目(式目)の発生がうながされた。それは一方では句材の重複を避け,調和をはかる方向にも発展し,連歌の詩としての高まりへの道を開くものでもあった。
鎌倉時代の末ころ,すなわち13世紀の半ばには,連歌の座をとりしきり,式目との合否を判定してその座の作者たち(〈連衆(れんじゆ)〉という)を統轄する専門家が出現し,連歌師と呼ばれるようになる。以後の連歌の展開には連歌師がきわめて重要な役割を果たす。1356年(正平11・延文1)には貴族のなかの連歌愛好者の頂点にいた二条良基が連歌師の代表である救済(ぐさい)と《菟玖波(つくば)集》という連歌の撰集を編集し,72年(文中1・応安5)には再び両者が協力して統一的な連歌式目である《応安新式》を制定し,連歌は和歌から独立した新しい中世詩の立脚点を得るに至る。良基は同時に多くの連歌論を発表してその理論的根拠を与えた。文芸化をめざした結果,和歌的な世界を持つ有心連歌が主流となり,俳諧的な連歌は底流化する。一方,前の句に付けること(付合(つけあい))の巧みさが競われ,その巧拙が賭の対象となり,いわゆる賭連歌が盛行するのもこのころである。幕府は禁令を出し,《二条河原落書》に〈点者ニナラヌ人ゾナキ〉と皮肉られるほど,賭連歌の点者(句の巧拙を判定して点を付ける人)が多かった。連歌はそうした遊芸的側面にも支えられて和歌をしのぐほど盛んになり,寺社の桜の木のもとにつどい,連歌を興行する花下(はなのもと)連歌も流行した。千句,万句などの長大な作品もしばしば作られるようになる。
室町時代に入り,梵灯庵主,今川了俊らの時代を経て,15世紀前半,宗砌(そうぜい),心敬(しんけい)らにより付合の妙味が深化し,やがて宗祇(そうぎ)を中心に,兼載(けんさい),肖柏(しようはく),宗長らにより有心連歌はほぼ完成成熟の段階を迎え,1488年(長享2)の《水無瀬三吟百韻(みなせさんぎんひやくいん)》,1495年(明応4)の《新撰菟玖波集》等に結実する。式目も整備が重ねられ,付句の微妙な味わいとともに百韻全体の詩としての流麗さが尊重され,それまでの文芸にない独自の世界を現出するに至る。理論の面でも,心敬の《ささめごと》や宗祇の《吾妻問答》のような高い精神性や芸術意識を持つ著作が現れる。以後はきわだった展開は見られず,詩としての完成度は低下してゆくが,一方で,織豊政権下の紹巴(じようは)のように,連歌が持つ社交的機能を重視して,座の円滑な運営に意を用いて,その意味では画期的な連歌の時代を現出させた連歌師の存在も軽視できない。また,宗牧,宗養,あるいは里村昌休・昌叱(しようしつ),紹巴・玄仍(げんじよう)ら父子の連歌師が中世末期に多く出現することで明らかなように,〈連歌の家〉が成立して連歌師が代々世襲されてゆく傾向が生じた。江戸時代,幕府や諸藩お抱えの連歌師はほとんど世襲であり,このことは連歌が文芸としての活性を失ってゆくことと考えあわせる必要がある
有心連歌はこのような経過をたどるが,連歌が発生当初から持ちつづけていた俳諧性が,ときに底流化しながらも生きつづけ,15世紀末には《竹馬狂吟集》という俳諧連歌集を生み出す力を示し,やがて,宗鑑の《犬筑波集》,荒木田守武の《守武千句》に見られるような作品が,連歌のもう一つの重要な流れになってゆく。中世末の連歌の様相は非常に多様化しているが,基本的にはこの二つの流れが貞徳によって再生し,やがて近世の俳諧の発展につながる。
連歌の形式は百韻が基本であるが,36句の〈歌仙〉,44句の〈世吉(よよし)〉(〈四十四(よよし)〉とも)と称するものも存する。各作品の最初の句を〈発句(ほつく)〉,次の句を〈脇(わき)句〉,第3の句を〈第三〉と呼び,まとめて〈三(みつもの)物〉と称する。発句は季を詠み込みその場に即して作るのが原則で,脇の句以下が,前の句によって提示された世界を展開・転換・変容させて,いわば虚構性を持つのと異質である。
連歌の詠作上の約束事は多岐にわたるが,主要な点は以下のごとくである。第1に〈賦物(ふしもの)〉というものがある。賦物は元来各句に用語上の制限を加えて全体を統制する役目を持ち,連歌の言語遊戯的側面を支える重要な契機であったらしく,初期には多種多様であった。詩としての表現性を重視するようになるに従って形式化し,ついには発句のみに賦するようになる。たとえば〈山何(やまなに)〉という賦物であれば,〈山〉とともに一つの熟語となる語,たとえば〈里〉をその次に詠み込むというものである。14世紀以後はほとんどこの形式である。第2に〈去嫌(さりきらい)〉がある。これは百韻という句の流れの中で,語彙や句材が適当に配置され,美的な構成を保つよう工夫された約束事で,連歌式目の主要部分を占める。要点は,同種の語彙の使用回数制限と間隔制限および内容上の連続制限の3種である。1例ずつ示せば,〈秋風〉は百韻の中で2回しか用いてはならない,〈山〉と〈山〉は5句隔てなければ再び詠んではならない,春の句は最少3句最多5句の範囲で連続させなければならない等である。これらの制約は一見きわめて煩瑣にみえるが,長い歴史の中で作者たちが追求してきた美の最大公約数的な体系性を有している。ただし,その美的世界はきわめて狭小で,時代,社会,生活,意識の変化に対応できないままに,逆に束縛となったことは否定できない。
連歌は,合作,連作という他に見られない方法により,本来個人的所産であった文芸を集団の場に解放し,個人の表現力を超えるものを生み出した。また合作ということで参加する人々の心理的連帯を可能にし,連作によって時間的契機が詩に導入され,変化・展開の相を一つの美として実現できたのである。
→俳諧 →連句

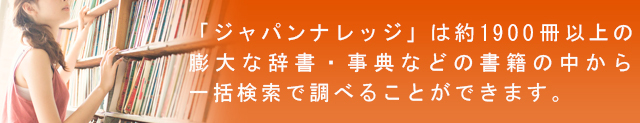










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.