2016年12月12日
今年、ある落語家が不倫の現場を写真週刊誌に撮られ、その謝罪の記者会見で自分の名に懸けて、「老いらくの恋」と言ったことがあった。そのことに関して何か意見を述べようということではなく、「老いらく」というのはけっこう面白いことばなので取り上げてみたいのである。
「老いらく」は文法的に説明すれば、「老いる」の文語形「老ゆ」のク語法である「おゆらく」が変化した語ということになる。ク語法というのは、活用語の語尾に「く」がついて全体が名詞化されるもので、「言はく(=言うこと。言うことには)」「語らく(=語ること。語ることには)」「悲しけく(=悲しいこと)」などの語がそれである。「老いらく」は、年をとり老いてゆくことや老年という意味である。
古くからある語で、たとえば平安初期に成立した最初の勅撰和歌集『古今和歌集』には、在原業平(ありわらのなりひら)の以下のような和歌が収められている。
「桜花ちりかひくもれおいらくのこむといふなる道まがふがに」(賀・三四九)
桜の花よ、散り乱れてあたりを曇らせよ。老いがやって来るという道が(花で隠されて)わからなくなるように、といった意味である。詞書(ことばがき)によれば、藤原基経(ふじわらのもとつね)の四十の賀の宴で読んだ歌とある。基経は最初の関白となった平安前期の公卿(くぎょう)である。さりげなく慶賀の気持ちを込めた名歌であろう。
この「老いらく」がのちに「らく」を「楽」と解され、「老い楽」の字をあてて、年をとってから安楽な生活に入ることや老後の安楽といった意味になる。
『日本国語大辞典』によれば、キリシタン宣教師の日本語修得のためにイエズス会が刊行した辞書『日葡辞書(にっぽじしょ)』(1603〜04)に「Voiracu (ヲイラク)」があり、ポルトガル語の部分を日本語に翻訳すると、「歌語、すなわち、老いの楽しみ」と書かれている。つまりけっこう古くから「老い楽」と思われていたことがわかる。以後、「老い楽」の例は、江戸期から近代になってもかなり見られるようになる。
ちなみに冒頭の落語家が言った「老いらくの恋」という語は、1948(昭和23)年、当時68歳だった歌人の川田順が弟子の女性と恋愛、家出し、「墓場に近き老いらくの、恋は怖るる何ものもなし」と詠んだことから広まったものである。この場合の「老いらく」は「老い楽」でないことは言うまでもないであろう。
「老いらく」は文法的に説明すれば、「老いる」の文語形「老ゆ」のク語法である「おゆらく」が変化した語ということになる。ク語法というのは、活用語の語尾に「く」がついて全体が名詞化されるもので、「言はく(=言うこと。言うことには)」「語らく(=語ること。語ることには)」「悲しけく(=悲しいこと)」などの語がそれである。「老いらく」は、年をとり老いてゆくことや老年という意味である。
古くからある語で、たとえば平安初期に成立した最初の勅撰和歌集『古今和歌集』には、在原業平(ありわらのなりひら)の以下のような和歌が収められている。
「桜花ちりかひくもれおいらくのこむといふなる道まがふがに」(賀・三四九)
桜の花よ、散り乱れてあたりを曇らせよ。老いがやって来るという道が(花で隠されて)わからなくなるように、といった意味である。詞書(ことばがき)によれば、藤原基経(ふじわらのもとつね)の四十の賀の宴で読んだ歌とある。基経は最初の関白となった平安前期の公卿(くぎょう)である。さりげなく慶賀の気持ちを込めた名歌であろう。
この「老いらく」がのちに「らく」を「楽」と解され、「老い楽」の字をあてて、年をとってから安楽な生活に入ることや老後の安楽といった意味になる。
『日本国語大辞典』によれば、キリシタン宣教師の日本語修得のためにイエズス会が刊行した辞書『日葡辞書(にっぽじしょ)』(1603〜04)に「Voiracu (ヲイラク)」があり、ポルトガル語の部分を日本語に翻訳すると、「歌語、すなわち、老いの楽しみ」と書かれている。つまりけっこう古くから「老い楽」と思われていたことがわかる。以後、「老い楽」の例は、江戸期から近代になってもかなり見られるようになる。
ちなみに冒頭の落語家が言った「老いらくの恋」という語は、1948(昭和23)年、当時68歳だった歌人の川田順が弟子の女性と恋愛、家出し、「墓場に近き老いらくの、恋は怖るる何ものもなし」と詠んだことから広まったものである。この場合の「老いらく」は「老い楽」でないことは言うまでもないであろう。
キーワード:
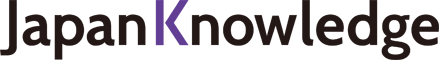


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
