2017年02月13日
「あまりの恥ずかしさに、いたたまらない気持ちになる」
この文章を読んでどのようにお感じになっただろうか。ひょっとすると、「いたたまらない」は「いたたまれない」の間違いではないかとお思いになったかたもいらっしゃるかもしれない。だが、「いたたまれない」も「いたたまらない」も江戸時代頃から両方とも使われていたらしく、意味や用法もほとんど区別がないようなのである。
『日本国語大辞典』の「いたたまれない」では、江戸時代後期の人情本と呼ばれる小説の例が引用されている。
*人情本・花の志満台(1836~38)三・一七回「詰らなくなると、さア、彼奴(あいつ)めが我儘一杯(いっぺえ)を働いて、なかなか居(ゐ)たたまれねえ様にするから、忌々しさに出は出て見たが」
一方「いたたまらない」のほうは、式亭三馬作の滑稽本『浮世風呂』(1809~13)の以下のような例である。
「わたしが初ての座敷の時、がうぎ〔=ひどく〕といぢめたはな〈略〉それから居溜(ゐたたま)らねへから下(さが)らうと云たらの」
『浮世風呂』のほうが成立は20年以上早いが、ほぼ同時期のものと考えていいだろう。ただ、語源を考えてみると、「いたたまらない」は「居・堪(たま)らない」、つまり「いることががまんできない」の意味だと考えられる。この「居る+たまる+ない」の「いたまらない」に、強調か口調のためにもう一つ「た」が挿入された形が「いたたまらない」だとされている。
さらに、「たまらない」は「がまんできない」の意であるが、「……できない」の意味の場合、たとえば「止まる」が「止まれない」、「終わる」が「終われない」などと、当時から「……れない」の形となることがあるため、それに引きずられて「いたたまらない」も「いたたまれない」に変化したと考えられている。
つまり、語源的には「いたたまらない」が元の言い方だと説明できるのである。だからというわけではなかろうが、現在でも「いたたまれない」「いたたまらない」どちらも使うが、「いたたまらない」のほうがやや古めかしい言い方に聞こえるような気がする。「いたたまれない」のほうが優勢だということはわかるのだが、小型の国語辞典では「いたたまらない」が完全に消滅してしまったわけではないのに、これを見出し語にしているものはほとんど無くなってしまった。残念なことである。
この文章を読んでどのようにお感じになっただろうか。ひょっとすると、「いたたまらない」は「いたたまれない」の間違いではないかとお思いになったかたもいらっしゃるかもしれない。だが、「いたたまれない」も「いたたまらない」も江戸時代頃から両方とも使われていたらしく、意味や用法もほとんど区別がないようなのである。
『日本国語大辞典』の「いたたまれない」では、江戸時代後期の人情本と呼ばれる小説の例が引用されている。
*人情本・花の志満台(1836~38)三・一七回「詰らなくなると、さア、彼奴(あいつ)めが我儘一杯(いっぺえ)を働いて、なかなか居(ゐ)たたまれねえ様にするから、忌々しさに出は出て見たが」
一方「いたたまらない」のほうは、式亭三馬作の滑稽本『浮世風呂』(1809~13)の以下のような例である。
「わたしが初ての座敷の時、がうぎ〔=ひどく〕といぢめたはな〈略〉それから居溜(ゐたたま)らねへから下(さが)らうと云たらの」
『浮世風呂』のほうが成立は20年以上早いが、ほぼ同時期のものと考えていいだろう。ただ、語源を考えてみると、「いたたまらない」は「居・堪(たま)らない」、つまり「いることががまんできない」の意味だと考えられる。この「居る+たまる+ない」の「いたまらない」に、強調か口調のためにもう一つ「た」が挿入された形が「いたたまらない」だとされている。
さらに、「たまらない」は「がまんできない」の意であるが、「……できない」の意味の場合、たとえば「止まる」が「止まれない」、「終わる」が「終われない」などと、当時から「……れない」の形となることがあるため、それに引きずられて「いたたまらない」も「いたたまれない」に変化したと考えられている。
つまり、語源的には「いたたまらない」が元の言い方だと説明できるのである。だからというわけではなかろうが、現在でも「いたたまれない」「いたたまらない」どちらも使うが、「いたたまらない」のほうがやや古めかしい言い方に聞こえるような気がする。「いたたまれない」のほうが優勢だということはわかるのだが、小型の国語辞典では「いたたまらない」が完全に消滅してしまったわけではないのに、これを見出し語にしているものはほとんど無くなってしまった。残念なことである。
キーワード:
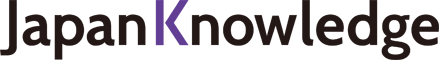


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
