
 の四つの官があり、魏への派遣官は、みな大夫と称していた。七万余戸の人口があり、国の以北にある諸国を検察するため伊都国に常駐していた一大率(あるいは大率)という官が特置されており、諸国はこれを畏憚していたと伝える。さらに国中には古代中国の地方官である刺史に類する官(あるいは一大率のこととみなされている)があって、魏の都洛陽や帯方郡さらに諸韓国に使者を派遣する場合、もしくは帯方郡の使者が倭国を来訪した際に、すべて船着場で捜査し、文書や物資を女王のもとに伝送するのに誤りがないようにしていたという。また国々には市があって物資の交換取引を監督する大倭と呼ばれる役人がいた。この国の王は、もと男子であったが、二世紀後半に倭国が乱れ戦いがつづいた後に卑弥呼が共立されて女王となり、宮室・楼観・城柵が厳重に設けられ、兵士が武器を手にして守衛していた。女王卑弥呼の死の直前、従来より不和であった狗奴国(のちの肥後国球磨郡、現在の熊本県球磨郡一帯か)と戦い、戦乱の最中に卑弥呼は世を去ったらしい。この後、男王が立てられたが、国中は服さないで戦乱となり、千余人が死んだ。そこで卑弥呼の宗女で時に十三歳の壱与(台与とも)を王に立てると国中は安定をとりもどしたという。大人・下戸の階層があり、また婢・生口など下層の階級の者も存在していた。婢は王などに召し使われ、また殉死させられていたらしい。生口は朝貢物として魏の皇帝に贈られていた。さらに持衰(じさい)と呼ばれ航海の安全を図るため精進潔斎をしてすごす特殊な職能者もいた。尊卑の差序が明確で顔面・身体にほどこした入れ墨で尊卑の差をあらわし、身分秩序は厳然としており、軽罪の者は妻子を没し、重罪を犯した者は、その門戸・宗族を没するという法秩序も整っていた。租税を納める制度も存在し、軍事物資を貯えたらしい邸閣も備わっていた。倭人の男子は冠をかぶらず髪を露出し、木緜(もくめん)を頭に巻き、ほとんど縫っていない横幅の布を身体にまとい、婦人は髪を延びるままにして束ね、布の中央に穴をあけ、頭をその穴にとおして着る衣服(貫頭衣)を着用し、すべて裸足で暮していた。食事の時は、
の四つの官があり、魏への派遣官は、みな大夫と称していた。七万余戸の人口があり、国の以北にある諸国を検察するため伊都国に常駐していた一大率(あるいは大率)という官が特置されており、諸国はこれを畏憚していたと伝える。さらに国中には古代中国の地方官である刺史に類する官(あるいは一大率のこととみなされている)があって、魏の都洛陽や帯方郡さらに諸韓国に使者を派遣する場合、もしくは帯方郡の使者が倭国を来訪した際に、すべて船着場で捜査し、文書や物資を女王のもとに伝送するのに誤りがないようにしていたという。また国々には市があって物資の交換取引を監督する大倭と呼ばれる役人がいた。この国の王は、もと男子であったが、二世紀後半に倭国が乱れ戦いがつづいた後に卑弥呼が共立されて女王となり、宮室・楼観・城柵が厳重に設けられ、兵士が武器を手にして守衛していた。女王卑弥呼の死の直前、従来より不和であった狗奴国(のちの肥後国球磨郡、現在の熊本県球磨郡一帯か)と戦い、戦乱の最中に卑弥呼は世を去ったらしい。この後、男王が立てられたが、国中は服さないで戦乱となり、千余人が死んだ。そこで卑弥呼の宗女で時に十三歳の壱与(台与とも)を王に立てると国中は安定をとりもどしたという。大人・下戸の階層があり、また婢・生口など下層の階級の者も存在していた。婢は王などに召し使われ、また殉死させられていたらしい。生口は朝貢物として魏の皇帝に贈られていた。さらに持衰(じさい)と呼ばれ航海の安全を図るため精進潔斎をしてすごす特殊な職能者もいた。尊卑の差序が明確で顔面・身体にほどこした入れ墨で尊卑の差をあらわし、身分秩序は厳然としており、軽罪の者は妻子を没し、重罪を犯した者は、その門戸・宗族を没するという法秩序も整っていた。租税を納める制度も存在し、軍事物資を貯えたらしい邸閣も備わっていた。倭人の男子は冠をかぶらず髪を露出し、木緜(もくめん)を頭に巻き、ほとんど縫っていない横幅の布を身体にまとい、婦人は髪を延びるままにして束ね、布の中央に穴をあけ、頭をその穴にとおして着る衣服(貫頭衣)を着用し、すべて裸足で暮していた。食事の時は、 豆(竹・木で作った高坏)を用い、箸などを使わず手で直(じか)に食べていた。屋内では父母兄弟の寝室が別々になっており、身体には朱丹を塗っていた。人が死ぬと棺は用いるが、槨は拵えず、土で冢を作った。死者をその冢に葬るまでの十余日間、喪に服し、肉食は避け、喪主は哭泣し、他の者は歌舞飲酒してすごした。死者を埋葬したあと家をあげて死の汚れを除くため水に入って沐浴し身を浄めた。また動物の骨を焼き、
豆(竹・木で作った高坏)を用い、箸などを使わず手で直(じか)に食べていた。屋内では父母兄弟の寝室が別々になっており、身体には朱丹を塗っていた。人が死ぬと棺は用いるが、槨は拵えず、土で冢を作った。死者をその冢に葬るまでの十余日間、喪に服し、肉食は避け、喪主は哭泣し、他の者は歌舞飲酒してすごした。死者を埋葬したあと家をあげて死の汚れを除くため水に入って沐浴し身を浄めた。また動物の骨を焼き、 (ひび)割れを見て吉凶を占う卜筮も行なっていた。このような倭人の習俗は、邪馬台国に居住していた人々も同様であったとみなしてよい。邪馬台国の時代は、考古学の時期区分では弥生文化時代の後期後半にあたるので、すでにひろく水稲耕作が行われていた。『魏志』倭人伝にも「禾稲・紵麻を種え、蚕桑緝績し、細紵・
(ひび)割れを見て吉凶を占う卜筮も行なっていた。このような倭人の習俗は、邪馬台国に居住していた人々も同様であったとみなしてよい。邪馬台国の時代は、考古学の時期区分では弥生文化時代の後期後半にあたるので、すでにひろく水稲耕作が行われていた。『魏志』倭人伝にも「禾稲・紵麻を種え、蚕桑緝績し、細紵・ 緜を出だす」とある。この記事から稲作を中心に、麻を栽培し、絹織物や綿織物が生産されていたことが察せられる。また女王卑弥呼が魏の皇帝に献上した物品の中に倭錦・絳青
緜を出だす」とある。この記事から稲作を中心に、麻を栽培し、絹織物や綿織物が生産されていたことが察せられる。また女王卑弥呼が魏の皇帝に献上した物品の中に倭錦・絳青 などの織物があったことによって錦や高級な絹布が織られていたと考えられる。邪馬台国の所在についての代表的見解は、大和説と九州説とであり、九州説にはさらにさまざまな地域に比定する説があって分立している。邪馬台国大和説は、『日本書紀』神功皇后摂政三十九年・四十年・四十三年条の分注に『魏志』倭人伝を引用し、卑弥呼を神功皇后に比定していたらしいことからすれば、すでに同書の編纂時代から存在していたことになる。この分注引用記事によったためか以後、大和説は長く引き継がれ、邪馬台国研究が学問的な対象となる江戸時代にまで至る。松下見林が『異称日本伝』で「卑弥呼は、神功皇后の御名、気長足姫尊を、故れ訛りて然か云ふ」と述べていることからも、それは明らかであり、そのあとを受けた新井白石も、『古史通或問』において「邪馬台国は即今の大和国なり」と主張していた。ところが新井白石は、やがて『外国之事調書』において邪馬台国を筑後国山門郡(福岡県山門郡)に比定するようになり、邪馬台国九州説の中ではもっとも有力な邪馬台国山門郡説の先鞭をつけた。新井白石の死後五年にして誕生した本居宣長は、邪馬台国を大和にあった国とみなしていたが、魏に朝貢したのは神功皇后ではなく、「熊襲」などの類が神功皇后の名を騙って通交したのであるとし、「熊襲偽僭説」の先駆けとなった。この説を発展させたのが鶴峯戊申(しげのぶ)であり、邪馬台国を大隅国囎唹郡(鹿児島県曾於郡)に比定し、また近藤芳樹は、肥後国菊池郡山門郷(熊本県菊池市一帯)説を主張した。ここに邪馬台国九州説での代表的三説、山門郡説・囎唹郡説・山門郷説が出揃い、これらがともに明治時代にまで及んだ。明治四十三年(一九一〇)に白鳥庫吉の「倭女王卑弥呼考」、内藤虎次郎(湖南)の「卑弥呼考」が発表され、近代における邪馬台国研究の画期となった。白鳥庫吉は詳細な里程論と日数論の上に立って、邪馬台国は肥後国(熊本県)内にあったとし、卑弥呼をその地方の女酋とみなした。一方、内藤虎次郎は『魏志』倭人伝の本文批判をとおして、邪馬台国は大和に擬するほかはないとし、卑弥呼を倭姫命にあてた。この両論以後、両者の間をはじめ大和説・九州説に拠る研究者の間に邪馬台国論争が展開された。白鳥説を承けて橋本増吉が、また内藤説を継いで笠井新也が代表格となって、それぞれ九州説・大和説を発表した。橋本増吉は邪馬台国を筑後国山門郡の地とし、笠井新也は卑弥呼を倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)命とし、卑弥呼の冢を箸墓(はしのはか)とみなした。この間、梅原末治は、三角縁神獣鏡が魏代の製作の可能性の高いことを説いて、この鏡が近畿地方に濃厚に分布することから邪馬台国大和説に同調して、考古学の見地からする新しい方向づけをした。その後マルクス史学者は、考古学からの指摘を重視して大和説をとる者が多く、邪馬台国は当時の日本列島内のもっとも先進的な社会を形成させており、国家体制への明確な徴候がみられるという指摘がなされ始めた。第二次世界大戦後、邪馬台国研究は活況を呈し、諸説は乱立し、現今に至るまで定説は打ち立てられていない。しかし『魏志』倭人伝の文献研究は深められ、邪馬台国の性格や構造、卑弥呼の王権についての研究も著しく進み、関係する論著が数多く出版されている。戦後の主立った論説をあげれば邪馬台国九州説では、榎一雄が『魏志』倭人伝の里程・日程記事をとりあげて、従来邪馬台国に至るまでの行程を直線的に読みとってきたことを退けて、伊都国までの行程記事は、それ以前の国からの方位・距離を示し、到達する国名をあげているのに対して、伊都国からは、方位・国名・距離の順に記述しているのは、伊都国から奴国・不弥国・投馬国・邪馬台国などそれぞれの国に至ることを意味しているものとし、邪馬台国は伊都国から南へ水行十日、または陸行一月で到達する地点、すなわち筑紫平野のうちに求められるとしたことが注目される所説とされている。一方、邪馬台国大和説では、小林行雄が三角縁神獣鏡の特殊な分有関係の存在に着目して、三世紀中葉の政治的情勢を見究め、邪馬台国九州説の成立は困難になると論じたことが、大和説に有力な一つの支えとなったものとしてあげることができる。また九州説からする藤間生大(せいた)の邪馬台国を中心とする諸小国で構成されていたとする連合国家論、井上光貞の邪馬台国の政治体制を原始的民主制の段階とみなした論説、さらに大和説の立場にたっての上田正昭の専制君主制萌芽的形態論などが相ついで提出された。卑弥呼が共立によって王となったこと、卑弥呼の死後、王位継承にあたって国人が服さなかったことなどから当時の邪馬台国の王制が確固たる世襲王制であったとはみなされないことをふまえて邪馬台国を古代国家の端緒形態と指摘した石母田正(いしもだしょう)の所論も注目された。かつて内藤虎次郎は、『魏志』倭人伝の本文批判の中で、諸版本が邪馬台国を「邪馬壹国」に作っていることを取りあげて、「邪馬壹は邪馬臺の訛なること、言ふまでもなし。梁書、北史、隋書皆臺に作れり」と論じていたが、古田武彦が「邪馬壹国」論を発表し、邪馬台国は諸版本の記すとおり、「邪馬壹国」が正しいとした。この論は『魏志』倭人伝の本文批判を再検討する気運を促した点で評価できるが、古田説への疑問は多方面から寄せられている。→魏志倭人伝(ぎしわじんでん),→親魏倭王(しんぎわおう),→台与(とよ),→卑弥呼(ひめこ)
などの織物があったことによって錦や高級な絹布が織られていたと考えられる。邪馬台国の所在についての代表的見解は、大和説と九州説とであり、九州説にはさらにさまざまな地域に比定する説があって分立している。邪馬台国大和説は、『日本書紀』神功皇后摂政三十九年・四十年・四十三年条の分注に『魏志』倭人伝を引用し、卑弥呼を神功皇后に比定していたらしいことからすれば、すでに同書の編纂時代から存在していたことになる。この分注引用記事によったためか以後、大和説は長く引き継がれ、邪馬台国研究が学問的な対象となる江戸時代にまで至る。松下見林が『異称日本伝』で「卑弥呼は、神功皇后の御名、気長足姫尊を、故れ訛りて然か云ふ」と述べていることからも、それは明らかであり、そのあとを受けた新井白石も、『古史通或問』において「邪馬台国は即今の大和国なり」と主張していた。ところが新井白石は、やがて『外国之事調書』において邪馬台国を筑後国山門郡(福岡県山門郡)に比定するようになり、邪馬台国九州説の中ではもっとも有力な邪馬台国山門郡説の先鞭をつけた。新井白石の死後五年にして誕生した本居宣長は、邪馬台国を大和にあった国とみなしていたが、魏に朝貢したのは神功皇后ではなく、「熊襲」などの類が神功皇后の名を騙って通交したのであるとし、「熊襲偽僭説」の先駆けとなった。この説を発展させたのが鶴峯戊申(しげのぶ)であり、邪馬台国を大隅国囎唹郡(鹿児島県曾於郡)に比定し、また近藤芳樹は、肥後国菊池郡山門郷(熊本県菊池市一帯)説を主張した。ここに邪馬台国九州説での代表的三説、山門郡説・囎唹郡説・山門郷説が出揃い、これらがともに明治時代にまで及んだ。明治四十三年(一九一〇)に白鳥庫吉の「倭女王卑弥呼考」、内藤虎次郎(湖南)の「卑弥呼考」が発表され、近代における邪馬台国研究の画期となった。白鳥庫吉は詳細な里程論と日数論の上に立って、邪馬台国は肥後国(熊本県)内にあったとし、卑弥呼をその地方の女酋とみなした。一方、内藤虎次郎は『魏志』倭人伝の本文批判をとおして、邪馬台国は大和に擬するほかはないとし、卑弥呼を倭姫命にあてた。この両論以後、両者の間をはじめ大和説・九州説に拠る研究者の間に邪馬台国論争が展開された。白鳥説を承けて橋本増吉が、また内藤説を継いで笠井新也が代表格となって、それぞれ九州説・大和説を発表した。橋本増吉は邪馬台国を筑後国山門郡の地とし、笠井新也は卑弥呼を倭迹迹日百襲姫(やまとととびももそひめ)命とし、卑弥呼の冢を箸墓(はしのはか)とみなした。この間、梅原末治は、三角縁神獣鏡が魏代の製作の可能性の高いことを説いて、この鏡が近畿地方に濃厚に分布することから邪馬台国大和説に同調して、考古学の見地からする新しい方向づけをした。その後マルクス史学者は、考古学からの指摘を重視して大和説をとる者が多く、邪馬台国は当時の日本列島内のもっとも先進的な社会を形成させており、国家体制への明確な徴候がみられるという指摘がなされ始めた。第二次世界大戦後、邪馬台国研究は活況を呈し、諸説は乱立し、現今に至るまで定説は打ち立てられていない。しかし『魏志』倭人伝の文献研究は深められ、邪馬台国の性格や構造、卑弥呼の王権についての研究も著しく進み、関係する論著が数多く出版されている。戦後の主立った論説をあげれば邪馬台国九州説では、榎一雄が『魏志』倭人伝の里程・日程記事をとりあげて、従来邪馬台国に至るまでの行程を直線的に読みとってきたことを退けて、伊都国までの行程記事は、それ以前の国からの方位・距離を示し、到達する国名をあげているのに対して、伊都国からは、方位・国名・距離の順に記述しているのは、伊都国から奴国・不弥国・投馬国・邪馬台国などそれぞれの国に至ることを意味しているものとし、邪馬台国は伊都国から南へ水行十日、または陸行一月で到達する地点、すなわち筑紫平野のうちに求められるとしたことが注目される所説とされている。一方、邪馬台国大和説では、小林行雄が三角縁神獣鏡の特殊な分有関係の存在に着目して、三世紀中葉の政治的情勢を見究め、邪馬台国九州説の成立は困難になると論じたことが、大和説に有力な一つの支えとなったものとしてあげることができる。また九州説からする藤間生大(せいた)の邪馬台国を中心とする諸小国で構成されていたとする連合国家論、井上光貞の邪馬台国の政治体制を原始的民主制の段階とみなした論説、さらに大和説の立場にたっての上田正昭の専制君主制萌芽的形態論などが相ついで提出された。卑弥呼が共立によって王となったこと、卑弥呼の死後、王位継承にあたって国人が服さなかったことなどから当時の邪馬台国の王制が確固たる世襲王制であったとはみなされないことをふまえて邪馬台国を古代国家の端緒形態と指摘した石母田正(いしもだしょう)の所論も注目された。かつて内藤虎次郎は、『魏志』倭人伝の本文批判の中で、諸版本が邪馬台国を「邪馬壹国」に作っていることを取りあげて、「邪馬壹は邪馬臺の訛なること、言ふまでもなし。梁書、北史、隋書皆臺に作れり」と論じていたが、古田武彦が「邪馬壹国」論を発表し、邪馬台国は諸版本の記すとおり、「邪馬壹国」が正しいとした。この論は『魏志』倭人伝の本文批判を再検討する気運を促した点で評価できるが、古田説への疑問は多方面から寄せられている。→魏志倭人伝(ぎしわじんでん),→親魏倭王(しんぎわおう),→台与(とよ),→卑弥呼(ひめこ)弥生(やよい)文化中・後期に確認される倭(わ)の女王国。『魏志倭人伝(ぎしわじんでん)』の刊本には邪馬壹国とみえるが、定説どおり邪馬台( )国とするのが妥当。邪馬台は正式には「やまと」と読むが、大和(やまと)王権と区別するために一般には「やまたい」と呼称している。
)国とするのが妥当。邪馬台は正式には「やまと」と読むが、大和(やまと)王権と区別するために一般には「やまたい」と呼称している。
邪馬台国の所在地に関しては古くから論争があり、いまだに定まるところがない。それは、史料の『魏志倭人伝』(正式には『三国志』魏書倭人条)の記載が所在地を確定するには内容的に不十分だからとされている。しかし、この問題は、日本古代国家の起源・性格、日本国土の統一時期、大和王権とのかかわり、記紀神話・伝承との絡みなど日本古代史研究上、そして国民の関心上、重要な位置を占めている。現在、学説の二大潮流として邪馬台国畿内(きない)説と九州説とがある。『魏志倭人伝』には帯方(たいほう)郡から邪馬台国への行程記事があるが、そのまま行程をとると九州のはるか南方の海上に邪馬台国の位置が求められるという矛盾のなかで、畿内の大和にその所在を求める論者は行程方位を変更・解釈し、九州論者は山門(やまと)・山戸(やまと)などを前提に距離・日数を短縮・理解し、持論を展開してきた。最近では、記紀神話・伝承の世界と邪馬台国を直結的に解釈する研究が顕在化し、市民権を得つつある兆候のなかで、種々雑多な見解が輩出し、邪馬台国研究の全体を視野に入れることは不可能となってきている。第二次世界大戦における敗北まで、邪馬台国の存在は国民に知らされなかったことをかんがみると、その存在自体が皇国史観と相いれないといえる。タブーであった邪馬台国が自由に論議される情況は歓迎されるべきものであるが、厳しい研究の史学史的総括が必要になってきている。また位置比定のためには、文献批判をさらに緻密(ちみつ)化するとともに大局的把握をつねに意図する姿勢をもたねばならない。弥生時代から古墳時代への移行期の墳墓研究、集落研究の成果の吸収、青銅器文化の評価、記紀批判のさらなる進展、神話学への接近、国語学の成果の尊重(上代特殊仮名遣いの甲類・乙類)などの多面的・複合的研究がまたれる。さらに、最近注目されている地域国家論、日本海文化論、そして大量の銅剣などが出土した荒神谷(こうじんだに)遺跡(島根県)なども視野に入れるべきであろう。
倭国はもともと男子を王としていたが、2世紀後半の倭の大乱の混迷が続くなかで邪馬台国の一女子卑弥呼(ひみこ)が諸国によって「共立」され、倭の女王に就任することでまとまったという。彼女が倭王に「共立」された背景は、彼女自身のシャーマンとしての能力が「能(よ)く衆を惑わす」というようにきわめて優れていたことと、彼女の所属していた邪馬台国が倭の30余国のなかでもっとも巨大であり(7万余戸)、政治的組織(官制)が整っていたからであろう。邪馬台国の卑弥呼は武力で諸国を制圧し、諸国に君臨したのではなく、逆に「共立」されたのであるから、その当初は政権の基盤は弱いものであったと推測できる。
卑弥呼は神に仕えるため(「鬼道(きどう)」を事とし)に宮殿にこもり、生涯独身を通し(神の妻)、婢(ひ)1000人をはべらせ、男子1人を介して辞を伝え、男弟をして政治をとらしめたという。しかし、卑弥呼はシャーマンとして神権的政治を展開しつつ、一方において中国魏王朝に倭の女王として朝貢し、冊封(さくほう)体制という外部の秩序のなかで国内の統治を強化するというもう一つの顔をもっていたことを忘れてはならない。卑弥呼に関して「卑弥呼はだれか」という問題関心があり、神功(じんぐう)皇后、天照大神(あまてらすおおみかみ)、倭(やまと)姫、倭迹迹日百襲姫(やまとととひももそひめ)という説が提出されている。「卑弥呼はだれか」という発想が皇室系譜に結び付けるという主旨になっていることに気がつく必要がある。卑弥呼は卑弥呼であり、必要なのはその後嗣(こうし)壹与(いよ)も含めて、その史的性格などを多面的に追究することにある。
邪馬台国を頂点とする倭人社会における身分としては「大人(たいじん)」「下戸(げこ)」「奴婢(ぬひ)」の3層が析出できる。「大人」は共同体の首長層と考えられ、文身(ぶんしん)(入墨(いれずみ))により特権的地位を示し、祭祀(さいし)を主導し、4~5婦を擁し、支配層を形成していた。当時の人々は「門戸」(家族)、「宗族」を構成し、竪穴(たてあな)住居に生活し、農業(禾稲(かとう)など)、狩猟採集、漁労に従事していた。生産などの事を決するには、卜占(ぼくせん)を行い、吉凶を占っていたという。
邪馬台国は30余の国々、すなわち、対馬(つしま)、一支(いき)、末盧(まつろ)、伊都(いと)、奴(な)、不弥(ふみ)、投馬(とうま)、斯馬(しま)、巳百支(しはき)、伊邪(いや)、都支(とき)、弥奴(みな)、好古都(ここと)、不呼(ふこ)、姐奴(そな)、対蘇(つそ)、蘇奴(そな)、呼邑(こお)、華奴蘇奴(かなそな)、鬼(き)、為吾(いご)、鬼奴(きな)、邪馬(やま)、躬臣(くし)、巴利(はり)、支惟(きい)、烏奴(うな)、奴(な)の諸国の頂点にたつ国であり、もっとも官制が整っていた。卑弥呼のもとには男弟がおり、官として伊支馬(いきま)、弥馬升(みましょう)があり、伊都(いと)には特別に一大率(いちだいそつ)を置き、また市を監督する大倭(たいわ)を設置したという。さらに、いくつかの国に共通している卑狗(ひこ)・卑奴母離(ひなもり)も邪馬台国の派遣官的存在である可能性が大である。以上の官制を通して、連座制を伴う法が運用され、租賦制が施行されたらしい。卑弥呼の都は「宮室(きゅうしつ)、樓観(ろうかん)、城柵(じょうさく)」によって構成され、その周囲はつねに兵が守衛するという厳しさであったという。邪馬台国に関して部族的性格の強い小国家連合とする見解、初期的専制国家とする見解があるが、その両面を発展的に把握することも可能である。所在論とも絡めて今後とも多面的研究が必要であり、大和王権の国造(くにのみやつこ)制・伴造(とものみやつこ)制とのかかわりにも目を向ける必要がある。
卑弥呼は国内的権力強化、そして狗奴(くな)国との抗争とのかかわりのなかで中国の魏王朝に朝貢し、その冊封体制の秩序のなかで自己の地位の強化を図っている。西暦239年(景初3)卑弥呼は大夫難升米(なしめ)らを魏の都洛陽(らくよう)に派遣し、生口(せいこう)と斑布(はんぷ)を献上している。魏の明帝は卑弥呼を「親魏倭王」に任命し、金印紫綬(しじゅ)、銅鏡などを下賜し、明帝が背後にあることを知らしめよといったという。243年(正始4)には大夫伊声耆(いせいき)らを派遣し、247年には、狗奴国との対立のなかで載斯烏越(さしうえつ)を帯方郡に派遣し、戦況を報告せしめている。その結果、中国皇帝の詔書・黄幢(こうどう)(軍旗)の賜与を受けている。卑弥呼の死後、宗女の壹与は掖邪狗(えきやく)を魏に派遣し、卑弥呼の外交を継承した。また266年(泰始2)に西晋(せいしん)の武帝のもとに遣使したのも壹与であろうと考えられている。
卑弥呼は狗奴国との戦争の渦中に死んだという。その後、男王がたったが、諸国は離反し、国中は乱れ、当時1000余人が死んだという。そういうなかで卑弥呼の宗女、年13なる壹与が擁立され、ふたたび倭国は治まった。その壹与を女王とする倭国がその後どうなったかは、266年の遣使以後まったく不明である。いわゆる「空白の4世紀」の霧のなかに姿を消していくのである。
邪馬台国畿内説にたてば、邪馬台国はそのまま大和王権へと移行・発展していくと考えるのが普通である。一方、九州説では種々の見解に分かれる。神武(じんむ)東征伝説を史実、史実の反映と考え、邪馬台国が東遷して大和王権となったとする邪馬台国東遷説をはじめとし、投馬国東遷説、騎馬民族説、ネオ騎馬民族説などがある。もう一つは逆に、大和王権によって邪馬台国が滅亡したとする見解である。位置論・政治形態論と絡み、最終的結論は彼岸(ひがん)のかなたにあるが、日本古代国家形成期の要(かなめ)となる問題であり、ないがしろにはできない。東アジア世界のなかで把握するという視点を堅持し、記紀批判の重要性を認識しつつ、考古学の成果を吸収していくことが解決への道であろう。
2~3世紀の日本列島の中にあった国。その所在地は,北部九州とも畿内大和ともいわれている。《魏志倭人伝》の版本に〈邪馬壹国〉とあるので,〈邪馬壱(壹)国(やまいちこく)〉とするのが正しいとする説があるが,中国の古い諸書に引用された《魏志》には〈邪馬臺(台)国〉とあるので,〈邪馬壱国〉説は疑わしい。《魏志倭人伝》によると,邪馬台国は,女王の都する所で,官に伊支馬(いきま),弥馬升(みましよう),弥馬獲支(みまかくき),奴佳鞮(ぬかてい)の四つがあり,7万余戸の人口があったという。この国の王は,2世紀末に近いころに倭国内の諸小国の首長によって共立された女性の卑弥呼(ひみこ)であった。女王以前には男王が立てられていたというが,当時の邪馬台国の王家は,卑弥呼が生まれた家の近親者によって王位が継承されていたということはなかったであろう。
邪馬台国は,対馬国,一支国,末盧(まつら)国,伊都(いと)国,奴(な)国,不弥(ふみ)国,投馬(つま)国,斯馬国など二十数ヵ国を統属下においていたが,倭国の中には,狗奴(くな)国のような邪馬台国連合の傘下に属していない国もあった。邪馬台国には女王の卑弥呼が君臨していたので,《魏志倭人伝》は,邪馬台国を〈女王国〉とも呼称している。女王卑弥呼の下には,政治を助けていた弟がおり,多数の奴婢を抱え,伊支馬以下の四つの官が備わり,宮室・楼観・城柵が立派に造られ,護衛の兵士も存在し,さらにその社会は,大人・下戸・奴婢の身分から成り立っていて,古代国家の様相がみとめられる。しかし,その反面,女王卑弥呼は,王となってから人々の前にその姿をあらわすこともなく,飲食をとるのにも,ただ1人の男性の手にゆだねられていたことは,原始的国家の王に多い〈幽閉された王〉の姿をほうふつさせている。こうした邪馬台国の複雑さは,原始社会から古代社会へと移り変わる社会に生じる古さと新しさとを具有した原始的古代国家であったことによるのである。
→弥生文化
Country in the Japanese islands, visited by Chinese envoys from the year 240. It was described in the Chinese book Sanguo zhi (Sankuo chih; History of the Three Kingdoms), written by Chen Shou (Ch'en Shou; 233−297) toward the end of the 3rd century. There are a few earlier, fragmentary references to Japan in the Chinese histories, but this is the oldest extensive description of Japan in any language. Its rich lode of information on the 3rd-century Wa people, as the Chinese called the Japanese, and their fascinating queen,
Rather than direct knowledge of Japan, Chen Shou apparently depended on archival records and earlier historical treatments of China's short-lived Wei dynasty (220−265), the northernmost of the three kingdoms into which China was divided for much of the 3rd century. Chen's history of Wei, the
Chen's account includes important information on the population and official titles in the key communities, an extensive statement on the manners and customs of the land of the Wa, and a brief section on administrative and social structure. Next there is a substantial statement on Queen Himiko, the character of her rule, and her close diplomatic relations with Wei from 239 until her death a short time after 247. The account then concludes with some details of the succession struggle that followed her burial.
The interesting ethnographic description of the Wa shows a sharply stratified society, with social and regional distinctions indicated by tattoo markings. Although living quarters were segregated according to age and sex, the mixing of the sexes in public activity appeared noteworthy to the Chinese observers. There was an intense concern with pollution and purification.
There appears to have been considerable commerce, both between Wa communities and with Korean and Chinese towns on the peninsula. There was a revenue office for the collection of various levies in grain and other products. Each community had markets under the supervision of a senior official based in Ito (
Queen Himiko was a personage of considerable mystery. According to the Chinese observers, the Wa had once been ruled by a king, but at some time during the 160s and 170s there had been a civil war that ended with the accession of Himiko. She devoted herself completely to religious affairs and was able to “delude the crowd.” She was rarely seen but was assisted by her younger brother, who exercised power for her. If she was between 10 and 15 at her accession, she might have been in her nineties when she died in the late 240s.
Most readers have assumed that the capital, Yamatai, with its reported 70,000 households, must have been somewhere in the central or southern part of Kyūshū. However, the oldest Japanese historical works, the
The first scholar to depart from the view of the chronicles was
But this created geopolitical problems. It was hard to imagine that a regime so far removed from the major areas of Kyūshū life could have dominated those areas, which, as history, tradition, and (later) archaeology showed, were in the northwest. Moreover, the Wei zhi located the hostile country of Kunu south of Yamatai, but there was nothing south of Satsuma. In 1910
Shiratori's treatment put the Kyūshū theory on much firmer philological and historical foundations than the earlier proponents had achieved. Yet, just at the time of his epochal article in 1910,
From the appearance of the articles by Shiratori and Naitō in 1910, no fundamentally new theory arose, only new arguments for the old theories. By the 1960s, most minds had been made up, and Kinai and Kyūshū theorists often seemed to be speaking only to their respective partisans. Moreover, the mass media became attracted to the issue.
But the localization of Yamatai is not a mere game, as it has sometimes seemed. If the growth and formation of the Japanese state is to be understood, it is of fundamental importance to know where Yamatai was. And yet, given the great differences in the two principal theories, and the determination and zeal with which they are advocated by very serious scholars, it is difficult to imagine that there will be an early solution.

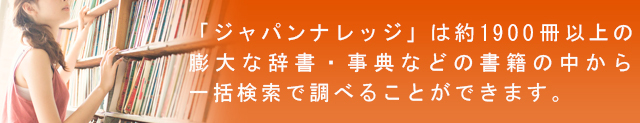
 山古墳】
山古墳】 山古墳】 : 大
山古墳】 : 大 山古墳/(一)
山古墳/(一)






©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.