
江戸時代に盛んに行われた趣味的文芸。古典和歌の形式のなかに、卑近通俗な機知や滑稽(こっけい)を詠み込む。それには、(1)人のよく知る和歌、歌謡、成語など既成のものを踏まえて、それをもじる型(「ほととぎすなきつるあとにあきれたる後徳大寺の有明の顔」四方赤良(よものあから)=蜀山人)、(2)縁語、掛詞(かけことば)などの技巧だけで構成する型(「世にたつは苦しかりけり腰屏風(びょうぶ)まがりなりには折りかがめども」唐衣橘洲(からころもきっしゅう))、(3)心の狂だけの型(「ほととぎす自由自在にきく里は酒屋へ三里豆腐やへ二里」頭(つむり)の光(ひかり))がある。いずれにせよ、和歌の伝統的権威をはぐらかして言語遊戯を楽しむ姿勢が根本であって、単に滑稽な内容を詠む和歌の意ではない。
鎌倉・室町のころ座興としてかなり行われたが、歌道神聖の意識が強いため、記録は許されず、その場限りの「言い捨て」が不文律となっていた。わずかに鎌倉時代の『狂歌酒百首』、室町時代の『永正狂歌合(えいしょうきょうかあわせ)』などが伝えられるが、それらは偶然いわば不法に残ったものである。
狂歌は江戸時代に入ると、俳諧(はいかい)と並んで新しい文芸として認められた。笑いを喜ぶ時代の空気と平和の到来とがしからしめたのであるが、とくに、戦国武将でありかつ歌道の権威者でもある細川幽斎(ゆうさい)が速吟の頓知(とんち)の狂歌をよくしたことが世人の関心を集め、また門下の宮廷人、高僧など京都の上層階級の間に流行がおこったのである。ついで、その一員であった貞徳(ていとく)がこれを一般人士に紹介することに努めたので、いわゆる貞門俳人の多くは狂歌をもつくり、なかでも半井卜養(なからいぼくよう)、石田未得(みとく)、豊蔵坊信海(しんかい)などはとくに狂歌で聞こえ、かなり広く普及した。
京都を中心とする初期の狂歌を、大坂の大衆に導入して浪花(なにわ)狂歌の大流行をおこしたのは、信海門下の永田貞柳(ていりゅう)である。狂歌は「箔(はく)の小袖(こそで)に縄(なわ)の帯」すなわち古典的様式と庶民感情との合一を目ざせと教えたが、古典の教養の乏しい大衆には困難で、全般的に低調卑俗に陥り、京都の初期狂歌の風流や機知とは異質のものとなった。
浪花狂歌は名古屋、広島その他各地に広がったが、江戸には市民の気質にあわないため波及しなかった。しかし18世紀中ごろ諧謔(かいぎゃく)文学を喜ぶ機運のなかで、川柳や狂詩のような軽文学が始まり、また若い幕臣知識層の間に狂歌への関心がおこった。和歌を好む唐衣橘洲、すでに狂詩で名高い四方赤良が中心となり、このような狂名をつけて狂歌会を開き、平秩東作(へつつとうさく)、元(もと)の木網(もくあみ)など好学の町人も参加して、かなり水準の高い狂歌グループが発足した。その後しだいに同好者が増えて地区別の連中(れんじゅう)もでき、1783年(天明3)に橘洲が『狂歌若葉集』、赤良が『万載(まんざい)狂歌集』とそれぞれ狂歌撰集(せんしゅう)を出版したのが刺激となって、いわゆる天明(てんめい)狂歌の大流行がおこった。とくに四方赤良の古典和歌にとらわれない機知と滑稽味豊かな作風が喜ばれて一代を風靡(ふうび)し、他の文芸や絵画、演劇などにも大きな影響を与えて、江戸狂歌の最盛期を現出した。武士を中核とする天明狂歌は、寛政(かんせい)の改革(1787~93)によって町人中心へと変化し、作風も和歌に近い上品さを意図して、鹿津部真顔(しかつべのまがお)は狂歌の名を捨て俳諧歌と称した。これに対して真顔の競争相手であった宿屋飯盛(やどやのめしもり)(石川雅望(まさもち))は笑いを失ったのを非難して天明調を支持し、対立は文政(ぶんせい)年間(1818~30)まで続いたが、狂歌はすでに第一線の文学ではなかった。その後、真顔門下の源真楫(まかじ)が興歌(きょうか)とよぶことを主張したり、尽語楼内匠(じんごろうたくみ)が天明調復帰を説いたりしたが、すでに江戸狂歌、上方(かみがた)狂歌の区別もなくなり、おしなべて低俗に堕して幕末に至ったのである。
狂歌は狂体の和歌であり,和歌の形式に卑俗滑稽な内容を盛ったものである。狂歌は素材用語においてはまったく自由であり,〈縁語〉〈懸詞〉〈本歌取り〉を駆使しつつ日常卑近の事物・生活を詠ずる。古典のもじりは狂歌の方法の眼目で,雅を俗に転じてそこに滑稽感をかもし出す。その先蹤(せんしよう)は早く上代の《万葉集》の戯笑(ぎしよう)歌や無心所着(むしんしよぢやく)歌,中古の俳諧歌に求められる。狂歌という名目はすでに中古の《喜撰式》や《和歌肝要》に見える。中世には狂歌の呼称が一般化し,落首が流行し,《永正狂歌合》やいくつかの職人歌合が作られ,小説,説話,狂言,紀行,日記,軍記などにも狂歌がとり入れられた。《世中百首》のごとき教訓歌や道歌(どうか)の中にも狂歌的性格が認められる。作者は堂上公家,僧侶,連歌師,武家などが中心である。近世の狂歌師たちから狂歌の祖と仰がれた暁月房は本名を藤原為守といい,為家と阿仏尼の子で《狂歌酒百首》の作がある。近世は京都中心の前期,大坂中心の中期,江戸中心の後期に分けられる。安土桃山時代の狂歌作者には,南禅寺の住持にまでなった禅僧で《詠百首狂歌》の作者雄長老,当代歌学の権威細川幽斎,碁の名人本因坊算砂,豊臣秀吉の御伽衆(おとぎしゆう)大村由己,狂歌百首をのこした聖護院道増,《醒睡笑》の作者で浄土宗誓願寺の住職安楽庵策伝,公家の烏丸光広らがあり,それぞれの道の第一級の人々が余技として狂歌を楽しんだ。寛永以後は貞門俳人が中心で,松永貞徳,斎藤徳元,半井卜養,池田正式(まさのり),石田未得,高瀬梅盛らにまとまった作品があり,俳諧点取りの奥書に狂歌が応酬されていたりする。《古今夷曲集》の生白庵行風(せいはくあんこうふう)や《鳩の杖集》の豊蔵坊信海(ほうぞうぼうしんかい)になると,俳諧より狂歌に重点が移ってくる。この時代には狂歌集もぼつぼつ出版され,小説,笑話,紀行,地誌などにも狂歌がとり入れられている。
近世中期には中心が大坂に移り本格的な流行期を迎え狂歌師も職業化してくる。大坂御堂前の菓子屋永田貞柳は,一族ことごとく狂歌をたしなみ,通俗的な作風で人気を博し門弟三千と称し,大坂の栗柯亭木端(りつかていぼくたん),一本亭芙蓉花(いつぽんていふようか),混沌軒国丸(こんとんけんくにまる),広島の芥川貞佐,名古屋の秋園斎米都,永田庵其律,江州八幡の千賀,京都の篠田栗彙ら皆貞柳の流れをくむ人々である。このころ京都には公家の風水軒白玉(正親町公通(おおぎまちきんみち))や自然軒鈍全,九如館鈍永がいた。近世後期には,中心が江戸へ移る。明和年間(1764-72)江戸山手の内山賀邸の門人たちが狂歌会を試みたのが始まりで,やがて急速に市中に広まり,天明から寛政(1781-1801)にかけて狂歌の黄金時代を現出し,世にこれを天明狂歌と称する。唐衣橘洲(からごろもきつしゆう),四方赤良(よものあから),朱楽菅江(あけらかんこう),元木網(もとのもくあみ),平秩東作(へずつとうさく),智恵内子(ちえのないし)らはその錚々たる者で,豊かな趣味教養と軽妙洒脱な機知とを併せもつ人々である。これに次ぐ江戸狂歌の第二世代として宿屋飯盛,鹿都部真顔(しかつべのまがお),頭光(つぶりひかる),馬場金埒の狂歌四天王があり,なかでも天明調の純正狂歌を主張する飯盛と,優美高尚な狂歌を主張して〈俳諧歌〉と称した真顔は,文政(1818-30)に至るまで長くライバルとして活躍した。文政以後は芍薬亭長根,文々舎蟹子丸らが活躍した。天明江戸狂歌は地方にも及んだが,京都,大坂,中国地方などには,中期上方狂歌の末流が勢力を保っていた。明治以後,狂歌は衰退した。

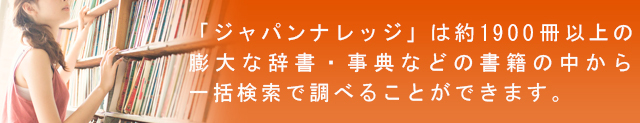










©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.