
山梨・静岡両県にまたがってそびえる日本の最高峰。
「甲斐国志」編纂当時の登山道は、北に
富士山はその構造上から小御岳・古富士・新富士の三つの火山に分けて考えられる。北麓の富士吉田市付近から富士山を望むと、御中道と西側の稜線とが交差する付近に肩がはったように突出している部分が認められる。その付近はほかとは植生が異なり細かい谷が沢山入っている。ここは古い火山体の北斜面にあたり、その後の噴出物に覆われずに残った個所である。この山は富士山の土台となっている小御岳で、津屋弘逵氏によって小御岳火山と命名された。山頂(噴火口)は、富士山有料道路(富士スバルライン)の終点、新五合目の富士吉田市の
新富士火山は、古富士火山とほぼ同じ位置に古い火山を被覆して成立するが、この火山の活動はそれまでの爆発的なものから迸出的な活動に変化し、火山灰の降下とともに山体や裾野の割れ目火口から粘り気の弱い溶岩を流出する活動が主体を占めている。溶岩は三期に区分されている。まずこの火山活動の最初には多量の玄武岩質溶岩を噴出した。これを旧期溶岩といい、北麓では梨ヶ原・猿橋・桂等々の溶岩が認められる。猿橋溶岩は縄文時代草創期前半に現大月市
奈良時代の末期から平安時代にかけては、富士火山帯の活動期であったらしい。富士山の火山活動は、史料に残されたものだけでも十数回の噴火が記録され、そのうち延暦一九年(八〇〇)・貞観六年(八六四)・宝永四年の活動を三大噴火とよぶ。「万葉集」巻三雑歌にはすでに「不尽山を詠ふ歌一首」に「燃ゆる火を 雪もち消ち」の山あるいは「日の本の 大和の国の 鎮とも 座す神かも 宝とも 生れる山かも」として歌われてあがめられてきた。六国史にみえる富士山噴火の初見は、「続日本紀」天応元年(七八一)七月六日条の富士山が灰を降らせ、木葉が彫萎(ちぢれる)した旨を駿河国が言上したものである。次いで延暦一九年三月一四日から四月一八日までの噴火が駿河国から報告され(「日本紀略」同年六月六日条)、同二一年一月にも噴火した(同書同年正月八日条)。同年の噴火では噴石が東海道の相模国
古代の最も大規模な噴火は貞観六年のもので、精進登山道一合目付近の側火山
 の海はこのとき溶岩で埋没し、残った部分が現在の
の海はこのとき溶岩で埋没し、残った部分が現在の 海千許町、仰而見之、正中最頂飾造社宮、垣有四隅、以丹青石立、其四面石高一丈八尺許、広三尺、厚一尺余、立石之門、相去一尺、中有一重高閣、以石
海千許町、仰而見之、正中最頂飾造社宮、垣有四隅、以丹青石立、其四面石高一丈八尺許、広三尺、厚一尺余、立石之門、相去一尺、中有一重高閣、以石 営、彩色美麗」と記される。この社が現在のどの神社に当たるかは諸説があって一定していない。ただ現一宮町
営、彩色美麗」と記される。この社が現在のどの神社に当たるかは諸説があって一定していない。ただ現一宮町
承平七年(九三七)一一月には神火によって湖が埋まったと甲斐国が報告している(日本紀略)。甲斐国の言上であるので、おそらくこの火山活動も甲斐側のどこかの湖水を埋没させるような溶岩の流入が推定される。これ以外にも「本朝世紀」長保元年(九九九)三月七日条、「日本紀略」長元六年(一〇三三)二月一〇日条(噴火は前年一二月一六日)、「扶桑略記」永保三年(一〇八三)三月二八日条にも噴火があったことが記録されている。このように八世紀の終り頃から一一世紀にかけて、富士山は盛んに噴火活動を続けていた。この後、中世に入ってからも何度か噴煙をあげ、また「勝山記」永正八年(一五一一)の条にみられる「富士山カマ岩モユルナリ」と記されるなどの活動を断続的に繰返し、やがて宝永四年の大爆発につながっていくのである。
 へ〕
へ〕富士山にかかわる神の古いものは、「常陸国風土記」の の海)が詠まれている。この時代にあっては富士山は白雪の絶えることのない崇高な山であり、その山神は福慈神・不尽神と称されていた。
の海)が詠まれている。この時代にあっては富士山は白雪の絶えることのない崇高な山であり、その山神は福慈神・不尽神と称されていた。
平安時代になると、山神の名は浅間大神とか浅間明神という神名へ変化する。それまで比較的静穏であった富士山の火山活動が、奈良時代末期から始まり、平安時代に至ってますます激しさを増す。神名の変化は噴火や火山活動にかかわる神の意識化であったといえよう。浅間大神は「アサマノオオカミ」とよみ、「アサマ」とは長野県の
鎌倉時代になると、「吾妻鏡」には富士浅間宮(承久元年三月二六日条)という呼称とともに富士大菩薩(治承四年八月一八日条)、浅間大菩薩(建仁三年六月四日条)という呼称が現れる。このような菩薩号の出現に続いて、南北朝期の「詞林采葉抄」、室町期の「覧富士記」には富士権現という呼称も現れてくる。これらの菩薩や権現の呼称が盛んに使用されるようになったことは、旧来の浅間神社の信仰が仏教と習合していった事実を示している。「吾妻鏡」に呼称がみえるから、平安時代末から鎌倉時代初期の段階で、習合が行われたのであろう。
「梁塵秘抄」巻二霊験所歌には「四方の霊験所は、伊豆の走湯、信濃の戸隠、駿河の富士の山、伯耆の大山、丹後の成相とか。土佐の室生門、讃岐の志度の道場とこそ聞け」の歌があり、霊験著しい寺社、修験の道場の一として、
北口の古道「ケイアウ道」より出土の鰐口には長久二年(一〇四一)の刻銘があったという(甲斐国志)。富士山内出土の金石資料としてはこれが早い時期のものである。鎌倉時代初頭、前述のように文治五年と建久三年の背銘を有する神像が御室に奉納された。山頂の三島ヶ岳の麓から「承久」の墨書を有する経筒(現東京国立博物館蔵)が発見されている。この経筒は富士上人の埋納と結び付けて論じられるが、同上人による埋納は久安五年である(本朝世紀)。乾元二年(一三〇三)には山頂初穂打場の地蔵菩薩が造られた。この地蔵像は初穂打場にあった左近小屋に祀られていたもので、背面に「富士禅定 乾元弐年癸卯七月日 大施主益頭庄沙弥光実、同比丘尼」の銘がある。南北朝期のものとしては、須走口六合目で発見された至徳元年(一三八四)の懸仏があり、「相州糟矢庄大竹郷 富士浅間大菩薩 至徳元年甲子六月十九日 願主来賢」の銘がある。
室町時代になっても山内への神仏などの奉納は継続し、吉田登山道二合目
富士山は詩歌・物語・紀行文などの文学にしばしば登場する。古くは一般に「駿河なる富士」と認識されており、駿河側から記したものがほとんどである。奈良時代には前述のように福慈岳、不尽の高嶺などと記された。平安時代初期には都良香の富士山記(本朝文粋)が生れた。同書は都にあって記され、都人の富士山の認識を示すものであるが、実際に見分した者に取材して記されたようで、頂上の噴火口の記述などは具体性をもつ。この頃には聖徳太子や役行者が富士山へ登ったという伝説はよく知られていた。役行者の富士登山については「日本霊異記」以降諸書に記されるが、伝説の域を出ない。実際に登頂したことが確実なのはおそらく久安五年(一一四九)の富士上人末代が最初であろう(「本朝世紀」同年四月一六日条)。「竹取物語」は不死の薬を捨てた山として「その山をふじの山とは名づけゝる」という山名の語源を説き、「伊勢物語」第九段東下りでは五月末に雪を冠した富士山を見て「時知らぬ山は富士の嶺いつとてか鹿の子まだらに雪のふるらん」の歌が詠まれた。「更級日記」には寛仁四年(一〇二〇)上総国から帰京の途次駿河国を通過する場面に「富士の山はこの国也」として、「雪の消ゆる世もなく積りたれば、色濃き衣に、白きあこめ着たらむやうに見えて、山の頂の少し平ぎたるより煙は立ちのぼる。夕暮れは火の燃え立も見ゆ」と記している。その後も「海道記」や「東関紀行」などの作者が東海道を下る途中で富士山を見て歌を詠んだ。また時宗二世他阿真教も
富士山などの霊山に信仰登山することを禅定といい、それを中心的に行うのは修験者たちであった。また登拝の最終的な到達点である頂上のことを禅定と称する場合もある。室町時代には、先達に引率されて一般の人々も盛んに登山するようになる。そのような登山者を道者(導者)という。「勝山記」によれば明応九年(一五〇〇)六月には「富士へ道者参ル事無限」であったが、関東の戦乱のために本来北口へ到着するはずの道者がみな須走へ着いて、そこから登山したとある。なおこの年は庚申年で富士山の縁年にあたる。縁年は富士山の全容が出現したのが孝安天皇九二年の庚申の年だとする縁起に由来し、この明応九年が庚申登山の初見である。同書永正一五年条には六月一日の夏山開きの初日の出来事として、富士山禅定(頂上か)に大嵐が吹荒れて道者一三人がたちまちに死に、そのうちに内院(噴火口か)から大きな熊が出てきて道者を三人食殺したという記事がある。夏山期には吉田・川口(河口)の御師宿坊は富士禅定を遂げようとする道者で賑わった。川口御師の宿坊は道者坊ともよばれ、おもに西関東から中部高地に檀那所を所持した。吉田御師は古くは東関東をおもな檀那所としていた。御師は
吉田宿の南限に
戦国時代末期に現れた長谷川角行は修験系行者の一人で、この世と人間の生みの親はもとのちち・はは、すなわち富士山が根本神であるとし、江戸とその周辺の庶民の現世利益的な要求にこたえて近世富士講の基礎をつくった。正保三年(一六四六)に一〇六歳で
さらにその信仰は身禄の三女花、参行、不二道を興した小谷三志などへと継承された。そのため幕府の弾圧の対象ともなった。一八世紀も半ばになると江戸市中にあっては禁制が出されるまでに組織化され、広がりをみせていた。寛保二年(一七四二)の御水の禁止に続いて、寛政七年(一七九五)には「富士講と号」して奉納物を建立し、行衣や数珠を用い、祭文を唱え、あるいは護符を出したりすることを禁止する触書が出されており(御触書天保集成)、その頃までに富士講が組織的に確立されたことがうかがわれる。「江戸は広くて八百八町、八百八町に八百八講」といわれるほどに数多くの講の分立をみた。これらの富士講道者の登拝口としての吉田とその御師宿坊の繁栄に対し、それとは一線を画して旧来の信仰を持伝えた川口御師坊は、中期以降しだいに衰微していくことになる。大衆化された道者が、信仰の拠点でまた地理的にも条件のよい吉田口へ直接向かうことになったためである。富士山縁年の庚申年には大祭が執行されて、いっそうの賑いを呈した。女人の登山は通常の年は二合目改所までに定められ、女人禅定場から山頂を拝するのみであったが、縁年には四合五勺の
明治初年の神仏分離により山内の仏像・仏具は下山させられた。北口の浅間神社でも鐘楼・鐘・仁王門・護摩堂などが「混淆に付取除」かれた(「届書」小佐野倍彦家文書)。一合目鈴原大日堂は鈴原神社に再編され、二合目役行者堂は廃された。明治七年には富士山中の仏教的な地名の改称がなされ、山頂八葉などでは文珠ヶ岳が三島ヶ岳、釈迦ノ割石が割石、薬師ヶ岳が久須志岳、釈迦ヶ岳が
富士山の側面には八百八沢という語で表されるほど多数の谷があり、その代表的なものとして、西側の大沢と北東側の吉田大沢がある。とくに大沢は現在でも浸食が進む富士山内最大の谷で、山頂火口西縁の
富士山は独立の高山であるため、植物の垂直分布を知るには格好の場所である。吉田登山道に沿って植生区分をみると、浅間神社から馬返付近まで(標高約八五〇―一五〇〇メートル)が低山帯にあたり、ミズナラ、コナラ、ブナの卓越する地域である。馬返から木立にかかり、そこから五合目の森林限界まで(標高一五〇〇―二四〇〇メートル)が亜高山帯にあたり、おもにコメツガ、シラビソ、オオシラビソ、カラマツ、ダケカンバの林相となる。それより上位は林相を示していないが、岩場を中心にオオタデ、メイゲツソウ、フジアザミなどの草本植物の生育がみられる。年ごとに標高の高い方へそれらの植物の分布が遡上しており、その付近の土壌の安定化とともにミヤマヤナギなどの木本植物が進出してきている。富士山植物では青木ヶ原溶岩上の富士山原始林(鳴沢村・上九一色村)、鷹丸尾溶岩上の山中のハリモミ純林(山中湖村)、吉田登山道
富士講道者の霊場で、
古代富士山北西麓にあった湖。「万葉集」巻三の「不尽山を詠ふ歌」に「石花の海と 名づけてあるも その山の つつめる海そ」と詠まれる。原表記は「石花海」。「石花」を「せい」とよむことは「伊呂波字類抄」などにみえる。また「三代実録」の貞観六年七月一七日条には富士山の大噴火により「埋八代郡本栖并 両水海」とあり、この「
両水海」とあり、この「 」の「水海」が「せの海」のことと考えられる。この噴火のため「せの海」は西湖と精進湖に二分されたという。その後「せの海」に限らず富士五湖のいずれもが和歌に詠まれることはほとんどなかった。
」の「水海」が「せの海」のことと考えられる。この噴火のため「せの海」は西湖と精進湖に二分されたという。その後「せの海」に限らず富士五湖のいずれもが和歌に詠まれることはほとんどなかった。
©Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo
静岡・山梨両県にまたがる本邦随一の高山。最高峰の
富士山の山容は完全無欠ではない。まず傾斜が頂上に行くほど急になる山腹(指数曲線に似る)、山麓に緩傾斜の裾野が展開すること。この裾野が古来、歴史の舞台となった。山腹は東側が西側より緩傾斜であること(空中噴出物が西風で運ばれ東側に落下する)。南東側からみた富士山は南西側からのそれよりとがってみえること(寄生火山が南東―北西の山腹に集中する)などがそれを示している。富士山の地質は単純ではない。いまの火山(新富士火山)の下に古い火山が二つも潜むことがわかっている。古い方が
富士山は「万葉集」以来、一貫して「駿河なる富士」と認識されていた。同書巻三に収める高橋虫麻呂の「不尽山を詠ふ歌一首」は冒頭で「なまよみの 甲斐の国 うち寄する 駿河の国と こちごちの 国のみ中ゆ 出で立てる」と双方の真中にそびえ立つとしながら、「駿河なる 不尽の高嶺は 見れと飽かぬかも」と結んでいる。一方、富士が三国にまたがるとの考えも根強く、一四世紀前半の「玉葉集」には「みくにをさかふふじのしば山」と詠む歌が収められている。五山僧の詩偈にも「山跨三州白雪堆」(攸叙承倫)・「根蟠伊駿相」(横川景三)などとあり、伊豆・駿河・相模の三国にあてることが多かった。「富士」の称について、都良香の「富士山記」(本朝文粋)は富士郡の郡名より起こるとする。これに対し、「竹取物語」は不死の薬を頂上で焼いたから、あるいはそのための勅使が士(つわもの)を数多く引連れて登ったがゆえに士に富む山で富士山とする両説をあげて物語を結んでいる。なお
火口は
「駿河志料」は「登山道路」として、南口は富士郡
富士山の噴火を伝える記録としては、「続日本紀」天応元年(七八一)七月六日条が最も古い。これによると駿河国は麓に降灰があり、降灰地点では木の葉に穴があき、萎れた旨が報告されている。しかし「万葉集」のなかには前述の巻三の「燃ゆる火を 雪もち消ち 降る雪を 火もち消ちつつ」をはじめ、巻一一の「吾妹子に逢ふ縁を無み駿河なる不尽の高嶺の燃えつつかあらむ」など、富士の噴煙を詠む歌が散見され、奈良時代には活発に活動していたらしい。次いで延暦一九年(八〇〇)三月一四日から四月一八日にかけて続いた頂上からの噴火の模様が駿河国から報告されている(「日本紀略」同年六月六日条)。同二一年一月八日、駿河・相模両国からの噴火の報に接した朝廷は、卜筮に「干疫」と出るや、両国に対しこれを鎮めるために読経を行うよう命じている(同書)。この噴火に伴う「焼砕石」が
古代で最も大規模な噴火とされているのが貞観六年(八六四)のものである。五月二五日に届いた駿河国からの報告によれば、最初の噴火から十余日を経過しながらなお活動は衰えず、溶岩流は「本栖水海」(現山梨県の本栖湖)を埋め、さらに駿河・甲斐の国境に迫ったという(三代実録)。七月一七日にもたらされた甲斐国からの報告によれば、溶岩流は本栖・
 の海はこれにより埋没し、現山梨県の
の海はこれにより埋没し、現山梨県の
「扶桑略記」永保三年(一〇八三)三月二八日条の記事をもって、富士山の噴火に言及する記録は中断する。しかし中世に富士山が完全に活動を休止したわけではないことは、東海道を往来した多くの人々が綴った詩文の数々が教えてくれる。一二世紀の半ば、東国へ下った西行は「けぶり立つ富士におもひの争ひてよだけき恋をするが辺ぞ行く」と詠んでいる(山家集)。富士から立上る噴煙を詠込んだ歌は、以後も「海道記」や「東関紀行」などに散見される。弘安二年(一二七九)に鎌倉へ向かった阿仏尼は「十六夜日記」のなかで、「富士の山を見れは、煙もたゝす」と述べるとともに、暦仁年間(一二三八―三九)に父平度繁とともに遠州へ旅した頃には噴煙を上げていたと回想している。一三世紀の後半には活動を休止したらしい。以後は噴煙を上げたり休んだりといった状態を三度ほど繰返し、宝永四年の大噴火に至る。
宝永四年一一月二三日、東南山腹の標高二六〇〇メートル付近から突如噴煙が上がった。貞観の噴火のように溶岩を噴出すことはなかったが、一二月八日(一説には九日)に終息するまで、麓の人々を恐怖させたばかりでなく、噴出した焼砂は須走村をはじめ、駿東郡の村々を埋尽した。西風に乗って運ばれた火山灰の被害は、相模国から遠くは武蔵国にも及んでいる(以上「小山町史」など)。これ以後は目立った活動は知られていない。なお延暦一九年・貞観六年・宝永四年の三度の活動を三大噴火とよんでいる。
富士山を描く文学作品が多岐にわたることは、これまでにあげた諸事例が示している。富士山の煙が「燃える」「消える」「絶える」といった表現は、恋愛感情の比喩として用いられ、前述の「吾妹子」の歌などすでに「万葉集」にも認められる。これは「古今集」に至って定型化され、多くの歌に詠込まれることとなった。「五代集歌枕」や「八雲御抄」などは「富士の山」「ふじのたかね」を駿河の歌枕としている。平安時代、観念化した和歌に対し、物語や紀行文が描く富士山は実にリアルである。残雪を「鹿の子まだら」と描写し、山容を「塩尻のやう」と表現する「伊勢物語」は、実景に基づく記述であろう。鎌倉時代にはこうした傾向はますます顕著となり、「東関紀行」は
絵画では「聖徳太子伝暦」推古六年九月条が伝える太子が甲斐の黒駒に乗って富士山上を飛翔したとのくだりを絵画化した延久元年(一〇六九)の秦致貞の聖徳太子絵伝障子絵(東京国立博物館蔵)が古いが、切立った山容は実景にはそぐわない。頂上は不規則な峰に分れている。こうした特徴は後代の「太子絵伝」に引継がれていくが、鎌倉期から室町期にかけて頂上を四峰あるいは三峰に、山容を左右対称にややなだらかに表現する図様が現れる(「一遍上人絵伝」「一遍上人絵詞伝」「山王霊験記」など)。やがて一五世紀の中頃に雪舟により富士美保清見寺図(永青文庫蔵)が描かれると、探幽をはじめとする狩野派の画家たちに継承され、山頂を三峰に描く定型が広く流布した。定型から脱した個性的な表現は、池大雅や与謝蕪村に代表される南画や葛飾北斎・歌川広重の風景版画が登場する近世後半を待たねばならない。
富士を霊山と崇めたのは原始にさかのぼる。現富士宮市
前述の都良香は「富士山記」で延暦二一年三月の噴火を取上げ、東麓に生じた小山について「神の造れるならむ」(原漢文)と述べたが、この山の神を浅間大神(アサマノオオカミとよむ)としている。浅間神の称が起こるのは、どうやらこの頃らしい。「アサマ」とは長野県の
富士山への登拝が始まったのはいつのことだろうか。「聖徳太子伝暦」や「日本霊異記」の記す聖徳太子や役行者の伝承はともかく、前述した「富士山記」には頂上の実景が描込まれているから、平安前期にはすでに登山が行われていたと考えられる。北口の古道「ケイアウ道」から出土した鰐口には長久二年(一〇四一)の刻銘があったというから(甲斐国志)、一一世紀の半ばには山内に信仰施設が設けられていたとみられる。実際の登頂例としては、「本朝世紀」久安五年(一一四九)四月一六日条などが伝える末代(富士上人)の例が古い。同書によれば、末代は富士へ登山すること数百度に及び、山頂に仏閣を構え(大日寺)、鳥羽法皇以下衆庶の結縁による経典の書写と埋納を企画したという。昭和五年(一九三〇)頂上奥宮の参籠所建設に伴って三島ヶ岳の麓を削ったところ、木槨・経巻軸・銅器・土器などとともに経筒三点と多数の経巻および土器などが発見され、ここが経塚(三島ヶ岳経塚)であったことが確認された。経筒はとくに外筒に入れられているわけではなく、三個発見されたが、二個は銅片のみで、経筒の形状を知ることができるのは一点のみであった。それは直径二八・五センチほどであったが、高さを想定できるほどの破片などはみられなかった。中の経巻の幅がおよそ二五センチであったことから、それよりやや大きめのものであったろうと想像される。経筒の一点の底部には「承久」と墨書されたものがあり、これによれば鎌倉時代前半のものということになる。
北口二合目の
富士山のような霊山に登拝することを禅定といい、それを中心的に行うのは修験者たちであった。また信仰登山の最終的な到達点である頂上のことを禅定と称する場合もある。頂上初穂打場の
大宮・村山からの登拝の情景は富士参詣曼荼羅に詳細に描かれる。富士山本宮浅間大社は二本の曼荼羅図を所持し、それぞれ国と静岡県の文化財に指定されるが、県指定の図のほうがより古相とされる。県指定文化財の富士浅間曼荼羅図は画面上部に富士山、右に箱根三山を描く。富士川辺に本宮を配し、
須山口の須山御師は東海道筋や関西方面をおもな檀那場にしていた。御師は須山浅間神社まで道者を案内し、そこから強力がついて荷物を担いで道案内を行った。道者は浅間神社の横から出発して、
旧来の富士禅定は、近世には富士浅間講(富士講)として継承された。登拝者は登山に先立って精進潔斎を行わなければならず、六〇日間の潔斎を必要とした(「富士浅間宮物忌令」大宮司富士氏文書)。旧暦五月二五日から河原に出て禊をするが、それを富士垢離・富士籠という。京都には富士垢離のための小屋・行屋が存在し(「富士山室小屋建立古帳面写」村山浅間神社文書)、年中行事として富士垢離が行われた。富士籠がすむと富士参詣・富士行に出かける。先達に引率されて東海道を下っていく。道者は六月上旬に集中し、七月の登拝は記されていない(「鈴木甚左衛門道者付帳」公文富士氏文書)。大宮・村山に宿泊し、
村山は村山浅間社と別当寺
戦国末期に現れた長谷川角行は修験系行者の一人で、この世と人間の生みの親はもとのちち・はは、すなわち富士山が根本神であるとし、江戸とその周辺の庶民の現世利益的な要求にこたえて富士浅間信仰のなかから近世富士講の基礎をつくった。正保三年(一六四六)に一〇六歳で
 から食行身禄へと受継がれる身禄派の二派に分れた。光清はその財力によって身禄派をはるかに凌駕していた。身禄は世直しの理想のため、享保一八年(一七三三)に北口七合五勺の
から食行身禄へと受継がれる身禄派の二派に分れた。光清はその財力によって身禄派をはるかに凌駕していた。身禄は世直しの理想のため、享保一八年(一七三三)に北口七合五勺の
富士山縁年の庚申年には大祭が執行され、いっそうの賑わいを呈した。多くの道者を誘引するため、江戸とその周辺、東海道の要衝などに立札が立てられた。女人の登山は通常の年は表口が女人堂まで、南口が御室明神まで、東口が三合目・四合目まで認められた(裾野市史)。なお女人登山の全面的な解禁は明治五年(一八七二)になってからである。万延元年の縁年には英国公使のオールコックが村山口から富士登山し、それを著書「大君の都」に記している。それによると、神奈川(現横浜市神奈川区)の領事館を出発し、吉原宿から村山大鏡坊に至り、そこから登頂している。その後、大宮・吉原・沼津・三島を経て熱海で一〇日余り過ごして江戸に帰った。
明治初年の神仏分離により山内の仏像・仏具は下山させられた。山頂の仏像の多くは大宮に下山している。各登山口の浅間神社でも鐘楼・鐘・仁王門・護摩堂などが取除かれ、村山では大日堂と村山三坊が廃された。明治七年には富士山中の仏教的な地名の改称がなされ、山頂八葉などでは
©Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo

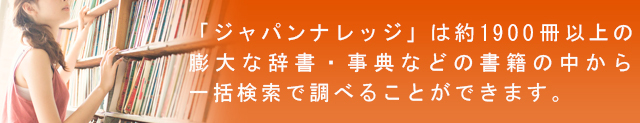
 タ ...
タ ... 】
】









©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.