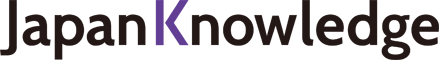もの言わぬ教師
河野龍也こうのたつや
『日本近代文学大事典』のデジタル版編集に加えていただいてから、使い慣れた大事典を編集の側から眺めるという思いがけない立場になった。旧版の紙の六巻本の偉業に改めて目を瞠る思いがしている。
大学院に入りたての頃、先輩たちが何気なく口にする文献のタイトルを、こちらも何気なく聞くふりをしながら、内心はその本の名を覚え込むのに必死で、記憶を頼りに何軒も本屋を渡り歩いた。
あの分厚い六冊の『日本近代文学大事典』も神保町で見つけ、それにしても持ち帰るのが難儀だなあと思っていた矢先に、当時まだ真新しかった古本横断検索サイトの存在を知った。自分にとっては初めてのネット・ショッピングだった。
注文ボタンを押して本当に本が送られてきたときの感動は今に忘れられない。ページをすぐ開けられるよう函を外して部屋の本棚に据え付けると、「こんな大きな買い物をしてしまって、もう後戻りはできない」という悲壮な感じが急に胸に来た。と同時に、やっと入門を「許された」という安堵もまた大きかったのを覚えている。
六巻中の三巻が人名辞典という構成は当たり前のようでありながら、「人が歴史を作る」という強い信念から導き出された形式であることに後から気がついた。その意味では、同じ講談社から出た伊藤整の『日本文壇史』に共通する思想がそこに流れている。この事典の一半はいわば「文学の志士たち」の名簿だ、と思った。
明治以来の「近代文学」の立役者たちが、「人」としての記憶を確かに残していた時代ならではの豊かな記述に触れて、ひとしおそのように感じたのだろう。
もちろん「人が歴史を作る」という歴史観はそれ自体が歴史的で一面的かも知れない。だが、記憶伝承の方法という見方をするなら、そこには簡単に色褪せない底力がある。
大事典の仕掛けはそれだけではなかった。第4巻の事項篇を読めば、日本文学の近代化が、いかに社会の近代化と相まって、外国文学の旺盛な摂取のもとに推進されたかを極めて具体的なレベルで知ることができたし、第5巻の雑誌篇は、「メディアが歴史を作る」という人名篇とは全く別角度からの文学史の眺め方を教えてくれた。
つまりこの事典は、単に知識を得る道具ではなく、ものの見方を手ほどきしてくれる「もの言わぬ教師」だったのである。
つい最近、本棚の整理をしていて『近代文学雑誌事典』(長谷川泉編、一九六六・一、至文堂)を見つけた。冊子体ながら大事典の雑誌篇の先蹤と言える内容だが、仰天したのは附録に「収録雑誌の市価一覧と有利な売り方買い方」という古書店主の座談会記事が載っていたことである。
この冊子の編集には、作家・研究者・古書店が一丸となって、読み捨てられる雑誌の散逸を何とか食い止めようと、読者と手をつなぐ熱意が満ちている。
大事典の雑誌情報の裏に、いかに多くの人の努力が傾注されてきたか。膨大な労力の成果として世に出た大事典は、もう二度と作れない本だと言われていたこともうなずけるのである。
しかし、今回デジタル化が実現した。従来漏れていた項目や特に「現代文学」分野の大規模な増補が行われて利便性が向上したが、さらに将来にわたって編集できる可能性を手に入れたことの意義が大きい。
あのサグラダ・ファミリアすら間もなく完成するらしいのに、一度仕上がった大事典は、これから終わりのない工事現場になっていく。そのなかで、知識の集積だけでない、「もの言わぬ教師」の形がどう変わっていくのかが、今後の大きな課題になる。
(東京大学准教授)
2024年11月13日
『日本近代文学館』館報 No.315 2023.9.15掲載
※この連載は日本近代文学館 館報の「『日本近代文学大事典』と私」の転載です。
執筆者の所属・肩書きは掲載当時のものです。