2016年03月07日
私のように辞書の編集にかかわっている者がこのようなことを書いてはいけないのだが、ことばの使い方がわからなくて辞書を引いても、知りたいことが載っていないということがけっこうあるのではないだろうか。
たとえば、「今日中にすべき仕事」と言うのが正しいのか、「今日中にするべき仕事」と言うのが正しいのか、つまり「~すべき」と「~するべき」とでは、どちらが正しい言い方なのかと悩んだときなどがそうであろう。
辞書の見出しには、「すべき」「するべき」を分解した動詞「す」「する」と助動詞「べき」の終止形「べし」はそれぞれ載っているのだが、通常の国語辞典では結びついた形の「すべき」「するべき」は載っていない。動詞と助動詞が結びついた言い方は無数にあるので、それを見出しにしたら大変なことになるからである。
文法的な話で恐縮なのだがここで確認をしておくと、「べし」という助動詞は本来は文語体の文章に用いられる助動詞で、一般に推量・当然・適当・意志・命令・可能の6つの意味があると考えられている。「今日中にす(する)べき仕事」は「しなければならない」という当然の意味である。
一方、動詞「す」と「する」だが、「す」は文語、「する」は口語の動詞である。
「べし」という助動詞の活用は、「〔未然形〕べから/〔連用形〕べく・べかり/〔終止形〕べし/〔連体形〕べき・べかる/〔已然形〕ベけれ/〔命令形〕〇」となるのだが、このうち連体形の「べき」のみが口語にも残ったのである。もちろん、「この橋渡るべからず」のようなよく知られた言い方もあるが、これは文語としての使い方である。
このようなことから、「べき」は文語の助動詞なのだから口語文の中で使う場合はその前の動詞を「す」と同じ文語にするという立場と、「する」と口語でもよいという立場のふたつに分かれてしまったのである。私見を述べさせていただけば、同じ文章の中でそれらが混ざっていなければどちらでもかまわないと思うのだが。
ただし、公用文ではいちおう決まりがある。いささか古いものだが1952年(昭和27年)に内閣官房長から各省庁事務次官あてに発せられた「公用文作成の要領」に以下のように書かれていて、それが今でも生きている。
文語脈の表現はなるべくやめて,平明なものとする。(中略)
3.「べき」は,「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」「べし」の形は,どんな場合にも用いない。「べき」がサ行変格活用の動詞に続くときには,「するべき」としないで「すべき」とする。
「文語脈の表現はなるべくやめ」るようにとしながら、なぜ文語である「すべき」を優先させるのか、この手の通達はいつも理由のよくわからないことが多い。しかしこれはあくまでも公用文を書くための約束事であって、一般に文章を書くときにまで及ぶことではないので、安心して両様ありなのだとご理解いただきたい。
★神永曉氏、朝日カルチャー新宿教室に登場!
辞書編集ひとすじ36年の、「日本語、どうでしょう?」の著者、神永さん。辞書の編集とは実際にどのように行っているのか、辞書編集者はどんなことを考えながら辞書を編纂しているのかといったことを、様々なエピソードを交えながら話します。また辞書編集者も悩ませる日本語の奥深さや、辞書編集者だけが知っている日本語の面白さ、ことばへの興味がさらに増す辞書との付き合い方などを、具体例を挙げながら紹介されるそう。
講座名:辞書編集者を惑わす 悩ましい日本語
日時:5月21日(土)13:30-15:00
場所:朝日カルチャーセンター新宿教室
住所:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル4階(受付)
くわしくはこちら→朝日カルチャーセンター新宿教室
たとえば、「今日中にすべき仕事」と言うのが正しいのか、「今日中にするべき仕事」と言うのが正しいのか、つまり「~すべき」と「~するべき」とでは、どちらが正しい言い方なのかと悩んだときなどがそうであろう。
辞書の見出しには、「すべき」「するべき」を分解した動詞「す」「する」と助動詞「べき」の終止形「べし」はそれぞれ載っているのだが、通常の国語辞典では結びついた形の「すべき」「するべき」は載っていない。動詞と助動詞が結びついた言い方は無数にあるので、それを見出しにしたら大変なことになるからである。
文法的な話で恐縮なのだがここで確認をしておくと、「べし」という助動詞は本来は文語体の文章に用いられる助動詞で、一般に推量・当然・適当・意志・命令・可能の6つの意味があると考えられている。「今日中にす(する)べき仕事」は「しなければならない」という当然の意味である。
一方、動詞「す」と「する」だが、「す」は文語、「する」は口語の動詞である。
「べし」という助動詞の活用は、「〔未然形〕べから/〔連用形〕べく・べかり/〔終止形〕べし/〔連体形〕べき・べかる/〔已然形〕ベけれ/〔命令形〕〇」となるのだが、このうち連体形の「べき」のみが口語にも残ったのである。もちろん、「この橋渡るべからず」のようなよく知られた言い方もあるが、これは文語としての使い方である。
このようなことから、「べき」は文語の助動詞なのだから口語文の中で使う場合はその前の動詞を「す」と同じ文語にするという立場と、「する」と口語でもよいという立場のふたつに分かれてしまったのである。私見を述べさせていただけば、同じ文章の中でそれらが混ざっていなければどちらでもかまわないと思うのだが。
ただし、公用文ではいちおう決まりがある。いささか古いものだが1952年(昭和27年)に内閣官房長から各省庁事務次官あてに発せられた「公用文作成の要領」に以下のように書かれていて、それが今でも生きている。
文語脈の表現はなるべくやめて,平明なものとする。(中略)
3.「べき」は,「用いるべき手段」「考えるべき問題」「論ずべきではない」「注目すべき現象」のような場合には用いてもよい。「べく」「べし」の形は,どんな場合にも用いない。「べき」がサ行変格活用の動詞に続くときには,「するべき」としないで「すべき」とする。
「文語脈の表現はなるべくやめ」るようにとしながら、なぜ文語である「すべき」を優先させるのか、この手の通達はいつも理由のよくわからないことが多い。しかしこれはあくまでも公用文を書くための約束事であって、一般に文章を書くときにまで及ぶことではないので、安心して両様ありなのだとご理解いただきたい。
★神永曉氏、朝日カルチャー新宿教室に登場!
辞書編集ひとすじ36年の、「日本語、どうでしょう?」の著者、神永さん。辞書の編集とは実際にどのように行っているのか、辞書編集者はどんなことを考えながら辞書を編纂しているのかといったことを、様々なエピソードを交えながら話します。また辞書編集者も悩ませる日本語の奥深さや、辞書編集者だけが知っている日本語の面白さ、ことばへの興味がさらに増す辞書との付き合い方などを、具体例を挙げながら紹介されるそう。
講座名:辞書編集者を惑わす 悩ましい日本語
日時:5月21日(土)13:30-15:00
場所:朝日カルチャーセンター新宿教室
住所:東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル4階(受付)
くわしくはこちら→朝日カルチャーセンター新宿教室
キーワード:
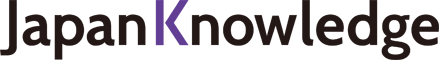


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
