2018年06月25日
「やらずぶったくり」99件
「やらずぼったくり」7件
何の数かというと、国会会議録検索システムでそれぞれの語を検索したときのヒット数である。国会会議録は第1回国会(1947年5月開会)以降のすべての本会議、委員会等の会議録で、現在でも更新されている。話しことばの資料として、私はよく活用している。
「やらずぶったくり」と「やらずぼったくり」、あまり日常語とはいえないかもしれないが、もし使うとしたら皆さんはどちらだろう。
「やらずぶったくり」の99件は、1956(昭和31)年以降ほぼ途切れることなく使われ、そのうちの25件は平成になってからのものである。一方の「やらずぼったくり」は、7件はすべて平成になってからのものである。つまりこれを見る限り、「やらずぶったくり」の方がもともとあった言い方だと言えるだろう。
「やらずぶったくり」は、人に与えずに、ただ取り上げるばかりであるという意味である。『日本国語大辞典(日国)』では以下の例が引用されている。
*手紙雑誌‐一・一一号〔1905〕郵便費附たり文房具の事〈矢野二郎〉「吉凶共に贈答の礼を欠くは勿論、総て遣らずブッタクリの法を守る男であるが」
「手紙雑誌」は古今東西の有名人や日露戦争兵士などの手紙を紹介した雑誌で、手紙の主の矢野二郎は、明治期に商業教育の基礎を築いた人物である。
「やらずぶったくり」の「やらず」は、動詞「やる(遣)」に打消の助動詞「ず」の付いたもので、与えないという意味である。「ぶったくり」は、強奪すること。動詞形で「ぶったくる」と言うこともある。
一方の「ぼったくり」は、ゆすって金を取ることや、不当に高い金を取ることをいう。この語にも「ぼったくる」という動詞形がある。「ぼったくり」「ぼったくる」の「ぼっ」は、「暴利」を動詞化した「ぼる」と関係があるかもしれないと言われている。「ぼる」は、法外な代価や賃銭を要求したり、不当な利益をむさぼったりすることを言う。「初めて入った居酒屋でぼられた」などと使う。
「やらずぼったくり」の方が新しい言い方であろうと書いたが、「やらずぶったくり」が「やらずぼったくり」になったのは、「ぼったくり」と「ぶったくり」とでは意味も発音も似通っているせいかもしれない。ただ、「やらずぼったくり」の存在は、辞書ではまだほとんど認められていないのである。実態は以下の通りだ。
『日国』『広辞苑』『大辞泉』『大辞林』『新明解国語辞典』『新選国語辞典』『岩波国語辞典』『明鏡国語辞典』『現代国語例解辞典』:「やらずぶったくり」のみ。同義語として「やらずぼったくり」はなし。
『三省堂国語辞典』:「やらずぶったくり」に「やらずぼったくり」同義語。「やらずぼったくり」の項目はなし。
これらを見る限り、新語に敏感な『三省堂国語辞典』が「やらずぼったくり」の存在を認めているだけなのである。だが「ぶったくり」「ぼったくり」は音が近いこともあって、「やらずぼったくり」と言う人は今後増えていくと思われる。「やらずぼったくり」が多くの辞書に登録されるのも、そんなに遠いことではない気がする。
「やらずぼったくり」7件
何の数かというと、国会会議録検索システムでそれぞれの語を検索したときのヒット数である。国会会議録は第1回国会(1947年5月開会)以降のすべての本会議、委員会等の会議録で、現在でも更新されている。話しことばの資料として、私はよく活用している。
「やらずぶったくり」と「やらずぼったくり」、あまり日常語とはいえないかもしれないが、もし使うとしたら皆さんはどちらだろう。
「やらずぶったくり」の99件は、1956(昭和31)年以降ほぼ途切れることなく使われ、そのうちの25件は平成になってからのものである。一方の「やらずぼったくり」は、7件はすべて平成になってからのものである。つまりこれを見る限り、「やらずぶったくり」の方がもともとあった言い方だと言えるだろう。
「やらずぶったくり」は、人に与えずに、ただ取り上げるばかりであるという意味である。『日本国語大辞典(日国)』では以下の例が引用されている。
*手紙雑誌‐一・一一号〔1905〕郵便費附たり文房具の事〈矢野二郎〉「吉凶共に贈答の礼を欠くは勿論、総て遣らずブッタクリの法を守る男であるが」
「手紙雑誌」は古今東西の有名人や日露戦争兵士などの手紙を紹介した雑誌で、手紙の主の矢野二郎は、明治期に商業教育の基礎を築いた人物である。
「やらずぶったくり」の「やらず」は、動詞「やる(遣)」に打消の助動詞「ず」の付いたもので、与えないという意味である。「ぶったくり」は、強奪すること。動詞形で「ぶったくる」と言うこともある。
一方の「ぼったくり」は、ゆすって金を取ることや、不当に高い金を取ることをいう。この語にも「ぼったくる」という動詞形がある。「ぼったくり」「ぼったくる」の「ぼっ」は、「暴利」を動詞化した「ぼる」と関係があるかもしれないと言われている。「ぼる」は、法外な代価や賃銭を要求したり、不当な利益をむさぼったりすることを言う。「初めて入った居酒屋でぼられた」などと使う。
「やらずぼったくり」の方が新しい言い方であろうと書いたが、「やらずぶったくり」が「やらずぼったくり」になったのは、「ぼったくり」と「ぶったくり」とでは意味も発音も似通っているせいかもしれない。ただ、「やらずぼったくり」の存在は、辞書ではまだほとんど認められていないのである。実態は以下の通りだ。
『日国』『広辞苑』『大辞泉』『大辞林』『新明解国語辞典』『新選国語辞典』『岩波国語辞典』『明鏡国語辞典』『現代国語例解辞典』:「やらずぶったくり」のみ。同義語として「やらずぼったくり」はなし。
『三省堂国語辞典』:「やらずぶったくり」に「やらずぼったくり」同義語。「やらずぼったくり」の項目はなし。
これらを見る限り、新語に敏感な『三省堂国語辞典』が「やらずぼったくり」の存在を認めているだけなのである。だが「ぶったくり」「ぼったくり」は音が近いこともあって、「やらずぼったくり」と言う人は今後増えていくと思われる。「やらずぼったくり」が多くの辞書に登録されるのも、そんなに遠いことではない気がする。
キーワード:
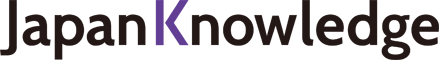


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
