2019年04月01日
私が編集にかかわった『日本国語大辞典』(『日国』)には、5千点近い図版(挿絵)が収録されている。第二版では動植物を中心に増補したが、初版からのものは過去の文献に掲載されているものを参考に、新たに描き起こしたものがほとんどである。過去の文献によった図版は、本文中の例文と同じように、キャプションに参考にした文献名も添えている。
私はこれらの図版はほとんど担当することはなかった。だが、ゲラを読むときに、時々出てくる図版を見るのは、ちょっとした息抜きになっていた。そしてお気に入りの図版もいくつかあった。今回はその一つをご紹介したいと思う。
それは「悪玉(あくだま)」という項目の図版で、山東京伝作の黄表紙(きびょうし)『心学早染艸(しんがくはやぞめぐさ)』(1790年)からのものである。
下に示したように、顔が「善」「悪」の文字になっている人物が若い男の両腕を引っ張っている。そして、その脇では遊女とおぼしき女性がその様子を見ている。『心学早染艸』は目前屋理太郎という商家の息子が、悪魂によって放蕩したことから勘当され、盗賊にまで落ちるのだが、やがて善魂によって教化されるというストーリーである。
この「善」「悪」の字の人物は魂を表していて、この絵を見る限りでは悪魂の方が勢力が強そうである。そしてこの善魂・悪魂がのちに「善玉」「悪玉」と呼ばれるようになる。『心学早染艸』では「善玉」「悪玉」ということばそのものは使われていないが、この小説によって「善玉」「悪玉」ということばが生まれたと考えられている。この絵がまさにその根拠とされるものなのである。
「善玉」「悪玉」の「玉」は人の意味で、「善人」「悪人」と置き換えられる。これは人間の心に善悪の二つがあるとする心学の説による。心学は石門心学とも呼ばれ、江戸後期に石田梅巌(ばいがん)により唱(とな)えられ、庶民の間に広まった実践道徳の教義である。儒教を根本とし、神道・仏教を融合して平易に説いたものである。
『心学早染艸』はそのタイトル通り、京伝が当時流行していた心学の教説を取り入れて書いた小説なのである。
この「善玉」「悪玉」だが、とても面白い話を近世文学の棚橋正博氏にお聞きしたことがある。この「悪玉」が若者に受けてしまい、「悪」と書いた丸提灯をさおにくくりつけて高くかかげた少年たちが、夜な夜な街中を走りまわり、町奉行が禁止令を出したほどであったというのである。まるで暴走族である。
今では、「善玉」「悪玉」は芝居や映画などでも使われるようになり、「善玉」は善人の役、「悪玉」は悪人の役を言う。また、「善玉」は良い作用を及ぼすものという意味で「善玉コルステロール」「善玉菌」などと言い、「悪玉」はその逆の意味で「悪玉コレステロール」「悪玉菌」などの形で使われるようになっている。
今も生きていることばの根拠が江戸時代の小説の挿絵に求められるなんて、なんだか面白いではないか。
●「日本語、どうでしょう?」講演会、開催決定!
「“辛党”が好きなものは何?」「世間ずれは“ずれ”ているわけではない」「灯台もと暗しの“灯台”って何?」――神永さんがおかしな日本語を解説!
小学館神保町アカデミー
「日本語、どうでしょう?辞書編集者を悩ます“おかしな”日本語」
■日時:2019年6月6日(木)18:30~20:00
■場所:小学館集英社プロダクションSP神保町第3ビル
(東京都千代田区神田神保町2-18)
■受講料:3240円(税込)
くわしくはこちら→https://www.shopro.co.jp/koza/list/
申し込みはこちらから→https://fs224.formasp.jp/g383/form1/
私はこれらの図版はほとんど担当することはなかった。だが、ゲラを読むときに、時々出てくる図版を見るのは、ちょっとした息抜きになっていた。そしてお気に入りの図版もいくつかあった。今回はその一つをご紹介したいと思う。
それは「悪玉(あくだま)」という項目の図版で、山東京伝作の黄表紙(きびょうし)『心学早染艸(しんがくはやぞめぐさ)』(1790年)からのものである。
下に示したように、顔が「善」「悪」の文字になっている人物が若い男の両腕を引っ張っている。そして、その脇では遊女とおぼしき女性がその様子を見ている。『心学早染艸』は目前屋理太郎という商家の息子が、悪魂によって放蕩したことから勘当され、盗賊にまで落ちるのだが、やがて善魂によって教化されるというストーリーである。
この「善」「悪」の字の人物は魂を表していて、この絵を見る限りでは悪魂の方が勢力が強そうである。そしてこの善魂・悪魂がのちに「善玉」「悪玉」と呼ばれるようになる。『心学早染艸』では「善玉」「悪玉」ということばそのものは使われていないが、この小説によって「善玉」「悪玉」ということばが生まれたと考えられている。この絵がまさにその根拠とされるものなのである。
「善玉」「悪玉」の「玉」は人の意味で、「善人」「悪人」と置き換えられる。これは人間の心に善悪の二つがあるとする心学の説による。心学は石門心学とも呼ばれ、江戸後期に石田梅巌(ばいがん)により唱(とな)えられ、庶民の間に広まった実践道徳の教義である。儒教を根本とし、神道・仏教を融合して平易に説いたものである。
『心学早染艸』はそのタイトル通り、京伝が当時流行していた心学の教説を取り入れて書いた小説なのである。
この「善玉」「悪玉」だが、とても面白い話を近世文学の棚橋正博氏にお聞きしたことがある。この「悪玉」が若者に受けてしまい、「悪」と書いた丸提灯をさおにくくりつけて高くかかげた少年たちが、夜な夜な街中を走りまわり、町奉行が禁止令を出したほどであったというのである。まるで暴走族である。
今では、「善玉」「悪玉」は芝居や映画などでも使われるようになり、「善玉」は善人の役、「悪玉」は悪人の役を言う。また、「善玉」は良い作用を及ぼすものという意味で「善玉コルステロール」「善玉菌」などと言い、「悪玉」はその逆の意味で「悪玉コレステロール」「悪玉菌」などの形で使われるようになっている。
今も生きていることばの根拠が江戸時代の小説の挿絵に求められるなんて、なんだか面白いではないか。

●「日本語、どうでしょう?」講演会、開催決定!
「“辛党”が好きなものは何?」「世間ずれは“ずれ”ているわけではない」「灯台もと暗しの“灯台”って何?」――神永さんがおかしな日本語を解説!
小学館神保町アカデミー
「日本語、どうでしょう?辞書編集者を悩ます“おかしな”日本語」
■日時:2019年6月6日(木)18:30~20:00
■場所:小学館集英社プロダクションSP神保町第3ビル
(東京都千代田区神田神保町2-18)
■受講料:3240円(税込)
くわしくはこちら→https://www.shopro.co.jp/koza/list/
申し込みはこちらから→https://fs224.formasp.jp/g383/form1/
キーワード:
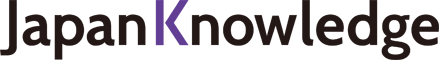


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
