
 a(婆羅門)だったが、この時代には王族が最上位を占めるに至った。また商工業者は多数のギルド(セーニse
a(婆羅門)だったが、この時代には王族が最上位を占めるに至った。また商工業者は多数のギルド(セーニse i、プーガpūga)を形成して、富者が社会的勢力をもつに至った。一般民衆はややもすれば物質的享楽にふけり、道徳頽廃の現象がようやく著しくなった。幾多の自由思想家があらわれて、バラモン教の祭祀の意義を否認し、ベーダVeda聖典の権威を拒否した。一部の宗教者は民間信仰と妥協し、または身をさいなむ苦行を実行していた。
i、プーガpūga)を形成して、富者が社会的勢力をもつに至った。一般民衆はややもすれば物質的享楽にふけり、道徳頽廃の現象がようやく著しくなった。幾多の自由思想家があらわれて、バラモン教の祭祀の意義を否認し、ベーダVeda聖典の権威を拒否した。一部の宗教者は民間信仰と妥協し、または身をさいなむ苦行を実行していた。 a)ともよばれる。実践の基本的立場としては、欲楽と苦行との両極端を排して、不苦不楽の中道を説いた。対他的には慈悲の精神を強調し、人間だけでなく、一切の生きとし生けるものにまで慈悲を及ぼすことを理想とする。
a)ともよばれる。実践の基本的立場としては、欲楽と苦行との両極端を排して、不苦不楽の中道を説いた。対他的には慈悲の精神を強調し、人間だけでなく、一切の生きとし生けるものにまで慈悲を及ぼすことを理想とする。 gha(僧伽)と称する。サンガとは、インド一般には共和国あるいはギルドの呼称であり、仏教はその組織と運営法をとりいれたのである。それは出家修行者と在俗信者とからなり、男性と女性とをともに含んでいる。出家修行者は家から離脱して独身生活をつづけ、世俗の職業から遠ざかり、経済行為を禁止されている。これに対して在俗信者には、家庭をまもり、正しい職業に従事して、他人の利益をはかり、精励努力して名誉財産を得て、死後には天の世界に生まれることをすすめている。個人的な戒律としては、生きものをころすな、ぬすみをするな、邪淫を行うな、虚言をいうな、酒をのむな、という五戒が特に強調されている。呪術・魔法・卜占の類をかたく禁止し、ベーダ聖典の権威を否認して、犠牲を伴う祭祀を排斥している。経済面に関しては、獲得した財貨は、自分が用いるだけでなく、他人にも享受させよと教え、負債は必ず返却せよという。万人の平等を唱え、四姓の身分的区別を否認した。国家は法(dharm′a)によって導かれねばならぬと主張している。またゴータマは共和政体を讃美している。
gha(僧伽)と称する。サンガとは、インド一般には共和国あるいはギルドの呼称であり、仏教はその組織と運営法をとりいれたのである。それは出家修行者と在俗信者とからなり、男性と女性とをともに含んでいる。出家修行者は家から離脱して独身生活をつづけ、世俗の職業から遠ざかり、経済行為を禁止されている。これに対して在俗信者には、家庭をまもり、正しい職業に従事して、他人の利益をはかり、精励努力して名誉財産を得て、死後には天の世界に生まれることをすすめている。個人的な戒律としては、生きものをころすな、ぬすみをするな、邪淫を行うな、虚言をいうな、酒をのむな、という五戒が特に強調されている。呪術・魔法・卜占の類をかたく禁止し、ベーダ聖典の権威を否認して、犠牲を伴う祭祀を排斥している。経済面に関しては、獲得した財貨は、自分が用いるだけでなく、他人にも享受させよと教え、負債は必ず返却せよという。万人の平等を唱え、四姓の身分的区別を否認した。国家は法(dharm′a)によって導かれねばならぬと主張している。またゴータマは共和政体を讃美している。紀元前5世紀ころインドに出たシャーキャムニ,すなわち釈迦(しやか)によって創唱された教えで,キリスト教,イスラムと並ぶ世界三大宗教の一つ。現在,(1)スリランカ,タイなどの東南アジア諸国,(2)中国,朝鮮,日本などの東アジア諸国,(3)チベット,モンゴルなどの内陸アジア諸地域,などを中心に約5億人の教徒を有するほか,アメリカやヨーロッパにも教徒や思想的共鳴者を得つつある。(1)は前3世紀に伝道されたスリランカを中心に広まった南伝仏教(南方仏教)で,パーリ語仏典を用いる上座部仏教,(2)はインド北西部から西域(中央アジア)を経て広まった北伝仏教で,漢訳仏典を基本とする大乗仏教,(3)は後期にネパールなどを経て伝わった大乗仏教で,チベット語訳の仏典を用いるなど,これらの諸地域の仏教は,歴史と伝統を異にし,教義や教団の形態もさまざまであるが,いずれもみな,教祖釈迦をブッダ(仏)として崇拝し,その教え(法)を聞き,禅定(ぜんじよう)などの実践修行によって悟りを得,解脱(げだつ)することを目標とする点では一致している。なお,発祥の地インドでは13世紀に教団が破壊され,ネパールなどの周辺地域を除いて消滅したが,現代に入って新仏教徒と呼ばれる宗教社会運動が起こって復活した。また欧米の宗教活動は,日本から伝わった禅,スリランカの大菩提会(だいぼだいかい),およびチベット人移民によるものがおもなものである。
釈迦はヒマラヤ山麓のカピラバストゥを都とする釈迦族の王子として生まれたが,29歳のとき,人生の苦悩からの解脱を求めて出家し,6年苦行の後,35歳にして,マガダ国ガヤー城郊外において菩提樹下で禅定に入り,苦悩の起こる原因と,その克服に関する縁起の理を悟ってブッダ(〈悟れる者〉の意)となった(成道(じようどう))。その後,ワーラーナシー郊外のサールナート(鹿野苑(ろくやおん))において,もと修行仲間だった5人の修行者を相手に,自ら悟った真理(法)を説き,弟子とした(初転法輪(しよてんぼうりん))。これによって仏(教主)・法(仏の教え)・僧(サンガすなわち弟子たちの集団)の三宝がそろい,仏教が成立した。以後,250人の弟子を連れるシャーリプトラ(舎利弗(しやりほつ))とマハーマウドガリヤーヤナ(大目犍連(だいもくけんれん)。目連ともいう),1000人の弟子をもつカッサパ(迦葉(かしよう))3兄弟らの入門があり,また,故郷で釈迦族の人々を入信させるなどして教団が確立した。その教化の範囲はマガダ国の都ラージャグリハ(王舎城(おうしやじよう))とコーサラ国の都シュラーバスティー(舎衛城(しやえいじよう))を二つの中心とするガンガー(ガンジス)川中流域の地方で(これを仏教の〈中国〉という),おもに国王や都市の大商人たちの間に支持者を得た。釈迦はこうして45年間,教化に努めた後,80歳にしてクシナガラの地で死去した。これを入滅(般涅槃(はつねはん))という。遺骸は信者たちの手で火葬され,遺骨は信者たちに分けられ,塔(ストゥーパ,舎利塔,仏塔)にまつられた。
弟子たちは最長老のマハーカッサパ(摩訶迦葉)を中心に集まって会議を開き,釈迦の遺言に従って,生前に説かれた教え(法)と制定された教団の規則(律)とを編集し入滅後のよりどころとして,教団の結束をはかった。これを結集(けつじゆう)と呼ぶ。釈迦の誕生・成道・初転法輪・入滅は仏伝中で四大事跡とされ,その記念の地,すなわちカピラバストゥ郊外のルンビニー園,ブッダガヤーの菩提樹下,ワーラーナシー郊外の鹿野苑,そしてクシナガラは聖地として,後世,信徒の巡礼の地となった。
釈迦の生存年代について,学界では前6~前5世紀説(《衆聖点記》などの説による前566-前486)と,前5~前4世紀説(中村元説では前463-前383)とがある。前者は南伝,後者は北伝の資料に基づく計算であるが,目下のところ,いずれかに正否を断定できる資料はない。
釈迦在世時のインドでは,正統派の宗教家たるバラモン(婆羅門)と並んで,沙門(しやもん)(シュラマナ)と呼ばれる多種多様な宗教家,思想家がおり,なんらかの方法で輪廻(りんね)からの解脱を求めて修行し,またその道を説いていた。釈迦もまた,この出家遊行して乞食によって生活する沙門の道を選び,また修行方法として,身心を苦しめ鍛えて超能力を得る苦行の代りに,精神の統一,安定によって真理を直観する禅定(ヨーガと同じ)を採用した。真理の直観とは真実をありのままにみること,すなわち悟りで,それによって生死輪廻の苦から解脱するという。これが苦の滅,涅槃と呼ばれる究極の目標である。釈迦の方法は,一方で自然的欲望に身をまかせる快楽主義を否定し,他面,苦行を捨てる点で,苦楽の両極端を離れた中道と称される。
また,釈迦は人生問題の解決に直接役だたない形而上学的問題(たとえば世界の有限・無限とか,創造因とか)については質問されても解答せず(無記),判断を中止している。この点,釈迦は実務的で,自らの立場を病いに応じて薬を施す医者にたとえている。すなわち,苦悩を観察し,その由来するところをつきとめて,これを断つべく,その方法を教えるのがその任務であるとする。これは,(1)苦,(2)苦を集めるもの(原因),(3)苦の滅,(4)苦の滅に至る道という四つの項目(四諦(したい))にまとめられ,仏教の基本とされる。
この知的・合理的方法の行き着くところ,仏教では真理を悟ることに直接の目標が移行し,悟りの完成者たるブッダ(仏陀,仏,覚者)がその理想像となった。同時に真理こそ永遠不変の絶対的価値で,釈迦はただそれを発見し,人々にそれに至る道を教えた仲介者にすぎない。人はその教えに従って,覚者となるべく修行する。真理が絶対で,ブッダを通じて開顕されるということは,真理がキリスト教などの〈神〉の地位に代わるものであることを示す。しかし,仲介者,教主としてのブッダはキリスト同様一人であるとしても,覚者たることが万人に開かれているのは,絶対者が非人格的な真理である点とともに,仏教の特色である。ここでいう釈迦が悟った真理を仏教ではダルマ(法)と呼び,仏の教えはその真理を内容とするので,同じくダルマ,あるいは法と呼ばれる。
以上は釈迦の宗教の特色であるが,釈迦入滅の後,事情は少し変化した。第一は教祖ブッダすなわち釈迦の神格化(超人化)である。ブッダ(仏)に対する崇拝はもともと在家(ざいけ)の信者の間に強かったが,入滅後は,仏塔をまつることを通じて高まった。この傾向は後に仏塔を中心とする在家信者の運動を出発点とする大乗仏教を生み出した。そこでは過去仏や未来仏と並んで,この世界の周囲十方に無数の諸仏とその世界(仏国土,浄土)の存在を認めた。それらの諸仏は,衆生済度(しゆじようさいど)の誓願をもって修行して仏となり,その誓いどおり衆生を救うべく,その姿を現したものとして崇拝された(たとえば西方極楽世界の阿弥陀)。しかしその場合でも,法(真理)の絶対性は失われず,仏は真理の体現者(如来,すなわち如=真理に来至し,また如より来至する者)とされている。仏の本質は法そのもので(法身),諸仏はその具体的顕現である(色身)。一方,修行の目標としての悟りを,絶対者たる法との合一に求めるのは,バラモン正統派のベーダーンタ学派が主張する〈梵我一如〉とも共通する神秘主義であるが,ことにこれは後期に発達した密教において著しい。
仏教はインド外の諸地域に発展するにつれて,それぞれの地域,民族の信仰や儀礼などと習合し,それらを仏道の方便と認めたため,かなり大きく変質した。これは一つには,ヒンドゥー教とも共通するインド思想の宗教的寛容性によるが,仏教が本質的に非人格的な真理を絶対とし,万象にその具現を見いだす,いわゆる汎神論的宗教であることにも由来する。
釈迦が悟り,人に説いたところの法(真理=教え)とは何か。仏教の教理の基本は,しばしば〈諸行無常(しよぎようむじよう)〉〈一切皆苦(いつさいかいく)〉〈諸法無我(しよほうむが)〉〈涅槃寂静(ねはんじやくじよう)〉の四句に要約される(これを一般に四法印と呼ぶ。ときには〈一切皆苦〉を除いて三法印という)。このうち前三句はわれわれが日常経験している世界の諸現象に関する真理で,(1)諸現象は無常で変化してやまず,(2)そのために苦をもたらす(たとえば最大の苦として死。死は無常の代表),(3)諸現象はすべて,自我でも自己の所有物でもなく,したがって自由にはならない。苦悩は実は,この自由にならないもの,無常なものを,われ,わがものと思い,執着をこすところに生ずる。〈無我〉について後には,無常と直接結びつけて,永遠不変な実体(=我)のないことと解釈され,〈空〉(中身のないこと)と同義とされた(無我説)。理論的には,無常であり,無我であるのがものの真実の姿で,それを認めぬところに苦が生じるということになろう(悟れば苦はなくなるが,無常であり,無我である事実に変りはない)。この苦の滅が第四句の〈涅槃寂静〉の表すところで,涅槃は具体的には苦悩を起こす根源たる欲望,執着の炎が鎮火し寂静,清涼となった状態と説明される。
同じ内容を組織的に説いたのが,前述の〈四諦〉である(諦は真実,真理の意)。教理上の説明を加えると,(1)苦諦(くたい) 人生には生老病死の四苦のほか,愛(いと)しい人に別れ,怨み憎しみある者に出会い,求めるものは得られず,この身は無常な諸要素(五蘊(ごうん)--肉体(色)と感覚(受),表象(想),意思(行),認識(識)の諸心理作用)の集合にすぎない,という合計8種の苦悩がある。(2)集諦(じつたい) この苦を集め起こすもの,つまり苦の原因としては,煩悩と総称される心のけがれ(むさぼり,にくしみ,無知など)がある。無知とは無常,無我といった真実を知らないこと(無明(むみよう))で,ときにはこれが悪の根源とみなされる。欲望や執着はすべてこの無知の結果おこるとみるのである。(3)滅諦(めつたい) 苦の滅,涅槃寂静が理想であること。これは無知がなくなったとき,つまり真実を知ったとき,悟ったときに実現する。(4)道諦(どうたい) この,苦の滅を達成するために実践すべき正しい道で,8項ある(八正道(はつしようどう))。すなわち,(a)正しい物の見方(正見),(b)正しい心のもち方(正思),(c)正しい言葉遣い(正語),(d)正しい行動--不殺生,不偸盗などの戒を守る(正業),(e)正しい生活(正命),(f)正しい努力精進(正精進),(g)正しく教えを憶念する(正念),(h)正しい禅定の修習(正定)。
以上の四諦は苦因→苦,道の実践による苦因の滅→苦の滅という2種の互いに相反する方向の因果関係を含む。前者は迷いの生ずる方向の因果で,後者は悟りに至る因果である。この因果関係が広く〈縁起〉と呼ばれる理(ことわり)で,総じていえば〈AがあればBがある。Aが生ずるからBが生ずる。AがなければBはない。Aが滅するからBが滅する〉という形式になる。これを苦因→苦という視点で具体的に説いたのが,いわゆる十二支よりなる縁起(十二因縁)である。その次第は,(1)無明(むみよう)(根源的無知)→(2)行(ぎよう)(身・口・意による三業)→(3)識(しき)(心。分別的な認識)→(4)名色(みようしき)(精神的要素と物質的要素。認識の対象)→(5)六入(ろくにゆう)(眼・耳・鼻・舌・身・意の六種の感官)→(6)触(そく)(認識,感官,対象の接触)→(7)受(じゆ)(苦楽などの感受)→(8)愛(渇愛(かつあい)。本能的欲望)→(9)取(しゆ)(執着。物,物の見方,まちがった行為軌範,自我に対する固執)→(10)有(う)(欲界,色界,無色界という三界の生存状態。総じていえば輪廻の世界)→(11)生(しよう)→(12)老死(ろうし)などの苦悩の集積,となる。釈迦はこの無明から順次に生・老死が生起する次第と,無明が滅すれば順次に老死に至るまでが滅する次第という両方向にわたって縁起を観じて,悟りを得たと伝えられている。
縁起説は業説(業は身・口・意の三業だが,それが果をひく力を重視する。総じて,輪廻を引き起こすのは業の力であるが,その業はさらに無知などの惑(わく)すなわち煩悩に基づいているとみる説)と結びつき,十二支を三世にわたる二重の惑・業・苦の関係として説明するようになった。これと並んで,縁起を広くすべての現象の間における種々な関係の理論と解する立場も生まれた。その場合,因果を成立させる条件として,すべての現象になんらかの形で果を生む力があるとみて,これを〈行〉(サンスカーラsaṃskāra)と呼び,その働きによって作られたものを〈有為(うい)法〉(サンスクリタ・ダルマsaṃskṛta-dharma)と名づけた(ここで〈法〉とは一定の性質をもった現象の意)。しかも,すべて有為法は同時に因となって他の現象を生む力をもっているものと考えた(すなわち〈諸行〉=〈諸有為法〉)。そして,それらの行=有為法は刹那ごとに生じては滅するものと考え,それが無常ということの意味とされた。たとえば個人存在(我)なども,五蘊が心(識)を中心に刹那生滅を繰り返しながら,一定期間相続すること(心相続)だと説明する。そして,刹那生滅を繰り返す諸法(諸現象)には永続的な実体はない,それが〈無我〉の意味であると解する。これら有為法に対し,理論上生滅のない存在として,空間(虚空)などが想定されるが,宗教的要請たる涅槃もまた,生滅を超えた常住のものとみなされた。これらを有為でないものという意味で〈無為法〉(アサンスクリタ・ダルマasaṃskṛta-dharma)と呼ぶ。ただし,これも決して実体あるものではない。つまり,有為法同様,無為法もまた無我である(諸法無我の諸法は有為法と無為法を含む,と解する)。
有為法と無為法と合わせて〈一切(いつさい)法〉であるが,法(ダルマ)は別様に分類すると,五蘊,十二処(十二入ともいう。眼・耳・鼻・舌・身・意とその対象としての色・声・香・味・触・法。触は身体で触れられて認識されるものの意。法は意識の対象となるすべての概念,無為法もその点で,法の仲間に入る),十八界(十二処と同じ内外の対応に,眼識などの六識を加えたもの)になるとされて,相互の包括関係が決められた(ただし五蘊は行=有為法だけに相当し無為法を含まない)。このような理論化・組織化は,アビダルマ(法の研究)の名でまとめられた。
さらに,縁起説の理解をめぐって,仏教内に種々の学説が現れた。代表的なものとしては,(1)一定の性質をもって実在する諸法相互の関係を縁起とみる説一切有部(せついつさいうぶ)の学説と,(2)これに反対し,諸法がその自体をもたず(無自性),空であることが縁起の意義であるとする大乗(中観派(ちゆうがんは))の立場がある。同じ大乗の中でも唯識(ゆいしき)説では,諸法も自我(我)も観念的存在(仮)にすぎないが,それらを実有とみる迷妄の世界が事実としてあることを認め,それをあらしめる根拠たるものとして,われわれの認識構造(識)が,過去無数の諸業によって縁起したものであり,したがって実有であると主張した(ただし実有といっても,縁起したものであるから有為法であり,刹那滅であり,空であり,また価値的には迷妄の存在であるから否定されるべきものである。ただ,否定を通じて悟りを実現させる意味で,悟りにとって不可欠な依処(えしよ)(土台)であると説明される)。唯識説ではまた,すべてが縁起したものであるという真理,空であるということ(空性),識のみであるということ(唯識性)などを,真如,法界の名で実有であるという。仏もまた,真如と一体となったもの,法身として実有である。この実有は,永遠不変の真理として絶対であることと,到達すべき宗教上の目標であることの二点を含んでいる。
以上のような教理を知るのが実践の目標たる悟り(菩提(ぼだい))である。したがって悟りは,四諦を現観する,諸法無我の理を知る,縁起・空性をみる,唯識たることに入るなど,教理に応じて種々に表現されるが,一言で言えば,真実をみる,あるいは,如実に知見するということである。この知る働きを智あるいは慧と呼び,般若と称する。これは通常の分別的認識とは異なり,無分別な直観である。この般若を身につけるにはその前段階として,修行が要求される。修行の基本は八正道で,そのあり方は中道と称されたが,具体的にはほかにも種々の徳目が挙げられ,それらを合わせて,三十七覚支(かくし),すなわち37種の菩提を得るための手段と呼ぶこともある。
またそれらをまとめると,戒・定・慧の三学におさまる。戒の基本は〈諸悪莫作,諸善奉行,自浄其意,是諸仏教〉(諸悪をなすな,諸善をなせ,自ら心をきよめよ,これは諸仏の教えである)と示されるとおりで,戒を守ることは入門の条件,修行の前提である。定(じよう)には四禅(しぜん),四無色定(しむしきじよう),滅尽定(めつじんじよう)と呼ばれる種々の段階(九次第定(くしだいじよう))があり,そのほかにも各種の三昧(さんまい)が説かれる。さらに,禅定中に慧のはたらきによって憶念し,観察する念,観と呼ばれる修行法もある。総じて,禅定は修行そのものと言ってもよく,それには常に慧が伴っている。定と慧を合わせて止観(しかん)ということもある。大乗では実践を六波羅蜜(ろくはらみつ)にまとめる。波羅蜜とは完成されたあり方,もしくは理想世界(彼岸)にわたることと解釈される。布施,持戒,忍辱(にんにく),精進,禅定,般若の6種の行で,そのすべてが般若(慧)に裏づけられているとき,波羅蜜と呼ばれる。三学に比して,布施という利他行が加わっているのが特色で,これは六波羅蜜が元来,仏の前身(成道以前)たる菩薩の行で,衆生済度が目的であるのによる。
修行にはまた修行者の機根(能力,性質)等に応じて,難易や段階の別がある。一般に禅定の修行により悟るのは難行であるので,機根の劣るものは信によることを勧めるが,大乗では仏の慈悲力で,信のみでも救済されると教える。修行者は修行の段階に応じて,凡夫(ぼんぶ)と聖人(しようにん)に分けられる。聖人は準備的修行(加行(けぎよう))を終えて四諦の理を観じて見道に達したもの以上で,その後究極的完成まで修行を続けることが要請される。この段階を修道(しゆどう)という。修行の完成者は阿羅漢(羅漢)と呼ばれる。阿羅漢は元来,仏の異称で,供養をうけるに値する者の意であるが,伝統的部派仏教では弟子たちの完成位の名として,仏とは区別した。そこでは,仏になる菩薩の道と,独学で悟る独覚の道と阿羅漢になる弟子の道が,三乗の名で区別される。これに対し大乗仏教では,仏になる菩薩の道を万人に可能とし,大乗(大きな乗り物の意)であることを自認した。誰でも仏と同じ悟り(阿耨多羅三藐三菩提(あのくたらさんみやくさんぼだい)二無上菩提)に向けて発心すれば菩薩である。菩薩にもまた凡聖が区別されるが,完成された学説では十地(十種の菩薩の階梯)の初地以上のものが聖人とされる。
教団を意味するサンガ(僧伽,僧)は共同体の意で,成員の和合を旨とする。サンガは宗教団体のほか,職人のギルド,共和政体をも指して用いられる用語で,成員が自分たちで規則をつくる,成員相互が平等の権利をもつなどのことが予想される。仏教では出家した修行者は出身の家柄や階級(バルナ)を問わず(四姓平等),等しく沙門釈子(しやもんしやくし)と称するものとして,諸川が大海に入って一味となるのになぞらえている。教団の成員は広義には比丘(びく)(男性修行者),比丘尼(びくに)(女性修行者),優婆塞(うばそく)(男性在家信者),優婆夷(うばい)(女性在家信者)の四衆より成るが,在家の信者に対しては入信に際し,仏法僧の三宝への帰依と五戒の遵守を誓わせる以外,特に取決めはない。これに対し,修行者は入門に際し,具足戒を受けて以後,団体生活を営むについて種々規制をうけ,また犯戒すれば罰則をうける。このような教団の規制を律(戒律)と呼ぶ。律は,戒本とそれの違反に対する罰則を決める部門と,教団運営に伴う諸規則を挙げる部門とより成る。前者は250戒を罰則の軽重によって5種あるいは8種に分けるが,そのうち最も重い罪は波羅夷(はらい)罪で,殺生,偸盗,婬,大妄語(悟っていないのに悟ったといううそ)を犯したものに対して課せられ,犯戒者は教団から追放される。その他は軽重はあってもすべて,懺悔(さんげ)によって許される。戒の条項は比丘で250,比丘尼では348とされる(部派により異なる)が,元来は随犯規制といって,その行為が問題として取り上げられるたびにしだいに増加したとされる(初犯は規定以前なので罰せられない)。後者,教団運営の規則類には,会議運営のやり方とか,出家受戒作法その他,布薩(一定の日に日頃の行為を懺悔する),安居(あんご)(毎年雨季に全員集まって修行する)などの行事の規定,修行者の生活資具としての四依(衣は糞掃衣(ふんぞうえ),食事用の鉢,住居は樹下石上,薬は陳棄薬による)の規定などがある。会議の運営は全員一致を旨とし,そのため会議の種類に応じて人数を決め,そのつどサンガの人員を確認した(たとえば,入門のための受戒の儀式には10人以上の成人修行者の出席を必要とするなど)。この,事に応じたサンガの構成を現前僧伽(げんぜんそうぎや)という。これに対し,全仏教徒(修行者)の教団を四方僧伽という(四方僧伽にあたるサンスクリットのチャートゥルディシャを音写した招提(しょうだい)の語は,唐招提寺の名に残っている)。律は部派ごとに,内容上に若干の差異がある。なお,大乗には戒があっても律はない。これは大乗が元来在家信者の集団から起こったことにも関連しよう。
仏教の教団は釈迦の入滅後100年ほどは統一を保っていたが,その後,保守的な上層部と,進歩的改革派の大衆との間で対立を生じて分裂し,それぞれ上座部(じようざぶ)と大衆部(だいしゆぶ)となった。その原因について,北伝仏教では修行完成者(阿羅漢)のあり方をめぐる見解の相違とし(大天の五事),南伝仏教では塩や金銭の保有などをめぐる戒律条項の争い(十事非法)に帰している。分裂はその後さらに両部派内部に及び,以後200~300年の間に18の部派に分かれ,根本2部と合わせて20部派となったという。このような分裂の年代については,基準となる釈迦の年代に異論が多いので確定できない。しかし,教団の分裂は仏教の発展の結果と考えれば,前3世紀アショーカ王治下のマウリヤ朝時代がそれにふさわしい。たとえば,スリランカの上座部はアショーカの王子マヒンダによる伝道と伝えるが,その根拠地は西インドの教団であったと考えられる(ただし,アショーカの碑文には分裂を戒める記事はあるが,部派名などはまったくあげられていない)。
仏教史では,上座,大衆二部への根本分裂以後を部派仏教の時代と呼ぶ。また,部派ごとに教理の研究(アビダルマ)を競ったのでアビダルマ仏教ともいう。これに対し,分裂以前を初期仏教あるいは原始仏教と呼んでいる。おもな部派としては,上座部の系統で北インドに勢力のあった説一切有部(略称有部),化地部(けじぶ),法蔵部など,西インドに勢力をもった犢子部(とくしぶ)などがあり,有部からさらに経量部(きようりようぶ)が分出した。犢子部からも正量部(しようりようぶ)その他が分出したが,正量部は後世(玄奘(げんじよう)の滞在した7世紀ころ)中インドに進出して大きな勢力をもっていた。他に雪山部(せつせんぶ)があり,根本上座部を自称している。大衆部もまた多くの部派に分かれたが,北インドにあった説出世部(せつしゆつせぶ)は仏伝《大事(マハーバストゥ)》を残している。南インドは大衆部系が多いが,地域的にアーンドラ派と呼ばれることもある。
スリランカにわたった上座部は分別説部とも呼ばれるが,パーリ語による聖典を完備して今日に伝えている。有部もまた,漢訳などに多くの資料を残していて,その教義もよく知られるが,そのほかの部派は有部やスリランカの上座部の伝承から知られる以外には,あまり多くの資料はない。有部はまた,大乗仏教から部派仏教の代表のごとくみなされ,批判の矢面に立たされているが,事実,北インドで最有力な部派であった。有部は後2世紀にクシャーナ朝の王カニシカのもとで拡張し,また,その学説は《大毘婆沙論(だいびばしやろん)》に集大成された。有部の名は三世にわたって一切法が実有であるとするその学説に基づくが,《大毘婆沙論》を所依とする点で,毘婆沙師(びばしやし)とも呼ばれる。これに対し,経典を所依とすることを主張したのが経量部で,この派は現在の法だけを実有とみた。5世紀に出たバスバンドゥ(世親)の《阿毘達磨俱舎論》(略称《俱舎論》)は有部学説の綱要書であるが,その立場は経量部に従っている。犢子部の系統では,身心を構成する五蘊とつかず離れず存在する自我(非即非離蘊の我)の存在を認め,そのため他派から,仏説違反とみなされた。大衆部の系統はブッダを超越的存在とみるところに特色があるが,これと大乗仏教とのつながりは定かではない。
前1世紀ころ,仏塔を中心に集まった信者たちの間から,仏を賛仰する新しい仏教運動が起こった。この運動は仏教を限られた出家修行者中心のものから,より広範な在家も含めた者たちのものに変えようとするもので,多数を悟りの世界に運ぶものという意味で,自ら大乗と称し,在来の修行者中心の仏教を小乗と呼んで批難した。この運動は急速に広まり後2世紀ころまでには,その新しい主張を盛る数多くの聖典,すなわち大乗経典を制作した。それには,修行者の一部も参加した模様である。彼らは法師として新しい経典の普及に努め,経典を遺骨の代りに崇拝し,まつることを勧めている。大乗経典は歴史的には仏説とはいえないが,そこには釈迦が弟子たちに対して,言うべくして説かなかった真意が開顕されていると自負する。それらのうち般若経は般若(はんにや)によって空性の理を悟ることを説いて大乗の教理的立場を明らかにした。《華厳経(けごんきよう)》は仏の宇宙にあまねき絶対性と,菩薩の実践の相即を説き,十地の階梯を確立した。《法華経(ほけきよう)》は大乗は声聞,独覚の二乗をも包括する仏一乗であるゆえんを明かし,仏の真実の姿は永遠の実在(久遠実成)で,入滅は方便と教える。また,《阿弥陀経》などは,仏を光明無量,寿命無量とし,それを名とする仏(阿弥陀仏)の本願に基づく極楽浄土への往生を説く。《維摩経(ゆいまきよう)》は大乗の菩薩の理想像を,市井にある在家の維摩居士の姿に反映させている。これらの種々な経典の成立した後をうけて,ナーガールジュナ(竜樹(りゆうじゆ))は,大乗の空観の教義を《中論》などによって祖述し,縁起,空性,仮(概念的存在)の同義語性を明らかにし,それは有無を離れ,去来,断常,一異を離れて中道であると教えている。ナーガールジュナの後継者たちは,のちに,《中論》にちなんで中観派(ちゆうがんは)と呼ばれた。
大乗経典の作成はナーガールジュナ以後もなお続き,その中で《如来蔵経(によらいぞうきよう)》《勝鬘経(しようまんぎよう)》《涅槃経(ねはんぎよう)》などの如来蔵説や,《解深密経(げじんみつきよう)》《瑜伽師地論(ゆがしじろん)》などに伝承された唯識説が新しい主張として説かれた。前者は《法華経》の一乗思想をうけて,すべての衆生に成仏の可能性(如来蔵,仏性)のあること(一切衆生悉有仏性)を主張するもので,後に《宝性論(ほうしようろん)》や《大乗起信論(だいじようきしんろん)》によって祖述された。後者は有部あるいは経量部と近い関係にある瑜伽師(ゆがし)(ヨーガーチャーラYogācāra)の一派から生まれた学説で,われわれの認識するいっさいの存在はすべて識(すなわち心)にほかならないと主張する。4世紀末から5世紀初めにかけて,アサンガ(無著(むぢやく)),バスバンドゥの兄弟によって組織,大成された。派祖にマイトレーヤ(弥勒)を仰ぎ,《大乗荘厳経論(だいじようしようごんきようろん)》や《中辺分別論(ちゆうへんふんべつろん)》などを彼の著として尊重する。アサンガはこれらの経論をうけてその学説を《摂大乗論(しようだいじようろん)》にまとめた。弟のバスバンドゥははじめ経量部にあって《俱舎論》を書いたが,後に大乗に転向し,《唯識三十頌(ゆいしきさんじゆうじゆ)》などを著し,また多くの大乗経典の注釈書を残した。バスバンドゥ以後,瑜伽行派(唯識派)は中観派と論争を生じ,また,ヒンドゥー教の諸哲学とも論争を交えるが,その過程でしだいに知識論と論理学(因明)が発達した。その最初の確立者が5~6世紀のディグナーガ(陳那)で,その後,7世紀のダルマキールティ(法称)によって継承,大成された。前者に《集量論》,後者に《量評釈》の大著がある(〈量〉とは知覚や推理などの知識根拠をいう)。中観派と瑜伽行派の論争はなお続き,互いに影響し合ったが,最終的には中観派が優位に立って,瑜伽行派を吸収したようにみえる。これは後にチベットに伝えられた仏教から判ぜられる。
哲学的論争と精密な理論の確立は,他面,大乗仏教から宗教運動としての迫力を薄くしたようで,民衆の新しい要求は新宗教運動として密教を生み出した。密教は仏の絶対性が超越的なものというより,人間に内在的に働くことを強調し,これを如来の三密(身・口・意による3種の秘密業)による加持(仏が絶対的慈悲から,衆生のために身・口・意のさまざまな形を示し,その形の中に住すること)と説明する。その由来するところは,ベーダ以来のインド的な,言葉のもつ呪力に対する崇拝にあり,大乗経典でも陀羅尼の形で多く説かれている(密教でいう真言,すなわちマントラとは,元来,ベーダの文句のもつ呪力を指す。したがって,ブラフマンと同義的関係にある)。しかし,その主張の純化されたものとして,《大日経》が7世紀初めに作られ,次いで同世紀の後半,《金剛頂経》の出現によって確立した。密教の隆盛はしかし,仏教をヒンドゥー教とあまり差異のないものとした。13世紀初め,東ベンガルの教団根拠地であったビクラマシラー寺院がイスラムの軍隊に蹂躙(じゆうりん)されたのを最後に,教団は壊滅し,頭を失った仏教はヒンドゥー教の中に溶けこみ,吸収されてしまった。しかし,後期インド仏教の主張するところは,関係経論のチベット訳とともに,チベットの教団によって正しく継承されて今日に至る。
仏教が中国に入るのは,紀元前後のことである。前漢の武帝が,大宛の天馬にあこがれて西方の経略にのりだしてから,東西文明の交流はにわかにたかまる。いわゆる〈糸綢之路〉(シルクロード)の開通と,仏教の東漸は表裏の関係にある。中国民族にとって,西方はつねに神秘の宝庫であった。仏教への対応は,その核といえる。仏と法と僧の三つを,人々は三宝とよぶ。
中国における最初の翻訳仏典とされる《四十二章経》の序は,その伝来の事情を次のように説く。一夜,後漢の明帝が,西方より殿庭に飛来するふしぎな金人の夢をみる。金人は,首の背後に円光を負うて全身より光明を放つ。臣下のもの知りが,西方インドの仏であろうという。帝は早速に,使者を派遣する。2人のインド僧が,大月氏より洛陽に迎えられ,《四十二章経》を翻訳する。インド僧は,仏像を将来し,焼香礼拝の儀式を伝える。帝は各地に寺をたてるほか,洛陽郊外に自分の寿陵をつくり,千乗万騎の儀仗が仏塔をめぐって降臨する西域風の壁画を描かせる。
以上は,当の《四十二章経》の序のほかに,3世紀末の《牟子理惑論》をはじめ,梁代の《出三蔵記集》や《高僧伝》,および北魏の正史である《魏書》の釈老志,首都洛陽の仏寺の歴史を集める《洛陽伽藍記》などに,共通して伝える説話である。説話に尾ひれがつくのは,当然のことである。明帝が西方に派する使者のうちに前漢の張騫(ちようけん)の名が加わり,インド僧の名が迦葉摩騰・竺法蘭という2人の三蔵法師となり,2人が白馬に仏像と経典をのせてきたこと,これが中国最初の仏寺,洛陽白馬寺の由来となること,《四十二章経》が後漢の宮廷に蔵せられて長く世に知られなかったことなど,時代が下るにしたがって伝説はしだいに詳細となり,まことしやかになる。そこにかえって,後に発展する中国仏教の本質についての重要なインデックスが含まれるわけだ。
明帝の在位は,1世紀の後半に当たる。義弟の楚王英が熱心な仏教者であったことは,すでに正史の《後漢書》に明記がある。当時,この国固有の民俗信仰であった道教が,西来の仏教の動きに対抗しつつ,教義や教団の組織を固めていたことも知られる。西方の異教である仏教がこの国に定着するには,時の天子に迎えられ,漢文の経典をもつという,公伝の形式が必要であった。とくに,明帝求法の伝説は,仏像の存在を前提し,全身より光明を放って空中を自由に飛翔することができる,仏教固有の神通力への魅力と重なる。神通力は,習禅の成果である。全身放光や空中飛翔のほか,前生と来生および他人の心を読む,透視の能力をも含む。先の2人の三蔵法師につづいて,この国に来る多くのインド僧は,すべてそうした神通力の達人である。神通力の条件となる持戒や禅定の実践は,仏教の定着に大きい動機をなすのである。無量寿仏や西方浄土の教説も,この国固有の神仙方術の信仰(神仙説)に結びつけて受容される。空中に立つ阿弥陀仏の姿を観察する般舟三昧(はんじゆざんまい)の教えが,もっとも由来の確かな翻訳経典の一つに含まれる。
あたかも,後漢末より三国・南北朝にかけて,華北は五胡とよばれる北方塞外民族の支配下にある。五胡の首領は争って仏教を利用し,胡僧の伝える新しい西域文明を軸に,中国の伝統を統一しようとした。亀茲(きじ)(クチャ)から華北に来た仏図澄は,一巻の経論も将来しなかったが,特異の神通力によって後趙の首領石勒を教化し,各地に仏寺を建立させて,多くの有能な漢人僧を育成し,中国仏教の基礎をつくる。前秦王苻健の帰依をうける最初の漢人僧道安は,その弟子の一人である。道安につぐ慧遠(えおん)は,江南の廬山に東林寺を創し,南北両朝の帰依をうけ,独自の教団をつくる。道安の前秦教化が動機となって,亀茲より新たにクマーラジーバ(鳩摩羅什)が西来し,後秦王姚興(ようこう)の帰依で長安に多くの仏寺が立ち,各地より胡漢の僧が集まる。クマーラジーバは,のちに八宗の祖と仰がれる南インドの竜樹の大乗仏教を伝え,初期中国仏教の展開に一期を画する。すべて,五胡の治下でのことである。クマーラジーバは仏図澄とちがい,持戒や習禅よりも仏典の翻訳と講義に全力を傾けるのであり,これが中国仏教の主流となる。74部384巻という,その翻訳仏典は,新しい文学と哲学の金字塔である。
さらに,西来の初期仏教は,高度に洗練された金銅仏や,塔を中心とする壮大な仏寺の建造によって,人々の美的関心を強める。インドのアジャンターや,アフガニスタンのバーミヤーン,クチャ(庫車)やトゥルファンなどの石窟寺にならって,敦煌や大同,洛陽竜門の各地に,華北独自の石窟寺が開削される。人々は造寺造像に熱中する。北魏末の洛陽には,すでに1367所の仏寺があった。いずれも,無数の大小仏像と珍奇な西域の文物で荘厳される。壁画の主題は,仏の本生ものがたりや,主要な大小乗経典の絵解きである。仏教独自の実践修行と,珍しい儀式や儀礼が,四季を通じてくりかえされている。
それらの造型と儀礼が思想の表現であることは,いうまでもない。知識層は,仏教独自の哲学に共感を寄せる。聖人の古典をもち,儒教や道教の高度の伝統をもつ中国社会で,仏教はまったく新しい展開をとげる。仏典翻訳の問題は,後につづく中国仏教史の軸となる。とくに儒教や道教の歴史と対抗しつつ,仏教は教祖釈迦仏の年代を,争って古代に引きあげるとともに,西域で発達した大小乗の仏教運動とその成果である仏典を,すべて同じ釈迦仏の一代の説法とする,独自の教学をつくりあげる。クマーラジーバを先駆とする無数の外国三蔵が,南北朝より隋・唐の時代にかけて断続的に大小乗の仏典を紹介し,すべてを漢文に翻訳しつくしたことは,そうした信仰と創造の成果である。
要するに中国仏教の特色は,時代と種族を異にする,大衆の歴史的帰依によって,かつてのインド仏教とも,中国の伝統文明とも異なる新しい世界宗教を生むことになる。いわゆる漢訳仏教圏の完成は,かつての東西文明の交流以上に,より壮大な精神文明の運動を,あらためて周辺民族に拡大するのであり,そんな新しい展望によって,ここに中国仏教の歴史は,ようやく第2期に移ることになる。あたかも中国史で,五代より宋に移る近世の開幕に重なる時期である。その初伝より約1000年,仏教はすでに母国のインドと異なる,東アジア文明の大きい胎動となる。たとえば,初期チベット仏教は,唐代の中国仏教を輸入することにはじまるが,やがてインド仏教を総合して,中国ともインドとも異なる,新しい第2の中国仏教をつくる。後にラマ教とよばれるチベット密教が,それである。さらに,漢訳仏典は,中国で印刷技術を発達させ,独自の《大蔵経》をもつことで,朝鮮や日本に新しい文明をおこす。交流は,すでに西方シルクロードの域にとどまらない。
いったい,中国仏教史の資料といえば,3種の《高僧伝》によるのが一般である。第1は,梁の会稽嘉祥寺の僧慧皎(えこう)が,519年(天監18)に編する《高僧伝》13巻で,後漢より梁にいたる450年,501人(本伝257,付伝244)の仏教者の列伝である。第2は,唐の道宣がこれをうけ,645年(貞観19)にいったん完成,自分の死の年に至るまで加筆する《続高僧伝》30巻である。前後144年,694人(本伝485,付伝209)の列伝を収める。第3は,宋の賛寧が,988年(端拱1)に上進する《宋高僧伝》30巻で,先の道宣のあとをうけ,編者の時代にいたる約300年,657人(本伝531,付伝126)の列伝である。
いずれも,勅撰の正史に準ずる一貫した編集であり,3書ともに同じ十科の分類方法(表参照)をとる。すなわち,訳経は経典の翻訳,義解はその解釈,神異は神通力,習禅は座禅の実践,明律は戒律の研究,亡身は生身供養,誦経は経典の暗誦,興福は社会福祉,経師は宗教音楽,唱導は説法・教化である。道宣は,神異を感通に,亡身を遺身に,誦経を読誦に改め,経師をやめて,護法の一科を新設する。賛寧は,唱導を雑科とする以外すべて道宣に従っていて,そこに時代の変化をみることができる。
護法は,道教徒の排仏に抗し仏法を守ることである。唐朝は李氏の出身で,老子と祖先を同じくするというので,道士が中央に進出する。仏教の大蔵経にならう,道教の経典も出そろう。太子令傅奕(ふえき)の排仏に対し,護法僧法琳が〈弁正論〉を上進して,これを論破する。〈弁正論〉は,後漢以来の仏教と道教の論争を軸とするユニークな中国仏教史である。道宣も,この論争に加わっている。《続高僧伝》の編集は,そんな護法の情熱によって一貫される。《宋高僧伝》も,これを受ける。
3種の《高僧伝》を通して,同じ十科に分類される高僧の員数の増減をみると,それぞれの時代の問題を一目に鳥瞰することができる。最初に,高い員数を示す訳経や義解僧の動きは,中国仏教のもっとも大きい特色である。内容的に,訳経は胡僧,義解は漢僧が多い。それらがしだいに,習禅や明律,感通,護法という,漢僧中心の実践に移るのである。《宋高僧伝》のごとき習禅と感通が,全体の半数に近づく。詳しくみると,習禅や感通と同じ傾向の人々が,他の分野のすべてに散在する事実がある。十科の分類は,すでに解体する。三蔵法師の来化がとだえ,仏典のすべてを漢文に翻してしまった中国仏教は,ここではじめて受容の域を出る。中国民族の仏教として,禅と浄土教が宋以後の主流となり,新しい居士仏教の時代となるのである。
もともと六朝より隋・唐の仏教は,教相判釈の仕事を中心に展開する。教相判釈とは,その初伝より当事者の時代まで,前後何百年かにわたって陸続と漢文に翻訳された,すべての仏教経典を総合し体系づけることによって,教祖仏陀の根本精神を明らかにしようとする方法である。成立が異なり,伝来も翻訳者も異なる,大小乗の無数の仏典を,すべて同じ仏陀の一代の説法として,解釈するのである。そこには,明らかに大きい矛盾がある。経典は,同じ仏陀の言葉であるが,説法の相手が異なり,事情が異なる。つまり,仏陀の30歳より80歳まで,50年という時の開きがある。そんな時の言葉のゆえに,説き方がちがうのは当然である。問題は,何が仏陀の根本真実であったか。根本真実と,時の言葉としての方便のちがいを,見きわめる必要があった。教相判釈は,そのことを問うのであり,もっとも中国的な学問となる。
教相判釈の典型は,隋の天台智顗(ちぎ)が集大成する五時八教論である。それは,この国はじめての一つの宗派,天台宗の開創をも意味する。天台の五時八教論は,先にいうクマーラジーバが訳する《妙法 華経》を真実とし,他のすべての仏典を,その方便として体系づける。仏陀は《法華経》の根本真実を明かすために,人々の理解能力に応じ,その向上をはかって,さまざまの仏典を説く。そこに,五つの段階,すなわち時の教えがある。華厳時,阿含(鹿苑)時,方等時,般若時,法華・涅槃時である。華厳時は,仏陀の自己の悟りの内容を,相手の能力を顧みることなしに一方的に告白したもの。《阿含経》はこれをもっとも能力の低い人々の,世間的な生活に応じて説き明かしたもの。方等は大乗の初歩であり,阿含が小乗といわれるのに対して小乗より大乗への向上をはかるもの。《般若経》はそんな大乗への徹底であり極意であるが,先の方等につづくために,すべて否定的な傾きをもつ。これに反して,《法華経》《涅槃経》は,仏陀晩年のもっとも円熟した思想をあらわし,すべてを包容し肯定する,総合を特色とする。要するに,五時とは,教化の秩序であり,八教は,そんな教化の方法をより詳しく分析したもの,特に五とか八とかいう数字は,農耕社会に特有の四季の区別と,その総合の知恵よりきている。春は種子を下ろし,夏は育て,秋は収め,冬は次の春の種子を蔵する,そんな不断の循環にかたどって仏教の思想を受けとめたものが,五時八教の教判にほかならぬ。問題は,そんな教相判釈の仕事が,仏陀の言葉のすべてを衆生教化の方便とする,中国的な発想そのものにある。天台の五時八教論に対し,華厳の五教十宗判,三論宗の大小二教判,密教の顕密二教と《十住心論》など,他の教相判釈についても,事情はほぼ同じである。
華経》を真実とし,他のすべての仏典を,その方便として体系づける。仏陀は《法華経》の根本真実を明かすために,人々の理解能力に応じ,その向上をはかって,さまざまの仏典を説く。そこに,五つの段階,すなわち時の教えがある。華厳時,阿含(鹿苑)時,方等時,般若時,法華・涅槃時である。華厳時は,仏陀の自己の悟りの内容を,相手の能力を顧みることなしに一方的に告白したもの。《阿含経》はこれをもっとも能力の低い人々の,世間的な生活に応じて説き明かしたもの。方等は大乗の初歩であり,阿含が小乗といわれるのに対して小乗より大乗への向上をはかるもの。《般若経》はそんな大乗への徹底であり極意であるが,先の方等につづくために,すべて否定的な傾きをもつ。これに反して,《法華経》《涅槃経》は,仏陀晩年のもっとも円熟した思想をあらわし,すべてを包容し肯定する,総合を特色とする。要するに,五時とは,教化の秩序であり,八教は,そんな教化の方法をより詳しく分析したもの,特に五とか八とかいう数字は,農耕社会に特有の四季の区別と,その総合の知恵よりきている。春は種子を下ろし,夏は育て,秋は収め,冬は次の春の種子を蔵する,そんな不断の循環にかたどって仏教の思想を受けとめたものが,五時八教の教判にほかならぬ。問題は,そんな教相判釈の仕事が,仏陀の言葉のすべてを衆生教化の方便とする,中国的な発想そのものにある。天台の五時八教論に対し,華厳の五教十宗判,三論宗の大小二教判,密教の顕密二教と《十住心論》など,他の教相判釈についても,事情はほぼ同じである。
教化は,国主の仕事である。仏教は,国主の教化を助ける御用哲学となる。時の政治に奉仕する,輔教の哲学となるほかはない。現実の苦悩を解脱し,みずから涅槃の悟りを得ることをねがった仏教は,この国に来て大きく変化する。中国の政治思想に合う,仏教のみが受容される。中国仏教に固有の宗派の成立もまたそのことに関係する。ひっきょう,教化の方法がゆきとどき,一人も漏らさぬ体系化が完成すると,方便の言葉だけが空転し,仏教の真実はその所在を隠す。衆生も,その存在意識を失う。教えは,人々を縛る枷鎖(かさ)となる。善意ゆえに,苦悩は倍加する。
天台や華厳の教相判釈に対し,まったく新しい立場より,本来の仏教を考え直そうとする運動が起こり,幾度か試行錯誤をかさねる。信行の三階教や,道綽(どうしやく)・善導の浄土教はその一つで,いずれも教相の総合より,それらに対する適応を欠く,一般民衆の能力にふさわしい,独自の実践を選ぶところに特色をもつ。時の政治に背をむけたために,三階教は弾圧につぶれ,浄土教はしだいに変質の方向をとり,中国よりも日本で徹底する。要するに,従来の教相判釈が,教化の体系に向かうのに対し,今は教化される側の機の反省に向かうのであり,これが前後500年を超える中国仏教史前半の結論となる。
そんな唐代仏教の動きのうちで,大きい画期となったのは,玄奘(げんじよう)の唯識法相宗である。玄奘は,天台の教学が大乗の初歩とする,瑜伽唯識を再編するのであり,みずからインドに赴いて,インド本土の後期大乗を学ぶ。とりわけ玄奘の運動は,世界国家としての唐朝の草創と時を同じくする。前後16年におよぶインド西域旅行の成果を記す彼の《大唐西域記》は,前漢以来の東西文明史を総括し,新しい時代を開くものとして,高く評価される。唯識法相宗は,そうした歴史地理に裏付けられて,すでに中国の風土に同化してしまった後漢以来の旧仏教に反省を求めた。唐代以後の中国はもとより,新羅や日本の仏教史に大きく作用するのは当然である。クマーラジーバの翻訳を旧訳,玄奘以後を新訳とよぶ。新羅も日本の仏教も,新訳の受容を最初とした。
一方,唐代仏教は,禅の運動によってさらに変質する。禅は,従来の翻訳仏教に対し,仏陀の教えの外にあることを自任する。自分は一生何も説かなかったという,仏陀の晩年の述懐を伝える《楞伽(りようが)経》によって,方便の言葉ならぬ,その本心に直参しようとするのである。禅は,そうした仏陀の心を伝えたインド僧菩提達磨を初祖とし,〈不立文字〉〈以心伝心〉を主張して,独自の仏教史を説く。禅もまた,玄奘の場合と同じように,あまりにも中国化した旧仏教を,本来のところにもどす復古であるが,それが同時に中国民族自身の新しい宗教の創造となるところが異なる。宋代以後の中国仏教は,そんな禅を中心に発展するのである。
もともと,宋代は中国文明の大きい再編期に当たる。仏教も,そのうちに含まれる。南宋の朱熹(子)に集大成される新儒教と禅の運動のあいだには,共通する発想がはなはだ多い。新道教についても,事情は同じである。かつて初期の道教の形成と対決し,相互に融合することによって,この風土に定着した仏教は,今やこの国固有の儒教と融合し,新しい総合に成功するのであり,成果は宋代より明代の陽明学におよんで深まる。いわゆる三教一致論が,それである。儒家はそろって仏教を排撃し,儒家の優位を説くけれども,仏教は三教一致をもって,これに答えた。仏教を内学,儒教を外学とする思考は,すでに六朝に始まる。宋の士大夫たちは,公的には仏教を異端とし,無用として排除しつつ,個人や家庭の立場では,つねに仏教による修養と先祖の追薦を怠らず,有縁の禅僧を迎えて,経典や語録の学習につとめた。
宋以後の近世仏教は,従来の宗派や教学のように,出家のものというより一般社会の各層に進出して,人々の日常生活を導く職業倫理となる。花祭や盂蘭盆会(うらぼんえ),冬至冬夜の儀式など,年中行事と化した仏教儀礼が多い。日本では,春秋の彼岸会(ひがんえ)がこれに加わる。それらは単に宗派の教義や,信仰の問題にとどまらぬ。一般社会の風俗となって,人々の心の底に沈潜する。いわゆる禅文化の創造は,中国より日本で顕著だが,そうした端緒はすでに近世中国にあった。
明代以後の中国仏教は,必ずしも禅に限らない。事実上の仏教の担い手は,出家比丘よりも居士の手に移る。彼らは,むしろ積極的に旧教学の学習にはげむ。華厳や天台,唯識法相の学問を再編し,近代の開幕に参加する。そして出家比丘も,同じ傾向をとる。明代の四大高僧とよばれる雲棲袾宏(うんせいしゆこう),紫柏真可(しはくしんか),憨山徳清(かんざんとくせい),藕益智旭(ぐうえきちきよく)らが,広く各派の教学を起こして,高い研究成果を収めるのは,居士仏教の展開と同時である。いずれも広く近世社会の苦悩に対決しつつ,あるいは新しく知られるキリスト教に学んで,僧俗一貫の結社を起こし,あるいは《大蔵経》の開版をすすめて,学問研究の気運を起こすなど,幅広い社会活動が知られる。進んで社会改革に身を投じ,獄死するものもある。近代思惟の先駆とされる李卓吾が,深く仏教学の研究に沈潜するのも,そんな時代のことである。康有為,譚嗣同(たんしどう),梁啓超,章炳麟(しようへいりん)(太炎)など,清朝末期の革命思想家たちにも,仏教学の成果がある。
注目してよいのは,彼らの戒律思想である。中国仏教の戒律は,つねに利他的,献身的思考で一貫される。もともと,戒律は出家と在家を結ぶ僧伽の規則である。仏教の行われるところ,一方に出家あり,これを支える在家の教団がある。出家の規則は,古代より現代まで,さらに地域によって変わることがないが,僧伽の観念には振幅がある。国家単位で仏教を受容している東南アジア諸国と,中国の場合は事情が異なる。中国では,かつて仏教を国教とすることがなかった。むしろ,外国の宗教として,異端視するのが一般である。仏教が中国民族の共感を得たのは,個々の出家比丘の厳しい持戒の精神と,対他的寛容の態度による。人間の本性を善とし,相互の善意を信ずる思考は,儒教にもっとも顕著であるが,中国では仏教もまたこれに同化する。インド仏教の一切皆苦や,日本仏教の罪業意識に比して,中国の仏教ははなはだ楽天的である。
《涅槃経》が教える,一切衆生悉有仏性の説を,人々は草木や無生物にまで拡大した(草木国土悉皆成仏)。この国独自の,天人一貫,万物一体の共感である。戒律もまた,人々の善意にもとづいて,インド仏教のもつ否定的禁止的性格を改め,本有無作の哲学に変わる。仏性が,新しい戒律の根拠となる。仏教はこの国に来て,大乗菩薩戒を生むのである。先にいうように,僧伽は僧俗和合の意であるが,中国語の僧は,むしろ個々の出家を指すこととなる。僧は,比丘や沙門と同義に使われる。戒律もまた,個人の自覚が中心となる。後漢の襄楷が,桓帝に呈した上書のうちに,仏や沙門の清潔をたたえるのは,そんな仏教に対する中国民族の期待をあらわす。すでに知られていたはずの,多くの大小乗経典のうちから,襄楷は《四十二章経》の数章を選ぶのである。後に,自利と利他,他力と自力の思考が教相の問題になるのも,同じ事情による。
要するに,中国仏教は,教団の戒律よりも個人の自覚を先とした。自律自戒を尊ぶゆえに,それは一種の倫理宗教となる。大乗菩薩戒の運動は,日本に来てさらに徹底し,最澄による小乗戒の廃除と,大乗戒壇の独立を見る。日本仏教は,大乗戒に統一されるが,中国では大小乗の二つの戒律を平行して保持し,その融合をはかることに特色をもつ。くりかえし国家権力による弾圧と廃仏令をうけつつ,仏教は個人の倫理道徳として,その真理性を深めた。前後2000年,すでに完全な世界であった中国は,仏教によって近代を迎える。とくに,唐代以後の禅仏教は,小乗の戒律が禁じた生産労働を,みずからの修行として肯定する。僧がみずから労働すれば,僧俗の区別が消えて,新しい職業倫理を導くこととなる。清朝末期より中華人民共和国の誕生まで,廟産興学とよばれる新しい廃仏運動下にあって,仏教が今日に生きのびたのは,寺院の外に出た居士仏教と,出家僧の自活の力である。社会主義体制下にある現代中国でも,仏教は対外友好の重要な契機となっている。
中国,朝鮮,日本の仏教は《漢訳大蔵経》に基づいている点では共通しているが,教理や儀礼,教団組織についてはそれぞれ異なり,朝鮮半島に伝来した仏教は,中国とも日本とも異なった独自な仏教を創造した。
朝鮮における仏教の受容は,《三国史記》によると,372年(小獣林王2)に高句麗に伝来したのが最初である。秦王苻堅が使いを派遣し,経文とともに順道が来,次いで374年には阿道が来ている。翌年の春2月,順道に省門寺,阿道に伊弗蘭寺を建てたのが海東(朝鮮の異称)仏法の始めであるという。百済については,384年(枕流王1)7月,東晋に遣使朝貢し,さらに9月にはインド僧摩羅難陀(まらなんだ)が晋より来朝したので,宮中に迎えて礼敬したのが百済仏教の始めである。新羅については,第19代訥祇(とつぎ)王(417-458)のときに沙門墨胡子が高句麗から新羅の一善郡に仏教を伝えた。また,百済からは6世紀前半の聖王代に日本に仏教が伝えられ,百済の観勒,高句麗の慧慈,慧灌など,来日した学僧も少なくない。
新羅では6世紀の法興王・真興王が奉仏天子であったために仏教は盛んとなり,皇竜寺,芬皇(ふんこう)寺,浮石寺,仏国寺など多くの寺院が建立された。新羅仏教の極盛期は半島が統一された文武王から恵恭王にいたる,670年代から約100年余りの間である。この時期の仏教界を代表するのが元暁と義湘であった。元暁は和諍(わじよう)思想を説き,義湘は華厳十刹を創建した。この華厳をはじめ律(慈蔵),涅槃,法性,法相の五教のほか浄土教や密教も行われたが,8世紀以後になると,中国の禅宗が新羅人によって伝えられ禅門九山が成立し,高麗時代に盛行するに至った。
高麗の太祖王建は崇仏の念あつく,護国鎮護の法として仏教を保護し,多くの寺院を建立し,無遮大会や八関会(はちかんえ),燃灯会などを行ったため,仏教は社会全体に深く浸透した。寺院は広大な寺田をもち,多数の僧侶をかかえていたが,高麗末期には辛 (しんとん)のように国政を壟断(ろうだん)する僧も現れた。高麗仏教で最も有名なのは文宗の第4子である義天(大覚国師)である。入宋した義天は天台学を高麗に伝え,《新編諸宗教蔵総録》という経典目録を作った。また,この時代には朝鮮仏教の重要史料である《海東高僧伝》が著されている。李朝になると朱子学を国教としたため排仏運動が盛んとなり,仏教は弾圧の中にかろうじて命脈を保つに至った。とくに15世紀末の燕山君によって寺院は廃棄され,寺田は没収,僧侶は還俗されるにおよんで,僧侶の社会的地位は八賤の一つに低下した。
(しんとん)のように国政を壟断(ろうだん)する僧も現れた。高麗仏教で最も有名なのは文宗の第4子である義天(大覚国師)である。入宋した義天は天台学を高麗に伝え,《新編諸宗教蔵総録》という経典目録を作った。また,この時代には朝鮮仏教の重要史料である《海東高僧伝》が著されている。李朝になると朱子学を国教としたため排仏運動が盛んとなり,仏教は弾圧の中にかろうじて命脈を保つに至った。とくに15世紀末の燕山君によって寺院は廃棄され,寺田は没収,僧侶は還俗されるにおよんで,僧侶の社会的地位は八賤の一つに低下した。
朝鮮仏教の最も大きな特質は,新羅以来,護国仏教の伝統が存在することである。その精神を端的に表すのは新羅の円光の〈世俗五戒〉である。五戒とは〈一に曰く,君に事(つか)うるに忠を以てす。二に曰く,親に事うるに孝を以てす。三に曰く,友に交わるに信を以てす。四に曰く,戦に臨みて退くこと無し。五に曰く,殺生に択むあり〉である。臨戦無退と殺生有択を教えた世俗五戒は護国仏教のイデオロギーとなり,弥勒信仰とともに花郎道の精神的基盤となった。この伝統は高麗時代になって《高麗大蔵経》の彫造となって現れた。契丹や元が侵入したとき,敵国撃退の悲願をこめてつくられたのが世界的な文化財として現在,海印寺蔵経閣に保存されている《高麗大蔵経》である。新羅,高麗と受け継がれてきた朝鮮護国仏教の伝統は,李朝においてもいかんなく発揮された。1592年の壬辰の倭乱(文禄の役)に際して西山大師(休静)と泗溟(しめい)大師(惟政)は,義僧を率いて蜂起し戦闘に参加した。これらにみられるように護国仏教が朝鮮仏教を貫く特質の一つである。
朝鮮仏教の教理的な特質としては,その総合性にある。たとえば新羅の元暁は中国仏教とは異なった独自な無礙(むげ)の哲学を創造し,新羅という国家と朝鮮民族の枠をこえた普遍的な思想を形成した。また新羅の義湘や,高麗の均如は朝鮮独自な華厳教学を樹立した。さらに高麗の知訥(ちとつ)の教禅一致思想は,朝鮮禅の伝統を確立させた。朝鮮仏教の修行においては禅と念仏とを双修したが,これも日本仏教とは大いに異なっている。
朝鮮仏教の伽藍配置のなかで,中国や日本の寺院とまったく異なった建造物は,山神閣(山霊閣),七星閣,冥府殿である。山神や道教の七星をまつっているところに,仏教と民間信仰,仏教と道教との習合がみられるが,これも朝鮮仏教の著しい特色である。
日本の植民地支配のもとでは朝鮮総督府の寺刹令(1911)により,禅・教両宗を総合して本山31,末寺1200余が置かれた。1919年の三・一独立運動の際には仏教界を代表して韓竜雲らが独立宣言書に署名している。45年,第2次世界大戦が終結し,大韓民国が独立してから,韓国の仏教は日本の仏教の支配と影響とを否定して,再び復興へと向かった。その第一歩は妻帯僧の追放であった。62年,宗団の革新を意図して大韓仏教曹渓宗が成立した。また妻帯僧を主とする太古宗が分立した。そのほか新興仏教としての円仏教が大きな社会的基盤を獲得した。現在,仏教系の諸宗としては,真覚宗,元暁宗など多くの小宗派がある。最大の宗派である大韓仏教曹渓宗は24の本山を有し,東国大学校をはじめとして多くの高校,中学を設立している。なお,朝鮮民主主義人民共和国の仏教については情報が少なく,その状況を把握することは困難であるが,おそらく中国革命のときに寺院の破壊と僧侶の追放が行われたのと同じような状況があったと思われる。しかし由緒ある寺院は文化財として保護修復されているものと推定される。
仏教は一部の渡来人系の子孫のなかではすでに6世紀の初めに信奉されていたと考えられるが,公式の伝来は百済の聖明王が釈迦仏像と経典その他を朝廷に献上したときとされる。この仏教公伝の年について538年説と552年説があるが,今日では《上宮(じようぐう)聖徳法王帝説》や《元興(がんごう)寺伽藍流記資財帳》により前者の538年(宣化3)を公伝の年と考える学者が多い。公伝当初,蘇我稲目(いなめ)は崇仏を,物部尾輿(もののべのおこし)は排仏を,天皇は中立の立場をとったといわれるが,仏教はいくたびかの迫害をうけながらも,蘇我氏を中心に渡来系氏族が多く居住していた飛鳥の地に最初に根づいた。そして,587年(用明2)の排仏派の物部守屋(もりや)滅亡を契機に,用明朝つづく摂政聖徳太子の推古朝に,仏法興隆の道がひらけた。この時期の仏教の中心は飛鳥と斑鳩(いかるが)だった。飛鳥では6世紀末,蘇我馬子が百済系の技術を取り入れて日本最古の伽藍とされる法興寺(飛鳥寺)を建立し,そののち当寺はこの地域の仏教の中心として栄えた。蘇我氏とともに仏教興隆に尽くした聖徳太子の事績も大きい。太子は仏教に深く帰依し,法華・勝鬘(しようまん)・維摩(ゆいま)の三経の注釈書,いわゆる《三経義疏(ぎしよ)》を著した。594年(推古2)有名な三宝興隆の詔が出され,これを契機に臣(おみ)・連(むらじ)などの豪族が競って寺を建て,またその第2条に〈篤(あつ)く三宝を敬え〉の有名な文言がある十七条憲法は今日偽撰説が主張されるが,それでも太子の政治思想が,仏教を根幹に置いて,その普遍的な教理思想のなかで国家統一を志向したことは確かであろう。太子は605年(推古13)斑鳩に移り,この地が飛鳥とならんで当代仏教の中心となった。斑鳩には前後三つの法隆寺が存在したと考えられる。在地豪族の膳(かしわで)氏が建立した第1次の寺,太子が建てた第2次の若草伽藍,そしてその再建の第3次の寺である。こうして推古朝期,中央豪族の私寺建立が多くなった。この時代の建立と確認される寺址は,今日,奈良県21,大阪府6,京都府4,兵庫県1,岡山県1の計33ヵ寺に達している。これら推古朝期までの寺院は,正確にはすべて豪族の私寺である。推古天皇はその在位中,みずから寺を建てることも,宮廷内で仏事法会を営むこともなく,天皇自身は異国の神である仏教に対して天皇家伝統の傍観的態度で終始した。
天皇が建立した日本最初の寺院は,舒明天皇が639年(舒明11)に建立した百済大寺である。舒明天皇の2人の皇子,天智・天武両帝も仏教を積極的に受容した。天智天皇は飛鳥の川原寺と大津の崇福寺を建て,天武天皇は諸国の家ごとに仏舎を作り仏像と経典を置くことを命じ,また父舒明天皇が建立した百済大寺の後身として飛鳥京に高市大寺(たけちのおおでら)を造営した。この寺はのちに大官大寺(だいかんだいじ)と呼ばれて,東大寺ができるまで,官寺第1位を占めた。さらに天武朝期,難波の荒陵寺が四天王寺と改称され,また皇后の病気平癒を祈って薬師寺の建立を発願し,これが次の文武朝に完成し,この天皇代に大官大寺,川原寺,薬師寺,法興寺が飛鳥四大寺に指定され,ここで仏教的な国家行事が行われた。こうして舒明,天智,天武,文武に至る時期に,仏教は氏族受容の段階から宮廷受容のものとなり,天皇が帰依する国家仏教の道を歩みだした。舒明・天智・天武の陵墓が八角墳であることは,仏の世界の象徴である 華往生の思想と関連するものと考えられる。白鳳時代の寺院数は,今日520余を数え,分布は関東から北九州に及び,仏教の急速な地方伝播が,律令体制の全国的拡張と照応することを示している。
華往生の思想と関連するものと考えられる。白鳳時代の寺院数は,今日520余を数え,分布は関東から北九州に及び,仏教の急速な地方伝播が,律令体制の全国的拡張と照応することを示している。
奈良時代の仏教は国家仏教の性格をますます強めた。官寺を中心に,そこでは学問のほか,国家鎮護の祈禱が盛んに行われた。それを象徴するものが,聖武天皇による741年(天平13)の国分寺造営の詔と,743年の大仏造営発願の詔だった。相続く政局の動揺で衝撃をうけた聖武の朝廷が,仏教による国家の平安と繁栄を祈る試みだった。国分寺は国ごとに僧寺と尼寺から成り,僧寺の塔には読誦すると四天王がその国土を擁護すると説かれた護国の経典《金光明最勝王経》が安置され,尼寺では国土の災害を除去し,女性成仏と庶民の滅罪のための経典《法華経》が読誦され,国家が抱いた官寺仏教への期待がどこにあったか雄弁に語っている。南都仏教はどの時代よりも経典を重視し,ために写経が盛行した。国家や寺や貴族が写経所を経営し,そこで多くの写経生が一切経や特殊な願経を書写した。このことは正倉院文書や現存する優れた写経の現物で知ることができる。中国で形成された俱舎(くしや)・三論・成実(じようじつ)・法相(ほつそう)・華厳・律の六つの宗派,いわゆる南都六宗が留学僧などによって,この時代に奈良の寺院に伝えられた。奈良の都に多くの大寺が建立されたのも,この時代の特色だった。大官大寺(大安寺と改称),法興寺(元興寺と改称),薬師寺が移建され,また新しく東大寺,西大寺,法華寺,新薬師寺,唐招提寺などの大寺が建立された。仏教伝来当初から奈良時代までに国家や氏族が建てたこれらの大寺は,当初から七堂伽藍を擁し,伽藍のなかでは釈迦の遺骨である舎利(しやり)を安置した塔が中心となった。金堂(こんどう)では現世安穏と後世善処を祈る法会が行われ,講堂では僧尼が勉学し,諸堂の朱塗の柱,瓦葺きの雄大な屋根,金色の塔の九輪,堂内に安置された金色さん然たる異形の仏像,壁面に描かれた仏国土の絵など,当時の仏寺はさながら天皇や豪族の権勢と富を示す大陸文化の坩堝(るつぼ)だった。こうして,官大寺に存在する仏教は,一般民衆の信仰とはかけはなれた存在だった。これにかわって,国家仏教からはずれた立場にあった行基や道昭や万福,それに官寺の外縁にあった私度僧らが,民衆へ仏教信仰をひろめた。これに山林修行などで術力をつけた私度僧らも,山から降りて民衆社会で現世利益(げんぜりやく)の霊験をあらわし,あるいは村堂を建て,造仏や写経,放生や架橋など知識活動を展開して在家仏教信者を増やしたことが,《日本霊異記》などの説話文学で知られ,この時代の仏教の底辺を知ることができる。
行き詰まった律令政治の刷新をめざした794年(延暦13)の桓武天皇の平安遷都は,その裏面に奈良の仏教の官大寺経営に費やされる膨大な国費,増大する寺領荘園,加えて教団の腐敗堕落,僧綱制度の欠点などを改革しようとする意図を秘めていた。果たして,従来遷都とともに行われた大寺移建の慣例は放棄された。ここに新しい平安仏教が出現する契機があった。桓武朝の末年,入唐求法(につとうぐほう)して持ち帰った最澄の天台宗,空海の真言宗がこれである。だが,南都仏教も平安仏教も,前者は〈鎮護国家〉,後者は〈護国仏教〉を標榜し,目的語句こそ異なったが,ともに古代国家の隆盛期に形成された仏教として,所詮は国家仏教の性格を共通してもっていた。だが,それでも,両者の間に政治とのかかわり方で大きな隔りがあった。南都仏教は平城京という都城に存在し,僧侶はつねに中央政界に進出するいわば都市の仏教だった。だが平安仏教では,天台宗は比叡山,真言宗は高雄の神護寺や高野山など,主要寺院が山岳に営まれた。この都市仏教から山林仏教への変化は,政治に従属する仏教から,政治に一定の距離を置いてそこに政治から不可侵独立の〈聖域〉を築き,国家を護持しようとする平安仏教の政治に対する新しい姿勢を語るものだった。こうして,〈王法と仏法は車の両輪のごとし〉という,王法・仏法の対等相依の理論が平安仏教の段階で初めて唱えられ,新時代の国家仏教の理念となった。円禅戒密の四種相承を果たして帰朝した最澄の大戒独立の運動は,仏教教理でみると戒律における大乗・小乗の優劣論にすぎないが,歴史的にみると国家権力に緊縛された南都の僧戒を,仏教側の自主的管理に取り戻そうとする僧戒自立の運動だった。この比叡山大乗戒の独立は,最澄の没後7日目に勅許され,日本天台宗の名実ともの独立がなしとげられた。長安の青竜寺の恵果(けいか)から純粋密教の秘法をうけて帰朝した空海は,嵯峨天皇に重用され,816年(弘仁7)高野山を開創,823年(弘仁14)東寺を給付され,真言宗の拠点を確保した。仏果を得ることは文字や学解によるのではなく,字(真言)・印(印相)・形(曼陀羅)などで表現され,如来の言葉である真言陀羅尼を念誦し,観修することで即身成仏できると説く空海の教えは,彼の南都諸宗に対する妥協的態度や加持祈禱の容認と相まって,貴族や地方の豪族や民衆のなかに急速にひろまった。法相宗学を主流とした南都仏教が,成仏の可否は人間の素質によるという〈五性各別〉を説いたのに対して,天台・真言の平安仏教は〈一切皆成〉,すなわち素質や能力に関係なく,すべての人間が成仏できるとの一乗主義を説き,これも平安仏教の新しい特色だった。こうして,平安時代,化外の地域とされた東北地方まで天台・真言の僧が布教の足跡をのばし,仏教はほぼ日本全域にひろまった。天台宗は最澄のあとの円仁・円珍のころ,密教(台密)が教学の中心となり,東密(真言密教)とともに,平安貴族の厚い帰依と保護をうけた。
寺院造営や法会や加持祈禱が宮廷貴族社会に盛行し,貴族出身の僧侶が大寺の住持を独占するようになり,平安仏教もしだいに貴族仏教となった。諸大寺は貴族から寄進された荘園をもつ大領主となり,僧兵という武力をもち,権門と呼ばれて栄えた。だが,平安中期以降,末法思想が飢饉・疫病・地震・洪水などの当時の災害現象と相まって人心を強くとらえるようになると,阿弥陀浄土信仰(阿弥陀)が盛んになった。念仏によって極楽往生を願うこの信仰は,市聖(いちのひじり)と呼ばれた空也,《往生要集》を著した源信,融通念仏宗を開いた良忍らによって急速に古代末期の社会に浸透していった。
仏教が真の意味で民衆の宗教として確立したのは鎌倉時代だった。いわゆる鎌倉新仏教の成立である。念仏門の系統から,まず法然(源空)が日本浄土宗を開いた。法然は主著《選択(せんちやく)本願念仏集》を著し,富と知識を独占する貴族しかできない造寺・造仏・学解・持戒などの意義を退け,往生の要諦は阿弥陀-仏を信じて,念仏だけを唱えること(一向専修)で,これにより人びとは貴賤・男女の差別なく在家の生活のまま往生できると説いた。これまでのように観想の阿弥陀仏礼拝も,浄土三部経の読誦も不要であり,称名念仏だけが〈正定業(しようじようごう)〉であるという点で,阿弥陀信仰はより易行(いぎよう)となり,在家民衆の生活のなかに定着する条件をそなえた。法然の教えをさらに徹底化したのが,浄土真宗(真宗)を開いたその弟子親鸞である。師の法然がおもに京都で活躍したのに対し,親鸞は晩年こそ京都に帰ったが,越後に流されたあと妻帯し,そののち関東に移り,東国辺地の農民や下級武士に法を説いた。彼は往生の当否は称名よりも,阿弥陀仏への絶対的な信心にあるとし(信心為本),しかも《歎異抄(たんにしよう)》のなかで〈善人なをもて往生をとぐいはんや悪人をや,しかるに世のひとつねにいはく,悪人なを往生す,いかにいはんや善人をや〉,阿弥陀仏の〈願をおこしたまふ本意,悪人成仏のためならば,他力をたのみたてまつる悪人,もともと往生の正因なり〉と,絶対他力と悪人正機の説を述べた。法然・親鸞におくれて元寇のころ,念仏門に新境地を開いたのが,時宗の宗祖一遍である。一遍は,念仏往生の鍵は信心の有無,浄や不浄,貴賤や男女に関係するのではなく,すべてを放下(ほか)し,〈空〉の心境になって,名号(みようごう)(念仏)と一体に結縁(けちえん)することにあると説いた。一遍は生涯を廻国遊行(ゆぎよう)の旅に過ごし,念仏に結縁した人びとに往生決定の証明として念仏を書いた紙の札を与え(賦算(ふさん)),彼らに阿弥号をつけた。時衆に〈某阿弥陀仏〉と称する人が多いのはこのためである。彼らは賦算と阿弥号をうけ,生きながら阿弥陀仏と一体となると信じた。一遍が遊行し賦算するところ,歓喜の踊(念仏踊)の輪がひろがり,これが時宗の特色となった。一遍と同じころ,東国で日 が日
が日 宗を開いた。日
宗を開いた。日 は《法華経》だけを唯一の正法と認め,この《法華経》の眼目が〈南無妙法
は《法華経》だけを唯一の正法と認め,この《法華経》の眼目が〈南無妙法 華経〉の題目であるとし,《法華経》への唯一絶対の信心をもとに,専持法華と唱題だけで,すべての人びとが差別なく成仏できると説いた。しかも日
華経〉の題目であるとし,《法華経》への唯一絶対の信心をもとに,専持法華と唱題だけで,すべての人びとが差別なく成仏できると説いた。しかも日 は,彼岸での救済よりも,主著《立正安国論》で明示したように,正しい仏法が興隆すれば国土の災害除去は可能であると,現実国土の世なおしや現世での救済を重視し,この教説における強靱な現世性がこの宗派の特色となった。
は,彼岸での救済よりも,主著《立正安国論》で明示したように,正しい仏法が興隆すれば国土の災害除去は可能であると,現実国土の世なおしや現世での救済を重視し,この教説における強靱な現世性がこの宗派の特色となった。
以上述べたように,浄土宗・浄土真宗・時宗・日 宗は,それぞれ教説に特色をもつが,その反面でいくつかの共通点ももっていた。一つは諸経や諸仏や諸行のなかで,4宗とも一つの経,一つの仏を選びとって,余仏・余経・雑行を徹底的に排し,念仏や題目を専修することを主張する,いわば〈一筋の信仰〉だった。二つには4宗とも貴賤・男女・貧富の差別なく,殺生を業とする悪人さえ往生や成仏を認める徹底した民衆宗教だった。三つには,したがって奈良・平安の貴族仏教が重視した戒律の意義を認めず,民衆の日常生活のなかで信仰が維持できるよう,易行にして,在家成仏の仏教だった。四つにはこれら4宗の寺には,旧仏教や禅宗の大寺のように,創建当初から朝廷や幕府の官寺や祈禱所として七堂伽藍を整備し,寺領寄進をうけて出発した寺はなかった。浄土宗の知恩院,真宗の本願寺や専修(せんじゆ)寺,日
宗は,それぞれ教説に特色をもつが,その反面でいくつかの共通点ももっていた。一つは諸経や諸仏や諸行のなかで,4宗とも一つの経,一つの仏を選びとって,余仏・余経・雑行を徹底的に排し,念仏や題目を専修することを主張する,いわば〈一筋の信仰〉だった。二つには4宗とも貴賤・男女・貧富の差別なく,殺生を業とする悪人さえ往生や成仏を認める徹底した民衆宗教だった。三つには,したがって奈良・平安の貴族仏教が重視した戒律の意義を認めず,民衆の日常生活のなかで信仰が維持できるよう,易行にして,在家成仏の仏教だった。四つにはこれら4宗の寺には,旧仏教や禅宗の大寺のように,創建当初から朝廷や幕府の官寺や祈禱所として七堂伽藍を整備し,寺領寄進をうけて出発した寺はなかった。浄土宗の知恩院,真宗の本願寺や専修(せんじゆ)寺,日 宗の久遠(くおん)寺など,いずれも武士や民衆に支えられて草庵から出発した寺院である。五つには,旧仏教や禅宗が宗祖によって中国から将来された仏教だったのに対し,これら4宗の宗祖,法然・親鸞・一遍・日
宗の久遠(くおん)寺など,いずれも武士や民衆に支えられて草庵から出発した寺院である。五つには,旧仏教や禅宗が宗祖によって中国から将来された仏教だったのに対し,これら4宗の宗祖,法然・親鸞・一遍・日 は入唐求法の意志もまたその経験もなく,経典や聖教を模索して教説の体系を形成した歴史をもち,この意味では鎌倉時代の日本がその社会のなかで育て上げた日本仏教ともいうべき宗教だった。
は入唐求法の意志もまたその経験もなく,経典や聖教を模索して教説の体系を形成した歴史をもち,この意味では鎌倉時代の日本がその社会のなかで育て上げた日本仏教ともいうべき宗教だった。
鎌倉新仏教のうち,残る禅宗は宋からもたらされた。臨済禅は1191年(建久2)帰国した栄西が,曹洞禅は1227年(安貞1)道元が伝えた。本来の禅は来世の概念がなく,不立文字(ふりゆうもんじ)を旨とし,坐禅や公案(こうあん)を中心として自力による悟りを自己の心中に形成することを目的とした。この気骨ある教義と,禅のもつ郁々とした中国文化の香りが,新しい時代の担い手として台頭する武家,それに一部の公家の気風に合致し,当代仏教界に禅宗は新風を吹きこんだ。臨済宗は幕府の保護をうけ鎌倉や京都に唐様建築による大寺院を建立し,蘭渓道隆,無学祖元,一山一寧など宋元の中国禅僧を迎え,次の室町時代に五山禅・五山文学の隆盛を築いた。曹洞宗は道元が中央権勢に接近して名利を得ることを拒んだので,彼が拠点とした越前の永平寺を中心に,鎌倉・室町時代,おもに地方武士層に教線をのばした。こうした新仏教諸宗の活躍に対して,旧仏教側にも新しい改革の運動が興った。禅宗を除く新仏教諸宗が戒律を軽視もしくは無視したことに対して,法相宗の貞慶(解脱)や華厳宗の高弁(明恵(みようえ)),律宗の叡尊(興正)・忍性(良観)・俊芿(しゆんじよう)らが,戒律の復興や施薬・土木建設などの社会事業をすすめた。また従来の外護者だった宮廷貴族層の衰退に伴って,旧仏教系の諸寺では,古い由緒や秘蔵する仏像の霊験をあらためて世間に喧伝し,観音・阿弥陀・地蔵など諸仏の霊場として,台頭する武士や庶民の信仰を集め,民衆仏教に再生脱皮しようとする動きが盛んとなった。
鎌倉新仏教諸宗が,全国的規模の教団に成長したのは,宗祖入滅後1世紀以上を経た室町時代のことだった。たとえば,1282年(弘安5)の日 入滅の時点で,日
入滅の時点で,日 宗は直弟・直檀を合わせても数百人,それらが散在するところも東国数ヵ国にすぎず,まだ微々たる地方宗教にすぎなかった。だが,13世紀末,日像が京都で布教を始め,15世紀に入ると,宗内の諸門流の教線は北は東北地方,西は南西諸島にまでひろがり,しかも中央京都の町衆社会ではその半分が日
宗は直弟・直檀を合わせても数百人,それらが散在するところも東国数ヵ国にすぎず,まだ微々たる地方宗教にすぎなかった。だが,13世紀末,日像が京都で布教を始め,15世紀に入ると,宗内の諸門流の教線は北は東北地方,西は南西諸島にまでひろがり,しかも中央京都の町衆社会ではその半分が日 宗信者といわれるほど確固たる地位を築き,全国的な教団に成長した。折伏(しやくぶく)の布教で知られる日親が活躍したのはこの世紀のことであり,また次の16世紀前半,京都では町衆信徒による法華一揆が史上に光彩を放った。浄土宗は法然の滅後,分派して発展したが,なお中世には純粋な浄土宗寺院の成立は少なかった。専修念仏者の集団は他宗寺院内に止住し,浄土宗の大勢は〈寓宗(ぐうしゆう)〉として推移したが,それでも室町後期,弁長のひらいた鎮西派が宗内外で雄飛し,知恩院を中心に独立した全国的教団に成長した。真宗では15世紀,本願寺に
宗信者といわれるほど確固たる地位を築き,全国的な教団に成長した。折伏(しやくぶく)の布教で知られる日親が活躍したのはこの世紀のことであり,また次の16世紀前半,京都では町衆信徒による法華一揆が史上に光彩を放った。浄土宗は法然の滅後,分派して発展したが,なお中世には純粋な浄土宗寺院の成立は少なかった。専修念仏者の集団は他宗寺院内に止住し,浄土宗の大勢は〈寓宗(ぐうしゆう)〉として推移したが,それでも室町後期,弁長のひらいた鎮西派が宗内外で雄飛し,知恩院を中心に独立した全国的教団に成長した。真宗では15世紀,本願寺に 如が出て,東海・北陸・東山・畿内の諸国を精力的に巡錫し,宗勢を飛躍させるとともに,真宗内部において仏光寺・専修寺を抜いた巨大な本願寺勢力を築き上げた。
如が出て,東海・北陸・東山・畿内の諸国を精力的に巡錫し,宗勢を飛躍させるとともに,真宗内部において仏光寺・専修寺を抜いた巨大な本願寺勢力を築き上げた。 如の膨大な消息と著述は〈御文(おふみ)〉とか〈御文章〉(《
如の膨大な消息と著述は〈御文(おふみ)〉とか〈御文章〉(《 如仮名法語》)と呼ばれ,宗祖親鸞の著述よりも,長らく門徒に大きな影響を与えた。本願寺は
如仮名法語》)と呼ばれ,宗祖親鸞の著述よりも,長らく門徒に大きな影響を与えた。本願寺は 如の代に法主制を確立し,寺基も洛東の大谷から山科(やましな)に移ったが,この城廓構えの山科本願寺は1536年(天文5)法華一揆に焼討ちされ,ために孫の証如は本願寺を大坂石山へ移した。16世紀に畿内・東海・北陸に蜂起した一向一揆は,本願寺法主を頂点とした門徒支配の郷村か,戦国大名が支配する郷村かを決する戦国群雄と本願寺門徒の血みどろの戦いであり,この決戦に最終的に勝利して登場したのが信長・秀吉の近世統一政権であった。遊行上人と呼ばれた一遍の時宗は,宗祖の代には止住すべき草庵さえもたなかったが,室町時代になると時宗寺院が諸国に建立され,とりわけ京都に大きな基盤をもった。特殊な技能をもって室町将軍に近侍した同朋衆などのなかに,時宗の阿弥号をもつ人が多く,東山文化に果たした阿弥集団の芸術活動の役割には注目すべきものがある。
如の代に法主制を確立し,寺基も洛東の大谷から山科(やましな)に移ったが,この城廓構えの山科本願寺は1536年(天文5)法華一揆に焼討ちされ,ために孫の証如は本願寺を大坂石山へ移した。16世紀に畿内・東海・北陸に蜂起した一向一揆は,本願寺法主を頂点とした門徒支配の郷村か,戦国大名が支配する郷村かを決する戦国群雄と本願寺門徒の血みどろの戦いであり,この決戦に最終的に勝利して登場したのが信長・秀吉の近世統一政権であった。遊行上人と呼ばれた一遍の時宗は,宗祖の代には止住すべき草庵さえもたなかったが,室町時代になると時宗寺院が諸国に建立され,とりわけ京都に大きな基盤をもった。特殊な技能をもって室町将軍に近侍した同朋衆などのなかに,時宗の阿弥号をもつ人が多く,東山文化に果たした阿弥集団の芸術活動の役割には注目すべきものがある。
一方,室町前期の中央政界では臨済宗五山派が全盛をきわめた。幕府は京都・鎌倉五山以下,十刹・諸山(五山・十刹・諸山)の寺格を指定し,これら五山派の禅寺を官寺として保護した。五山派寺院の住持任命は将軍が行い,寺領を寄せ,伽藍維持を援助し,かわって幕府は寺から莫大な礼銭を取り,五山派の禅寺は幕府の大きな財源となっていた。将軍にならって守護大名の多くも五山派禅寺を領国に建立経営し,五山禅に帰依した。こうして室町前期,五山禅は黄金期を迎え,名僧が輩出したが,五山禅僧は名利に接近し,内部では坐禅よりも詩文の教養が貴ばれ,ここに五山文学の隆盛をみた。だが,五山禅は幕府の衰退とともに室町後期にはしだいに衰え,かわって林下(りんか)の禅が台頭した。宗峰妙超が開いた大徳寺,関山慧玄が創建した妙心寺,それに道元が伝えた曹洞の禅がこれである。林下の禅は中央の権勢におもねることなく在野の禅を標榜し,詩文よりも禅家本来の坐禅を守り,地方武士や庶民社会にその支持者を増やした。一休宗純によって大徳寺禅が堺町衆社会に根づき,それが堺町衆の茶数寄を接点にして,戦国武将や町人茶人と大徳寺禅との結びつきが生まれ,その結びつきが契機となって,大徳寺が戦国期に雄飛することとなったのはその好例である。
近世の仏教は,同じ宗派でも,中世と大きく変わった。近世の統一政権は中世のように,政権から一定の距離を置きその不可侵性を認めた仏教の存在を許さなかったからである。近世の仏教は,完全に幕府の宗教行政の枠のなかで存在する仏教だった。そこには中世のような教説の新しい発展もなければ,宗派の組織からはみだした遁世僧・廻国聖(ひじり)などに象徴される自由闊達な旅の宗教者の姿も消えていた。新しい宗派としては,臨済の一派である黄檗(おうばく)禅が,明(みん)の僧隠元によって伝えられただけである。幕府の宗教行政にそむいて,俗権に対する教権,王法に対する仏法の不可侵自立性や独立を主張した日 宗不受不施(ふじゆふせ)派などは,容赦なく禁教された。他方で,幕府は寺領を安堵し,寺地を免租とし,さらに僧尼の課役を免除するなど,仏教と寺院に対する保護策をとった。この限りでは,近世における仏教は,過去のどの時代よりも安定した時期を迎えたということができる。
宗不受不施(ふじゆふせ)派などは,容赦なく禁教された。他方で,幕府は寺領を安堵し,寺地を免租とし,さらに僧尼の課役を免除するなど,仏教と寺院に対する保護策をとった。この限りでは,近世における仏教は,過去のどの時代よりも安定した時期を迎えたということができる。
こうして,近世仏教にはいくつかの特色が指摘できる。一つは近世の寺院本末制度の成立である。各宗本山が幕府に提出した末寺帳を台本にして,全国の寺院は本山・直末・孫末・曾孫末と分けられ,その本末関係が幕府によって公認され,変更は事実上不可能だった。これは寺院の自由な改宗や転派の不可能を意味し,本山の末寺支配をどの時代よりも強化することに役だった。逆にいうと,幕府は本山住持の任命について,その事前承認権さえ留保しておけば,全国寺院を末端まで支配できることを意味した。二つには幕府が行った人別宗門改によって,近世寺檀制度が生まれたことである。幕府は毎年,キリシタン宗門改を人別に実施し,このとき各人から寺請(てらうけ)証文を提出させた。寺請証文は檀那寺の僧が檀家各人について,当人が自分の寺の檀家であってキリシタンでないことを書いた証文である。人別の寺請による宗門改が全国に実施されたとき,近世の民衆はいや応なく檀那寺をもたねばならなかった。その檀那寺は寺院本末制で宗旨宗派が確定していたから,近世の民衆は固定した宗旨と宗派と檀那寺を生まれたときからもつことになり,この変更は結婚のとき以外,原則としてできなかった。こうして,近世の日本人はすべて先祖以来,固定した宗旨と宗派と檀那寺をもった仏教徒となった。しかも,幕府は寺請証文の提出を宗門改のときのほか,結婚・転住・奉公・検死・埋葬・旅行のときにも必要と定めたので,寺檀の関係はますます強固となり,寺を通じて幕府は民衆を支配できるようになった。このような制度を近世寺檀制度という。他面,この寺檀制度は,寺と檀家の関係をどの時代よりも強固とした。人びとは檀那寺を中心にまとまり,寺参りや先祖の年忌法会や葬礼が民衆社会のなかに定着し,郷村の寺院はその地域の農民の団結や文化活動の中心としての役割を果たすことにもなった。近世郷村の寺の僧侶は,信仰だけでなく,政治・教育・生活倫理・医術,ときには農業技術の改良の面でも村のリーダーだった。郷村の寺院に比べて中央の本山は,末寺や全国檀家からさまざまな名目の志納銭を寄せられ,大伽藍を造営し,儒者や国学者などの識者からその弊害を指摘され,また排仏論を育てる基をつくった。各宗を問わず宗学の研鑽が盛んとなり,檀林や学校などの僧侶の勉学機関が整備され,いわゆる近世宗学が勃興したのも,近世仏教の特色の一つだった。しかし,宗祖教説の研究も,幕府によって新義や異義は禁じられ,宗学の自由な発展はなかった。幕末の幕藩体制の解体期,興隆する洋学や国学のように,新時代の民衆社会の指導理念になるものを,近世の仏教はついに民衆の前に提示することはできなかった。
明治維新とともに,新政府が出した神仏分離令と神道国教化政策(神仏分離)は,仏教界に大きな打撃を与えた。法親王は還俗(げんぞく)し,宮中からいっさいの仏像や仏具は取り払われ,天皇家と仏教は完全に無縁となった。平安時代から続いた神仏習合の風習は禁止され,塔や仏像や仏具が神社から撤去され,社僧は復飾し,寺院と神社は分離した。政府は廃仏令こそ出さなかったが,明治初年,寺領の上地令,宗門改の停止に伴う寺檀制度の解体,旧来の陋習(ろうしゆう)としての祈禱禁止令などをつぎつぎと打ち出し,加えて士族階級の没落や農村人口の都市流入に伴う離檀の増加,滔々として押し寄せてくる西洋の文明開化の思想が他方にあり,仏教界は1872年から74年をピークとして,廃仏毀釈の嵐にさらされた。都市でも農村でも多くの寺院が廃寺となり,僧侶の還俗が続き,優れた仏像や仏具や仏画が狂騒の巷に消失した。この廃仏の嵐のなかで,諸宗それぞれの立場で近代社会のなかで生き抜くことができる市民仏教のあり方を模索する運動が,1871-72年ころから興ったことは注目される。いわゆる仏教近代化の運動である。東・西本願寺は,この時期,早くも宗内の青年僧を欧米に派遣し,西洋市民社会で果たすキリスト教の役割を参考に,近代仏教のあるべき姿を研鑽させた。国内では各宗とも,キリスト教の活動にも刺激されて,女子教育や宗門高等教育機関の設置に乗り出した。これが今日,いわゆる宗門系大学と呼ばれる竜谷・大谷・仏教・花園・京都女子・光華・立正・駒沢・大正大学などとなり,教育文化の発展に寄与する基礎となったのである。さらに明治末年には諸宗の海外仏教布教が行われ出し,1913年には世界仏教大会も開催された。
日露戦争から第2次大戦に至る戦争期,諸宗派の戦争への協調的態度は,戦後の仏教界に深い反省を生み,今日の仏教界では人類の平和と幸福を求め,世界仏教徒会議を開くなど,世界仏教への成長発展をめざす動きが着実に進んでいる。
東南アジアの仏教は,記録や宗教的遺構,遺物によって知られる歴史的仏教と,今日なお信奉されている現代仏教とに分けられる。
ボロブドゥールなどの遺跡を残したジャワのシャイレンドラ王朝の密教系大乗仏教は前者の代表例である。ジャワ仏教はのちにシバ教(ヒンドゥー教シバ派)と混交してジャマン・ブドと呼ばれる独特な形態の仏教を生み,マジャパイト王朝の下で繁栄したが,新来のイスラムが支配層に浸透するに従って衰微し,15世紀以後消滅した。スマトラ島では7世紀末にこの地を経てインドへ赴いた義浄が,スリウィジャヤにおける仏教の隆盛を指摘し,インドに赴いて仏法修行を志す唐僧に準備のためこの国に滞在することを勧めている。スマトラ島の仏教は14世紀後半まで碑文によってその存在を確認できるが,イスラムの到来にともなって滅亡した。
大陸部ではまず1~2世紀から7世紀ころまでインドシナ半島南東部にあった扶南(ふなん)において仏教が行われていたことが知られている。6世紀に興った真臘(しんろう)では碑文から大乗仏教の弘通が確認される。9世紀初頭に成立したアンコール帝国ではヒンドゥー教と並んで大乗仏教が行われ,バイヨンなどの優れた仏教遺構を残した。半島西部のビルマでは3世紀ころから9世紀にかけて栄えたピュー族の国シュリークシェートラで上座部とサンスクリット聖典を信奉する根本説一切有部系の小乗仏教と大乗仏教とが並び行われていた。仏教は5世紀以降タトンなどの沿海地方を中心とするモン族の諸国家においても盛んに行われた。これら各地の仏教はいずれものちに衰亡したため,今日その伝統は伝わっていない。
現代仏教は,ミャンマー,タイ,ラオス,カンボジアと,ベトナム南部,インドネシアの一部にみられるスリランカ系の上座部仏教が中心であるが,このほかベトナム,シンガポール,および東南アジア各国に住む華人によって信奉され読誦用に漢文経典を用いる中国系の大乗仏教とがある。ただ後者については,独立の宗教であると同時に,儒教,道教と併せ中国的な〈三教〉を構成するとする視点をもつことが要請される。
東南アジア各地に広まった上座部仏教(テーラバーダ)はスリランカの大寺派(マハービハーラ)の伝統を引く。それぞれの固有文字を用いているため一見異なった印象を与えるが,いずれも同じパーリ語で同一の内容を記した三蔵経を護持している。最も古いのはビルマ系上座部仏教で,国家的規模での受容が11世紀中葉に開始された。2世紀遅れて東隣のメナム(チャオプラヤー)川中流域に最初のタイ族国家スコータイが成立すると,そこにもマレー半島経由でスリランカ系の上座部が伝えられた。元の周達観の《真臘風土記》には,13世紀末までにカンボジア仏教の上座部仏教化が進行していた事実を示唆する記事がみえる。14世紀初頭にはパーリ語碑文が現れ,カンボジアにおける宗教交替の事実が明らかとなる。伝承によると,14世紀半ばこのカンボジア上座部仏教はラオスに伝えられたという。
歴史的にみると,上座部仏教はサンガすなわち出家者の教団が王権と相即不離の関係を結びつつ維持発展を続けてきた。
(1)ビルマ(現,ミャンマー) 11世紀中葉,上ビルマのパガンを中心に国家統一を行ったアノーヤター王が,下ビルマのモン族の国タトンを攻略し,そこから500人の僧とパーリ三蔵をパガンに将来したのがビルマにおける上座部仏教確立の始めとされている。その後スリランカに赴いて受戒したチャパタが大寺派の伝統をビルマに伝え,〈ムランマ・サンガ〉(タトン系),〈シーハラ・サンガ〉(スリランカ系)の両サンガが並立した。13世紀末元軍の攻撃を受けてパガン朝が滅亡し,タイ族の一派シャン族による分割統治が始まると,仏教サンガもまた分裂しながら広域に拡大していった。15世紀後半ダンマゼーディー王はスリランカから大寺派の正しい授戒作法を導入して分裂したサンガを統一した。17世紀から18世紀にかけて発生した伝統的な〈通肩派〉と革新的な〈偏袒派〉の正統をめぐる対立は,1788年ボードーパヤー王の開催した宗教会議により〈ツーダンマ〉(宗教会議派)として統一された。しかしその後イギリスによる下ビルマの植民地化の影響もあってサンガの統一が乱れると,ミンドン王は第5次結集(けつじゆう)をマンダレーに招集したが,〈シュウェジン〉〈オッポ〉の2派の参加が得られず,結局〈ツーダンマ〉,〈シュウェジン〉,〈オッポ〉(ドワーラ),〈ゲトゥイン〉の各派に分裂したまま現在に至っている。1980年,ラングーン(現,ヤンゴン)において第1回ビルマ上座部全宗派合同会議が開催され,公認9派を統括する組織が結成された。
(2)タイ 最古のタイ語資料であるラーマカムヘン王碑文(1292)は,スコータイの民衆の間に上座部仏教が深く浸透していた事実を生き生きと描写している。14世紀中葉の王リタイはタイ語による最初の仏教書《トライプーム》を著した。同書は長期にわたってタイ民衆の仏教観に影響を与え続けた。政治の中心がアユタヤに移ってからも仏教は歴代国王の庇護を受けて繁栄した。1750年にはスリランカ王の招請により,オランダの植民地支配のもとで衰微した仏教サンガを再興するため,アユタヤから仏教使節がスリランカの首都キャンディに派遣された。スリランカ最大の宗派シアム・ニカーヤはこのとき創始された。アユタヤ滅亡後の混乱がバンコク遷都によって終息すると,新王ラーマ1世は結集を行って仏教の再建を図った。4世王モンクットは即位に先立ち長らく僧侶であった時代に,厳重な持戒の復興を目ざしてタマユット運動を興した。この運動の結果,タイには在来派のマハーニカイ派と並んでタマユット派が生まれた。20世紀初頭,〈サンガ統治法〉が制定され,仏教教団の強力な国家管理体制が確立した。同法はその後2度にわたって改正されたが,国家に対するサンガの従属体制は今も変わっていない。
(3)カンボジア この国への上座部仏教の渡来経路は不明であるが,タイ族を媒介としたとする説が有力である。最古のパーリ語碑文(1308)には,国王による精舎の寄進の事実が記され,王権と仏教との関係が示されている。19世紀以降カンボジアの王族がタイで出家するようになってから,タイ仏教の影響が強まった。タマユット派は1864年カンボジアに伝えられ,トアンマユット派と呼ばれるようになった。1863年カンボジアを保護国としたフランスは,タイの影響の除去に努めた。1930年プノンペンに創設された仏教研究所は仏教界におけるタイの影響排除が一つの目的であったといわれている。カンボジアのサンガは43年に制定された勅令によって法的地位を与えられ,モハーニカイ派とトアンマユット派の2派に分かれるが,サンガ組織は75年の革命によって壊滅的打撃を受けた。
(4)ラオス 1975年に王制が廃止されるまで,上座部仏教は国王の保護の下に繁栄した。1945年以来政府によるサンガ統一が進められ,51年,59年の2度にわたりサンガ規則を定める勅令が制定された。
(5)インドネシア 1930年代以降スリランカ,ビルマ,タイの3系統の上座部仏教がインドネシアにもたらされ,主として華人系プラナカン(インドネシア生れの華僑)を中心に信奉されている。イスラムが圧倒的な同国において,仏教信者数はとくに65年以来急激に増加し,10年後には100万人をはるかに超えるに至った。インドの新仏教運動とともに,20世紀に発生した仏教への大量改宗の事例として注目される。
(6)ベトナム 前漢の武帝以来漢文化の影響下に置かれたベトナムは,仏教においてもまた圧倒的に優勢な中国仏教の影響を受けた。中国において〈三教〉がいわれるように,ベトナムの宗教もまた儒教,仏教,道教の3宗教が混じり合って一つのベトナム仏教が形成されたとみるほうが理解しやすい。歴史的にはビニータルチ,無言通,草堂,竹林各派の禅宗や禅宗に浄土念仏,密教儀礼と民間信仰を加えた 宗などが盛んに行われている。1920年代に入ると仏教革新の運動が興り,各地に仏教研究協会が設立されて,寺院の修復,仏教教育の振興が叫ばれた。54年カトリック教徒のゴ・ディン・ジェム政権が成立して仏教差別政策がとられると,ベトナム仏教は急激に政治色を強め,焼身自殺によって弾圧に抗議する僧侶も現れた。64年統一ベトナム仏教教会が結成されたが,のち国寺派とアン・コアン寺派に分裂したまま,76年の南北統一を迎えている。
宗などが盛んに行われている。1920年代に入ると仏教革新の運動が興り,各地に仏教研究協会が設立されて,寺院の修復,仏教教育の振興が叫ばれた。54年カトリック教徒のゴ・ディン・ジェム政権が成立して仏教差別政策がとられると,ベトナム仏教は急激に政治色を強め,焼身自殺によって弾圧に抗議する僧侶も現れた。64年統一ベトナム仏教教会が結成されたが,のち国寺派とアン・コアン寺派に分裂したまま,76年の南北統一を迎えている。
国民のなかに占める上座部仏教徒の割合は,ミャンマー(旧ビルマ。85%),タイ(95%),ラオス(50%),カンボジア(85%)と人口の大多数を占めている。そのため国王を仏教の守護者とする伝統を失わず今日まで独立を維持してきたタイを除き,第2次大戦後独立したこれら諸国の仏教は憲法によって国教(カンボジア,ラオス)ないし国教に準じた地位(ビルマ)を保障されてきた。このうちビルマでは1961年の憲法改正によって仏教を国教と定めたものの,その措置が非仏教徒の反発を買い政治的混乱を招いた。この経験から,社会主義共和国となって以後のビルマ政府は政教分離政策を堅持し,仏教の政治化を極度に警戒する態度をとっている。
出家者の教団であるサンガを中核とする上座部仏教は,近代化に伴う都市化の急速な進行とともに発生した民衆の価値意識の変容に新たな対応を迫られつつある。この傾向は東南アジアの上座部仏教諸国のうち近代化の進展の速いタイにおいて最も著しい。主として知識人仏教徒層を対象とする瞑想重視の宗教運動,マス・メディアを利用して大衆に平易な言葉で仏教の徳目を説く個人僧の出現,寺院の教育機関としての役割の近代的復興ともいうべき寺院での職業教育の実施などがその二,三の事例として挙げられる。
 日
日 宗 立正安国論 禅宗 栄西 道元 臨済宗 曹洞宗
宗 立正安国論 禅宗 栄西 道元 臨済宗 曹洞宗  如 本願寺 五山派 林下 本末制度 寺檀制度 寺請(てらうけ)証文 神仏分離 廃仏毀釈 宗門系大学 義浄 上座部仏教 テーラバーダ
如 本願寺 五山派 林下 本末制度 寺檀制度 寺請(てらうけ)証文 神仏分離 廃仏毀釈 宗門系大学 義浄 上座部仏教 テーラバーダ  宗
宗 
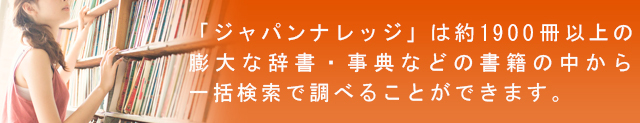
 [0] ...
[0] ... ...
...









©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.