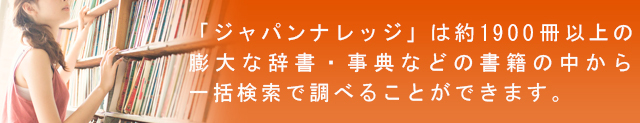幕藩制を廃し、中央集権統一国家と資本主義化との出発点を築いた政治的・社会的変革。「明治維新」という歴史学の概念ができる起源は、当時の人が用いた「御一新 (ごいっしん)」ということばにある。お上の命令によって世の中が新しくなるという意味である。
日本資本主義論争
明治維新の科学的研究が進む契機となったのは、1920年代末から30年代前半にかけて、コミンテルン(共産主義インターナショナル)が出した日本の革命戦略方針(一九二七年テーゼおよび一九三二年テーゼ)の理解をめぐって、マルクス主義学者の間に行われた論争であった。これは日本資本主義論争といわれ、論争点の一つが、明治維新の歴史的性格についてであった。山田盛太郎 (もりたろう)、平野義太郎 (よしたろう)、服部之総 (はっとりしそう)、羽仁 (はに)五郎ら(講座派とよばれた)は、明治維新はブルジョア革命ではなく、その結果として樹立された天皇制権力は、独占資本主義の段階でも、絶対主義である本質を変えてはいないと主張し、その論証を『日本資本主義発達史講座』で行った。これに対し大内兵衛 (ひょうえ)、向坂逸郎 (さきさかいつろう)、土屋喬雄 (たかお)ら(労農派とよばれた)は、明治維新は不徹底であるとはいえ、ブルジョア革命であり、天皇制権力はなし崩しにブルジョア権力に移行したと論じた。戦後の学界でも、この論争点は受け継がれ深められているが、研究の焦点は戦前と異なっている。絶対主義の形成といっても、西ヨーロッパのような15、16世紀の古典的なそれではなく、産業資本主義段階末期の世界資本主義に強く規制された19世紀なかばのそれが、明治維新の問題である。したがって、絶対主義=封建国家か、しからずんばブルジョア権力=資本主義国家かといった形式的な問題のたて方では解明できないと考えられ、両者の構造的関連が実証的に追究されている。
歴史学の画期としての明治維新が、いつからいつまでの政治過程をさすかは、明治維新の本質をどう意義づけるかとかかわり、次の諸説がある。
〔1〕始期について
(イ)天保 (てんぽう)期(1830~43)、とくに大塩平八郎 (へいはちろう)の乱(1837)、あるいは幕府の天保の改革の失敗(1843)に置く考え。この考えは、明治維新を実現させた国内的条件、すなわち階級闘争の激化、幕府の施政の決定的な失敗、幕府に反抗する政治運動の出現を重視するという立場に基づいている。
(ロ)ペリー来航(1853)または安政 (あんせい)通商条約の締結(1858)に置く考え。明治維新を生起させた原因のうちで、国際的条件を重視する見解、また日本が資本主義の世界市場の一環に組み込まれたという世界史的観点にたっての見解である。
〔2〕終期について
(イ)西南戦争(1877)に置く考え。封建復帰を目ざす士族の反政府運動がこれをもって終わり、これ以降は、統一国家建設と資本主義化の路線をめぐる明治政府と自由民権運動との対抗が政治史の基本をなす新しい段階だとみる考え方である。
(ロ)自由民権運動の激化形態であり貧農が主体である秩父 (ちちぶ)事件(1884)に置く考え方。封建社会の基本的階級対立である封建領主対封建小農民の関係が、資本主義社会の基本的階級対立である寄生地主・資本家対小作人・賃労働者の関係へ転換する出発点をこの事件は示すとする見解に基づく考えである。
(ハ)大日本帝国憲法の発布(1889)に置く考え方。天皇制国家が機構のうえで整備、確立されたのは憲法発布によってであり、同時にこの時期、経済のうえでは原始的蓄積が進み、寄生地主制と産業資本主義の成立の土台がほぼできあがったことを重視する見解である。今日学界では、終期について(イ)と(ハ)の考え方が有力であるが、終期をどう考えるかによって、明治維新の性格のとらえ方は違ってくる。
幕府の倒壊
すでに天保年間には、幕藩制の解体傾向は顕著に現れた。農民は封建領主の年貢の生産だけに専心する存在ではなくなり、商品生産者、商品販売者の性格を増し、各地に農村工業、それも問屋制家内工業あるいはマニュファクチュア(工場制手工業)が生まれ、ブルジョア的地主、小ブルジョア的富農、半プロレタリア的貧農という新しい階層が農民身分のなかから形成され始めた。年貢の輸送・販売を中心に三都(江戸、大坂、京都)や各藩の城下町の特権的大商人が独占的に支配していた従来の商業機構は、農民の商品生産に依存する新興中小商人の勢力の台頭によって崩されつつあった。幕府・諸藩とも財政窮迫に悩み、その打開策としてとった貨幣経済の農村侵入の阻止、年貢の増徴、専売制の拡大が、農民・商人の反抗を招いて失敗に帰したのも、この時期である。百姓一揆 (いっき)は激発し、しかも領主に対する反抗だけでなく、村役人・地主に対する闘争も頻発し、村落秩序の根底から封建支配を揺るがした。加うるに都市では、物価騰貴に悩む下層民の蜂起 (ほうき)である「打毀 (うちこわし)」が起こり、一時封建支配が麻痺 (まひ)するという情況も現れた。
こうした封建制崩壊の諸条件を政治抗争にまで結集せしめたのは、1853年(嘉永6)のペリー来航を契機とする対外問題の切迫であった。欧米列強が武力の威嚇をもってわが国に強要したものは、鎖国制度を撤廃し、資本主義の世界市場の一環に組み込むことであった。しかも彼らの圧力のもとで結んだ安政通商条約は、欧米諸国と清朝 (しんちょう)中国との間の条約を雛型 (ひながた)とする不平等条約であり、開国に反対する封建支配者との間に武力衝突も起こった。幕末に日本は欧米強国により植民地化される危険をもったといえる。
この植民地化の危機の進行を押さえることのできた第一の条件は、封建支配者が鎖国復帰と攘夷 (じょうい)の実行の不可能を比較的早く悟ったことである。すなわち、通商条約締結をめぐって、幕府と雄藩、上層藩士と下層藩士の対立が激化し、攘夷を旗印とする幕閣批判の政治勢力が力をもったが、貿易は比較的順調に伸び、国内経済は当初若干の混乱はあったものの、商品経済発展の力をいっそう強める結果となり、大勢としては、農民・商人が武士の攘夷運動を支持することとならなかった。そのうえ幕府・諸藩の財政窮乏のため軍備充実は進まず、また1863年(文久3)の薩英 (さつえい)戦争、翌年の四国連合艦隊下関 (しものせき)砲撃事件という対外戦争の経験から、武士は彼我の武力の差を痛感するに至った。かくて幕府側にせよ、反幕派諸藩にせよ、指導者は、列国との接触を深め貿易に参加することによって、強兵と富国を実現しようとした。
植民地化の危機が深まらなかった第二の条件は、列強側の事情にあった。在日外交団の指導的位置にあったイギリスは、アヘン戦争後の中国民衆の反英闘争、太平天国の乱、インドのセポイ(傭兵 (ようへい))の乱の鎮圧に東アジアでの武力を割かざるをえず、日本に対する武力行使には慎重であった。しかもイギリス対ロシア、イギリス対フランスの列強間の対立の増大のため、一国が独占的に日本に利権を設定することは困難であった。列強、とくにイギリスは、貿易発展の障害となっている封建制度の廃止を望んでいたが、民衆の力による革命、あるいは列国の直接干渉による実現は、むしろ市場の混乱をもたらすことになるとしてこれを避け、封建支配者内部の開明派を育成し、彼らの手で「上からの漸進的改革」を行わせることが望ましいと考えるようになった。
1866年(慶応2)、米価をはじめ物価の暴騰、貢租の加重に悩む民衆は、江戸・大坂とその周辺地帯を中心に各地で一揆・打毀に立ち上がり、民衆の反封建闘争は江戸時代を通じ最大の高揚を示した。時あたかも幕府の第2回長州征伐の真っ最中であった。幕府が諸藩の大軍を動員しながら、当初の戦闘の敗北にくじけて早々に休戦を令したのは、財政窮迫に苦しむ諸藩が戦争の負担を嫌い、また内乱が下民の蜂起と外国の干渉を招くのを恐れたからであった。こうして薩摩藩ら雄藩を中心に、従来の幕閣専制を改めて、天皇の下での諸藩連合政権という形態によって、封建権力の統一と強化を図る工作が進行し、将軍徳川慶喜 (よしのぶ)の政権返上に続いて、1867年12月9日に王政復古の宮中クーデターが行われ、幕府は廃止され、天皇政権が樹立されたのである。
統一国家の樹立と諸改革
王政復古の直後、薩摩藩・長州藩の挑発によって引き起こされた戊辰 (ぼしん)戦争は、佐幕派勢力に打撃を与えただけでなく、天皇政府方を含めた藩全体の支配体制の解体を促進した。西ヨーロッパの絶対主義王権は、大規模かつ長期の内乱を通じて、強大な領主が他の領主を圧服して封建権力の統一を実現し、中央集権国家をつくりあげたものであるが、天皇は、古代以来の権威をもつとはいえ、実質の権力はなく、倒幕派雄藩によって「玉 (ぎょく)」として新しく担ぎ出されたものであったから、改めて諸藩の藩主・藩士層や豪商・豪農層の支持を取り付けるために、幕藩制に対する革新的な姿勢をとった。江戸城総攻撃開始を目前に出された五か条の誓文はその表れであった。1869年(明治2)正月、薩・長・土・肥4藩主が王土王民思想を強調し、土地と人民を形式上天皇に返すという建白をすると、他の藩主もこれに倣い、版籍奉還 (はんせきほうかん)が実現した。ついで1871年7月、詔勅の発布という形で廃藩置県を行い、さらに引き続いて華族(藩主と公卿 (くぎょう))と士族の封禄の整理を重ねたすえ、76年の金禄公債の支給によって、封禄制度を全廃した。藩制度と封禄制度の廃止―封建支配者の特権の主要なものの解消―が、戊辰戦争と、74~77年の西南一部地域の士族反乱という、封建支配者間の比較的小規模の内乱を経ただけで、しかも民衆の革命的蜂起なしに実現をみたのは、ヨーロッパの歴史と比較して顕著な特色であった。すでに藩体制は、財政的にも軍事的にも破産情況にあり、それを救済できる中央権力の確立が全封建支配者の要望であった。そして領主制の解体にあたっては、藩の借金の大部分は政府に肩代りされ、華士族には金禄公債支給によって多額の補償費が支払われ、その結果は、民衆に重い租税負担を負わせることとなった。公債の利子で自活できる層は、華族と旧上層藩士に限られていたが、中下層士族には、官吏・軍人・教員に転身する機会が独占的に開かれており、農工商に従事する者への士族授産には、政府から特権的保護が与えられていた。もとより彼らのなかには没落し、不平を抱く者も多かったが、統一国家の建設、中央政府の強化、欧米文化の摂取による強兵富国の実現という政府の方針に反対することはできなかった。幕末以来の欧米列強の圧力と民族独立の危機とを痛感していたからである。
廃藩置県後、政府は文明開化の改革政策を積極的に展開し、国民各層の多数を政府支持に引き付けようとした。1872年、学制を発布し、身分にかかわらずすべての国民の義務教育制を定め、翌年には、国民皆兵を看板とする徴兵令を出して、武士軍隊を廃止し、さらに地租改正条例を定めて、農民に土地所有権を認め、これまでの現物年貢を金納地租に改めた。これらの大改革の性格をどのように評価するかは、明治維新がブルジョア革命であるかどうかの理解と深くかかわることである。評価のうえでの問題点の第一は、これらの改革が、天皇の絶対的権威を国民に浸透させる施策および政府の中枢を占める藩閥勢力が内部対立を重ねながらしだいに統一強化してゆく過程と相表裏していることである。第二は、諸改革は、欧米資本主義国家の制度を模範として制定され、法令の内容、制度のたてまえはブルジョア的性格のものであったが、それと実際の立案意図、実施においてもつ現実の機能の歴史的性格とは、いちおう区別して考える必要があることである。すなわち、小学校の設立・維持の費用がもっぱら地域住民の負担と授業料によってまかなわれたため、権力の厳しい強制にかかわらず、国民皆学の実はあがらなかった。四民平等をたてまえとする徴兵令も、実際には広範な免役規定をもち、兵役を負担するのは貧しい民衆の二、三男に限られていた。また地租改正は、現実には法令の規定するとおりの地価の算定方法がとられず、従来の年貢総額を確保するという前提にたっての権力の強制による押し付けの決定であった。したがって、改革はいずれも民衆の激しい反対を受けた。これら改革の法令がたてまえとするブルジョア的内容が現実に成果として現れるのは、すなわち、小学校就学率が学齢児童の50%を超え、徴兵制の免役規定が廃止されて国民皆兵の実をもち、地租改正の結果が寄生地主制と資本主義経済に安定的に結び付くのは、1890~1900年代であった。この時期は、自由民権運動の発展とその挫折 (ざせつ)を経過して、1889年大日本帝国憲法が発布され、藩閥専制が改められ立憲制が導入された反面、統帥権(軍隊の指揮権)をはじめとする天皇の絶大な大権が規定され、天皇を頭とする官僚機構が整備され、軍国主義が強化された。そして1894~95年の日清 (にっしん)戦争に勝利することで、植民地台湾を領有するという日本帝国主義が樹立する時期であった。
終期を1877年とするか89年とするか、いずれの見解をとるにせよ、明治維新とは、封建制から資本制への移行過程における政治的・社会的変革であり、その結果は、強力な天皇制官僚支配の確立と、軍国主義および寄生地主制と深く結び付いた日本資本主義の形成とをもたらしたということができよう。

 天下
天下 、嚮
、嚮 明而治」、また、「維新」は『詩経』の「周雖
明而治」、また、「維新」は『詩経』の「周雖 明
明 揚惟神之道
揚惟神之道 也」というように、神道イデオロギーで接合された。「明治」の語は、慶応四年(一八六八)九月七日の夜、天皇睦仁が宮中の賢所で、五条・高辻らの菅家の堂上が上った勘文に就き、改元のための元号候補からくじで選んだ。これは翌八日の改元と一世一元の制の詔で睦仁治世の元号となった。「維新」に通ずる「一新」の語は、幕末期の幕府側の文書にも散見し、また、慶応期長州藩諸隊の中の被差別部落民の隊名に「一新組」「維新団」の呼称が付され、この「一新」や「維新」の語には、これら被差別部落民の解放の願望が込められていた、と思われる。維新政府はこの「一新」意識を「御一新」と表現し、天皇による上からの「御一新」を強調した。これに対し江戸的な心情をもつ庶民からは「上からは明治だなどといふけれど、おさまるめいと下からは読む」と皮肉られたという。
也」というように、神道イデオロギーで接合された。「明治」の語は、慶応四年(一八六八)九月七日の夜、天皇睦仁が宮中の賢所で、五条・高辻らの菅家の堂上が上った勘文に就き、改元のための元号候補からくじで選んだ。これは翌八日の改元と一世一元の制の詔で睦仁治世の元号となった。「維新」に通ずる「一新」の語は、幕末期の幕府側の文書にも散見し、また、慶応期長州藩諸隊の中の被差別部落民の隊名に「一新組」「維新団」の呼称が付され、この「一新」や「維新」の語には、これら被差別部落民の解放の願望が込められていた、と思われる。維新政府はこの「一新」意識を「御一新」と表現し、天皇による上からの「御一新」を強調した。これに対し江戸的な心情をもつ庶民からは「上からは明治だなどといふけれど、おさまるめいと下からは読む」と皮肉られたという。 琿条約は一八五八年)、フランスはインドシナの植民地化を企図し、アメリカは太平洋航路を開いて中国に迫ろうとした。外圧に対するこうしたアジア民族の状況の中で明治維新は遂行されたのである。アジア民族の抵抗は全体的には孤立分散してはいたが、主観的にはその関連が自覚され、いち早く情報は日本にもたらされ、危機意識を高揚させた。そして、客観的にはインドや中国の世界市場への組み込まれ方が日本を規定し、また、日本の対応がやがて朝鮮にも影響を及ぼすことになった。イギリスやフランスがアジア民族の諸抵抗に逢着し手間どる間に、アメリカの使節ペリーの率いる「黒船」が日本に来た。したがって、一八五三年の「黒船」来航とその後における日本の歴史的変革は、世界資本主義の法則がアジア的状況の中で日本に貫かれ、それに対する日本の対応=変革の発現形態として捉えることができよう。では、「内から」、そして「下から」の力とは何か。近世中期以降、農民的商品経済の展開によって、幕藩体制の矛盾は拡大・深化し、天保期には全国的にその矛盾が顕在化してきた。「黒船」来航=開国による貿易開始と情報ルートのいや応なしの開放は、これにいちだんと拍車をかけ、国内の経済・社会は激しく変動した。この激変の中で次第にブルジョア的発展を促進されたプラス地帯と、逆のマイナス地帯とが現出し、その地域的なさまざまな落差の中で幕末期の小ブルジョア経済は全国的な規模で発展した。それは幕藩体制の個々の領域、分立的な各藩の網の目を解きほぐし、商品流通や情報の伝達を容易ならしめるとともに、民族的統一への経済的社会的条件を急速に整える役割を果たしたのである。「黒船」来航以後わずか十五年にして、二世紀半以上続いた強固な幕府の支配体制が一挙に崩壊したゆえんである。この経済・社会の激動の中で、農民や商人層などの分解・分化はいっそう進み、支配階級たる武士層も分裂した。そして、中・下層武士や知識人、あるいは地主・豪農商層の一部は、外圧の危機感の中で急速に民族的自覚を促され、政治運動へと走った。ときあたかも高まる農民一揆や打ちこわしは、変転する政治運動と微妙に関連しつつ維新変革をその背後で規定したのである。また、この民衆運動は、曲折と変容を経ながらも、やがて明治十年代の自由民権運動へと継受・発展せしめられていく。「上から」の力は、この「内から」ないし「下から」の力や「外から」の外圧に対応しつつ、あるときはこれを利用し、あるときは拮抗・弾圧して幕藩体制にとって代わる明治天皇制国家を創出・形成する力を指し、討幕派―維新官僚―天皇制政治家という系譜をもつ勢力をいう。彼らは当初は西南雄藩という旧権力に拠りつつ、次第に上昇・転回して「朝臣」化し、「朝臣」化することによって天皇中心のイデオロギーのもとで欧米の近代的国家にならいながら、中央集権的な近代官僚機構を整備し、天皇をその権力の中核にすえて絶対化し、明治天皇制国家を創出・形成し、やがて確立していったのである。以上のような世界史的状況下での維新変革のプロセスは、後発国特有の「上から」の「文明」化による経済・軍事そして文化の強力的な集中となる。そして、この「文明」化は同時に「脱亜」の発想と表裏一体をなし、アジアへの侵略的性格を色濃くもつ。「上から」の「文明」化による近代天皇制の形成過程は、「内」における強力的な中央集権的専制と、「外」に対する軍事的侵略的指向を構造的性格たらしめたのである。
琿条約は一八五八年)、フランスはインドシナの植民地化を企図し、アメリカは太平洋航路を開いて中国に迫ろうとした。外圧に対するこうしたアジア民族の状況の中で明治維新は遂行されたのである。アジア民族の抵抗は全体的には孤立分散してはいたが、主観的にはその関連が自覚され、いち早く情報は日本にもたらされ、危機意識を高揚させた。そして、客観的にはインドや中国の世界市場への組み込まれ方が日本を規定し、また、日本の対応がやがて朝鮮にも影響を及ぼすことになった。イギリスやフランスがアジア民族の諸抵抗に逢着し手間どる間に、アメリカの使節ペリーの率いる「黒船」が日本に来た。したがって、一八五三年の「黒船」来航とその後における日本の歴史的変革は、世界資本主義の法則がアジア的状況の中で日本に貫かれ、それに対する日本の対応=変革の発現形態として捉えることができよう。では、「内から」、そして「下から」の力とは何か。近世中期以降、農民的商品経済の展開によって、幕藩体制の矛盾は拡大・深化し、天保期には全国的にその矛盾が顕在化してきた。「黒船」来航=開国による貿易開始と情報ルートのいや応なしの開放は、これにいちだんと拍車をかけ、国内の経済・社会は激しく変動した。この激変の中で次第にブルジョア的発展を促進されたプラス地帯と、逆のマイナス地帯とが現出し、その地域的なさまざまな落差の中で幕末期の小ブルジョア経済は全国的な規模で発展した。それは幕藩体制の個々の領域、分立的な各藩の網の目を解きほぐし、商品流通や情報の伝達を容易ならしめるとともに、民族的統一への経済的社会的条件を急速に整える役割を果たしたのである。「黒船」来航以後わずか十五年にして、二世紀半以上続いた強固な幕府の支配体制が一挙に崩壊したゆえんである。この経済・社会の激動の中で、農民や商人層などの分解・分化はいっそう進み、支配階級たる武士層も分裂した。そして、中・下層武士や知識人、あるいは地主・豪農商層の一部は、外圧の危機感の中で急速に民族的自覚を促され、政治運動へと走った。ときあたかも高まる農民一揆や打ちこわしは、変転する政治運動と微妙に関連しつつ維新変革をその背後で規定したのである。また、この民衆運動は、曲折と変容を経ながらも、やがて明治十年代の自由民権運動へと継受・発展せしめられていく。「上から」の力は、この「内から」ないし「下から」の力や「外から」の外圧に対応しつつ、あるときはこれを利用し、あるときは拮抗・弾圧して幕藩体制にとって代わる明治天皇制国家を創出・形成する力を指し、討幕派―維新官僚―天皇制政治家という系譜をもつ勢力をいう。彼らは当初は西南雄藩という旧権力に拠りつつ、次第に上昇・転回して「朝臣」化し、「朝臣」化することによって天皇中心のイデオロギーのもとで欧米の近代的国家にならいながら、中央集権的な近代官僚機構を整備し、天皇をその権力の中核にすえて絶対化し、明治天皇制国家を創出・形成し、やがて確立していったのである。以上のような世界史的状況下での維新変革のプロセスは、後発国特有の「上から」の「文明」化による経済・軍事そして文化の強力的な集中となる。そして、この「文明」化は同時に「脱亜」の発想と表裏一体をなし、アジアへの侵略的性格を色濃くもつ。「上から」の「文明」化による近代天皇制の形成過程は、「内」における強力的な中央集権的専制と、「外」に対する軍事的侵略的指向を構造的性格たらしめたのである。