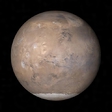地球のすぐ外側の軌道を回る、金星に次いで地球に接近する太陽系の惑星。直径は地球の約53%、質量は地球の約11%しかない。公転周期は1.88年。火星の軌道離心率は、水星に次ぐ大きさの0.093もあり、太陽からの距離は太陽と地球の間の距離の約1.4~1.7倍に変化する(平均距離は約2億2800万キロメートル〈1.5241天文単位〉)。
軌道
太陽系の惑星としてはかなり楕円(だえん)の軌道を描く。そのため、太陽にもっとも近づく近日点距離と太陽からもっとも遠ざかる遠日点距離の違いがかなり大きく、近日点付近で火星が地球と接近すると、距離が小さくなり「大接近」とよばれる。大接近は15年あるいは17年に一度おこる。自転周期は24.6229時間。表面重力は地球上の約38%。
約2年2か月ごとに火星が地球に接近するころ、地球から見て火星は太陽と反対方向に見える(衝(しょう)の位置)ため、火星は真夜中に南中し、一晩中眺めることができる。星座を背景に独特な動き方をするのが惑星の特徴であるが、地球に近い軌道を動く火星では動きが比較的速く、目だっている。さらに火星が目だつのは、その色と明るさである。赤い火星は地球に接近するころに明るく見え、人々の注目を集めてきた。赤い色は血や炎を連想させ、古代から戦争や災害と関係する神やシンボルとされることが多かった。
望遠鏡発明以前の時代、デンマークのティコ・ブラーエは肉眼と観測器具だけで火星の精密な位置観測を行った。そのデータから試行錯誤の末、1605年に火星軌道が楕円であると見抜いたのがドイツのヨハネス・ケプラーであった。
表面
望遠鏡による初期の火星スケッチとしては、オランダのクリスティアーン・ホイヘンスが1659年11月28日夜、口径7センチメートル、倍率87倍の望遠鏡で観測したものがあり、そのスケッチには、今日の火星地図で「大シルチス」とよばれる模様が描かれている。また、ホイヘンスは火星の自転周期が約24時間であると、同年に記録している。さらに、1666年にパリに移住したホイヘンスは、1672年の火星接近時に火星の南極域に白く輝く「南極冠(水や二酸化炭素が凍った平原。北極冠もある)」をスケッチしている。
イギリスのウィリアム・ハーシェル(父)は1777~1783年に火星を観測し、火星の自転軸が軌道面の垂線に対し約30度傾いていると結論した。これは、火星には地球のように四季が存在することを意味した。
衛星
1877年の火星大接近時には、アメリカ海軍天文台のアサフ・ホールが火星に二つの衛星を発見した。衛星は火星に近いほうからそれぞれフォボス、デイモス(ダイモス)と名づけられた。戦争の神(ローマ神話のマルス、ギリシア神話のアレス)の息子たちの名である。
運河
同じ1877年、イタリアのジョバンニ・スキャパレリが観測した火星スケッチは大きな反響をよんだ。口径22センチメートルの屈折望遠鏡を使って、注意深く火星を観測した彼は、火星が複雑な網目模様に包まれていることを報告した。スキャパレリは、そうした直線状の模様を「カナーリ」とよんだ。イタリア語で水路(天然、人工を問わず)や経路、管を意味するが、英語に翻訳された際に「カナル(運河)」、運河と訳され、スキャパレリは火星に運河を発見したと世界中の目が火星に注がれるようになった。スキャパレリはかなりの近眼で色覚異常もあった。彼には火星はほとんど明暗像のように見えたという。ただ、コントラストについては敏感で、濃淡がわずかに異なる境界部分が線として見えたのかもしれない。
アメリカの資産家パーシバル・ローウェルは、アリゾナ州に1894年、私設の天文台を建設した。口径61センチメートルの大型屈折望遠鏡がもっぱら向けられたのは火星であった。ローウェルは運河や運河が交わるところにある黒い斑点を多数記録している。ローウェルは、運河そのものは地球上の望遠鏡で識別するには小さすぎるはずで、見えているものは運河沿いの植生なのだと考えていた。「火星人による運河」というローウェルの主張に反対する者もあり、運河とよばれる模様を見たという者も少数派であった。
探査機の時代
火星に関する新しい知識をもたらしたのが火星探査機である。初めて成功した火星探査機は、1964年にアメリカが打ち上げたマリナー4号だった。翌1965年7月には火星表面から約9800キロメートルを通過。初めて火星の近接撮影を行った。火星表面には月と同じようなたくさんのクレーターがみつかり、火星はおもに二酸化炭素からなる大気に覆われていることが確認された。表面気圧は地球上の0.4~0.7%。マリナー4号は火星にわずかな磁場を観測した。
1971年5月に打ち上げられたソ連の火星探査機マルス3号では、周回機(オービター)に加えて、着陸機(ランダー)と小型探査車(ローバー)も搭載していた。同年12月に火星に軟着陸を果たすも直後に送信がストップ。その後、探査車がどうなったかも不明である。
同じく1971年5月に打ち上げられたアメリカのマリナー9号は、その年の11月には探査機として初めて火星周回軌道に入った(他の惑星の周回軌道に入った初めての探査機)。なお、巨大楯状火山のオリンポス山は、1879年にスキャパレリが明るく輝く地点として初めて観測し、Nix Olympia(オリンポスの雪)と名づけたが、マリナー9号により「山」であることが確認され、オリンポス山Olympus Monsと命名された。また、火星赤道に沿う巨大峡谷もマリナー9号によって発見され、マリナー9号にちなんでマリネリス峡谷Valles Marinerisと命名された。続いてソ連のマルス2、3号が11月下旬~12月上旬に火星周回軌道に入った。マルス2号の着陸機(と小型探査車)は大気圏降下中に問題が発生し、表面に激突したもよう。このころ、火星は惑星規模の砂嵐(グローバルダストストーム)にみまわれていたため、表面のようすはほどんどわからなかった。1972年1月には砂嵐も収まったが、マリナー9号による火星の写真に運河らしきものはみつからなかった。
1975年8月打ち上げのアメリカのバイキング1号(周回機・着陸機)は翌1976年6月に火星周回軌道に入り、同年7月、着陸機がクリュセ平原に着陸した。バイキング2号(周回機・着陸機)は1975年9月に打ち上げられ、翌1976年8月に火星周回軌道に入り、着陸機は9月、ユートピア平原に着陸した。周回機は火星表面全体を撮影。最初の火星表面カラー画像など5万2000枚以上の画像を送信。着陸機には土壌に生命が存在する可能性を調べる三つの実験装置を搭載していたが、明確なデータは得られなかった。地上1.5メートルで測定された気温は氷点下25℃~氷点下119℃であった。極冠と大気との間にはH2Oのやりとりがあり、季節周期があることも明らかになった。火星の土壌を分析し、あの赤い色は酸化第二鉄などの鉄の酸化物、つまり鉄さびの色であることを明らかにした。オレンジ色の空も赤い色の細かい塵(ちり)が風によって吹き上げられているためである。火星の大気は薄いため、地球のようなレーリー散乱(空が青くなる)の効果が目だたず、塵による色が目だっている。大量の水が流れたとみられる流水地形があちこちにみつかり、過去には温暖な時期があったと推測されている。
地球上でみつかる一部の隕石(いんせき)には、そこに含まれるアルゴンなどの気体の同位体組成が火星大気のもの(バイキング〈1号、2号〉着陸機が測定)とよく一致している。こうした火星から飛来したとされる火星隕石が2024年3月時点で370個以上みつかっている。
アメリカの「マーズ・グローバル・サーベイヤー」探査機は、1997年9月に火星周回軌道に入った。その高解像度画像によって2000年に発見されたガリとよばれる小規模な筋状地形については、流れたものが水である可能性も含め、成因がよくわかっていない。また、「マーズ・パスファインダー」探査機は1997年7月、火星のアレス渓谷にパラシュートとエアバッグを使って着陸した。着陸機からは初めてとなる火星探査車「ソジャーナ」が地上に降ろされ、周囲の岩石などを調査した。さらに火星探査機「2001マーズ・オデッセイ」は、2001年10月に火星周回軌道に入った。そのおもな目的は火星表面のリモート・センシング(遠隔探査)であった。
日本の文部省(現、文部科学省)宇宙科学研究所は、1998年(平成10)7月に鹿児島宇宙空間観測所(現、宇宙航空研究開発機構〈JAXA(ジャクサ)〉内之浦(うちのうら)宇宙空間観測所)から火星探査機「プラネットB」を打ち上げた(打ち上げ後、探査機は「のぞみ」と命名)。途中トラブルが起こり、計画の大幅な修正がなされ、2003年(平成15)12月に火星に接近したが周回軌道にのせることができなかった。
2003年6月と7月に相次いで打ち上げられたアメリカの2台の火星探査車が、「スピリット」と「オポチュニティ」であった。それぞれ2004年1月上旬と下旬に異なる地点に到着し、移動を伴う探査が始まった。水中で沈殿・堆積(たいせき)したとみられる岩石も発見している。岩石中の硫酸塩鉱物は、地球上では水のある環境で形成されている。
ESA(イーサ)(ヨーロッパ宇宙機関)が初めて取り組んだ火星探査機計画「マーズ・エクスプレス」では、軌道周回機と着陸機を使い、火星の大気・電離層、表面、地下構造などを調べることになっていた。マーズ・エクスプレス探査機は、2003年12月に火星到着。着陸予定日の6日前には本体(周回機)から着陸機が分離された。着陸機には生物の痕跡(こんせき)を調べるための各種観測装置などが積まれていたが、残念ながら着陸機からの応答はなく失敗に終わり、周回機のみによる観測となった。
アメリカは「マーズ・レコネサンス・オービター」探査機を打ち上げ、2006年3月、火星周回軌道にのせた。それまでの惑星探査機では最大口径の50センチメートルカメラが搭載された。同じくアメリカの「フェニックス」探査機は、2008年5月に火星に到着。重い機体のため、パラシュートとエアバッグによる着陸はできず、バイキング着陸機と同様にロケット噴射で減速を行い、北緯68度の高緯度地域に着陸。着陸地点の気温は氷点下80℃~氷点下30℃。地面の下に水氷が広がっているのが確認された。さらにアメリカは新たな火星探査車「キュリオシティ」を打ち上げ、2012年8月に着陸させた。
インド初の火星探査機となる火星周回機(マーズ・オービター・ミッション。愛称「マンガルヤーン」)が2013年11月上旬にインド南東部、サティッシュ・ダワン宇宙センターから打ち上げられ、2014年9月には火星周回軌道に入った。
アメリカの火星周回機「メイブン」は、2014年9月に火星周回軌道に入った。火星大気や、火星大気と太陽風との関係などを調べるのが目的であった。火星全体としての磁場がないため、火星では太陽風が直接大気にぶつかり、上層の大気が太陽風により流失していくことがわかった。かつては大量にあった水の一部は地下に氷として蓄積しているが、大部分は大気を通じて失われたらしい。
2016年3月にカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から打ち上げられたESAとロシア宇宙庁の火星探査機「エクソマーズ2016」の軌道周回機と着陸機は、同年10月に火星に到着。火星大気と火星表面の観測を行う周回機の「トレース・ガス・オービター」(TGO)は周回軌道にのったが、着陸機の「スキャパレリ」は着陸に失敗。
アメリカが打ち上げた火星着陸機「インサイト」は、2018年11月に火星の赤道近く、エリシウム平原西部に着陸。高感度火星地震計(火震計)を搭載し、火星の内部構造を探っている。
2020年7月には、3か国の火星探査機が相次いで打ち上げられた。
アラブ首長国連邦初の火星探査機の「アルアマル」(HOPE、周回機)は種子島(たねがしま)宇宙センターからH-ⅡAロケットにより打ち上げられ、2021年2月10日0時42分(日本時間)に火星周回軌道に入った。
中国の火星探査機「天問一号」は2021年2月10日21時ころ火星周回軌道に入った。5月15日に着陸機を火星に着陸させ、22日には探査車を着陸機から火星表面に降ろした。
アメリカの火星探査車「パーサビアランス」は、2021年2月19日に大シルチス内の北東部、イェゼロ(ジェゼロ)・クレーターに着陸。同機腹部から世界初の火星ヘリコプター「インジェニュイティ」を分離。同年4月に初飛行を行った。
なお、現時点では火星の自転軸の傾きは、0~60度と大きく変動してきたことが理論的な研究からわかってきた。その変化は、火星が受ける日射量の緯度分布や季節変化のようすを大きく変える。火星の極冠には色の暗い層と明るい層が交互に堆積しているが、自転軸傾斜角の変動によるものと考えられている。