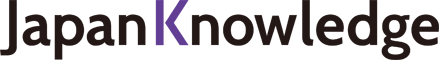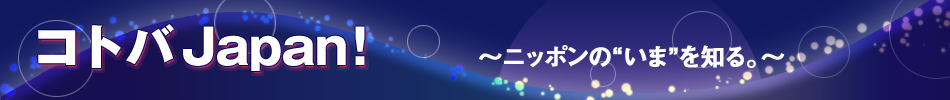元プロ野球選手。48歳。甲子園通算最多本塁打記録保持者(13本)で桑田真澄とともに
PL学園を2度の優勝に導いた立役者だった。
本人は巨人軍入りを切望したが、桑田が巨人と密約を結んでいたため指名されず、涙をのんで西武ライオンズへ入団する。新人王、オールスターゲームMVP7回、日本シリーズ優秀選手賞3回受賞するも、首位打者、本塁打王、打点王の獲得経験はなく「無冠の帝王」と呼ばれた。
1997年に巨人軍に移籍するが故障などで期待された働きができず、2005年に戦力外通告。オリックスに移籍するが2008年に引退。その後は野球評論家やタレントとして活動していた。
長嶋茂雄ほどではないが「記憶に残る」選手であった。特に私のような巨人ファンにとっては。清原が入団2年目の秋だった。巨人との日本シリーズで西武の優勝が決定的になった9回表、一塁の守備についた清原の目から涙があふれ出した。
自分を裏切った巨人を倒せる感激の涙だった。
もう一つ忘れられないのは、
西武時代に吉永小百合と噂になったことだ。サユリは自分の亭主が年上なためか、若いマッチョな男が好きだった。真偽のほどはわからないが、このときほど清原を憎いと感じたことはない。
清原が変わったのは巨人軍に移籍してからだと、私は思っている。当時、私は『週刊現代』の編集長だった。編集後記「音羽の杜から」に
「ブタは空を飛べない」と書いた。明らかに打者としては落ち目だったし、巨人のようにメディアもファンも口うるさい球団では、力を発揮できないと思ったからだ。残念ながらその予想は当たってしまった。
『フライデー』が名付けた
「番長」というあだ名が示すとおり、球界一のワルとして球場外での粗暴な行動や言動が話題になったが、引退後は薬物疑惑も囁かれ続けた。
2000年に
モデルの木村亜希と結婚し2人の息子をもうけた。
『週刊文春』(2014年3/13号、以下『文春』)で薬物疑惑が報じられた。
「じつは清原は覚せい剤などの薬物の禁断症状に苦しんでいるのです。
昨年、彼は足立区にある精神科の病院に一週間ほど極秘入院しています。入院したのは、傍目にも言動が異常をきたしていたから。隣で呼びかけても無反応、目の焦点が合わず、口はネチャネチャと粘つき、ときおり意味不明のことを口走っていた。この病院で電気ショックなどの治療を受け、“シャブ抜き”が行われたそうです」(清原と親しい友人)
別の友人による証言もある。
「清原の妻・亜希さんは、『最近夫の様子がおかしい。暴力的になり、すぐ激昂する。刃物持って追いかけ回されたこともある』と、複数の親しい知人に相談しているのです」
この報道に清原は、入院したのは
重度の糖尿病のためだと弁明したが、その後2人は
離婚している。子供は亜希が引き取った。
そして『文春』報道から2年近くが過ぎようとした今年の2月2日、
警視庁組織犯罪対策5課が清原の自宅に踏み込んだのだ。『週刊新潮』(2/18号、以下『新潮』)からその時の模様を引用しよう。
「キヨは、ダイニングの椅子でくつろぐように座っていました。目の前のテーブルに、0.047グラムの覚醒剤が入った小袋が置かれ、彼の左手には、開封したばかりの注射器と先端が斜めに切られたストローがあった。つまり、覚醒剤を注射するところだったんです」(社会部デスク)
現行犯逮捕だ。『新潮』によれば、入手先は群馬県みどり市に住む40代半ばの売人だという。
捜査関係者はかなり前から清原に目を付け、清原のタニマチと言われ、昨年2月に覚せい剤使用の咎(とが)で逮捕された田辺大作(45・仮名)なる人物に拘留中、「どうしても清原をやりたいんだ」「協力してくれ」と言っていたという。
捜査関係者は『新潮』で、「清原が口座からカネを引き出すタイミングを定期的に見ていたんだ」と語っている。つまり数十万円レベルで口座から引き出せば、クスリを買いに行くのではないかとマークするのだという。それ以外にも清原が出すゴミを漁り、クスリを使用している頻度などを調べていた。
頭を刈り上げサングラスに刺青という暴力団も真っ青な清原の姿は世を忍ぶ仮の姿で、本当の清原は
気の小さい繊細な神経の持ち主だという見方がある。それを誤魔化すためにクスリを使ったというのだ。かつて清原自身が相談相手で友人だった人間にこう話している。『文春』(2/18号)から引用してみよう。
「初対面の人と一緒に食事をしたりすることが嫌で仕方ない。見知らぬ人がいる場所は緊張してドキドキする。小学生の頃は、野球の練習に行くのが嫌で、母親の陰に隠れてばかりいた。
現役時代もバッターボックスに出て行くのが嫌だった。五万人いる球場の打席でバットを構えるのは、どうしようもなく緊張する。空振りしてしまうとお客さんのハァーッていうため息が全部自分に吹きかかるようで、緊張と不安で発狂しそうになる」
そのうえ、子供と別れた寂しさが重なった。離婚会見で清原は「いまは自由に子供に会えへんのが一番ツライ。毎日、子供の写真を眺めてはひとりで泣いてんねん……」と語っている。
逮捕される2週間ほど前に『フライデー』(2/19号)が清原にインタビューしていた。そこでも息子たちへの“愛”を語っている。
「週末になったら、息子に会える。いまはそれだけが楽しみで、それだけを支えに生きてるわ。そのほかの日はメチャメチャ寂しいから、息子とLINEできるように、わざわざ専用のiPhoneも買(こ)うたし」
『文春』の薬物疑惑報道と離婚で一気に周りから人が離れ、仕事もまったくなくなったという。大阪・岸和田に住む両親についてこう語る。
「こないだ大阪に帰って、(認知症の施設に)入院してるお母さんのとこに行った。手ェ握ったら、小さァなっててな。だいぶいろいろわからんようになってるのに、オレに『一人で大丈夫か』って何べんも聞くねん。涙出てきて」
そりゃこんなできの悪い息子をもちゃ、認知症の母親だって心配で心配でたまらんやろう。
離婚の原因は(元夫人)にDVと薬物使用を見られたり、疑われたことではないのかという問いに、「ないない」と言い張った。そして最後に、
「いろいろ腹立つヤツもおるけど、殴ったりしたら、
自分の息子を犯罪者の子にしてしまう。それだけは絶対しとうない」
暴力沙汰よりもっと恥ずかしい覚せい剤で逮捕されてしまった。清原は次に息子に会ったとき、どんな言葉をかけるのだろうか。
気になる刑期だが、『新潮』で元東京地検特捜部検事の郷原信郎氏が、
「2月の下旬までに起訴が行われ、そのひと月程後から始まる公判は、2週間程度でケリが付く。所持量から鑑みて、判決は懲役1年6カ月、執行猶予3年というところでしょう。起訴後まもなく保釈される可能性もあります」
と話している。また元近畿厚生局麻薬取締部長の西山孟夫氏が薬物中毒についてこう話している。
「(報道が事実だとしたら=筆者注)量の面で言うと、清原はASKAのような大量服用ではありませんから、フラッシュバックについてはさほど心配はいりません」
同じように覚せい剤で逮捕、起訴され、実刑を受けた江夏豊のように、時間はかかったが球界復帰した人間もいる。江夏には彼の更生を助けた女性がいたが、清原にはいるのだろうか。どん底まで堕ちた元スーパースターの茨の道はまだまだ続く。
元木昌彦が選ぶ週刊誌気になる記事ベスト3
エリートが転ぶとき、というのは週刊誌が大好きなテーマだ。今週はみずほ銀行のエリート行員がタクシー代を払わなかったことで警察に逮捕されたケースだが、
酒のうえとはいえ、バカなことをしたものだと「同情」する。なぜなら私はエリートではなかったが、酒のうえでの失敗は掃いて捨てるほどある。よく警察沙汰にならなかったものだと、酒から醒めてゾッとしたことも一度や二度ではない。本心をいえば、憶えていないことも多々あるので、もしかすると……。冷や汗が出る。
第1位 「石坂浩二イジメ 司会降板『なんでも鑑定団』プロデューサーの“犯行動機”」(『週刊文春』2/11号)
第2位 「黒い割烹着『小保方手記』に『笹井副センター長』未亡人単独インタビュー」(『週刊新潮』2/11号)「小保方晴子さんを許さない3人の女」(『週刊文春』2/11号)
第3位 「みずほ銀行『51歳・東大卒・頭取候補』が何もかも失った瞬間」(『週刊現代』2/20号)
第3位。『現代』が、
みずほ銀行のエリート銀行員がたった7000円のタクシー料金を払わず警察沙汰になり、将来を棒に振ったと報じている。
この御仁、みずほ銀行公共法人部長の小山田泰幸容疑者(51)で、泥酔してタクシー運転手に暴行して料金を払わずに立ち去ったというのだ。
運転手が警察に通報し、自宅で小山田容疑者を逮捕した。彼は、ふざけるなとは言ったが殴ってはいないと容疑を否認しているが、料金を払わなかったことはたしかなようだ。
酔ったうえとはいえ、カネを払わなかったのは大変な落ち度だが、それだけではあるまい。相当な暴力沙汰がなくて、ここまでこじれるとは思いにくい。
『現代』によると、彼はエリートで「
タイミング次第では頭取だって夢ではなかったはずです」(メガバンク関係者)と言われていたそうだ。
酒は人を狂わせ人生を狂わせる。
『現代』の中でタクシー運転手の気になる言葉がある。
「会社からは運賃の支払いなどでお客さんと揉めたら、すぐ警察に通報するよう言われています。(中略)証拠はしっかり残っていますから」
クルマの中でのやりとりを「録音」かなにかしているということだろうか。言った、言わないのトラブルは両者の言い分だけでは判断しにくい。それを裏付けるものが今回もあったというのか。酒飲み諸君、気をつけような。
第2位。講談社から
『あの日』という意味深なタイトルの本を出した
小保方晴子氏だが、『文春』、『新潮』が批判している。
批判の多くは、共同研究者であった若山照彦・山梨大学教授に責任転嫁したり、毎日新聞の須田桃子記者の取材攻勢を「殺意を感じさせる」と難じたり、ほかのメディアにも敵意を剥き出しにしているのはいただけないというものである。
そして最大のポイントは先週の『ポスト』が指摘していたように「自らの口で発表した『STAP細胞はある』ことを科学者として示すこと」にあるはずなのに、できていないところである。
そこをスルーしてどんな弁明をしても、受け入れられるはずはない。元理研上級研究員の石川智久氏が『文春』でこう語る。
「自己弁護的な部分が文章から読み取れます。詳しく記述した部分と、事実をはぐらかした部分とのコントラストに違和感を憶えますね。特に、ES細胞の混入に関しては、記述に不明確な点が多いのです」
『新潮』では
自殺した笹井氏の未亡人の「単独インタビュー」(『文春』でもインタビューしているが)をやっている。
そこで未亡人は、小保方氏宛の遺書に
「STAP細胞を再現してください」と書いてあったことを認めている。
「主人はSTAP現象そのものについては、最後まで『ある』と思っていたと思います」と語っているが、小保方氏への評価が変わったのは、彼女が作成した細胞が、若山教授が渡した元のマウスと遺伝子系統が異なることがわかってからだったという。
「この時には、これはもう致命傷だな、と言っていました。その頃には、論文を引っ込めた方が良い、と感じていたようです。“終わり”を覚悟していました。
ちょうどその頃でしょうか、主人は、小保方さんについて、
『研究者に向いていない』とこぼすようになりました。科学の世界はデータがすべて。証明するものはそれしかない。たとえ悪意のないミスであったとしても、データをそれだけ杜撰に扱うということは、信用できるものは何もなくなってしまう──と非常に驚いていたのです。(中略)あの頃になると、主人は小保方さんには『根本的に研究者としての適性がない』と思うようになっていました」(未亡人)
しかし未亡人は、小保方氏とは「いつかいろいろと話をしてみたいとは思います」と言っている。それだけに「またいつか本を出すのだとしたら、もう少し、感情を抑え、客観的な、科学的なものを出してほしい」という指摘は、私にも頷ける。
第1位。私は会ったことはないが、
石坂浩二(74)はだいぶ前に大橋巨泉事務所に所属していた。いまフジテレビの「とくダネ!」をやっている小倉智昭も同じ事務所だった。
私は巨泉さんとは長い付き合いだが、彼が参議院選挙に出て当選すると、石坂氏は政治色が出るのを嫌がったのだろう、巨泉事務所を離れ、たしか個人事務所をつくったと記憶している(編集部注:現在はプロダクション尾木に所属)。
彼はたいそうな博学だそうだが、彼の看板番組と言っていいテレビ東京の
「開運!なんでも鑑定団」の司会を降ろされたことが色々憶測を呼んでいるようである。
はじめ聞いたとき、彼も歳だから認知症にでもなったのかと心配したが、そうではないようだ。
降板の内情をスクープしたのは『女性自身』(2月9日号)だった。
「制作側がコメントを意図的にカットするという陰湿なイジメ」があったという。
何しろ、番組では石坂がしゃべっているのに、放送するときはその部分をカットしてしまうというのだ。たしかに編集すればそうはできるだろうが、石坂も芸能生活の長い実績のある俳優&タレントである。それにこの番組は22年間も続いていて一時は20%以上の視聴率を誇ったこともあるのだ。そんなイジメができるのだろうか?
『文春』によると、Aというプロデューサーが約15年前にチーフになった直後の忘年会で、Aが酔って石坂に突っかかり、それ以後2人の間は燻り続けてきたそうだ。
Aは鑑定士らがお宝を覗き見る「鑑定ルーム」を廃止し、鑑定額の算出にも口を出してきたという。
「お宝の鑑定額は、実は予め鑑定士が鑑定し、決めています。しかしA氏がプロデューサーになってから、その事前鑑定の際に“過剰な演出”が入るようになったのです。『このお宝はトリだからもっと高値にしろ』とか、逆に『タダ同然にしろ』とか」(番組関係者)
何のことはない、
素人が値付けをしていたのだ。美術商「こもれび」店主の北御門博(きたみかど・ひろし)氏もこう話す。
「〇五年に柿右衛門様式の壺が過去最高金額の五億円を叩き出しましたが、柿右衛門の壺で国宝級としても市場価格はせいぜい一億円程度。五億円っていうのは考えづらい」
こうした「インチキ」が明るみに出ることこそ、視聴者の不信感を募らせ視聴率低下につながるのではないか。私は今後絶対この番組は見ない! 元々見たことはないのだが。
結局、降板した石坂はBSジャパンで「開運!なんでも鑑定団 極上!お宝サロン(仮題)」という番組の司会者になるという。このイジメの話、どこぞの週刊誌が石坂からじっくり聞いてほしいものだ。