2015年11月16日
このコラムでもしばしば紹介している深谷圭助氏の「辞書引き学習」の講演会では、深谷氏が「ひとびと」という語を実際に辞書で引かせて、辞書の表示と多くの人の思い込みの違いを示し、当たり前の語を辞書で引くことの大切さを教えるコーナーがある。
なぜ「ひとびと」かというと、通常は「人々」と書かれることが多いこの語は、辞書の見出しの漢字表記欄ではほとんどが「人人」となっていて、それにはそれなりの意味があるからである。
というのは、「人々」の「々」はもともと漢字ではなく繰り返しを表す符号で、漢字を使った本来の表記は「人人」となるからである。「々」は、「踊り字」「畳字(じょうじ)」などと呼ばれていて、ワープロソフトなどでは「どう」「おなじ」「くりかえし」「おどりじ」と入力すると変換できる。
この「々」という符号が広く使われるようになったのは、1952(昭和27)年の内閣総理大臣官房総務課が発した「公用文作成の要領」による。そこには、「同じ漢字をくりかえすときは『々』を用いる」と書かれていて、これによって、「人々」だけでなく「年々」「点々」「日々」なども「々」を使って書かれるようになるのである。
しかし、これらの語を試しにお手元の辞書で引いてみてほしいのだが、見出しの漢字表記欄では「々」は使っていないはずである。ただ、語釈に添えられた例文で、見出し部分を ─ などの記号を使って省略をしていない辞書では、見出しは「人人」でも例文は「人々」のように書かれているものもある。これは例文では一般的な使い方を優先して示したからである。
このようなわけで、表記欄にないからと言って「人々」と書くことが間違いではないのだが、最近は「ひとびと」のように訓読みの重なる語の場合は、「人びと」のように書くことも増えている。また、印刷されたものでは、行頭に二字目の「々」がくるのを避けるようにしていることも多い。
ところで「辞書引き学習」の講演会の話に戻るのだが、ある会場で子どもが漢字テストで「いろいろ」を「色色」と書いたら × になったのだがどうしてかという質問が保護者の方からあった。どうやら正解とされたのは「色々」であったらしい。
先生の意図はわからないのだが、実は「いろいろ」は漢字テストで出題するには適さないことばなのである。
というのも、「いろいろ」はいろいろな色、各種の色というのが原義で、これが「さまざま」という意味になった語であるため、仮名書きが望ましいからである。多くの辞書も仮名書きされることが多い語であることを注記している。1981(昭和56)年に当時の文部省が公用文作成の際の参考にするため、大臣官房総務課から省内に配布した「文部省 用字用語例」でも、「いろいろ」と仮名書きにするものとしている。また、新聞も同様で、たとえば時事通信社の『用字用語ブック』も「いろいろ」と仮名書きにしている。
当たり前のことばこそ辞書で引いてみるべきだと思うのだが、特に教える立場の学校の先生は、自分の思い込みでテスト問題を作成することだけはやめていただきたいのである。
なぜ「ひとびと」かというと、通常は「人々」と書かれることが多いこの語は、辞書の見出しの漢字表記欄ではほとんどが「人人」となっていて、それにはそれなりの意味があるからである。
というのは、「人々」の「々」はもともと漢字ではなく繰り返しを表す符号で、漢字を使った本来の表記は「人人」となるからである。「々」は、「踊り字」「畳字(じょうじ)」などと呼ばれていて、ワープロソフトなどでは「どう」「おなじ」「くりかえし」「おどりじ」と入力すると変換できる。
この「々」という符号が広く使われるようになったのは、1952(昭和27)年の内閣総理大臣官房総務課が発した「公用文作成の要領」による。そこには、「同じ漢字をくりかえすときは『々』を用いる」と書かれていて、これによって、「人々」だけでなく「年々」「点々」「日々」なども「々」を使って書かれるようになるのである。
しかし、これらの語を試しにお手元の辞書で引いてみてほしいのだが、見出しの漢字表記欄では「々」は使っていないはずである。ただ、語釈に添えられた例文で、見出し部分を ─ などの記号を使って省略をしていない辞書では、見出しは「人人」でも例文は「人々」のように書かれているものもある。これは例文では一般的な使い方を優先して示したからである。
このようなわけで、表記欄にないからと言って「人々」と書くことが間違いではないのだが、最近は「ひとびと」のように訓読みの重なる語の場合は、「人びと」のように書くことも増えている。また、印刷されたものでは、行頭に二字目の「々」がくるのを避けるようにしていることも多い。
ところで「辞書引き学習」の講演会の話に戻るのだが、ある会場で子どもが漢字テストで「いろいろ」を「色色」と書いたら × になったのだがどうしてかという質問が保護者の方からあった。どうやら正解とされたのは「色々」であったらしい。
先生の意図はわからないのだが、実は「いろいろ」は漢字テストで出題するには適さないことばなのである。
というのも、「いろいろ」はいろいろな色、各種の色というのが原義で、これが「さまざま」という意味になった語であるため、仮名書きが望ましいからである。多くの辞書も仮名書きされることが多い語であることを注記している。1981(昭和56)年に当時の文部省が公用文作成の際の参考にするため、大臣官房総務課から省内に配布した「文部省 用字用語例」でも、「いろいろ」と仮名書きにするものとしている。また、新聞も同様で、たとえば時事通信社の『用字用語ブック』も「いろいろ」と仮名書きにしている。
当たり前のことばこそ辞書で引いてみるべきだと思うのだが、特に教える立場の学校の先生は、自分の思い込みでテスト問題を作成することだけはやめていただきたいのである。
キーワード:
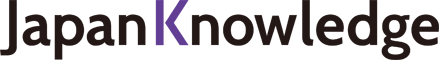


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
