2016年05月16日
「次第」という語は、名詞として使われたり接尾語として使われたりするのだが、接尾語の使い方がわかりにくいと思ったことはないだろうか。
接尾語の「次第」とは、「この仕事が終わり次第出かけます」などがそうである。動詞の連用形に付いて、その動作がすんだら直ちに、の意を表す言い方である。ただし、「この仕事が終わり次第出かけます」のような場合は、使い方に悩む方はあまりいらっしゃらないかもしれない。
だが、「この仕事は終了し次第出かけます」という場合はいかがであろうか。「終了し次第」なのか「終了次第」なのか、迷うことはないだろうか。つまり、「次第」が「漢語+する」の動詞に付く場合に、ということである。
「終了」が「する」を伴って動詞化した場合、連用形は「終了し」で、接尾語「次第」は連用形に付くのだから「終了し次第」が正しいと言うことになる。ところが「終了」と「次第」の間に「し」が入るとけっこう発音しづらく、かといって「し」を省くと、俗な言い方に思えてしまう。
この「し」の扱いに関してはけっこう悩む方が多いのではないかと勝手に思っているのだが、残念ながらそこまで触れている辞書はあまり多くはない。私が調べた限りでは、『現代国語例解辞典』(小学館)、『明鏡国語辞典』(大修館)だけがその点に言及している。
たとえば前者では、『動作・作用の完了の意味をもつ漢語のサ変動詞に限り、「し」の重なりを避けて語幹に接続する形も行われている。「到着次第」「終了次第」など』と補注で述べている。後者も、俗だとしながら、「到着次第」という言い方はあると認めている。
では、話しことばの場合はどうかというと、NHKは、「~ししだい」は「し」が重なって発音しづらく、話しことばとしてこなれていないとして、「次第」はなるべく使わないようにして「~したらただちに(すぐに)」などのようにするとよいとしている(『ことばのハンドブック 第2版』)。
「し」を入れても入れなくても今や特に問題はなさそうであるが、言いづらかったら(私自身も確かに発音しにくいと感じることが多い)、NHKのように無理に「~ししだい」を使おうとしないほうがいいのかもしれない。
接尾語の「次第」とは、「この仕事が終わり次第出かけます」などがそうである。動詞の連用形に付いて、その動作がすんだら直ちに、の意を表す言い方である。ただし、「この仕事が終わり次第出かけます」のような場合は、使い方に悩む方はあまりいらっしゃらないかもしれない。
だが、「この仕事は終了し次第出かけます」という場合はいかがであろうか。「終了し次第」なのか「終了次第」なのか、迷うことはないだろうか。つまり、「次第」が「漢語+する」の動詞に付く場合に、ということである。
「終了」が「する」を伴って動詞化した場合、連用形は「終了し」で、接尾語「次第」は連用形に付くのだから「終了し次第」が正しいと言うことになる。ところが「終了」と「次第」の間に「し」が入るとけっこう発音しづらく、かといって「し」を省くと、俗な言い方に思えてしまう。
この「し」の扱いに関してはけっこう悩む方が多いのではないかと勝手に思っているのだが、残念ながらそこまで触れている辞書はあまり多くはない。私が調べた限りでは、『現代国語例解辞典』(小学館)、『明鏡国語辞典』(大修館)だけがその点に言及している。
たとえば前者では、『動作・作用の完了の意味をもつ漢語のサ変動詞に限り、「し」の重なりを避けて語幹に接続する形も行われている。「到着次第」「終了次第」など』と補注で述べている。後者も、俗だとしながら、「到着次第」という言い方はあると認めている。
では、話しことばの場合はどうかというと、NHKは、「~ししだい」は「し」が重なって発音しづらく、話しことばとしてこなれていないとして、「次第」はなるべく使わないようにして「~したらただちに(すぐに)」などのようにするとよいとしている(『ことばのハンドブック 第2版』)。
「し」を入れても入れなくても今や特に問題はなさそうであるが、言いづらかったら(私自身も確かに発音しにくいと感じることが多い)、NHKのように無理に「~ししだい」を使おうとしないほうがいいのかもしれない。
キーワード:
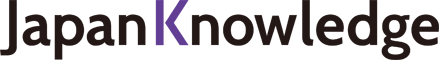


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
