2017年07月03日
「冷や奴をあてに一杯飲む」などのように、「あて」ということばを普通に使っているだろうか。「あて」を、酒の肴(さかな)の意味で。
もし国語辞典がお手近にあったら、この「あて」を引いてみていただきたい。辞典にもよるのだが、意味が載っていなかったというかたも、けっこういらっしゃるのではないだろうか。あるいは、関西方面で使われるといった内容の但し書きのある辞典をお持ちかもしれない。
そう「あて」はもともとは関西の方言だったのである。だから、この語を載せていない辞典も存在しているというわけである。私の周りでも「あて」と言う人は最近増えているのだが、千葉県出身の私はまったくと言っていいほど使うことはない。「さかな」か「つまみ」である。
関西方面ではけっこう古くから酒の肴のことを「あて」と言っていたらしく、『日本国語大辞典(『日国』)』では、『大坂繁花風土記(おおさかはんかふどき)』(1814年)の「酒の肴を、あて」という例を引用している。
ただ、なぜ関西方面で酒の肴を「あて」と言うのかはよくわからないらしい。『日国』では、この酒の肴の意味とは別に、「食事のおかずをいう、演劇社会などの隠語」という意味も記載されているのだが、それとの関係も不明である。だが、全く無関係とも思えない。
その意味では、以下のような例が引用されている。
*浮世草子・当世芝居気質〔1777〕一・一「ホヲけふは何とおもふてじゃ大(やっかい)な菜(アテ〈注〉さい)ぢゃな」
*南水漫遊拾遺〔1820頃〕四「歌舞妓楽屋通言〈略〉あて 飯のさい」
『当世芝居気質(とうせいしばいかたぎ)』の作者半井金陵(なからいきんりょう)は大坂の人である。
また、『南水漫遊拾遺』の作者は歌舞伎役者で随筆家でもあった浜松歌国(はままつうたくに)だが、歌国も出身は大坂である。『南水漫遊』は初編・続編・拾遺とあり、内容は歌国が在住していた大坂の事跡、特に演劇について述べられている。『大坂繁花風土記』とほぼ同時代のものであるので、関係がまったくないとは言い切れない気がする。だとすると、酒の肴の「あて」も大坂の芝居関係者の隠語だったのかもしれない。
こんな話もまた、酒のいい“肴”になりそうだと思うのだが、いかがであろうか。
神永さんがジャパンナレッジ講演会に登場!
忖度、そもそも、忸怩、すべからく……国の最高機関である国会においても、本来の意味や使い方とは違う日本語がたくさん出現しています。国語辞典ひとすじ38年目の編集者が巷で話題の日本語をピックアップ。それぞれの言葉の歴史を紐解き、解説します。
日比谷カレッジ 第12回ジャパンナレッジ講演会
「アップデートされることば~辞書編集者を悩ます、日本語⑤」
■日時:2017年7月26日(水)19:00~20:30(18:30開場)
■会場:日比谷図書文化館4階スタジオプラス(小ホール)■定員:60名■参加費:1000円
■お申し込み:日比谷図書文化館1階受付、電話(03-3502-3340)、eメール(college@hibiyal.jp)にて受付。
くわしくはこちら→日比谷図書文化館
もし国語辞典がお手近にあったら、この「あて」を引いてみていただきたい。辞典にもよるのだが、意味が載っていなかったというかたも、けっこういらっしゃるのではないだろうか。あるいは、関西方面で使われるといった内容の但し書きのある辞典をお持ちかもしれない。
そう「あて」はもともとは関西の方言だったのである。だから、この語を載せていない辞典も存在しているというわけである。私の周りでも「あて」と言う人は最近増えているのだが、千葉県出身の私はまったくと言っていいほど使うことはない。「さかな」か「つまみ」である。
関西方面ではけっこう古くから酒の肴のことを「あて」と言っていたらしく、『日本国語大辞典(『日国』)』では、『大坂繁花風土記(おおさかはんかふどき)』(1814年)の「酒の肴を、あて」という例を引用している。
ただ、なぜ関西方面で酒の肴を「あて」と言うのかはよくわからないらしい。『日国』では、この酒の肴の意味とは別に、「食事のおかずをいう、演劇社会などの隠語」という意味も記載されているのだが、それとの関係も不明である。だが、全く無関係とも思えない。
その意味では、以下のような例が引用されている。
*浮世草子・当世芝居気質〔1777〕一・一「ホヲけふは何とおもふてじゃ大(やっかい)な菜(アテ〈注〉さい)ぢゃな」
*南水漫遊拾遺〔1820頃〕四「歌舞妓楽屋通言〈略〉あて 飯のさい」
『当世芝居気質(とうせいしばいかたぎ)』の作者半井金陵(なからいきんりょう)は大坂の人である。
また、『南水漫遊拾遺』の作者は歌舞伎役者で随筆家でもあった浜松歌国(はままつうたくに)だが、歌国も出身は大坂である。『南水漫遊』は初編・続編・拾遺とあり、内容は歌国が在住していた大坂の事跡、特に演劇について述べられている。『大坂繁花風土記』とほぼ同時代のものであるので、関係がまったくないとは言い切れない気がする。だとすると、酒の肴の「あて」も大坂の芝居関係者の隠語だったのかもしれない。
こんな話もまた、酒のいい“肴”になりそうだと思うのだが、いかがであろうか。
神永さんがジャパンナレッジ講演会に登場!
忖度、そもそも、忸怩、すべからく……国の最高機関である国会においても、本来の意味や使い方とは違う日本語がたくさん出現しています。国語辞典ひとすじ38年目の編集者が巷で話題の日本語をピックアップ。それぞれの言葉の歴史を紐解き、解説します。
日比谷カレッジ 第12回ジャパンナレッジ講演会
「アップデートされることば~辞書編集者を悩ます、日本語⑤」
■日時:2017年7月26日(水)19:00~20:30(18:30開場)
■会場:日比谷図書文化館4階スタジオプラス(小ホール)■定員:60名■参加費:1000円
■お申し込み:日比谷図書文化館1階受付、電話(03-3502-3340)、eメール(college@hibiyal.jp)にて受付。
くわしくはこちら→日比谷図書文化館
キーワード:
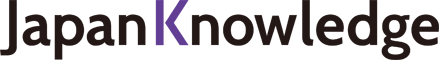


 出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。
出版社に入りさえすれば、いつかは文芸編集者になれるはず……そんな想いで飛び込んだ会社は、日本屈指の辞書の専門家集団だった──興味深い辞書と日本語話が満載。希少な辞書専門の編集者によるエッセイ。




 辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。
辞書編集37年の立場から、言葉が生きていることを実証的に解説した『悩ましい国語辞典』の文庫版。五十音順の辞典のつくりで蘊蓄満載のエッセイが楽しめます。 「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
「満面の笑顔」「汚名挽回」「的を得る」……従来誤用とされてきたが、必ずしもそうとは言い切れないものもある。『日本国語大辞典』の元編集長で、辞書一筋37年のことばの達人がことばの結びつきの基本と意外な落とし穴を紹介。
